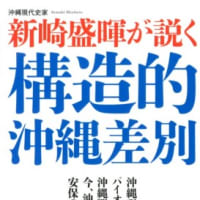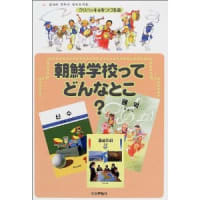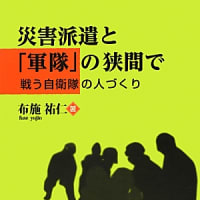2011年10月3日、東京都・参議院議員会館で「区外域避難(「自主的」避難)に賠償を求める院内集会」が、国際環境NGO FoE Japan、福島老朽原発を考える会(フクロウの会)、福島の子どもたちを放射能から守る福島・全国ネットワーク主催で開催された。
以下、集会の概要である。
1、避難区域外の「福島」で今、生じていること 満田夏花(FoE Japan)
福島市大波地区で行われた環境放射線モニタリング詳細調査(7月23日、26~28日)では、軒並み、放射線管理区域の基準である0.6μSv/時 以上を記録。自動車走行サーベイでは、局所的に避難区域指定基準の3.1μSv/時 を超える地域もあった。このように、基準値を超える放射線が観測されていても、避難区域として指定されていない地域が数多く存在している。福島からの避難を望んでいる人は多いが、経済的な事情、職・住居がない・家族の同意が得られない、などという理由で、“避難したくてもできない”という状況に置かれている。住民の流出を恐れ、避難を“タブー視”する自治体は、除染キャンペーンによって、住民を土地にしばりつけようとするが、除染による効果はほとんど見られていない(大波地区:測定高1m 放射線の低下 6.7%)。避難区域外の住民たちは、高い放射線下で、不安を抱えた生活を強いられている。
2、「自主的」避難の論点整理 ~原賠審の議論より 阪上武(フクロウの会)
現在、福島第一原発事故にともなう避難についての賠償範囲の指針作成が原子力損害賠償紛争審査会(以下、原賠審)で議論されている。8月5日付けの中間指針には「中間指針に明記されない個別の損害が賠償されないということのないよう留意されることが必要である。」と記載されている。しかし、9月14日に行われた第14回審査会では、賠償の対象時期を2つのカテゴリーに分ける案が出ており、4月22日(計画的避難区域設定日)以降に区域外から避難した人々に対する賠償が、指針に盛り込まれない可能性が出てきた。これに対し、「原発事故に対する賠償が、政府指示に基づく避難による損害にすりかえられているのでは」「4月22日というのは機械的な線引き。この日を境に事故の恐怖と健康影響への不安はなくなったのか」「そもそも、政府基準の20ミリが高すぎるのではないか」といった問題点は投げかけられた。今後、より多くの人と危機意識を共有し、裾野を広げていくことで、政府・文科省・東電へプレッシャーをかける、審査会委員に意見を届け、避難の実態を知らしめる、といった活動を行っていくことで、全面的な賠償を勝ち取りたいとしている。
3、原賠審の議論の問題点 ~法律化の視点から 福田健治(弁護士)
原賠法に基づく損害賠償の範囲は、原子炉の運転等により及ぼした原子力損害であるとされる。中間指針においては、福島第一原発事故と“相当因果関係”がある損害、すなわち「社会通念上、当該事故から当該損害が生じるのが合理的かつ相当であると判断される範囲のもの」であれば、原子力損害に含まれるとされている。これらのことから考えると、少なくとも、区外域避難のうち、原発事故以前に存在していた放射線の影響回避に関する社会的合意(放射線防護に関する国際的枠組み及び国内法令)に基づく避難は、合理的な行動であり、原賠法に基づく損害賠償が認められるべきである。
4、区域外から「自主」避難した人/これからする人の声
「今の福島には戻れない」「福島で子供を育てることは、もうできない」
今回話をしてくださった5名の方が述べていた言葉である。知人も、職も、住居もない土地に避難した方。家族を避難させ、自分は福島で仕事を続ける“二重生活”を送っている方。“避難=故郷を捨てる”ことだと考える周囲に対し、後ろめたさを感じている方。原発事故は多くの方々から、故郷・家族との生活・コミュニティー間の繋がり・仕事・家など、今までの“当たり前の生活”を奪い取ってしまった。
「家族を守るためには、自主避難という選択しか残されていなかった」と語る避難者の方がいた。避難者の方々の行動が、命を守るための正当な選択だったと認められるためにも、区域外避難に対する賠償は認められなければならないものである。
今回の集会に出席してみて私が感じたのは“行政の対応の遅さ”である。このような状況を生みだしている一原因に、活動の母数の少なさがあるのではないだろうか。福島、そして避難者の現状を知らない、知らされない人々を活動に組み込んでいく必要性を強く感じた。今後、福島支援も含め、避難をしてきた方々の声を届ける、そういった活動にも取り組んでいければ、と思う。