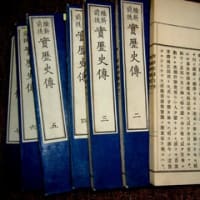吉田松陰、 田中河内介、 真木和泉守
すごい先生たち-45
田中河内介・その44 (寺田屋事件ー33)
外史氏曰
【 生麦事件ー1 】 (薩摩藩士による異人殺傷事件)
文久二年六月七日、勅使大原重徳(しげとみ) 一行は江戸に到着。 そして、将軍家茂に 幕政改革の朝命を伝えた。 勅使に随従した久光の江戸滞在は、足かけ三ヶ月近くにも及んだ。
役目を終えた久光は、勅使の帰京に先立ち、八月二十一日に供奉の者 七〇〇 ( 四〇〇との説もある ) 人余を従えて 江戸より帰途についた。
行列は、先払い( 進行前方の通行人を退かせる役目の侍 )に続いて鉄砲隊・玉薬箱・旗竿・長持・具足櫃・徒士( 従者 )・中道具台弓・挟箱( 着換えの衣服を入れたもの )・徒士・槍・徒士・箱入・鉄砲隊・小姓・長刀・力筒・駕籠廻り若党約三〇人・乗物・手槍・長柄・茶弁坊主・黄羅紗鉄砲・蓑箱・虎皮馬・供具足・両掛・乗替駕籠・供槍・長棒駕籠など 長々とした行列が続いた。 勿論、人馬や荷駄から成る行列の中には、外見はふつうの荷物の運搬に見せかけた 例の小砲、弾薬、小銃などが箱入にして運搬されていた。
久光自身はこの当時、攘夷論者ではなかったが、攘夷実行にも反対ではなかったという。 薩摩藩士の中には強硬な攘夷論者もいるので、江戸留守居 西筑右衛門より幕府に、外国人による街道の通行に関して、道中不都合が生じないよう 取締方を要請し、さらに各国の代表部へもその旨 連絡して欲しい、との届書をすでに提出していた。 幕府に提出した書面には次のような事が書かれていた。
「 最近、無作法にも 外国人らは馬で府内のあちこちを乗回っている。 歩行についても同じこ とがいえる。 藩主や国主久光の参府の折などに、もし外国人らに 無礼なふるまいがあったら、 国威を傷つけられないためにも 時宜によって相当の処置を とるつもりである 」
薩摩藩の意向は、大名行列の際、外国人が街道に横行し、万一無礼を働くような事があれば、定法に照らして当方で処理するので そのように承知しておいて 欲しいというものであった。 これに対して幕府は、外国人らに無礼な振舞いがないようにと、各国政府の出先機関へもすでに伝えてあるが、何分 外国人は我が国とは風習も異なり、また言葉も通じないことでもあるから、出来るだけ穏便に 計らうようにされたしと伝えてきた。
このように その頃の薩摩藩には 外国人の横行に対して、 極めて強硬な考えもあった。
かくして日雇いの人足を加えると 千数百名?にもなる行列は、品川・川崎の宿を経て、午後三時頃生麦にかかった。 事件はここで起きる。
この日、八月二十一日、横浜居留地に住む英国生糸商、 ウイリアム・マーシャル、横浜米国人経営 オーガスティン・ハード商会の店員で絹の検査員、ウッドスロープ・チャールズ・クラーク、上海より来日のイギリスの商人で、帰英の途次、観光のため横浜に来た、チャールズ・レノックス・リチャードソン、香港在住英国商人の妻でマーシャルの義妹のボロデール夫人ら 英国人四名が、日曜日でもあったので川崎まで リクレーションに出かけようとしていた。
当日は 六郷川畔の 川崎大師を見学するのが主な目的で、あらかじめ馬丁(ばてい) に馬を神奈川の宮之河岸( 渡船場 ) に廻させて置き、自分達はオーガスティン・ハード商会のボートで 湾内を横切り 神奈川に上陸、そこで馬丁から馬を受け取り、早速 騎乗して 午後二時半頃に神奈川を出発、東海道を北東に川崎方面へと向った。
当時、外国人が東海道を通行できる範囲は条約で、川崎六郷川から南保土ヶ谷までの間と決められていた。( 下図に示す )
川崎から神奈川までの東海道は海に沿っており、松並木の間に富士山が見えかくれする風光明媚な場所で、外国人の間では 快適な乗馬コースとして 人気があった。( 写真参照 )



フェリックス・ベアト写真集(横浜開港資料館編) 東海道の風景
しかし、東海道は 参勤交代で大名行列が通行する機会の多い 幹線道路でもある。 トラブルが起こる危険性もあるので、神奈川奉行 阿部越前守正外(まさと) は 各国公使に前日の二十日に、
「 二十二日、勅使が帰京するため、行列が大挙して通過するので、その日と翌日は 東海道へ出ないでほしい 」 という通達を出していた。
この二十日は週末だった。 通知を受けた英国代理公使ジョン・ニールは このオランダ語の通達を英語に翻訳して、二十二日には掲示しようと準備をすすめていた。

横浜周辺外国人遊歩区域図(幕末日本の風景と人びと・明石書店より)
つづく 次回
すごい先生たち-45
田中河内介・その44 (寺田屋事件ー33)
外史氏曰
【 生麦事件ー1 】 (薩摩藩士による異人殺傷事件)
文久二年六月七日、勅使大原重徳(しげとみ) 一行は江戸に到着。 そして、将軍家茂に 幕政改革の朝命を伝えた。 勅使に随従した久光の江戸滞在は、足かけ三ヶ月近くにも及んだ。
役目を終えた久光は、勅使の帰京に先立ち、八月二十一日に供奉の者 七〇〇 ( 四〇〇との説もある ) 人余を従えて 江戸より帰途についた。
行列は、先払い( 進行前方の通行人を退かせる役目の侍 )に続いて鉄砲隊・玉薬箱・旗竿・長持・具足櫃・徒士( 従者 )・中道具台弓・挟箱( 着換えの衣服を入れたもの )・徒士・槍・徒士・箱入・鉄砲隊・小姓・長刀・力筒・駕籠廻り若党約三〇人・乗物・手槍・長柄・茶弁坊主・黄羅紗鉄砲・蓑箱・虎皮馬・供具足・両掛・乗替駕籠・供槍・長棒駕籠など 長々とした行列が続いた。 勿論、人馬や荷駄から成る行列の中には、外見はふつうの荷物の運搬に見せかけた 例の小砲、弾薬、小銃などが箱入にして運搬されていた。
久光自身はこの当時、攘夷論者ではなかったが、攘夷実行にも反対ではなかったという。 薩摩藩士の中には強硬な攘夷論者もいるので、江戸留守居 西筑右衛門より幕府に、外国人による街道の通行に関して、道中不都合が生じないよう 取締方を要請し、さらに各国の代表部へもその旨 連絡して欲しい、との届書をすでに提出していた。 幕府に提出した書面には次のような事が書かれていた。
「 最近、無作法にも 外国人らは馬で府内のあちこちを乗回っている。 歩行についても同じこ とがいえる。 藩主や国主久光の参府の折などに、もし外国人らに 無礼なふるまいがあったら、 国威を傷つけられないためにも 時宜によって相当の処置を とるつもりである 」
薩摩藩の意向は、大名行列の際、外国人が街道に横行し、万一無礼を働くような事があれば、定法に照らして当方で処理するので そのように承知しておいて 欲しいというものであった。 これに対して幕府は、外国人らに無礼な振舞いがないようにと、各国政府の出先機関へもすでに伝えてあるが、何分 外国人は我が国とは風習も異なり、また言葉も通じないことでもあるから、出来るだけ穏便に 計らうようにされたしと伝えてきた。
このように その頃の薩摩藩には 外国人の横行に対して、 極めて強硬な考えもあった。
かくして日雇いの人足を加えると 千数百名?にもなる行列は、品川・川崎の宿を経て、午後三時頃生麦にかかった。 事件はここで起きる。
この日、八月二十一日、横浜居留地に住む英国生糸商、 ウイリアム・マーシャル、横浜米国人経営 オーガスティン・ハード商会の店員で絹の検査員、ウッドスロープ・チャールズ・クラーク、上海より来日のイギリスの商人で、帰英の途次、観光のため横浜に来た、チャールズ・レノックス・リチャードソン、香港在住英国商人の妻でマーシャルの義妹のボロデール夫人ら 英国人四名が、日曜日でもあったので川崎まで リクレーションに出かけようとしていた。
当日は 六郷川畔の 川崎大師を見学するのが主な目的で、あらかじめ馬丁(ばてい) に馬を神奈川の宮之河岸( 渡船場 ) に廻させて置き、自分達はオーガスティン・ハード商会のボートで 湾内を横切り 神奈川に上陸、そこで馬丁から馬を受け取り、早速 騎乗して 午後二時半頃に神奈川を出発、東海道を北東に川崎方面へと向った。
当時、外国人が東海道を通行できる範囲は条約で、川崎六郷川から南保土ヶ谷までの間と決められていた。( 下図に示す )
川崎から神奈川までの東海道は海に沿っており、松並木の間に富士山が見えかくれする風光明媚な場所で、外国人の間では 快適な乗馬コースとして 人気があった。( 写真参照 )



フェリックス・ベアト写真集(横浜開港資料館編) 東海道の風景
しかし、東海道は 参勤交代で大名行列が通行する機会の多い 幹線道路でもある。 トラブルが起こる危険性もあるので、神奈川奉行 阿部越前守正外(まさと) は 各国公使に前日の二十日に、
「 二十二日、勅使が帰京するため、行列が大挙して通過するので、その日と翌日は 東海道へ出ないでほしい 」 という通達を出していた。
この二十日は週末だった。 通知を受けた英国代理公使ジョン・ニールは このオランダ語の通達を英語に翻訳して、二十二日には掲示しようと準備をすすめていた。

横浜周辺外国人遊歩区域図(幕末日本の風景と人びと・明石書店より)
つづく 次回