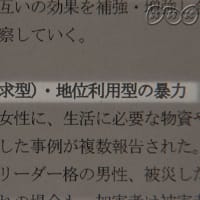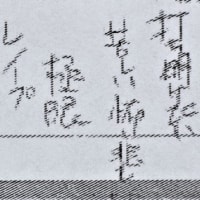ジャニー喜多川やダウンタウン松本人志の性加害事件など、社会を揺るがすスクープが新聞から出てこないのは、もはや当たり前になった。全国紙での記者経験がある柴田優呼さんは「女性記者から見ると、新聞社には岩盤のように強固な男性主観の壁がある。そのせいで働き方改革が進まないだけでなく、女性記者の意見が通らないため、性暴力問題を積極的に取り上げる動きも出てこなかった」という――。
■「松本人志と告発女性の対決を」と言った読売テレビ社長
新聞が社会のあり方を大きく変えていくような報道が明らかに減っている。現在問題になっている松本人志氏の性加害疑惑にしても、結局、追及しているのはジャニーズ問題同様、週刊文春だ。新聞は既に報じられた話を一部追いかけているだけ。ニューヨーク・タイムズがハリウッドに対して行ったように、かねて噂うわさされてきた芸能界における女性への性加害がどれだけ深刻か明らかにしていく絶好の機会なのに、感度は鈍い。人権問題というより、またも芸能ゴシップのようにとらえているようにも見える。
それどころか、読売新聞出身で読売テレビ社長の大橋善光氏が「松本氏と被害に遭われたという女性側が対決するなら、すぐにでも放送したい」などと発言し、大きな批判を浴びた。大手メディアの社長さえ性暴力被害者の置かれた心理状態や二次加害がどのようなものか、よく理解していないことを示すものだった。
大橋氏の発言は、視聴率を追い求めるテレビの節操のなさと結びつけられて批判されているが、大橋氏は読売新聞東京本社副社長など、新聞社内の要職を歴任した後、日本テレビ系列の読売テレビ社長に就任している。新聞社にいたとき、性暴力についての報道に真摯しんしに向き合っていたら、このような発言を安易にするとは思えない。
■記者が性暴力の被害者の尊厳を傷つけるケースも多い
自衛隊での性暴力加害を告発した五ノ井里奈氏が2023年1月に日本記者クラブで会見したときも、五ノ井氏に対して二次加害となるような配慮に欠けた質問を、年配の男性記者が行った。五ノ井氏の告発内容は、既に約半年にわたり再三報じられていた。それを考えると今さらなぜというあまりに基本的な質問でもあった。嫌がらせでないとしたら、性暴力取材に対する無知をさらけ出しているとX(旧ツイッター)で多くの批判が集まった。
新聞・テレビ関係者が会見の場で、性暴力の被害を受けたと訴えている女性の尊厳を傷つける発言を平然と行うといったことが、いまだに相次いでいる。こうした発言の背景事情として考えられるのが、男社会である新聞社特有の閉鎖性だ。記者たちは大学卒業から一括採用で入社し、退社まで過ごす。最近までその大半が男性で、男中心の集団が形成されてきた。
新聞の根底にあるのは、「岩盤のような男性主観」。毎日新聞で25年働き、日本新聞労働組合連合(新聞労連)委員長を務めたジャーナリストの吉永磨美氏は、そう話す。「岩盤のような男性主観」とは、組織のマジョリティーである男性たちが良しとする考え方のことだという。たとえば働き方だと、「24時間戦える」ことが理想的。でも出産や育児のため、それができない女性記者にとっては、キャリアを阻害する元凶でもある。
■女性に男性同様の権限を与えてこなかった新聞の現場
前回は、この「岩盤のような男性主観」が女性記者のキャリアをどのように狭めてきたか考えたが、今回は新聞のニュース判断や記事掲載にどう影響してきたかを見ていきたい。
『群像』2024年2月号の「男性管理職の『納得感』?」という記事に、その一例が載っている。2023年3月の国際女性デー連載企画で女性の就労差別を取り上げたときに経験したことを、元朝日新聞記者の阿久沢悦子氏が書いたものだ。
記事の初稿を男性編集幹部たちがチェックした後、リクエストが回って来た。
「男性読者に読ませるような書き方をしてほしい」
「女性を取り立てる側が、その方が得で幸せなのだ、と思えるような記事にするのが重要だ」といった内容だった。
さらに、「自分のキャリアを優先するため、妻の方を退職させた男の話も入れて」というものまで。阿久沢氏は「女性の側が男性に『得だ』『幸せだ』と思わせるように努力するべきだというロジックが、差別の再生産だということになぜ気づかないのか」「『差別』の話に両論併記、いらないよね?」と率直に感想をつづっている。
■「岩盤のような男性主観」に疲れ新聞社を辞める女性も多い
こうした要望の取り扱いはデスクの裁量に任せられるため、実際の記事にさほど反映されたわけではないという。だが事実であるなら、男性編集幹部たちは、職場で差別を受けている女性の側ではなく、組織の中枢を占める既得権益層の男性側の立場から問題を見ているということになる。女性が経験してきた賃金や雇用形態、昇進面などでの差別的な扱いを伝えるのがポイントのはず。でもそれをテーマに書くなら、同時に、女性を公平に扱うことのメリットも挙げろ、と言わんばかりの反応だ。
新聞記事が紙面に載るまでには、企画・編集段階でいろいろな攻防が起きる。特にジェンダーなどマイノリティーの問題が絡む記事ではこのように、「岩盤のような男性主観」を具現化したような反応が管理職側から起こることがある。「頑張って押し返すのだけど、それをしょっちゅう繰り返すうちに疲弊して、辞めていく記者たちが少なくない」と吉永氏は指摘している。
「新聞の中には意識の壁がある」。1990年代から性暴力被害の取材をしてきた元朝日新聞記者の河原理子氏は2023年6月、日本記者クラブでの会見でそう指摘している。2017年以後、性暴力に関する記事は目に見えて増えてきた。ジャーナリストの伊藤詩織氏が当時TBS記者だった山口敬之氏を提訴し、アメリカでMeToo運動が盛り上がった年だ。
■新聞の品位を保つため「強姦」という言葉を使わなかった
だが、かつてはかなり性暴力の記事は少なく、しかも「いたずら」といった、被害の深刻さが全く伝わらない言葉が新聞の紙面では使われていた。「強姦」は使用禁止だった。調べていくうち、別に人権に配慮したわけではなく、新聞の「品位」を保つこと、かつ不快感を与える用語は使わない、というのが理由だと知って、河原氏はショックを受けたという。
今も大きな変化は起きていないが、当時も社内の編集幹部は全員男性だった。「妻が言っていたけど、電車で女性の痴漢ちかん被害が多いって本当?」。先輩男性記者から真顔で質問された時代だった、と河原氏は言う。痴漢を含む性暴力が常習的に起きていることを知らない人たちばかりで紙面を作っていた。その結果、「性犯罪は伏せるのが一番。それが被害者のためでもある」と信じ込み、記事にしないことを正当化する空気があった。
そのため、河原氏が1996年に性暴力について最初の連載をしたときは、編集局内に人が少ない、つまり「載せるな」とストップをかける人が少ないと思われる週末をわざわざ狙って、連載を開始したというほどだ。
https://www.youtube.com/watch?v=qyPz-R1-bGc
■性加害でも「シモ」の話は記事にすべきではないという空気
「被害者のため、といったきれいごとじゃない。単純に『下半身』の問題なのでふさわしくない、という意識があった」。2023年3月に配信された朝日新聞ポッドキャスト「ニュースの現場から」で、MCの神田大介氏もそう指摘している。地方支局にいたとき男児が被害者の性犯罪事件が起きたが、記事にはしなかった。この件だけでなく、被疑者が犯罪行為の後に自慰行為をしていた場合も、その部分は伏せたという。理由はやはり「下(しも)の話」だから。
新聞社内に、性暴力について積極的に書くのを好まない雰囲気が存在していた。でも、それは新聞の「品位」や被害者への配慮だけが理由だったのだろうか。河原氏が最初に性暴力の連載を始めたとき、地方支局にいた若手の女性記者に「こういう記事って書いていいんですね。でも今私はやりません。にらまれるから」と言われてショックを受けたという。
性暴力は、男性が加害者、女性が被害者のケースが圧倒的に多い。女性の就労差別の件でもそうだが、広義の男性を批判する記事を女性記者が書くと、男社会の新聞社内で風当たりが強くなることがある。
男性記者の中には時々、「朝、食卓で家族の前で広げる新聞に、性暴力の記事が載っているのは、いかがなものか」といった考えを口にする人がいる。でも、なぜ殺人やテロの記事は良くて、性暴力の記事だと問題になるのか、疑問だ。被害者の憤りや苦しみに寄り添うというより、興味本位で見ているという認識があるような気がする。
■風俗店を平気で勧めるような男性記者が紙面を作っている
性暴力の記事化が長年避けられてきたことと、根深い男社会である新聞社の体質とは、完全に切り離せるものだろうか。『週刊金曜日』2023年11月17日号に、新聞の「品位」などとは裏腹な話が載っている。元毎日新聞記者の韓光勲氏が、地方支局の男性上司に過労を訴えたら、「息抜きに風俗に行けば」と言われたという。「少し前に結婚すると報告したばかりなのに」と男女平等の価値観が崩れ、人格が否定されるようなショックを受けて、その後退社に至った。
私自身、新聞社で働いていたとき、わずかだが男性記者のそうした言動を目にしたことがある。昔のことだと思っていたので、いまだに残っていることに驚いた。そうした言動が許容されてきたことは、閉鎖的で「岩盤のような男性主観」が根付いている新聞社の体質がどのようなものであるかを物語っている。
河原氏によると、性暴力という言葉で朝日新聞などのデータベースを検索すると、日本最初のセクハラ訴訟が起きた1980年代の終わりごろから散見されるようになり、その後小さな山が1990年代初めや2000年前後にあった。社会面というより、暮らしや家庭面での展開が多かった。「女性記者の増加が背景にある」と河原氏は話す。
■ジャニーズ問題を追及できなかったのも「男性主観」のせいでは
たとえ現実に性暴力が起きていても、それを問題だと考えて書こうとする記者がいなければ、報じられることはない。性暴力を大きな社会問題として喚起してきたのは、そうした女性記者たちの力だ。河原氏が指摘したような意識の壁は、「今もメディアの中に存在する」と、東京新聞記者の坂田奈央氏は、河原氏の会見リポートに書いている。取材の際に、自分の体験が「ネタ」のように扱われた、と辛く感じている被害者もおり、報道する側の課題は多い。
こうした状況を考えると、ジャニーズ児童性虐待問題で、新聞が長年沈黙を続けていたことも、不思議ではない。報道してこなかった理由としてよく、「芸能ゴシップだと思った」「男性の性被害に対する意識が低かった」「警察による捜査がなかった」「訴訟リスクを恐れた」などが挙げられるが、実情は、「岩盤のような男性主観」の下で、新聞が報じるには値しないニュースだ、と無視してきたのではないだろうか。
MeToo運動を広げたハリウッドのワインスタイン事件を暴いたのが、ニューヨーク・タイムズ紙の女性記者たちだったこと、そして男性編集幹部らが彼女たちを全面的に支えていたことを考えると、日本の新聞社との違いはあまりにも大きい。
■花形扱いされる男性記者も私生活では社会の一員ではない
日本の新聞社では、入社早々警察回りになり夜討ち朝駆けをさせられ、自分自身の生活は、かなぐり捨てて生きることに慣れさせられる。専業主婦の配偶者や親族に支えてもらうか、独身でないと、持続可能な働き方はではない。つまり、生活経験が乏しく、社会の一員でありながら社会の一員として暮らしていない。
経験者採用も増えているが、彼らが持つ異なる文化を組織に取り入れようとするというより、彼らが既存の文化に染まり、溶け込むことが求められる。多様な人材の均衡が基本、という立て付けになっていない。
一方で、若手でも、名刺1枚で首長や官僚のトップ、大企業社長と会うことができる。一般人が入れない場所にもアクセスできる。その際の取材相手も男性が中心。花形とされる永田町や霞が関などの取材現場はそもそも、男性優位の牙城のようなところだ。決定権を持つ場に女性がいないのが当たり前で、新聞社内でも同じ風景が広がっていることに違和感を持たない。
■新聞記事を作る編集部門がエリートの特殊な社内構造
記者の社内での立ち位置も特殊だ。通常は企業内に社業を支える多様な部門が並立している。だが新聞社では編集部門が他を圧倒しており、記者出身でない者が社長になることは、ふつうない。外部を含めたチームで動くテレビ局や、企画者としての側面も強い出版社と違い、新聞記者は1人で動くことが多い。他社との競争に常時さらされているため、精神的にも体力的にもタフであることが期待される。唯我独尊になりやすい環境だし、「岩盤のような男性主観」という一元的な価値観がすんなりと入り込みやすい組織構造になっている。
そして花形の当局回りでキャリアを積んだ男性記者が管理職に登用され、組織の中枢に据えられる。彼らが良しとする、つまり「岩盤のような男性主観」を反映したニュースが紙面の中心を飾っていく。「どこから探し出したかわからないような、一般の人たちの話から出てきたニュースではなく、記者クラブに所属しなければ取れない情報にこそ、希少価値があるという暗黙の了解がある」と吉永氏は指摘する。
その結果、そうした「岩盤のような男性主観」から外れたような話、たとえば性暴力や選択的夫婦別姓などの問題は、それほど重要ではないと見られる。「記者が頭を下げて、何度も頼まないと載せてもらえないようなことも起きている」と吉永氏は言う。“やらせてもらうジェンダー平等”というわけだ。
■私たちはこれから新聞に何を望むのか、考えてみるべき時期
そうでなくても、「学童保育の帰り道に、『子供がこんなことを言ってきて』みたいなことや、近所の人が『こんなことを言っていたけど、あれどうなっているの、この政策ちょっとおかしいんじゃないの』というような発想を重用する価値観に変わらない限り、どんどん社会とずれていく」と吉永氏は指摘する。
新聞とは、一体誰のものだろう。新聞が果たす社会的役割の大きさを考えるなら、急激な部数減で影響力が落ちている今、もはやこの問題を新聞社だけに任せるのではなく、広く社会に開いて、私たちはどんな新聞を望んでいるのか、もっとオープンに論じるべきだ。
2024/02/10 6:00
PRESIDENT Online
柴田 優呼(しばた・ゆうこ)
アカデミック・ジャーナリスト
コーネル大学Ph. D.。90年代前半まで全国紙記者。以後海外に住み、米国、NZ、豪州で大学教員を務め、コロナ前に帰国。日本記者クラブ会員。香港、台湾、シンガポール、フィリピン、英国などにも居住経験あり。『プロデュースされた〈被爆者〉たち』(岩波書店)、『Producing Hiroshima and Nagasaki』(University of Hawaii Press)、『“ヒロシマ・ナガサキ” 被爆神話を解体する』(作品社)など、学術及びジャーナリスティックな分野で、英語と日本語の著作物を出版。