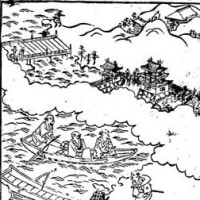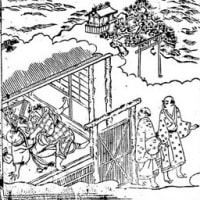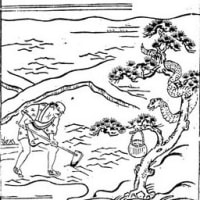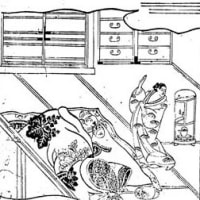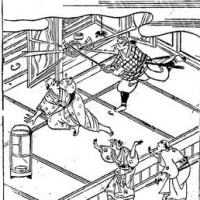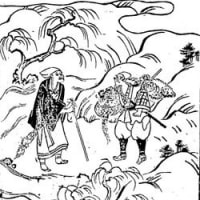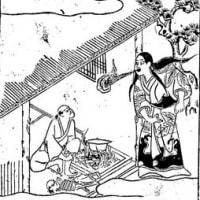ご訪問ありがとうございます→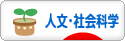 ←ポチっと押してください
←ポチっと押してください
いにしえの都、奈良の京二条村に住んでいた林浄因は、もと宋の国の人であった。花洛建仁寺第二世の龍山禅師が宋へ行ったとき、この林浄因に逢ったのだが、浄因も龍山に帰依して、浅からぬ膠漆の交わりを持った。宋が元になって、順宗皇帝至正元年に及び、龍山禅師は帰朝したが、これは第九十七代光明天皇(北朝)在位の、暦應四年のことである。
林浄因も龍山禅師の徳を慕い、禅師に伴って日本に来て、今の南都二条村に住居を構えた。昔はこの村が奈良の都であったので、晒や味噌など奈良の名産品も、なお、ここにある。
浄因もこの里に住もうと思ったが、それにはまず、家業というものがなくては生活できないと思い巡らせ、古くは諸葛孔明が造り広めたという饅頭を作って広めたところ、我が朝の人もあまねくもてはやし、吉事にも凶事にも用いるようになった。
しかし、この家では林の名を姓にせず、塩瀬という姓を名乗った。それは、その昔、浄因の遠祖は林和靖(=林逋)という詩人であったが、浄因は、自分が詩人の後裔でありながら、詩で名を上げるのではなく、食べ物で名を上げたのでは、詩人だった先祖に恥を与えると思ったので、林ではなく塩瀬と名乗ったそうである。
さて、この浄因、奈良にあって生業を勤めているうち、いつしか病身となって虚火(きょか=熱の出る慢性疾患)を患い、歳をとってからは度々眩暈が起こるようにもなり、死んでしまいそうな心地を覚えたので、龍山禅師の恵みを心に念じ、
「私の、このたびの病が治って、命算を延べられるならば、私が日本に来てからもうけた子のうち、一人を弟子に参らせます」
など、仏に向かってかき口説くように祈ることひたすらであった。
そんなある日、浄因が寝ている寝屋の北にあたる壁の後ろあたりで、大勢の人が寄って何やら作業をしている音がしたので、看病の者どもに言って様子を窺わせたが、そこには誰もいなかった。そのようなことが七日ほど続いた後、突然、壁が透き通り、星のように明るく見えたので、浄因は驚いて、看病の者に指差して見るように言ったが、これも浄因以外の者には見えることがなかった。
それから一日経ったら、透き通ったところがさらに大きくなっていたので、浄因が自ら立ち窺い見ると、壁の北は妻の化粧室にしている一間であるはずが、思いのほか広い野となっていて、草などがえも言われず生い茂っている中に、農民とおぼしき者が数人ばかり、てんでに鋤や鍬を取って穴の前に立ち来た。
浄因の不思議さは言うばかりではなかったが、この者どもに訳を問えば、皆が跪いて答えるには、
「これは、花洛建仁寺の龍山禅師が御所分の地として、我らに命じ、ここを開かせ給うたものです。龍山禅師は、塩瀬浄因が重病になったとお聞きになって、我らに仰せ付けられ、この道を開かせ、取り急ぎ、この家に参った次第です」
と説明したが、その言葉が終わらないうちに、五・六人の騎馬侍が、鞍に乗る姿も鮮やかに、列をつくってこちらの方へ進んできた。するとその次には、一山の僧と見える法師どもが数百人と、児(ちご)喝食(かっしき・かつじき=寺の食事を知らせる稚児)たちが花を飾り取り囲む中に、龍山禅師が上輿に座していた。
貴く有難く覚えた浄因が、少し退いて首(こうべ)を傾け、礼をして控えていると、穴の向こう二三間を隔てて、龍山禅師は輿を下させた。

龍山禅師は、
「そなたの、この度の病は、すでに命運が定まっていて、もう寿命は残っていなかったのだが、私はそなたのため冥府に行き、再三にわたって嘆願し、十二年の命を申し受けてきた。今日からはもう、病を憂うことはないぞ」
と宣った。と思ったら、透き通っていた壁は元のようになってしまった。
さて、このようなことがあってから、浄因は日毎に本復していったので、やがて、三人いる子のうち一人を連れて都に登り、龍山禅師の弟子とした。この子がすなわち、建仁寺の内で両足院の開祖、無等以倫だということである。
まことに龍山禅師の聖は、はるか幽冥にまで通じるという、ありがたい僧である。
注:この話に出てくる人物はみな実在で、「塩瀬」は現在でも饅頭の老舗として続いている。
いにしえの都、奈良の京二条村に住んでいた林浄因は、もと宋の国の人であった。花洛建仁寺第二世の龍山禅師が宋へ行ったとき、この林浄因に逢ったのだが、浄因も龍山に帰依して、浅からぬ膠漆の交わりを持った。宋が元になって、順宗皇帝至正元年に及び、龍山禅師は帰朝したが、これは第九十七代光明天皇(北朝)在位の、暦應四年のことである。
林浄因も龍山禅師の徳を慕い、禅師に伴って日本に来て、今の南都二条村に住居を構えた。昔はこの村が奈良の都であったので、晒や味噌など奈良の名産品も、なお、ここにある。
浄因もこの里に住もうと思ったが、それにはまず、家業というものがなくては生活できないと思い巡らせ、古くは諸葛孔明が造り広めたという饅頭を作って広めたところ、我が朝の人もあまねくもてはやし、吉事にも凶事にも用いるようになった。
しかし、この家では林の名を姓にせず、塩瀬という姓を名乗った。それは、その昔、浄因の遠祖は林和靖(=林逋)という詩人であったが、浄因は、自分が詩人の後裔でありながら、詩で名を上げるのではなく、食べ物で名を上げたのでは、詩人だった先祖に恥を与えると思ったので、林ではなく塩瀬と名乗ったそうである。
さて、この浄因、奈良にあって生業を勤めているうち、いつしか病身となって虚火(きょか=熱の出る慢性疾患)を患い、歳をとってからは度々眩暈が起こるようにもなり、死んでしまいそうな心地を覚えたので、龍山禅師の恵みを心に念じ、
「私の、このたびの病が治って、命算を延べられるならば、私が日本に来てからもうけた子のうち、一人を弟子に参らせます」
など、仏に向かってかき口説くように祈ることひたすらであった。
そんなある日、浄因が寝ている寝屋の北にあたる壁の後ろあたりで、大勢の人が寄って何やら作業をしている音がしたので、看病の者どもに言って様子を窺わせたが、そこには誰もいなかった。そのようなことが七日ほど続いた後、突然、壁が透き通り、星のように明るく見えたので、浄因は驚いて、看病の者に指差して見るように言ったが、これも浄因以外の者には見えることがなかった。
それから一日経ったら、透き通ったところがさらに大きくなっていたので、浄因が自ら立ち窺い見ると、壁の北は妻の化粧室にしている一間であるはずが、思いのほか広い野となっていて、草などがえも言われず生い茂っている中に、農民とおぼしき者が数人ばかり、てんでに鋤や鍬を取って穴の前に立ち来た。
浄因の不思議さは言うばかりではなかったが、この者どもに訳を問えば、皆が跪いて答えるには、
「これは、花洛建仁寺の龍山禅師が御所分の地として、我らに命じ、ここを開かせ給うたものです。龍山禅師は、塩瀬浄因が重病になったとお聞きになって、我らに仰せ付けられ、この道を開かせ、取り急ぎ、この家に参った次第です」
と説明したが、その言葉が終わらないうちに、五・六人の騎馬侍が、鞍に乗る姿も鮮やかに、列をつくってこちらの方へ進んできた。するとその次には、一山の僧と見える法師どもが数百人と、児(ちご)喝食(かっしき・かつじき=寺の食事を知らせる稚児)たちが花を飾り取り囲む中に、龍山禅師が上輿に座していた。
貴く有難く覚えた浄因が、少し退いて首(こうべ)を傾け、礼をして控えていると、穴の向こう二三間を隔てて、龍山禅師は輿を下させた。

龍山禅師は、
「そなたの、この度の病は、すでに命運が定まっていて、もう寿命は残っていなかったのだが、私はそなたのため冥府に行き、再三にわたって嘆願し、十二年の命を申し受けてきた。今日からはもう、病を憂うことはないぞ」
と宣った。と思ったら、透き通っていた壁は元のようになってしまった。
さて、このようなことがあってから、浄因は日毎に本復していったので、やがて、三人いる子のうち一人を連れて都に登り、龍山禅師の弟子とした。この子がすなわち、建仁寺の内で両足院の開祖、無等以倫だということである。
まことに龍山禅師の聖は、はるか幽冥にまで通じるという、ありがたい僧である。
注:この話に出てくる人物はみな実在で、「塩瀬」は現在でも饅頭の老舗として続いている。