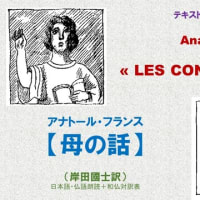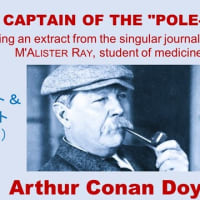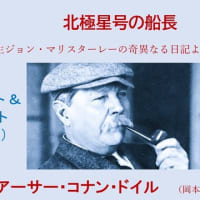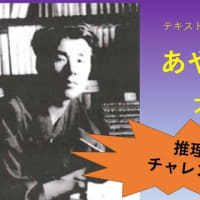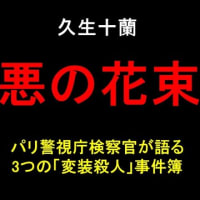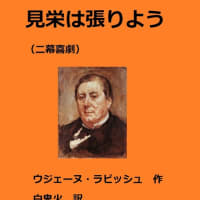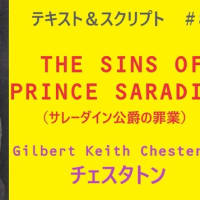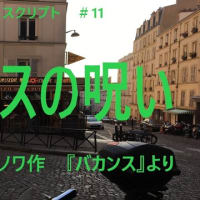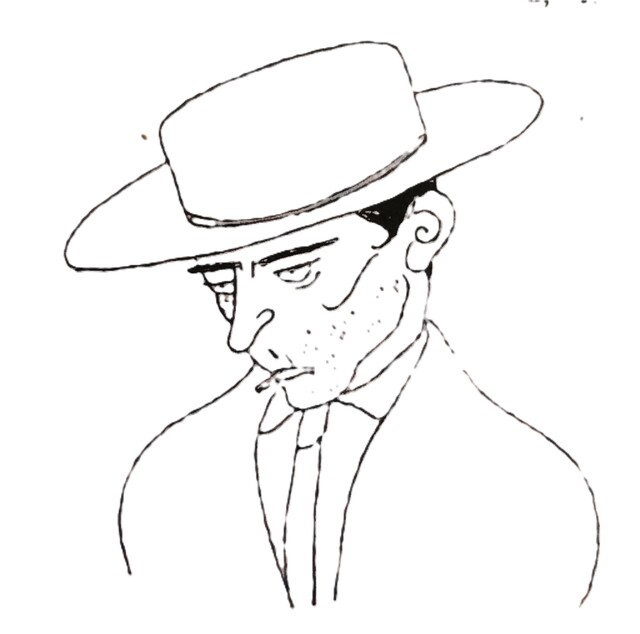アビダンマの際だった第二の特徴は、表面的には連続している意識の流れを、チッタ(心)という瞬間的で不連続な認知イベントの連なりに分断したことである。このそれぞれのチッタは、対象を認識する基本的力としての意識それ自体と、認知という行為において特定の仕事を行う心の成分(cetasika:「心所」)の集まりによって作られた複雑な統一体である。意識に対するこのような見方は、少なくともそのアウトラインは、経験を五つの集合体(五蘊)から説明し、そのうち四つの集合体が常に分離不可能な形で結びついているというスッタ・ピタカの分析から容易に導き出すことができるが、しかしその概念はスッタ・ピタカではまだ示唆の域を出ていない。アビダンマでは、この示唆を単に採り上げるのではなく、微視的な即時性と生命から生命への拡張的な連続性の両面を備えた、驚くほど詳細で均質な意識機能の絵を描き出している。
第三には、仏教の教説が流布するのに伴って雑多な専門用語が現れ、それらに秩序を与えようとしている点である。それぞれのダンマを定義するとき、アビダンマの本文は、主にスッタから抜き出した長い同義語のリストを対照させている。このような用語定義により、一つのダンマが違った名前で異なるカテゴリーのセットに入れられることが示される。
たとえば、様々な汚れ(煩悩)の中に貪欲(lobha:「貧」)という心の成分(心所)があるが、これは、感覚的欲求による汚れという意味でも、存在の汚れ(生存欲)という意味でも、身体への愛着、快楽への執着、悟りを妨害する感覚的欲求の意味でも使われる。悟りのための前提条件(覚支)の中に知恵(paññā:慧)という心の成分があるが、これは知恵の力(bala)の意味にもなっているし、現象を追求するという悟りの要素(dhamma-vicaya-bojjhaṅga)にもなり、正しい実践道(八正道)における正しい見解(sammādiṭṭhi:正見)の意味ともなる。このような対応関係を作ることで、アビダンマは、スッタ自体ではあまり明確になっていなかった理論的用語間の相互関係がわかるようになる。また、このプロセスにより、アビダンマは、ブッダの教えを解釈するための精密に仕上げられた道具を提供する。