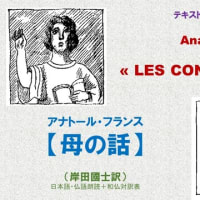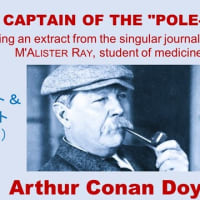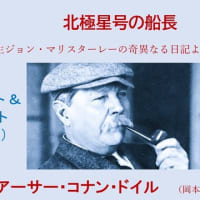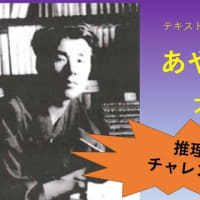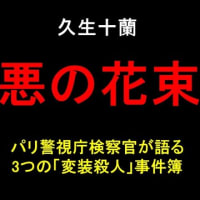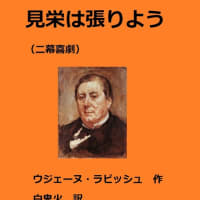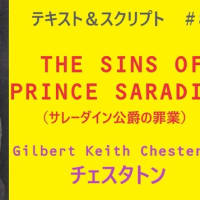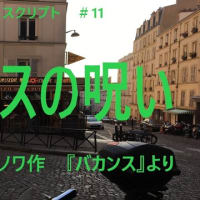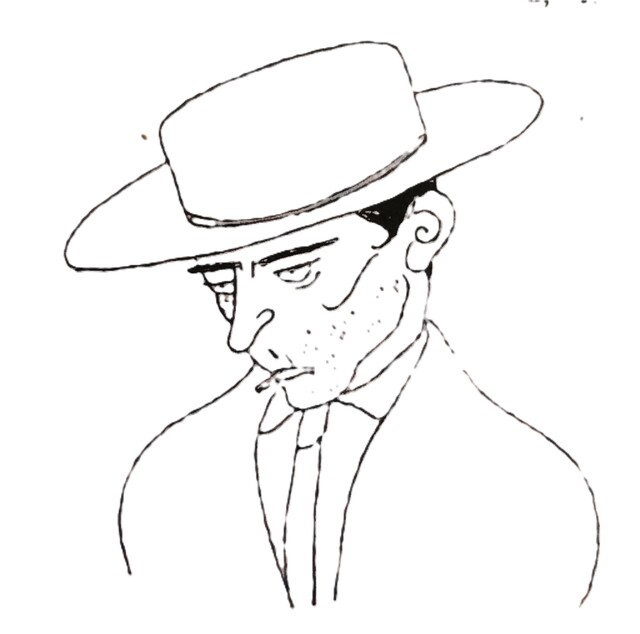ただしブッダは、体力を維持するために、毎日人間界へ下りていき、Uttarakuru 北部地方で托鉢を続けていた。食物を得ると、それを食べるためにブッダはAnotatta 湖のほとりへ行った。そこで、法将軍と呼ばれたサーリプッタ長老がブッダと出会い、その日に天界で説法した内容のあらましを聞くことになる。「尊師はそのメソッドを彼に伝授し『サーリプッタよ、これほど多くの理論を説いてきたのだ』と言った。こうして、このメソッドは、特に分析能力に恵まれたこの直弟子に与えられた。それは、あたかもブッダが岸辺に座り、大海を指さしたかのようであった。「サーリプッタ長老は、これまで尊師から教えられた数百、数千のメソッドの理論が明瞭になった」。[7]
サーリプッタは、尊師から教えられた法を習得し、今度はそれを五百人の弟子に教えた。こうしてアビダンマ・ピタカの原本ができあがった。発趣論の連続数字だけでなく、アビダンマ論の順序もサーリプッタ長老が決めたものとされている。おそらく、Atthasālinī がこのようにはっきりと認めているということから考えて、アビダンマの思索的部分の基本的骨格はブッダによって作られたものであるが、実際に詳細部分を著述し、おそらく原文のプロトタイプまで作成したのは、おそらくこの高名な弟子と彼の側近の学僧であったのではないかと思われる。初期の他の部派においても、アビダンマはサーリプッタ長老と深く結びついており、一部の伝承では、アビダンマ論を書いた作者は彼であると見なされている。[8]