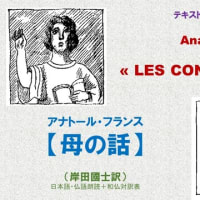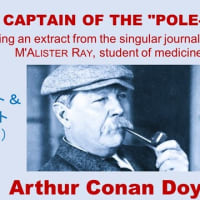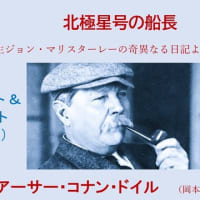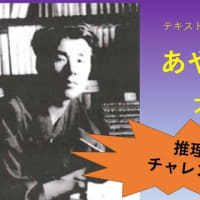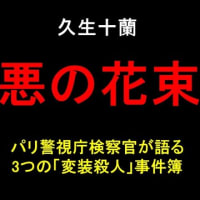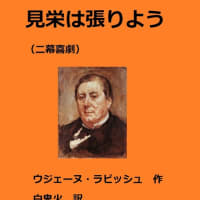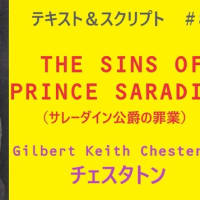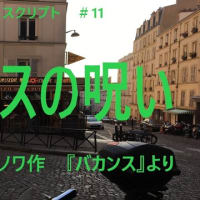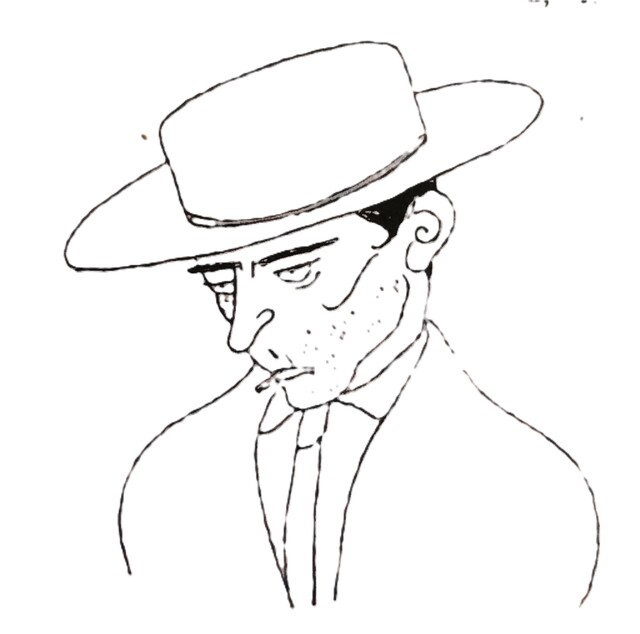アッタサーリニー(Atthasālinī:「勝義説」、ダンマサンガニー(法集論)の注釈書)では、悟りを得てから四週間、ブッダは菩提樹の傍らにとどまり、北西の向かう宝の家(rataṇaghara)に座していたと説明している。この宝の家とは、文字通り貴金属で作られた家屋ではなく、ブッダがアビダンマ・ピタカ七巻を熟慮した場所のことだとされる。ブッダは、ダンマサンガニー(Dhammasaṅgaṇī:法集論)の内容を順番に熟考したが、最初の六巻を調べている間、ブッダの身体から光線が発することはなかった。しかしパッターナ(Patthāna:発趣論)まで進むと、「原因や事物などの普遍的な二十四の条件関係を熟考し始めた時、彼はこれこそ自分の全知全能を発揮する場所だと知った。巨大な魚ティミラティピンガラ(Timiratipingala)が深さ84,000ヨージャナの大海にしか棲めないように、彼の全知全能はこの偉大なる書物の中に住処を見いだした。彼の全知全能が力を発揮して深遠難解なダンマに集中したとき、尊師の身体からは藍色、金色、赤、白、黄褐色、強烈な輝色の六色光線が出た」。[6]
したがって、テーラワーダの正統的見解は、アビダンマ・ピタカはブッダによった実際に語られたものであると主張しており、この点では彼らの初期のライバル部派であった説一切有部(Sarvastivadins)と異なっている。この部派も七巻から成るアビダンマ・ピタカを持っていたが、その内容はテーラワーダの論集と著しく異なっている。説一切有部によれば、アビダンマ・ピタカの諸巻はブッダの弟子達によって編成されたもので、いくつかの巻については、ブッダの死後から数世代後の人々によって作成された。これに対してテーラワーダの部派は、アビダンマの諸巻はブッダ自身が説示したものだと主張する。ただし、異なる意見に対して詳細に反駁した書Kathāvatthu(論事)は例外であり、これはアショーカ王の時代にモッガリープッタ・ディッサ(Moggalīputta Tissa)長老が作者であるとされる。