
人間、日々の生活の中で心身のバランスを崩してしまうことや、無意識に喪失感・疲労感を味わってしまう事もある。
お遍路を始める人は、意気込みの大小はあるだろうけど、何かを見失いかけて、新しく何かを見つけたい・見直したいという気持があって思い立ち、お遍路をはじめるのだろうと思う。
いったん、空(カラ)にしたい、リセットしたいという感覚もあると思う。
一般的にお遍路とは、空海が修行した四国で八十八ヶ所のお寺を参拝して廻る巡礼旅の事。
四国を一周するそのルートはループしていて、世界的に見ても珍しいそうだ。
一番寺から八十八番寺までの八十八ヶ所寺、どのお寺から開始してもよく、逆に廻っても、何回廻っても、途中で一旦やめてもOK。
ちなみに八十八番寺から一番寺に向かって逆に廻る事を「逆打ち」、途中で一旦区切って廻ることを「区切り打ち」という。
逆打ちは空海に出会いやすいという。空海没後も、順周りで空海はずっとお遍路を廻っているから、逆に廻っているとどこかで空海さんと対面するんだとか。
四国のお遍路は1000年以上の歴史があり、室町期には33箇所のお寺を巡礼していたそうだ。
当時、巡礼していたのは修行僧で、そのルートもまちまちで、道は生死が保障出来ない悪路、まさに修行のための巡礼だったとか。
江戸時代の頃から、修行目的だけではなく、一般的に庶民の間でも行われるようになったそうだ。
今なお毎年20万人の人たちが巡礼している。
昔は徒歩で巡礼していたのだが、最近では、車や観光バス、自転車で廻る人も多い。
巡礼旅の別の例だが、お伊勢参りは既に室町期辺りには白河(福島県)の講が300人くらいの集団がお参りに来た記録(しかも定期的に)も残っているそうだ。

いまだにお財布に大切に持ってる金の納札
で、写真は納札(おさめふだ)。
お遍路ではこの納札に住所と名前を書き込む。願い事を書いても何を書いてもいい。これを八十八ヶ所のお寺、参拝時に奉納する。各お寺には、本堂と太子堂(空海をまつったお堂)があり、それぞれに奉納するので、結果176枚の納札に住所と名前を書いて奉納する。あと、地元の人にお接待を受けた際、お礼としてこの納札をお渡しする。お接待については、また別の機会に説明します。
その他、参拝にはお線香とロウソク、お賽銭がいる。あと必要なものとしては経書と納経帳。
経書というはお経の本で、参拝時にお経を唱えるためのもの。
納経帳は、各お寺で参拝の証であるご朱印と墨字を貰うための帳面。参拝が終わった後で、実際に納経帳に書いて頂く。その為に300円が必要。
お寺は8時から17時までなので、参拝に20分程度時間がかかる事も頭にいれてスケジュール立てて行動しないといけない。
簡単にお遍路について説明したつもりだけど、どうでしょうか。
続きは>>お遍路を自転車で・・・40で。
>>papalionホームページ













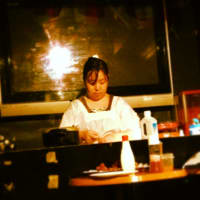










※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます