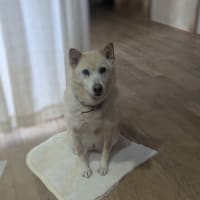これまでの文章
3,空っぽな世界に引きこもる
物語のクライマックス。彼は自分の肉体を救うために「神の都」の指導者マールテンと議論し、牢獄の中延々探求しつづけていた書物の秘密を解く。が、紙の上に図表を書きつけ、世界を変える一点を発見したかに思えたその夜、彼はフィリッパのものとなる。翌朝には「意味」も「何の役に立つのか」も「感情」も失い、「図表はそこにありながら、しかも白紙同然だった」(二十章、322頁)。そして最後に、彼は女の長持の中に仕舞い込まれる。
それは中を繻子で刺し子にした長持で、ゆったりと横たわれるだけの幅と長さがあり、フィリッパの道化たちに囃し立てられながら中に隠れた時には綺麗に研かれたされこうべが一つ入っているきりだった。彫刻を施した重い木の蓋が頭上で閉ざされたが、ヨハネスはされこうべの存在に幾らかの安堵をおぼえた(中略)。
グァネリウスが部屋に入った時、ヨハネスは蓋を開けた長持の片方の縁にクッションを宛がって寄り掛かり、立てた膝の上にその頭蓋骨を載せて、ひんやりとした堅さを確かめながらまじまじと見入っていた。(最後にして結末の章、333頁)
「天地を統べる至高の法則を追求して、把握しおおせたと思ったことさえあった」ヨハネスは、それを覚えてもいるし、描くこともでき、説明することもできるが「そんな問いと答えにどんな意味があったのか」「どうしても思い出せない」(同)。そのためにその法則を書きつけた紙を友人のグァネリウスにあげる。そして長持から「出たくない」、「私は幸せ者だ。二度と道を踏み外さないように、フィリッパが私を導いてくれるだろう」と言う。「道を誤った」という思いが、世界の探求によって快適な寝床と十分な食事を失ったときに齎されることから、これは世界が空っぽであることによってそれらを失わないこと―「どの道」死んで「長持の中に仕舞い込まれて土塊に還る」まで―を指すだろう。
グァネリウスはヨハネスの顔を覗き込んだが、そこには何も見当たらなかった―物の見事なまでに、ヨハネスは空っぽだった。(中略)
(中略)グァネリウスが知らないか、知っていながら知らないふりをしていることがひとつだけある。ヨハネスはそれを発見していた。どの道、誰もが長持ちの中に仕舞い込まれて土塊に還るのだとしたら、遅いか早いかにさしたる意味はないのではなかろうか。(同、334頁)
世界を変える一点とは、単純なものであった。内部と外部の、私と世界の関係は完全に反転させること。彼自身が内なる炎を持たず、真実の探求をせず、空っぽであること。腐ったり、冷えて灰のようになったりはしない、空っぽな体であること。
悔恨の歯は、自惚れの否定としての白髪、老いと衰えの白髪として別の形で生き残った。齧りとられた心臓の空洞は、物語最後にヨハネスが引き籠る女の長持へと姿を変える。彼が空洞の長持に潜り込むことは、物語最後に描かれる、ベアトリクスの妊娠に対応していよう。ベアトリクスは眠っている間に妊娠したのであるが、その眠りは魂が体から離れ鼬の「フェリクス」に導かれ移動したことによって齎されている。その魂はおそらくボーレンメント籠城中に妊娠したのだろう。長持は胎内のようにゆったりと快適で、永遠の鏡の影であるところの、よく磨かれた頭蓋骨がひとつ。空っぽになった彼は空っぽの胃袋に子豚の丸焼きを詰め込むように、その中に潜り込む。
「重い木の蓋」が「閉ざされ」、主人公の視点は物語の中に閉じ込められてしまったかに見える。しかしながらその蓋は、開けることができる。それでもフィリッパが「最初の夜、私が彼女を拒んだ時から、いつか必ずこんな風に私を仕舞い込んで、自分だけのものにしてしまおうと決めた」ために、ヨハネスは「ここから出られないし、出ようとも思わない」(同、333頁)。ヨハネスは物語の中に自ら閉じこもってしまった。ただし、探求の旅、そしてシュピーゲルグランツとともにヨハネスを長持から解放しようとする旅は、小説は閉じられながらも別の人物に受け継がれる。
5.空っぽな世界――結びに代えて
『黒の過程』においては、主人公ゼノンの自殺は「彼は自由だった」「彼にとってはもはや開かれる扉の鋭い音でしかなかった。そしてそれがゼノンの最期を辿って行き着くもっとも遠い地点であった」と表現され、金で守られた空虚な日常に住むマルタについては、その虚しさが強調される。作者ユルスナールもマルタに対する嫌悪をあからさまにしているように(*)、物語の主流では意に生きたゼノンに比べ臆病で何もないマルタに対して否定的な描き方がなされているといえるだろう。
しかしながら、『ハドリアヌス帝の回想』においてそうであったような人間性への深い肯定を、ユルスナールは守りきれない。人間的な意思に生きるというゼノンの生き方は、自殺によってのみ可能であったのに対し、何もないマルタの生活は末長く続くだろう。そして何より、いかに人間としてのユルスナールがマルタという登場人物を嫌おうとも、マルタが小説内で大きな機能を持ち、そのありように説得力があることは否定できない。
一方、その十五年前に書かれた『心臓抜き』では、空っぽな主人公はその空洞を満たすために、恥を引き受けるものとなって、黄金の部屋に引きこもる。重要な登場人物である三つ子たちは、母親に黄金の鳥かごに閉じ籠められ、物語の視点は唐突に家具屋の小僧に切り替わり、その家の黄金の扉が閉じられるところで閉じられている。「開かれる扉」によって物語が閉じられる『黒の過程』が、語りの寄り添う人物の精神の解放とともに読み手が小説から抜け出すものであると言えるのに対し、『心臓抜き』では読み手は物語世界から追い出されて終わり、登場人物たちは永遠にその中に閉じこもっている。
『鏡の影』では、主人公は女の長持のなかにしまいこまれ、「重い木の蓋が頭上で閉ざされる」(再掲)。世界を変える一点は、長い間主人公が探求していたようなものではなく、「どの道、誰もが長持ちの中に仕舞い込まれて土塊に還るのだとしたら、遅いか早いかにさしたる意味はない」(再掲)という感慨であった。その一方で、物語は眠りから覚め処女のまま妊娠したベアトリクス姫の話題へと移り変わる。主人公の世界が閉ざされても、物語は継続する。つまり、読者は主人公の視点が閉ざされその物語から追い出されても、未だ物語は続いているのだという感覚に曝され、完全には小説世界から出ることが出来なくなる。
小説の終わり方は、極言するならば、扉が閉ざされるか開かれるかしかないのかもしれない。
本文引用について:『黒の過程』『心臓抜き』『鏡の影』
注記:著者インタビュー「ある「黒の過程」・・・・・・」(聞き手:マチュー・ガレー、岩崎力訳『目を見開いて』白水社、二〇〇二年)
3,空っぽな世界に引きこもる
物語のクライマックス。彼は自分の肉体を救うために「神の都」の指導者マールテンと議論し、牢獄の中延々探求しつづけていた書物の秘密を解く。が、紙の上に図表を書きつけ、世界を変える一点を発見したかに思えたその夜、彼はフィリッパのものとなる。翌朝には「意味」も「何の役に立つのか」も「感情」も失い、「図表はそこにありながら、しかも白紙同然だった」(二十章、322頁)。そして最後に、彼は女の長持の中に仕舞い込まれる。
それは中を繻子で刺し子にした長持で、ゆったりと横たわれるだけの幅と長さがあり、フィリッパの道化たちに囃し立てられながら中に隠れた時には綺麗に研かれたされこうべが一つ入っているきりだった。彫刻を施した重い木の蓋が頭上で閉ざされたが、ヨハネスはされこうべの存在に幾らかの安堵をおぼえた(中略)。
グァネリウスが部屋に入った時、ヨハネスは蓋を開けた長持の片方の縁にクッションを宛がって寄り掛かり、立てた膝の上にその頭蓋骨を載せて、ひんやりとした堅さを確かめながらまじまじと見入っていた。(最後にして結末の章、333頁)
「天地を統べる至高の法則を追求して、把握しおおせたと思ったことさえあった」ヨハネスは、それを覚えてもいるし、描くこともでき、説明することもできるが「そんな問いと答えにどんな意味があったのか」「どうしても思い出せない」(同)。そのためにその法則を書きつけた紙を友人のグァネリウスにあげる。そして長持から「出たくない」、「私は幸せ者だ。二度と道を踏み外さないように、フィリッパが私を導いてくれるだろう」と言う。「道を誤った」という思いが、世界の探求によって快適な寝床と十分な食事を失ったときに齎されることから、これは世界が空っぽであることによってそれらを失わないこと―「どの道」死んで「長持の中に仕舞い込まれて土塊に還る」まで―を指すだろう。
グァネリウスはヨハネスの顔を覗き込んだが、そこには何も見当たらなかった―物の見事なまでに、ヨハネスは空っぽだった。(中略)
(中略)グァネリウスが知らないか、知っていながら知らないふりをしていることがひとつだけある。ヨハネスはそれを発見していた。どの道、誰もが長持ちの中に仕舞い込まれて土塊に還るのだとしたら、遅いか早いかにさしたる意味はないのではなかろうか。(同、334頁)
世界を変える一点とは、単純なものであった。内部と外部の、私と世界の関係は完全に反転させること。彼自身が内なる炎を持たず、真実の探求をせず、空っぽであること。腐ったり、冷えて灰のようになったりはしない、空っぽな体であること。
悔恨の歯は、自惚れの否定としての白髪、老いと衰えの白髪として別の形で生き残った。齧りとられた心臓の空洞は、物語最後にヨハネスが引き籠る女の長持へと姿を変える。彼が空洞の長持に潜り込むことは、物語最後に描かれる、ベアトリクスの妊娠に対応していよう。ベアトリクスは眠っている間に妊娠したのであるが、その眠りは魂が体から離れ鼬の「フェリクス」に導かれ移動したことによって齎されている。その魂はおそらくボーレンメント籠城中に妊娠したのだろう。長持は胎内のようにゆったりと快適で、永遠の鏡の影であるところの、よく磨かれた頭蓋骨がひとつ。空っぽになった彼は空っぽの胃袋に子豚の丸焼きを詰め込むように、その中に潜り込む。
「重い木の蓋」が「閉ざされ」、主人公の視点は物語の中に閉じ込められてしまったかに見える。しかしながらその蓋は、開けることができる。それでもフィリッパが「最初の夜、私が彼女を拒んだ時から、いつか必ずこんな風に私を仕舞い込んで、自分だけのものにしてしまおうと決めた」ために、ヨハネスは「ここから出られないし、出ようとも思わない」(同、333頁)。ヨハネスは物語の中に自ら閉じこもってしまった。ただし、探求の旅、そしてシュピーゲルグランツとともにヨハネスを長持から解放しようとする旅は、小説は閉じられながらも別の人物に受け継がれる。
5.空っぽな世界――結びに代えて
『黒の過程』においては、主人公ゼノンの自殺は「彼は自由だった」「彼にとってはもはや開かれる扉の鋭い音でしかなかった。そしてそれがゼノンの最期を辿って行き着くもっとも遠い地点であった」と表現され、金で守られた空虚な日常に住むマルタについては、その虚しさが強調される。作者ユルスナールもマルタに対する嫌悪をあからさまにしているように(*)、物語の主流では意に生きたゼノンに比べ臆病で何もないマルタに対して否定的な描き方がなされているといえるだろう。
しかしながら、『ハドリアヌス帝の回想』においてそうであったような人間性への深い肯定を、ユルスナールは守りきれない。人間的な意思に生きるというゼノンの生き方は、自殺によってのみ可能であったのに対し、何もないマルタの生活は末長く続くだろう。そして何より、いかに人間としてのユルスナールがマルタという登場人物を嫌おうとも、マルタが小説内で大きな機能を持ち、そのありように説得力があることは否定できない。
一方、その十五年前に書かれた『心臓抜き』では、空っぽな主人公はその空洞を満たすために、恥を引き受けるものとなって、黄金の部屋に引きこもる。重要な登場人物である三つ子たちは、母親に黄金の鳥かごに閉じ籠められ、物語の視点は唐突に家具屋の小僧に切り替わり、その家の黄金の扉が閉じられるところで閉じられている。「開かれる扉」によって物語が閉じられる『黒の過程』が、語りの寄り添う人物の精神の解放とともに読み手が小説から抜け出すものであると言えるのに対し、『心臓抜き』では読み手は物語世界から追い出されて終わり、登場人物たちは永遠にその中に閉じこもっている。
『鏡の影』では、主人公は女の長持のなかにしまいこまれ、「重い木の蓋が頭上で閉ざされる」(再掲)。世界を変える一点は、長い間主人公が探求していたようなものではなく、「どの道、誰もが長持ちの中に仕舞い込まれて土塊に還るのだとしたら、遅いか早いかにさしたる意味はない」(再掲)という感慨であった。その一方で、物語は眠りから覚め処女のまま妊娠したベアトリクス姫の話題へと移り変わる。主人公の世界が閉ざされても、物語は継続する。つまり、読者は主人公の視点が閉ざされその物語から追い出されても、未だ物語は続いているのだという感覚に曝され、完全には小説世界から出ることが出来なくなる。
小説の終わり方は、極言するならば、扉が閉ざされるか開かれるかしかないのかもしれない。
本文引用について:『黒の過程』『心臓抜き』『鏡の影』
注記:著者インタビュー「ある「黒の過程」・・・・・・」(聞き手:マチュー・ガレー、岩崎力訳『目を見開いて』白水社、二〇〇二年)