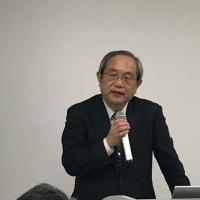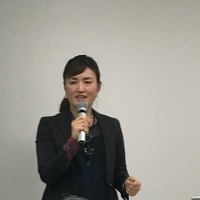2016年7月12日(火)、ベルサール八重洲にて大来塾2016年度総会が開催されました。
総会では、林田英治大来塾会長のご挨拶の後、以下の議案が承認されました。

第1号議案 2015年度活動報告並びに2015年度決算報告及び監査報告の件
第2号議案 2016年度活動計画案並びに2015年度予算案の件
第3号議案 役員選任の件
総会後の記念講演では、1994年から駐フランス大使を務めた後、1999年から10年にわたり、アジア人として初めてとなるUNESCO(国連教育科学文化機関)事務局長(第8代)として活躍された松浦 晃一郎氏を講師にお招きし、「世界遺産の現状と課題」と題してご講演をいただきました。

お話は、第二次大戦後、世界平和実現のために、いわゆる「ハードパワー」を担う機関として設立された国連に対し、車の両輪として機能させるべく、教育・文化・科学・コミュニケーションという「ソフトパワー」を担う機関として、「人の心に平和の砦を築く」との理念の下にUNESCOが設立されたという経緯から始まりました。
現在千件(うち8割が文化遺産、2割が自然遺産)を超える世界遺産のうち、日本の世界遺産は19件(文化遺産15、自然遺産4)で、現在イスタンブールで開催中の世界遺産委員会の審議において、フランスが主となって推薦している「ル・コルビュジエの建築作品」の構成資産として、国立西洋美術館本館が登録されることはほぼ確実なので、20件となる見込みとのことです。
世界遺産の選定に当たっては、「顕著な普遍的価値(outstanding universal value)」が基準とされますが、その「価値」を説明する確固たるストーリーと、それを裏付ける歴史的建造物または遺構(つまり有形の文化遺産=不動産)が存在し、しかも両者が整合していなければ登録には至らないということを、2度目のチャレンジで世界遺産に登録された「平泉」や、今年の委員会審議を前に推薦を取り下げて再検討に入った「長崎の教会群とキリスト教関連遺産」の実例に即してわかりやすくご説明いただきました。
また、日本の文化財制度との違いとして、世界遺産で重視される「ストーリー性」が、文化財の場合には要件とされないこと、世界遺産は有形の文化遺産のみを対象としており、日本でいう「文楽・歌舞伎・能」のような「無形文化財」や「歴史的文書」が含まれていない点に限界があるが、これを取り込む動きに対しては、西欧諸国の賛同が得られにくいなどの問題もあることをお話しいただきました。
「世界遺産は、『平和の砦を築く』ための手段であり、人々のコミュニケーションを深めて誤解を解いていくことが本来の目的なので、世界遺産を訪れるときは、ぜひその歴史的背景をよく理解しておいてください」という言葉が印象に残りました。
ご講演の後、懇親会に移りましたが、松浦先生にも途中までご参加いただき、会員一同、和やかな雰囲気のうちに懇親を深めることができました。