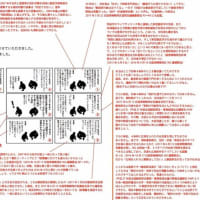抵抗力を下げる危険も!風邪は「市販薬では治らない」驚きの理由- VenusTap(2015年2月8日20時40分)
風邪が大流行するこの季節。「風邪っぽいな」と思ったら、ひどくなる前にと早い段階から市販の風邪薬を飲んでいる人も多いだろう。
生活情報リサーチサイト『TEPORE』が35,236人を対象に行った「風邪について」のアンケートでも、54.4%の人が「市販の風邪薬を飲んで治す」と回答している。
しかし、この市販薬には“風邪を完治させる効果がない”ということをご存じだろうか? しかも、正しく使わないとその効果を得られないどころか、治りにくくなることすらあるという。
今回は、市販の風邪薬の効能を踏まえた風邪の効果的な予防法を、厚生労働省の情報などを元にご紹介していこう。
■市販薬はムダな成分が多すぎる?
市販の風邪薬のパッケージを見てみると“風邪の諸症状の緩和”と書かれている。このことからわかるように、市販薬の目的は、“風邪の症状を抑える”ことであり“風邪を治す”のではない。
そもそもウイルスが原因の風邪は、市販薬によって無理に症状を抑えるよりも、本来身体に備わっている自己治癒力を用いてウイルスを排出する方が早く治る場合もあるのだ。
また、一言で“風邪”といっても症状はその時々によって違う。しかし市販の風邪薬は、熱やせき、吐き気や頭痛などの幅広い症状に対応した成分が配合されている。そのため、症状が出ていない関係のない成分まで一緒にとることになり、結果的に副作用が出たり抵抗力を下げてしまったりすることにもなりかねない。
病院で処方される風邪薬も、市販薬と同じく風邪を完治させる効果は少ないが、個々の症状に合わせた必要な成分の薬だけを処方されるため、辛い症状を和らげながら自己治癒力を高めて、効果的に風邪を治すことが出来るのだ。
■やっぱり手洗い&うがいは重要だった
風邪やインフルエンザなどの予防には、手洗いやうがいが非常に効果的なのは周知の事実。これらを含め、今一度風邪の予防法についておさらいをしておこう。
(1)うがい
うがいに関してはその効果がたびたび議論されているが、ある研究によると、水でうがいを行った場合と、うがいをしなかった場合では、うがいをしたほうが風邪の発症率が40%も低いとの結果が出たそう。帰宅時はもちろん、休憩時間など外出をした際には、こまめにうがいを行うことが大切だ。
(2)手洗い、消毒
通勤時の電車の手すりやつり革はもちろん、ドアノブやエレベーターのボタンなど、無意識のうちに他人が触ったものに触れている。そのため、こまめな手洗いやアルコール消毒で手についたウイルスを洗い流す必要がある。
(3)適度な加湿を行う
空気が乾燥するとウイルスに感染しやすくなる。特に乾燥しやすい室内では、加湿器などで適切な湿度(50~60%)を保つことが効果的。
(4)睡眠を十分にとる
睡眠をとることで自己治癒力を高め、風邪を治すことが出来る。睡眠中は代謝が活発になるので、免疫力が上がって身体の中の風邪ウイルスを退治することが可能に。
症状が辛い場合は、放っておくと他の病気を発症してしまう可能性もあるため、速やかに病院に行くことをお勧めする。
病気になったときに、どの市販薬を使用するのかは自己判断にゆだねられてしまう。市販薬を使うなら、その効果や効能について十分理解した上で使用し、効率よく風邪を治してほしい。
http://news.infoseek.co.jp/article/venustap_1161697
……………
【憲法改正】民主・岡田代表「安倍首相との議論危ない」 枝野氏は緊急事態条項に「議論の余地ある」
2015年2月6日 22時23分
産経新聞
憲法改正をめぐり、民主党の岡田克也代表と枝野幸男幹事長との間に6日、齟齬(そご)が生じた。
枝野氏はCS番組で、憲法に規定されていない緊急事態条項の創設について「建設的な議論をする余地はある」と述べた。具体例として大震災時の対応を挙げ、「衆院選、参院選が半月後に迫っているときに東日本大震災のようなことが起こったら選挙ができるか」と指摘した。憲法は衆参両院の任期を定めているが、非常時の対応を明記していない。
一方、岡田氏は記者会見で「枝野氏の考えも分かるが」と前置きした上で「まず入り口が大事だ。安倍晋三首相の憲法観を修正してもらわないと」と述べ、安倍政権下で憲法論議はしないとの考えを改めて表明。「首相は今の憲法を非常に低く見ている。そういう首相の下での憲法論議は非常に危ない」とも語った。
http://news.livedoor.com/article/detail/9759931/
……………
5年で10%超カットも… 給料激減で地方公務員が生活破たんか
2015年2月6日 6時50分
DMMニュース
「就職できれば一生安泰」──そんな風にいわれた公務員だが、今や昔のことのようだ。地方公務員の給与が、ここ10年ほどの間で激減しているのだ。
2013年(平成25年)の地方公務員給与実態調査によると、一般行政職の平均年収は633万8000円(勤続22.1年)で、5年前と比べて47万2000円も減っている。さらに10年前と比べると78万5000円も減っているのだ。
警察職では、平均年収732万1000円(勤続20.1年)で、5年前の81万8000円減、10年前の148万7000円減。さらに教育職(小中学校)では平均年収679万5000円(勤続22.5年)で、5年前の92万4000円減、10年前の103万6000減と、特に下落ぶりが目立っている。
年収300万円未満を理由に彼女にもフラれる
西日本の某市の上級職採用試験に合格し、市役所で勤務している男性(25歳)は自身の境遇についてこう話す。
「勤続4年目になるのに、月の手取り給与は今でもギリギリ20万円です。外食なんて高嶺の花なので、職場の仲間との飲み会はもっぱら家飲みです。ただ、田舎なので夜11時過ぎるとバスもない。かといってタクシーにも乗れず、1時間近くかけて歩いて帰るのが習慣です。ちなみに隣接した政令都市に就職した大学の同期に聞けば、ぼくの給与と2割近い開きがある。自治体によって、地方公務員の給与格差はかなり大きいと思います」
また、この男性によると、薄給のあまり婚活も満足にできないという。
「SNSで知り合って2か月ほど交際していた女性に、収入について告げた途端、『え!? 大人の男の人なのにそれだけしかないの!』って絶句され、音信不通になりました……。公務員と結婚して安定した家庭を築きたかったんでしょうけど、年収300万円台と聞いて『話が違う』と思ったんでしょうね」
しかし、もっと苦しいのは既婚者の方だ。中部地方の公立中学校教員の男性(38歳)は話す。
「公務員というだけで、昔はいくらでもローンが組めたんですよ。というより、どこの銀行も『ぜひうちで組んでください』という感じだった。新婚だった12年前、月の手取りは25万円程度だったんですが、『公務員の方は年齢とともに順調に収入が増えるので、最初は苦しくても思い切ったほうが、資産形成上、有利です』などという行員の言葉に乗せられ、頭金ほぼナシで4000万円を借り入れてマンションを購入しました。こうして毎月15万円の返済を30年間続けることとなった。しかし、実際に給与が順調に増加したのはそれから3年程度で、30代になってからは給与はほぼ平行線状態。子どもの教育費も嵩んできて、ローンが苦しくなっていく一方でした。一昨年、震災復興のための地方交付税削減でさら給与がカットされたことを機に、泣く泣くマンションを売却しました。今は、家賃9万円の賃貸マンションに住んでいます」
妻に嘘をつき、こっそりアルバイト
一方、生活苦の中、禁止されている副業に手を染める公務員も少なくないようだ。関東某県県庁の土木管理課に務める男性(40歳)は話す。
「子供2人を私立のエスカレーター校に入れた5年ほど前は、今くらいに年収が700万円くらいになっているだろうと思っていたんです。それが実際、蓋を開けてみればギリギリ600万円です。5年前までは選挙の際の投票所運営の仕事や、臨時の清掃作業など1日あたり3~4万円の手当がもらえ、いい小遣い稼ぎになっていた。でも、今は単なる休日出勤扱いで時給換算されているので、せいぜい1万円ちょっと。こうした誤算が少しつづ積み重なったことが、今の生活の苦しさの元凶です。このまま子供たちを卒業させるのは厳しくなってきた。また財布を握る妻からの月の小遣いは3万円で、とても足りない。去年から土日には妻に『昇級試験の勉強』と嘘をついて、こっそりアルバイトをやっています。日当5000円のキャバクラの送迎なんですが、いつかバレるのではとヒヤヒヤしながらやっています」
最近、全国で、教員や警察を始めとする地方公務員の不祥事が相次いでいるが、その背景には給与低下によるモチベーションやモラルの低下があるのかもしれない。
かつては「楽して儲かる」と、やっかみの声も聞こえた公務員の待遇だが、そんな彼らさえもアベノミスクの恩恵をまだ受けられないでいる。一般庶民へのトリクルダウンは、一体いつになることやら……。
http://news.livedoor.com/article/detail/9756109/
……………
「首相、今の憲法低く見ている」…岡田氏が批判
2015年2月7日 9時21分
読売新聞
民主党の岡田代表は6日の記者会見で、安倍首相の憲法観について「今の憲法を非常に悪くというか、低く見ている。『さげすんでいる』というと言い過ぎかもしれないが、そういう首相の下での憲法論議は非常に危ない」と批判した。
首相が過去に「日本国憲法はGHQ(連合国軍総司令部)の素人が8日間で作り上げた代物」と発言した点を問題視し、改正議論に容易に応じない考えを示したものだ。
http://news.livedoor.com/article/detail/9760689/
……………
枝野氏、首長選で「我々も自民党もお互い苦労」
2015年2月7日 22時36分
読売新聞
民主党の枝野幹事長は7日、奈良市内で記者団に、4月の統一地方選で行われる10道県知事選と5政令市長選について、「首長の場合、行政マネジメント(管理)能力を持ち、なおかつ選挙に手を挙げてくれる人(の発掘)が難しくなっている。我々も自民党も、お互い苦労している」と述べ、与野党の相乗りによる候補擁立はやむを得ないとの考えを示した。
民主党は、統一地方選を党再建の節目とする考えだが、与野党対決の首長選となるのは大分県知事選など一部にとどまる見通し。
http://news.livedoor.com/article/detail/9762303/
……………
「北方領土の日」CM 予想以上にブーイングが多かった理由
2015年2月7日 20時50分
日刊SPA!
「そこは日本なのに。今、日本人が住むことができない場所。ほら、こんなに近いのに……。北方領土は日本固有の領土です」
そんなナレーションとともに、真っ白いキャンバスに見立てた画面には、北海道本島から見てわずか16km程度しか離れていない国後島の稜線と、それを眺める少女がパステル鉛筆でササッと描かれる――。
今年は例年にも増して、2月7日の「北方領土の日」を知らせる政府広報を多く目にしたのではないだろうか。2009年の鳩山政権時におこなった「事業仕分け(行政刷新会議)」により、大幅な予算カットを余儀なくされた政府広報番組が軒並み姿を消したため、このように同種の政府広報が繰り返しテレビで流されるというのは久々のような気もする。
今年が戦後70年の節目に当たるだけでなく、現在、安倍政権が推し進めている対ロシア外交の先を見据えて、このタイミングで北方領土問題を広く国民の間に啓発することが目的であることは容易に想像できるのだが……。残念ながら、このCMに対する評判がすこぶる悪いのだ。
「国民の愛国心煽る目的しか考えられない。キナ臭くなってきたよ…」
「北方領土は日本の領土です! とかいうCM怖いよ」
「北方領土は日本のものです。ってCM初めてみた。少しぞっとした。静かに何かが始まってる感じ」
「最近『日本の領土なのに日本人が住めない土地があります』ってCMが流れてる。一瞬『福島?』って思ったのは我が家だけではあるまい。北方領土についての政府公報と分かってげんなり。北方領土に『住みたい』人がどんだけいるんだよ。まず生きてる国民が住みたい場所に住めるようにしてから言え」
ツイッター上には、安倍政権に向けてのものだろう。こんなにべもない批判的なつぶやきが溢れており、なかには、北方領土の問題そのものを知らないとおぼしき層の“批判ツイート”もちらほら散見された。現在、四十路を越えたオジサン世代からすると、昭和50年代にテレビのブラウン管を通して流れていた、あの昭和チックな“イガグリ坊主”の少年が出てくる色褪せたCMを思い出した程度だが、今を生きるネット世代の反応を見ていると、改めて、北方領土問題の“風化”が年を重ねるほどに加速しているのを見せつけられた思いだ。
そもそも北方領土とは、北海道の根室半島沖に連なる歯舞群島、色丹島、国後島、および択捉島を指し、現在もロシアに不法占領され続けている島々のこと。第2次世界大戦末期、日本がポツダム宣言を受託し連合国に「無条件降伏」することが決まった1945年8月15日のわずか3日後、それまで外国の施政下にあった歴史はなく、日本人によって開拓され、日本人が住みつづけたこれらの島々は、ソ連軍の不法な侵略に屈することになる。8月18日、千島列島最北端の占守島にソ連軍が上陸したのを皮切りに、8月31日にかけて島づたいに南下し、最終的に千島列島の南端であるウルップ島までを不法占拠。加えてソ連軍は別働部隊も駆使して、8月28日に択捉島を、9月1~5日には国後島と色丹島、さらには歯舞群島のすべてを占領し、これ以降、四島は今もロシアの実効支配下にあるのだ。
ツイートのなかには、上に挙げたように「北方領土に『住みたい』人がどんだけいるんだよ」といった少々乱暴な物言いもあったが、当時、択捉島以南の4島で暮らしていた人たちは実に1万7290人にものぼる。島民の半数はソ連軍の侵攻によりサハリンでの抑留生活を余儀なくされるなど多くの人が亡くなったが、故郷に帰ることを夢見る島民は今なお6596人(2013年末時点)もいるのだ。
毎年2月1日~28日は「北方領土返還運動全国強調月間」に指定されており、2月7日には全国各地で多くのイベントが催された。内閣府のホームページにも「北方四島の1日も早い返還実現のためには、国民の皆さん一人ひとりがこの問題への理解と関心を深めることが重要です。2月は北方領土返還運動全国強調月間として、全国各地で講演会やパネル展、キャラバン、署名活動など様々な広報・啓発活動が展開されます。皆さんもこの機会に、北方領土問題について考えてみてください」と書かれている。
ただ、近年「領土教育」の拡充もはかられているものの、現実の世界に目を向けると、まだまだロシアとの返還交渉を支えるだけの国民全体の「総意」となっているとは言いがたい状況なのだ。
2月12日には、モスクワで日ロ外務次官級協議が開かれる予定だ。ウクライナ情勢を受け孤立化を深めるプーチン大統領との首脳会談を逸早く開催し、北方領土問題の解決に向け、政府には全力で取り組んでもらいたいものだ。
http://news.livedoor.com/article/detail/9762169/
……………
自公与党、批判封殺のため最高裁への圧力発覚 政界に激震、国会で追及へ発展か- Business Journal(2015年2月8日06時00分)
最高裁判所の元裁判官で明治大学法科大学院教授の瀬木比呂志氏が、1月16日に上梓した『ニッポンの裁判』(講談社現代新書)において、衝撃の告発をしている。1月29日付当サイト記事『与党・自公、最高裁へ圧力で言論弾圧 名誉毀損基準緩和と賠償高額化、原告を点数化も』でも報じたが、自民党と公明党による実質上の言論弾圧が行われているというものだ。
2001年、当時与党であった自民党は、森喜朗首相の多数の失言を受けて世論やマスコミから激しく批判され、連立与党の公明党も、最大支持母体の創価学会が週刊誌などから「創価学会批判キャンペーン」を展開されるなど、逆風にさらされていた。そのような状況下、自公は衆参法務委員会などで裁判所に圧力をかけ、裁判所がそれを受けて最高裁を中心に名誉棄損の主張を簡単に認めるように裁判の基準を変え、賠償額も高額化させ、謝罪広告などを積極的に認めるようになった。
両党が森内閣や創価学会への批判を封じるために最高裁に圧力をかけたという事実はもちろん、最高裁が権力者である自公与党の意向を受けて裁判における判断基準を変えていたことも、民主主義の大原則である言論の自由、また三権分立をも根底から脅かす、大きな問題である。
また、名誉棄損の基準が歪み、それを悪用した恫喝訴訟が民事でも刑事でも蔓延しており、大きな社会問題となって各方面に影響が広がっている。瀬木氏の告発を報道する国内メディアが相次ぎ、海外の報道機関も取材に訪れていることから、さらに騒動は拡大する見通しだ。時の政権が実質上の言論弾圧をしていた事実が明らかになったことで、政界にも動揺が走っている。
●政界に広がる反響
前回記事は瀬木教授の最高裁内部の実態の告発を中心としていたが、政界での事実経緯を振り返るため、今回は当時の議会での動きを振り返ってみたい(以下、肩書はいずれも当時のもの)。
森政権や創価学会が世論から批判を強く浴びていた01年3月、法務大臣の高村正彦氏(自民党)は参院法務委員会で、「マスコミの名誉毀損で泣き寝入りしている人たちがたくさんいる」と発言した。これを受けて故・沢たまき氏(公明党)は「名誉侵害の損害賠償額を引き上げるべきだと声を大にして申し上げたい」と、同月の参院予算委員会で損害賠償額の引き上げについて、まさに“声を大にして”要求。魚住裕一郎氏(同)も同年5月の参院法務委員会で「損害賠償額が低すぎる」「懲罰的な損害賠償も考えられていけばいい」と強く要求した。
そして同月の衆院法務委員会で、公明党幹事長の冬柴鐵三氏が大々的にこの問題を取り上げて「賠償額引き上げ」を裁判所に迫った。これを受けて最高裁民事局長は「名誉毀損の損害賠償額が低いという意見は承知しており、司法研修所で適切な算定も検討します」と回答した。
つまり、自民党と公明党の圧力によって最高裁が名誉棄損の基準を変えていたのだ。そして裁判所が安易に名誉毀損を認めるようになり、その結果、不祥事を起こし追及されている側がそれを隠ぺいするために、また性犯罪者が告訴を取り下げさせるために、告発者や被害者を名誉毀損だとして訴える“恫喝訴訟”が頻発するようになった。
このような経緯について、現役の国会議員からも与党に対して批判の声が上がっている。衆議院議員の落合貴之氏(維新の党)は、告発に驚きを隠さない。
「実質的な恫喝目的で名誉棄損を悪用するケースや、公益通報者を保護しないケースなど、多様な陳情が寄せられています。その原因が、与党の自民党の圧力にあったという告発に大変驚いています。恫喝訴訟の問題については、国民を適切に保護するために、また被害者の方々が保護されるように、議員としてしっかりと取り組んでいきたいと思います」
一方、都内の区議会などでも反響が上がっている。世田谷区議を務める田中優子氏(無所属)は、次のように語る。
「性犯罪者側が、被害者女性や支援者を訴えている恫喝訴訟問題などに強い憤りを感じていました。しかし、その元が与党による最高裁への圧力だと聞き、大変驚いています。司法がこんな状態では、いったい国民は何を信じればよいのでしょうか。このような問題は区議としても注視して、被害者が適切に保護されるように尽力していきます」
このように本問題については、政界でも国会から地方議会に至るまで、多くの議員から批判の声が上がっており、今後国会での質問主意書などで取り上げられる可能性も高い。
これは現在の安倍政権ではなく、過去の自民党・公明党の問題であるが、安倍政権が過去の与党の問題に対しても毅然とした対応をできるのか、今後の動きに注目が集まっている。
http://news.infoseek.co.jp/article/businessjournal_111091
……………
【貧困ビジネス最前線】生活保護費ピンハネ対策に乗り出した政府の思惑- DMMニュース(2015年2月8日07時50分)
貧困層や低所得者から金銭を搾取する「貧困ビジネス」が横行している。昨今、社会問題化しているのは、無料低額宿泊所(生活困窮者に無料もしくは低額で提供される簡易住宅や宿泊施設)による生活保護費のピンハネだ。
ホームレスなどの生活困窮者は、野宿などをしていて住所不定のため、生活保護の受給を申請しても、行政側から生活保護の対象として認定されにくいという問題がある。
ホームレスが生活保護を受けづらいという状況に目をつけた心無い個人や団体は、善意のボランティアを装って、ホームレスに声をかけ、アパートの部屋や食事などを提供してやる。住所が決まって生活が落ち着いたところで、ホームレスに生活保護を申請させる。無事、行政側の審査が通って福祉事務所から保護費が支給されるようになると、保護費の大半を、住居を提供した個人や団体がピンハネしてしまうのだ。
もちろん、すべての無料低額宿泊所がこのような「貧困ビジネス」に手を染めているわけではないが、無料低額宿泊所に悪質業者が多く紛れ込んでいることは間違いのない事実である。
無料低額宿泊所に悪質業者が多く参入するのは、無料低額宿泊所の法的な位置づけが、白黒がはっきりしない「グレーゾーン」になっているからにほかならない。
2年間で約1億6996万円を荒稼ぎした業者の例
本来、無料低額宿泊所は、社会福祉法に基づく届け出制の施設なのだが、無届けでも処罰されることがないため、無届け業者はかなりの数に上る。厚生労働省の調査によると、2010年の時点で全国1802施設のうち、1314施設が無届けであった。
家賃についても規定があいまいになっており、2003年に設けられたガイドラインでは単に「無料または低額」と規定されているに過ぎない。実際の家賃の設定は事業者の判断にゆだねられている。家賃は低めに設定しておきながら、それに「管理費」や「運営費」を上乗せすることで、実態としては相当に割高な家賃になっているケースもある。
このように無料低額宿泊所が法的に「グレーゾーン」のままになっていることが、悪質業者の参入を招いている側面がある。
では、「貧困ビジネス」に手を染める無料低額宿泊所の実態はどうなっているのか。2014年10月、さいたま市などで無料低額宿泊所を運営していた男が所得税法違反の容疑で逮捕された。この男は2009~2010年の2年間で約1億6996万円を荒稼ぎしたにもかかわらず、所得を316万円と申告し、所得税6183万円の支払いを免れていた。
この男の運営していた施設の実態が明らかとなっており、これをみれば、入居していた人がいかに劣悪な居住環境に置かれていたがわかる。
ある男性は、今回摘発された事業者が運営するさいたま市内の住宅街にある一戸建ての無料低額宿泊所に入居した。この男性はベニヤ板で3畳のスペースに仕切られた6畳一間の部屋に住まわされたという。出てくる食事はカップ麺やレトルトばかりであったと証言している。家賃が4万7000円、食費・光熱費が約6万円、入居者には生活費として毎日500円と月に1度5000円が渡されるだけだった。
生活保護費の支給日になると、入居者は車で最寄りの福祉事務所に連れて行かれ、約12万円の生活保護費を受け取る。その後、コンビニエンスストアに連れていかれ、生活保護費が入った袋ごと事業者に回収されていた。
宿泊所の平均的な床面積はなんと9㎡!
こうした状況下、政府は2015年度から生活保護費のうち家賃に相当する住宅扶助の上限額を引き下げることを決定した。「貧困ビジネス」のうまみをなくすことが狙いだ。
「貧困ビジネス」に手を染める無料低額宿泊所は、利益を最大にするため、ひとつの部屋に複数人を押し込むなど劣悪な居住環境にしたうえ、住宅扶助の上限額に近い高めの家賃を設定することが多い。
実際、厚生労働省が2014年8月に実施した、生活保護受給世帯の居住環境についての調査結果によると、調査対象となった無料低額宿泊所の73%が住宅扶助の上限を超える家賃(家賃÷住宅扶助の上限≧1.0)を設定していた。しかも、無料低額宿泊所の平均的な床面積は9㎡と、平均的な民営借家(30㎡)に比べて極端に狭い間取りとなっていた。
住宅扶助の上限額を引き下げれば、施設運営業者の採算が悪化することになり、最終的には無料低額宿泊所の事業から排除できるという理屈だ。
ただし、住宅扶助の上限を引き下げると、(撤退する事業者が増えることで)無料低額宿泊所が不足気味となり、生活困窮者が住居を確保することがますます困難になるという本末転倒な結果を招く恐れもある。
やはり、無料低額宿泊所による「貧困ビジネス」の横行に歯止めをかけるには、届け出を義務付けるなど無料低額宿泊所に対する法的な規制を整備・強化し、きちんと行政の管理下に置くことが先決なのではないか。
http://news.infoseek.co.jp/article/dmmnews_916060
……………
政府の「シリア渡航阻止」に賛否両論 「事前に言う必要あったのか」の声も- J-CASTニュース(2015年2月8日17時54分)
シリアへの渡航を計画していた男性カメラマンに対し、外務省が2015年2月7日、これを阻止するため旅券を返納させた問題が波紋を広げている。
「渡航の自由」「表現の自由」への侵害として批判が相次ぐ一方、外務省の対応を支持する声、あるいは事前に渡航を宣言していたことなどに疑問を呈する向きもある。
朝日新聞インタビューなどでシリア行き表明
「これは報道の自由とか、取材の自由とか、表現の自由とか、渡航の自由とか......に関わる問題じゃないんですか? 基本的人権の問題でもありますし。権利を奪うことになるんじゃないんですかって(外務省の職員に言ったが、職員は)『そんなことよりも、まず日本人の生命の安全が第一です』と」(FNNニュースより)
メディアの取材に、憤りを隠さず答えたのは、新潟市在住の杉本祐一さん(58)だ。
杉本さんは30年来フリーのカメラマンとして活動、紛争地取材のキャリアも長く、2003年のイラク戦争時には、自ら「人間の盾」の一員となった経験もあるという。
2012~13年には、ISIL(イスラム国)に殺害された湯川遥菜さんが活動を共にしていた武装組織「自由シリア軍」に同行し、シリアを取材した。本人のものとみられるYouTubeアカウントでは、目を撃ち抜かれ即死した市民の姿など、生々しい「戦場」を捉えた動画が確認できる。14年10月にもトルコからシリア入りを目指したが、戦闘の激しさからトルコ軍に拒まれ、果たせなかった。
だが、杉本さんは諦めていなかった。朝日新聞(新潟版)は2015年1月25日朝刊で、杉本さんのインタビューに1000文字以上の紙幅を割いたが、その中で、「彼ら(※編注:アラブの人々)が苦しんでいるいま、何もしないで見ているわけにはいかない。私にできるのは撮影し、伝えること」と話し、2月中のシリア行きを宣言した。さらに地元紙・新潟日報にも、「27日に日本を出発」など、具体的なスケジュールを明かしていた。
ジャーナリストなどからは政府に批判相次ぐ
今回の旅券返納は、旅券法19条の規定「旅券の名義人の生命、身体又は財産の保護のために渡航を中止させる必要があると認められる場合」に基づくものだ。一方で、日本国憲法では22条で「海外渡航の自由」を保障しており、上記の規定による返納命令は史上初、異例中の異例といえる。
杉本さんの「渡航宣言」を掲載していた朝日新聞は、いち早く8日付朝刊の1面でこの問題を報じ、「踏み込んだ対応は論議も呼びそうだ」との見解を示した。同日の「報道ステーションSUNDAY」(テレビ朝日系)でも、ジャーナリストの後藤謙次さんが、「渡航の自由を超えた『報道の自由』への配慮が、政府はどこまであったのかな、とそこが非常に気になりますね」と疑問を呈している。
ツイッターでは、ジャーナリストの常岡浩介さんが、「憲法の自由権への直接制限ですから、ジャーナリストだけでなく、全国民、全人類への挑戦です」「今では中国にすら移動の自由があるが、日本はイスラム国への恐怖に駆られて9条以外の憲法も自主的に放棄し、北朝鮮並の不自由国になるのね。これこそ、テロへの屈服だよねえ」と激しい言葉で批判している。また、アジアプレス大阪オフィス代表の石丸次郎さんも、「恐れていた事態。このような取材者に対する強権発動は絶対に許されない」とツイートするなど、報道に携わる人々を中心に、反対の声が強い。
「台風の時に増水した川の様子見に行くなって...」
一方で、ネット上では、冷淡な反応も多い。お笑いタレントのガリガリガリクソンさんが「台風の時に増水した川の様子見に行くなって親に習わんかったんかいな。自由と勝手は違うって先生に習わんかったんかいな」と皮肉ったツイートは、一定の支持を受けていた。
そもそも事前にシリア行きを明かしていたことへの疑問の声もある。堀江貴文さんが、「この人スタンドプレーでしょ。黙っていけば返納命令はでない」と自らのサイトでコメントしたのを初め、ジャーナリストの安田純平さんも、外務省の対応を批判する一方で、自分の体験に基づいてこうつぶやいている。
「これは人によるけど、俺は出発前も滞在中もどこへ行くか、どこにいるかは帰国するか安全な場所まで出るまで公開しない。ネットで流れたら変な連中に知られて邪魔されたり危険なことになったりしかねないから。信頼できる人限定で取材過程を知らせるのは逆に安全対策になるけど、クローズドでやらんと」
http://news.infoseek.co.jp/article/20150208jcast20152227359
……………
人質殺害から1週間たたず…安倍首相が“夜の豪遊”もう解禁- 日刊ゲンダイ(2015年2月8日09時26分)
安倍首相にテロの犠牲者への「哀悼」の気持ちはあるのだろうか。「イスラム国」による後藤さん殺害映像の公開から1週間と待たず、再び、夜な夜な会食に繰り出しているのだ。自身の不用意なスピーチが邦人殺害事件の引き金になったと批判される中、“豪遊”再開の無神経ぶり。トップとしての力量以前に人間性が疑われる。
「日本は変わった。日本人にはこれから先、指一本触れさせない」
安倍首相の勇ましい発言が飛び出したのは、3日夜のこと。自民党の鳩山邦夫元総務相を中心とするグループ「きさらぎ会」が都内ホテルで開いた「新年会」に出席。あいさつに立つと、人質事件に触れて冒頭のように言い放った。
後藤さん殺害から、わずか2日後。日本だけでなく、国際社会が哀悼の意を表する中、親しい議員同士の“酒盛り”を催す鳩山元総務相の神経も疑うが、ノコノコ出かける安倍首相も安倍首相だ。しかも、悲劇的な結末を招いた政府の対応への反省や謝罪もなく、イスラム国に「指一本触れさせない」とたんかを切るなんて、完全に冷静さを失っている。
この日、安倍首相は18日ぶりに東京・富ケ谷の私邸に帰宅。中1日をあけた5日、またもや新年会に顔を出した。自由民主法曹団が自民党本部で開催したものである。
「会場にいる間、首相は終始ご機嫌で、何かつき物でも落ちたように笑顔を浮かべていました。中東歴訪から帰国した先月21日夜から人質事件の対応に追われ、公邸に連泊。睡眠時間も極端に減り、事件が長引けばダウン必至といわれていましたが、この日で衆参予算委の『内政・外交』の集中審議が終わったこともあり、解放感はひとしおだったのでしょう」(同席した自民党関係者)
新年会を切り上げ、安倍首相が次に向かった先は九段下のホテルグランドパレス。ホテル内の日本料理店「千代田」で、読売グループの渡辺恒雄会長と約2時間、酒食を交えた。「千代田」の1人当たりの予算は軽く1万5000円を超える。人質殺害から5日後には早々とメディア幹部との“食べ歩き”を解禁。高級料理に舌鼓を打つとは、いい気なものである。
「人質事件をめぐっては首相のカイロ演説など政府対応のマズさが、いくつも指摘されています。それでも首相は自分に火の粉は降りかかってこない、とタカをくくっているのでしょう。まだ人質殺害から日が浅いのだから、新年会や夜会合は自粛してもよさそうなもの。より緊迫度の高いテロとの長期戦を強いられた際、安倍首相はそのストレスに耐え切れるのか。このこらえ性のなさは、この国にとって致命傷となりかねません」(政治評論家の山口朝雄氏)
犠牲者への哀悼より、ストレス発散を優先させる安倍首相に、テロの脅威から国民を守れるとは思えない。
http://news.infoseek.co.jp/article/gendainet_239566
……………
介護「人手不足」を「外国人実習生=安価な労働力」で穴埋めする政府の“筋違い”- 産経ニュース(2015年2月8日17時58分)
政府は、外国人労働者の門戸を介護現場にも広げようとしている。厚生労働省の有識者検討会は1月26日、外国人に日本で働きながら技術を習得してもらう「外国人技能実習制度」の対象職種に介護職を加えるよう促す中間報告書をまとめた。「安価な働き手」を確保してでも介護現場の深刻な人手不足を少しでも解消したい、という「苦肉の策」でもある。しかし、高齢者らを相手に日本語で会話する「言葉の壁」が問題視されるほか、国民の生活を支えるための日本の社会保障を外国人が支えることから、社会保障制度の矛盾になりかねないという批判も出ている。
■介護福祉士よりも低いハードル
技能実習制度は、外国人の母国への技術移転を通じた国際貢献を目的としている。現在、農業や金属プレス加工、食品製造など約70職種を対象に約15万人を受け入れている。受け入れ上限は3年間だ。ここに対人サービスとしては初めてとなる介護職を平成27年度中に追加し、28年度に受け入れを始める見通しだ。
実は、介護の現場ではすでに外国人が働いている。政府は20年度から経済連携協定(EPA)に基づき、締結先のインドネシア、フィリピン、ベトナムから介護福祉士候補者の受け入れを始めている。
ベトナムは、現地で入国前の段階で、国際交流基金などが実施している日本語能力試験の「N3」の取得が必須となっている。試験のランクは最も難しい「N1」から最低の「N5」まであり、「N3」は、日常的な場面で使われる日本語をある程度理解できる小学校高学年レベルだ。ベトナム出身の介護福祉士を受け入れている施設責任者は「コミュニケーションには問題ない。利用者や家族からの苦情もない」と評価する。
ただ、こうした成功例は少数のようで、原則4年のうちに介護福祉士の国家試験に合格しなければ、直ちに帰国しなければいけない。合格してもやや待遇が向上する程度だが、これまで3カ国で計1538人が来日。国家試験に合格して日本で介護福祉士として働いているのは203人(昨年10月時点)にとどまる。会話はできても読み書きは苦手な外国人が多く、筆記試験をなかなかクリアできないのだという。人手不足の解消には「焼け石に水」といえる。
そこで、介護福祉士の資格を必要としない外国人介護労働者を「技能実習制度」で迎えるという案が出たのだ。介護の現場では介護福祉士の資格を持たない職員も多いが、資格の有無の差は待遇で若干の違いがある程度だとされている。
それでも、入浴や食事など要介護者への介助はコミュニケーション能力が欠かせない。とりわけ、認知症を抱える要介護者の対応には高い意思疎通能力が求められるという介護特有の事情を考慮し、検討会は介護職に限り日本語能力の確保を受け入れ要件に加えた。
「介護という人の命にかかわるようなものが追加されるので、ハードルを高くしておいた方がいい」
これまでの検討会では委員から、対象職種に追加する上で語学力を含めた要件設定を求める意見があった。これを踏まえ、中間報告は当初案で、「N3」レベルを基本とすると明記されていた。ところが最終的には、実習1年目で「N4」(基本的な日本語を理解することができる。小学校低学年程度)に達するところまで条件を引き下げ、「N3」は実習2年目の条件とした。
■国内の人材確保こそ課題
厚労省の推計によると、非常勤を含めた介護職員は25年度時点で全国に約177万人。団塊の世代が75歳以上になり、介護需要が増大する37年には約250万人が必要とされるが、このまま対策を講じなければ、介護職員は約220万人しか確保できず、約30万人もの不足が生じる見通しだという。
そこで着目したのが外国人技能実習制度だ。塩崎恭久厚労相は自民党政調会長代理時代に、職種に介護の追加を含めた自民党案作成に携わり、安倍晋三政権の成長戦略に盛り込んだ経緯がある。
とはいえ、日本語能力の確保を要件とした議論の出発点は、介護分野に外国人実習生を受け入れることで、「言語の壁」が利用者に不安を与えるとの懸念に対応するためだった。日本人の介護職員の指導を受けながら、たどたどしい日本語の実習生が要介護者に寄り添い、その表情やしぐさをみて適切な介助ができるのか。「意思疎通がとれず、現場の混乱や事故を招きかねない」(自民党厚労族)との指摘は少なくない。
また、技術移転による国際貢献が目的の技能実習制度について、中間報告は「人材不足への対応を目的としていない」とクギを刺し、こう念押ししている。
「37年に250万人規模の介護人材を確保するには、国内の人材確保策を充実・強化していくことが基本。外国人を安易に活用する考えはとるべきでない」 だが、実習現場は実習生を「安価な労働力」「雇用の調整弁」ととらえ、賃金未払いなどのトラブルが多発している。言葉の壁に加え、文化的な違いから起きる摩擦や治安への影響を懸念する声も絶えない。政府も制度見直しに乗り出している。
塩崎氏は27日の記者会見で、介護職の追加について「制度への批判も乗り越えられる形でやるのが前提だ。(介護職の追加は)進めていく」と強調した。
だが、なし崩し的な介護職の追加は介護の過酷な現場を世界に発信することになりかねない。まずは低賃金、過重労働という厳しい介護職の現状を改善し、本来は担うべき日本人による専門性を高めることが先決だろう。
http://news.infoseek.co.jp/article/sankein_sk220150208504
……………
谷垣氏、地球の裏側論は「誤解」 安全保障法制整備で- 共同通信(2015年2月8日21時13分)
自民党の谷垣禎一幹事長は8日、秋田県大館市での会合で講演し、集団的自衛権の行使容認を踏まえた安全保障法制整備について「地球の裏側」まで自衛隊を派遣することにつながるとの見方は誤解だとの認識を表明した。「国民の中に『地球の裏側』まで自衛隊を送るという誤解があると(法整備は)うまくいかない」と言及した。
法的に可能であっても、政府の政策判断として派遣先には事実上制限があるとの見解を示したとみられる。
谷垣氏は講演で「隙間のない安保法制をつくる」と強調。5月の大型連休明けが見込まれる国会審議について「丁寧に進める」と述べた。
http://news.infoseek.co.jp/article/08kyodo2015020801001687
……………