ポピュリズムとは何か 水島治郎著 世界のポピュリズムの動向を俯瞰する解説書
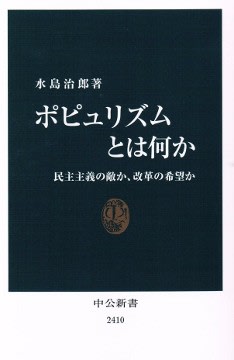
別の中公新書を買おうと思って訪ねた書店で見つけた。探していた自然科学系の本は売り切れていたようだ。著者の名前は知らなかったが千葉大学のヨーロッパ政治史研究者。専門はオランダ政治史だそうだ。
サブタイトルが「民主主義の敵か、改革の希望か」となっている。アメリカやヨーロッパを始め、世界を席巻するポピュリズムに強い懸念を抱く評者の立場からするとやや弱腰に映るが、内容もそれに近い印象を受けた。著者は決してポピュリズムを肯定しているわけではなさそうだが、強く否定しているわけでもなさそうだ。
まえがきで、「ポピュリズム研究に新境地を開いたカノヴァンによれば、『ポピュリズムは、デモクラシーの後を影のようについてくる』」と記す。「デモクラシーの成立と発展こそが、ポピュリズムの苗床となったとすれば、ポピュリズムなきデモクラシーはありえないのだろうか」と続ける。「『デモクラシーの逆説』の問題と解決の糸口を明らかにできれば幸い」というのが著者の問題意識のようだ。
カノヴァンという人も不勉強で知らない。その世界では有名なのだろうが、せめてどこの国のどういう仕事をしている人かくらいは書いておいてほしい(Wikipediaで調べたところ、イギリスの女性政治学者マーガレット・カノヴァン)。この本全体にいえることだが、日本人研究者の名前も次々に登場するが、評者には耳慣れない名前が圧倒的だった。国際政治学者とか社会学者といった程度には触れておいてほしい。インナーサークルの人はみんな顔見知りだろうから、これは著者というより、編集者の仕事かもしれない。
ポピュリズムについては2種類の定義があるという。ひとつは「固定的な支持基盤を超え、幅広く国民に直接訴える政治スタイルをポピュリズムととらえる定義」。政治学者の大嶽秀夫氏などがこの立場だという。大嶽氏の著作は読んだことがある。もうひとつは「『人民』の立場から既成政治やエリートを批判する政治運動をポピュリズムととらえる」という定義だ。「ポピュリズム研究者として名高いカノヴァンらがこの定義」をとり、日本でも何人かの政治学者がこの定義に賛同しているという。著者は何度もカノヴァンを引用しているから、この定義を強く支持しているようだ。
最初の定義は世上いわれるポピュリズムの定義に近いように思える。この定義に賛同する政治学者の吉田徹氏は、日本の中曽根政権、イギリスのサッチャー政権、フランスのサルコジ政権、イタリアのベルルスコーニ政権を代表例として上げているという。
後者の定義は政治運動としてのポピュリズムのようだ。「政治変革を目指す勢力が、既成の権力構造やエリート層を批判し、『人民』に訴えて主張の実現を目指す運動とされる」。「ここで主に例として挙げられるのは、フランスの国民戦線、オーストリアの自由党をはじめとする、いわゆるポピュリズム政党である。近年の政治学では、この定義をとる立場が多いように見受けられる」。2016年のアメリカ大統領選で予想を裏切って勝利したトランプ旋風はこの代表例というべきなのだろう。
筆者は近年の欧州における「ポピュリズム政党の台頭や、EU離脱をめぐるイギリスの国民投票、2016年のアメリカ大統領選挙で露わになったのは、既存のエリート層、エスタブリッシュメントに対する『下』の強い反発だった」と述べ、「これを踏まえれば、『幅広く国民に訴えかける』前者のポピュリズムの定義よりも、人民に依拠してエリートを批判する、『下』からの運動としてのポピュリズムの定義のほうが、より適切に現実のポピュリズムを把握できるのではないだろうか」と結論づける。確かに最近の欧米の動向を見る限り、そのとおりに思えるが、より巨視的な時間軸で見た場合、事態がどう展開していくかはまだはっきりしない。このあたりは従来どおりのポピュリズムの定義を支持する研究者の言い分を聞いてみたいところだ。
評者が著者の議論の進め方に違和感を持ったのは、日本のポピュリスト政治家を前大阪市長の橋下徹氏に代表させてしまったことだ。橋下氏がポピュリスト政治家であることに異論はないが、日本のポピュリスト政治家を彼に代表させるのにはちょっと無理があるのではないか。評者から見ると、自民党党則を変えて長期政権に固執する安倍首相もそうだと思う。(日米首脳会談では欧州の首脳に先んじてトランプ氏の別荘でゴルフをともにし、大いに気に入られたという)。元都知事の石原慎太郎氏、現知事の小池百合子氏などもその範疇に入ると思う。
大阪都をめぐる住民投票の僅差での敗北を受けて橋下氏は「負けは負けです。戦を仕掛けて...こちらがたたきつぶされた。これが民主主義なんです」と述べ、政界引退を表明した事実を引用している。潔い敗者を演じようとしたわけだが、筆者は「橋下において、そのポピュリズム的手法とデモクラシーは違和感なく接続していたようである」とその言葉を額面通り受け取っている。
だが、これは民主主義の浅薄で皮相的な理解というべきなのではないだろうか。橋下氏はたとえ僅差の敗北でも、デモクラシーの基本原則のひとつ、多数決の原理に従うと述べただけで、ポピュリストの彼がデモクラシーの何たるかやその基本的な意義をきちんと理解しているとは思えない。
それはともかく、本書を読んで、はじめて知ったことがいくつかあった。ひとつは昨年、イギリスで行われたEU離脱を問う国民投票。キャメロン首相が政治生命をかけて国民投票を実施したが、離脱賛成の衝撃的な結果に終わり、即刻辞任した。だが、EU離脱も元はイギリス独立党というマイナーなポピュリスト政党の政治公約だったという。一連の大騒動で、すっかり忘れてしまっていた。この結果はイギリス国内では、それまで政治から置き去りにされていた「労働者階級の反乱」という見方が強いそうだ。イギリス国内では、繁栄から取り残され、失業の危機にさらされる労働者階級出身の若者層をやや侮蔑的にチャブ(Chav)と呼んでいる。公営住宅に住む、「粗野な」白人労働者をイメージして語られることが多く、中産階級の品の良さとは対極に考えられている。サッカー界のスーパースター、デビッド・ベッカム選手もチャブ出身とされているそうだ。
もうひとつはアメリカ大陸、とくにラテンアメリカにおけるポピュリズムの広がりだ。「ラテンアメリカにおけるポピュリズムの登場を考える際に重要な背景は、ラテンアメリカで歴史的に形成されてきた、社会経済上の圧倒的な不平等である」。「長らくスペインやポルトガルの植民地支配が続いたラテンアメリカでは、本国経済に貢献することを目的とした典型的な植民地経済が成立し、農業と鉱山業の開発が進められた」。19世紀には経済が発展するが、政治はごく少数のエリートに支配され続けた。この支配が崩れるのは1930年代の大恐慌で国際自由貿易体制が崩壊し、支配層の権力の源泉である農鉱産品の輸出が困難になったからだという。「従来の輸出依存型経済は事実上崩壊した。続く第二次世界大戦の勃発により、欧米からの工業製品の輸入も困難となって、ラテンアメリカ経済は構造的な改革を迫られた」。
「寡頭支配層が動揺する中で、アルゼンチンのペロン、ブラジルのヴァルガス、メキシコのカルデナス、ペルーのパラスコなど、主として中間層出身のリーダーたちが民衆を大規模に動員し、ポピュリズムの担い手として政治の表舞台に躍り出た」。
アルゼンチンのペロン元大統領のことは知っている。大統領在職は1946~55年、73~74年と2度におよび、妻のエヴァ・ペロンの人気も手伝って、一時は熱狂的な支持を受けたが、経済の行き詰まりから軍のクーデターが起きた。1980年代を中心にした軍によるペロン派への過酷な弾圧が国際的な批判を浴びたことは記憶に新しい。
世界各地のポピュリズムの台頭も含め、現在を知ることはその国やその地域の過去の歴史を知ることでもある。日本から遠いラテンアメリカの歴史については不勉強でほとんど知らなかった。
その意味で、本書は世界のポピュリスムについて、俯瞰的な概観を伝えてくれる。ただある程度知識を持っている地域の分析は物足りないという印象を持ったことも事実だ。
たとえば評者が何年か勤務し、大統領選の取材も経験したアメリカ。トランプ大統領の誕生は新聞や雑誌でよく紹介されるラストベルト(錆びついた地域)と呼ばれる古い工業地帯の労働者の既成政治家への反乱だと指摘する。
ラストベルトの代表とされるウィスコンシン、オハイオ、ペンシルベニア州には時折、取材に訪れたので、その錆つき具合は知っている。ペンシルベニア州の代表都市ピッツバーグは鉄鋼産業で有名だが、20年以上前に取材したときも、川の中洲にある製鉄所がひどい鉄さびにまみれていて、その姿に愕然としたことを思い出す。ただピッツバーグは都市としての再生に全力を挙げていて、鉄鋼王カーネギーが設立したカーネギー・メロン大学はロボットなどハイテク研究で世界をリードしていた。周辺にベンチャー企業も立地したが、その後はどうなったのだろう。市街地にあるピッツバーグ大学は肝臓移植の世界的センターとして日本から留学する医師も多かった。ラストベルトの労働者の反乱というステレオタイプだけでは物足りないし、説得力にも欠けると思う。
トランプ氏が、メキシコに工場を新設する計画を持っていたトヨタを名指しで非難するなど、ラストベルトの労働者の歓心を買うのに懸命なことはよく理解できる。だが、単純な紋切り型の見方だけでいいのだろうか。メキシコ国境に壁をつくるだけでアメリカの経済が強さを取り戻すとも思えない。もっとも、これを欧州政治史が専門の筆者に要求するのは少し酷だろう。アメリカ政治や経済の詳細な分析については後輩の新聞記者を含め、現役の奮起を強く期待したい。
ささいな私事をひとつ。先月中旬、たまたまニューヨークを訪ねる機会があった。大雪で移動に難渋したが、結論からいうとトランプ時代に入ってもニューヨークの印象は変わっていなかった。目抜き通りの5番街に、今も家族が住むトランプタワーの警備はさすがに厳重だったが、それ以外は街の賑わいも人々の様子も変化がみられなかった。
あえて変化といえば大手書店のバーンズ&ノーブルに「反ユートピアコーナー」ができて、ジョージ・オーウェルの「1984年」や「動物農場」、アルダス・ハクスレーの「素晴らしき新世界」など反ユートピア小説が山積みになっていたことだ。戦前、ノーベル文学賞を受けたアメリカ人小説家シンクレア・ルイスの、大衆扇動家がアメリカの大統領に当選するという悪夢を描いた「It can't happen here」(この国ではそんなことは起きない)という80年前の反ユートピア小説(本邦未訳)も山積みで、衝動買いしてしまった。この小説は面白そうだが、300頁を超えるボリュームなので、このブログで紹介することはできそうもない。
そのあと訪れたストランドという大型の中古書店(新本も売る)はリベラル派の拠点だけに、入り口のドアに「難民歓迎」のメッセージが出て、店内にも「難民支持」や「反トランプ」のピンバッジが並んでいた。地下鉄を降りてホテルに戻ろうとすると、ストランド書店の紙袋を下げ、背中のリュックにも本を詰め込み、同じホテルに戻る人を見かけた。「自由なアメリカは健在」という思いを強くし、ちょっと明るい気分になった。
本書に戻ると、一線研究者による世界的なポピュリストの動向の概説としては面白いし、有益だ。ただ現在のポピュリズムをどう克服するのか、処方箋を求める立場からするとかなり物足りない。筆者が本当のところポピュリズムをどう考えているのか、克服すべき、立ち向かうべき存在だと考えるのか。あるいはそもそも民主主義に潜む影として、一定程度は許容しうると考えているかはわからない。ひょっとすると研究者としては非常に真面目に、自分の立場を鮮明に表明するのは適当でないし、得策でもないと考えているのかもしれない。
だが、現代は、日本でも多くの読者に支持される、フランスの思想家エマニュエル・トッド氏のように、進行中の事態をどう見るのか、自分の立場を明確にすることが強く求められている時代だと思う。
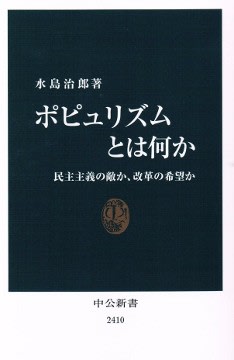
別の中公新書を買おうと思って訪ねた書店で見つけた。探していた自然科学系の本は売り切れていたようだ。著者の名前は知らなかったが千葉大学のヨーロッパ政治史研究者。専門はオランダ政治史だそうだ。
サブタイトルが「民主主義の敵か、改革の希望か」となっている。アメリカやヨーロッパを始め、世界を席巻するポピュリズムに強い懸念を抱く評者の立場からするとやや弱腰に映るが、内容もそれに近い印象を受けた。著者は決してポピュリズムを肯定しているわけではなさそうだが、強く否定しているわけでもなさそうだ。
まえがきで、「ポピュリズム研究に新境地を開いたカノヴァンによれば、『ポピュリズムは、デモクラシーの後を影のようについてくる』」と記す。「デモクラシーの成立と発展こそが、ポピュリズムの苗床となったとすれば、ポピュリズムなきデモクラシーはありえないのだろうか」と続ける。「『デモクラシーの逆説』の問題と解決の糸口を明らかにできれば幸い」というのが著者の問題意識のようだ。
カノヴァンという人も不勉強で知らない。その世界では有名なのだろうが、せめてどこの国のどういう仕事をしている人かくらいは書いておいてほしい(Wikipediaで調べたところ、イギリスの女性政治学者マーガレット・カノヴァン)。この本全体にいえることだが、日本人研究者の名前も次々に登場するが、評者には耳慣れない名前が圧倒的だった。国際政治学者とか社会学者といった程度には触れておいてほしい。インナーサークルの人はみんな顔見知りだろうから、これは著者というより、編集者の仕事かもしれない。
ポピュリズムについては2種類の定義があるという。ひとつは「固定的な支持基盤を超え、幅広く国民に直接訴える政治スタイルをポピュリズムととらえる定義」。政治学者の大嶽秀夫氏などがこの立場だという。大嶽氏の著作は読んだことがある。もうひとつは「『人民』の立場から既成政治やエリートを批判する政治運動をポピュリズムととらえる」という定義だ。「ポピュリズム研究者として名高いカノヴァンらがこの定義」をとり、日本でも何人かの政治学者がこの定義に賛同しているという。著者は何度もカノヴァンを引用しているから、この定義を強く支持しているようだ。
最初の定義は世上いわれるポピュリズムの定義に近いように思える。この定義に賛同する政治学者の吉田徹氏は、日本の中曽根政権、イギリスのサッチャー政権、フランスのサルコジ政権、イタリアのベルルスコーニ政権を代表例として上げているという。
後者の定義は政治運動としてのポピュリズムのようだ。「政治変革を目指す勢力が、既成の権力構造やエリート層を批判し、『人民』に訴えて主張の実現を目指す運動とされる」。「ここで主に例として挙げられるのは、フランスの国民戦線、オーストリアの自由党をはじめとする、いわゆるポピュリズム政党である。近年の政治学では、この定義をとる立場が多いように見受けられる」。2016年のアメリカ大統領選で予想を裏切って勝利したトランプ旋風はこの代表例というべきなのだろう。
筆者は近年の欧州における「ポピュリズム政党の台頭や、EU離脱をめぐるイギリスの国民投票、2016年のアメリカ大統領選挙で露わになったのは、既存のエリート層、エスタブリッシュメントに対する『下』の強い反発だった」と述べ、「これを踏まえれば、『幅広く国民に訴えかける』前者のポピュリズムの定義よりも、人民に依拠してエリートを批判する、『下』からの運動としてのポピュリズムの定義のほうが、より適切に現実のポピュリズムを把握できるのではないだろうか」と結論づける。確かに最近の欧米の動向を見る限り、そのとおりに思えるが、より巨視的な時間軸で見た場合、事態がどう展開していくかはまだはっきりしない。このあたりは従来どおりのポピュリズムの定義を支持する研究者の言い分を聞いてみたいところだ。
評者が著者の議論の進め方に違和感を持ったのは、日本のポピュリスト政治家を前大阪市長の橋下徹氏に代表させてしまったことだ。橋下氏がポピュリスト政治家であることに異論はないが、日本のポピュリスト政治家を彼に代表させるのにはちょっと無理があるのではないか。評者から見ると、自民党党則を変えて長期政権に固執する安倍首相もそうだと思う。(日米首脳会談では欧州の首脳に先んじてトランプ氏の別荘でゴルフをともにし、大いに気に入られたという)。元都知事の石原慎太郎氏、現知事の小池百合子氏などもその範疇に入ると思う。
大阪都をめぐる住民投票の僅差での敗北を受けて橋下氏は「負けは負けです。戦を仕掛けて...こちらがたたきつぶされた。これが民主主義なんです」と述べ、政界引退を表明した事実を引用している。潔い敗者を演じようとしたわけだが、筆者は「橋下において、そのポピュリズム的手法とデモクラシーは違和感なく接続していたようである」とその言葉を額面通り受け取っている。
だが、これは民主主義の浅薄で皮相的な理解というべきなのではないだろうか。橋下氏はたとえ僅差の敗北でも、デモクラシーの基本原則のひとつ、多数決の原理に従うと述べただけで、ポピュリストの彼がデモクラシーの何たるかやその基本的な意義をきちんと理解しているとは思えない。
それはともかく、本書を読んで、はじめて知ったことがいくつかあった。ひとつは昨年、イギリスで行われたEU離脱を問う国民投票。キャメロン首相が政治生命をかけて国民投票を実施したが、離脱賛成の衝撃的な結果に終わり、即刻辞任した。だが、EU離脱も元はイギリス独立党というマイナーなポピュリスト政党の政治公約だったという。一連の大騒動で、すっかり忘れてしまっていた。この結果はイギリス国内では、それまで政治から置き去りにされていた「労働者階級の反乱」という見方が強いそうだ。イギリス国内では、繁栄から取り残され、失業の危機にさらされる労働者階級出身の若者層をやや侮蔑的にチャブ(Chav)と呼んでいる。公営住宅に住む、「粗野な」白人労働者をイメージして語られることが多く、中産階級の品の良さとは対極に考えられている。サッカー界のスーパースター、デビッド・ベッカム選手もチャブ出身とされているそうだ。
もうひとつはアメリカ大陸、とくにラテンアメリカにおけるポピュリズムの広がりだ。「ラテンアメリカにおけるポピュリズムの登場を考える際に重要な背景は、ラテンアメリカで歴史的に形成されてきた、社会経済上の圧倒的な不平等である」。「長らくスペインやポルトガルの植民地支配が続いたラテンアメリカでは、本国経済に貢献することを目的とした典型的な植民地経済が成立し、農業と鉱山業の開発が進められた」。19世紀には経済が発展するが、政治はごく少数のエリートに支配され続けた。この支配が崩れるのは1930年代の大恐慌で国際自由貿易体制が崩壊し、支配層の権力の源泉である農鉱産品の輸出が困難になったからだという。「従来の輸出依存型経済は事実上崩壊した。続く第二次世界大戦の勃発により、欧米からの工業製品の輸入も困難となって、ラテンアメリカ経済は構造的な改革を迫られた」。
「寡頭支配層が動揺する中で、アルゼンチンのペロン、ブラジルのヴァルガス、メキシコのカルデナス、ペルーのパラスコなど、主として中間層出身のリーダーたちが民衆を大規模に動員し、ポピュリズムの担い手として政治の表舞台に躍り出た」。
アルゼンチンのペロン元大統領のことは知っている。大統領在職は1946~55年、73~74年と2度におよび、妻のエヴァ・ペロンの人気も手伝って、一時は熱狂的な支持を受けたが、経済の行き詰まりから軍のクーデターが起きた。1980年代を中心にした軍によるペロン派への過酷な弾圧が国際的な批判を浴びたことは記憶に新しい。
世界各地のポピュリズムの台頭も含め、現在を知ることはその国やその地域の過去の歴史を知ることでもある。日本から遠いラテンアメリカの歴史については不勉強でほとんど知らなかった。
その意味で、本書は世界のポピュリスムについて、俯瞰的な概観を伝えてくれる。ただある程度知識を持っている地域の分析は物足りないという印象を持ったことも事実だ。
たとえば評者が何年か勤務し、大統領選の取材も経験したアメリカ。トランプ大統領の誕生は新聞や雑誌でよく紹介されるラストベルト(錆びついた地域)と呼ばれる古い工業地帯の労働者の既成政治家への反乱だと指摘する。
ラストベルトの代表とされるウィスコンシン、オハイオ、ペンシルベニア州には時折、取材に訪れたので、その錆つき具合は知っている。ペンシルベニア州の代表都市ピッツバーグは鉄鋼産業で有名だが、20年以上前に取材したときも、川の中洲にある製鉄所がひどい鉄さびにまみれていて、その姿に愕然としたことを思い出す。ただピッツバーグは都市としての再生に全力を挙げていて、鉄鋼王カーネギーが設立したカーネギー・メロン大学はロボットなどハイテク研究で世界をリードしていた。周辺にベンチャー企業も立地したが、その後はどうなったのだろう。市街地にあるピッツバーグ大学は肝臓移植の世界的センターとして日本から留学する医師も多かった。ラストベルトの労働者の反乱というステレオタイプだけでは物足りないし、説得力にも欠けると思う。
トランプ氏が、メキシコに工場を新設する計画を持っていたトヨタを名指しで非難するなど、ラストベルトの労働者の歓心を買うのに懸命なことはよく理解できる。だが、単純な紋切り型の見方だけでいいのだろうか。メキシコ国境に壁をつくるだけでアメリカの経済が強さを取り戻すとも思えない。もっとも、これを欧州政治史が専門の筆者に要求するのは少し酷だろう。アメリカ政治や経済の詳細な分析については後輩の新聞記者を含め、現役の奮起を強く期待したい。
ささいな私事をひとつ。先月中旬、たまたまニューヨークを訪ねる機会があった。大雪で移動に難渋したが、結論からいうとトランプ時代に入ってもニューヨークの印象は変わっていなかった。目抜き通りの5番街に、今も家族が住むトランプタワーの警備はさすがに厳重だったが、それ以外は街の賑わいも人々の様子も変化がみられなかった。
あえて変化といえば大手書店のバーンズ&ノーブルに「反ユートピアコーナー」ができて、ジョージ・オーウェルの「1984年」や「動物農場」、アルダス・ハクスレーの「素晴らしき新世界」など反ユートピア小説が山積みになっていたことだ。戦前、ノーベル文学賞を受けたアメリカ人小説家シンクレア・ルイスの、大衆扇動家がアメリカの大統領に当選するという悪夢を描いた「It can't happen here」(この国ではそんなことは起きない)という80年前の反ユートピア小説(本邦未訳)も山積みで、衝動買いしてしまった。この小説は面白そうだが、300頁を超えるボリュームなので、このブログで紹介することはできそうもない。
そのあと訪れたストランドという大型の中古書店(新本も売る)はリベラル派の拠点だけに、入り口のドアに「難民歓迎」のメッセージが出て、店内にも「難民支持」や「反トランプ」のピンバッジが並んでいた。地下鉄を降りてホテルに戻ろうとすると、ストランド書店の紙袋を下げ、背中のリュックにも本を詰め込み、同じホテルに戻る人を見かけた。「自由なアメリカは健在」という思いを強くし、ちょっと明るい気分になった。
本書に戻ると、一線研究者による世界的なポピュリストの動向の概説としては面白いし、有益だ。ただ現在のポピュリズムをどう克服するのか、処方箋を求める立場からするとかなり物足りない。筆者が本当のところポピュリズムをどう考えているのか、克服すべき、立ち向かうべき存在だと考えるのか。あるいはそもそも民主主義に潜む影として、一定程度は許容しうると考えているかはわからない。ひょっとすると研究者としては非常に真面目に、自分の立場を鮮明に表明するのは適当でないし、得策でもないと考えているのかもしれない。
だが、現代は、日本でも多くの読者に支持される、フランスの思想家エマニュエル・トッド氏のように、進行中の事態をどう見るのか、自分の立場を明確にすることが強く求められている時代だと思う。









