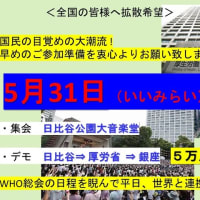吉原の秘密(その1)
平成十年に店をたたんだ吉原の引手茶屋・松葉屋について、猿若流八世家元・猿若清三郎氏が、あるところで次のように言っています。「松葉屋がなくなるということは、ちょっとやそっと何かが無くなるということでは済まないのです。我々踊りの世界、また歌舞伎、ひいては日本の芸能は、遊郭をはずしたら物語にならない。欠かせないものなのです。多くの演目の舞台となっている場所。そういう意味において、松葉屋は失ってはいけないものだったんです。それが無くなってしまったのは、大変な損失です。遊郭にも位どりというのがあり、歴史的に言えば京都・島原のほうが古いのかもしれないけれど、吉原は、遊郭の文化を発展させた、総元締。松葉屋はその玄関です」。
吉原の高級花魁は江戸の精華でした。彼女たちのまわりに自然に大名や豪商が集まり、吉原は華やかな社交場になりました。絵師や俳諧師、歌舞伎役者、戯作者なども競って吉原に出入りするようになり、その活力が歌舞伎、浮世絵、狂歌、川柳などの傑作をつぎつぎと生み、吉原には馥郁たる江戸文化が咲き誇ることになりました。松葉屋はそういう豊かな文化を生み出した吉原の玄関の役割を歴史的に果たしてきたのでした。それゆえおのずと、その豊かな文化を体現する希な存在となりました。その松葉屋がなくなるということは、すなわち、三百余年の伝統を有するひとつの大きな文化が消えてなくなるのと同じことである、と猿若清三郎は言っているのです。そのことを、彼は心から惜しんでいるのです。
これから、吉原についてあれこれとお話しします。道草を食うことも一度ならずあるとは思いますが、最後までお付き合い願えれば幸いです。これを読み終えた後、みなさんに″たしかに、猿若清三郎の言うとおりだ″と思っていただけたなら、私がこの文章を書いた目的は果たされたことになります。私としては、そのことを通じて、文化なるもののあり得べき姿かたちがどういうものであるかがつかめたら、と欲深い目論見を持っております。さらに、挑発的なことを申し上げるならば、現代のいわゆる文学者や文化人を自称する人々の抱いている文化のイメージは致命的に間違っているという思いが、私をしてこの文章を書かしめていることを白状しておきます。私は、故小沢昭一氏や『吉原酔狂ぐらし』(ちくま文庫・絶版)を書いた故吉村平吉氏などを本当の教養人としてこよなく尊敬する者であります。そんじょそこらの自称高踏派のお坊ちゃん大学教授や成り上がりの自称文学者など足元にも及びません。
では吉原について、ごく基本的なことから話しましょう。
吉原には主に、貸座敷・引手茶屋・芸者屋の三つの業種がありました。そのなかで引手茶屋は、大見世(おおみせ)に向かうお客を迎え、芸者・幇間(ほうかん)を呼んでお客をもてなし、そのあとお客を大見世に送る仕事を受け持っていました。また貸座敷は、いわゆる遊女屋のことで、六・七人から三〇人くらいの花魁をかかえお客に色事を提供するのが仕事でした。大見世は、いちばん上の等級の貸座敷で、ほかには中見世(ちゅうみせ)・小見世(こみせ)がありました。江戸時代には、さらにその下に、お歯ぐろ溝(どぶ)のそばの河岸見世(かしみせ)がありました。お歯ぐろ溝は、遊女の逃亡を防ぐために作られたものです。
私は分かったような顔をして吉原の薀蓄をたれておりますけれど、じつはいずれも『吉原はこんな所でございました』(福田利子・ちくま文庫)というすぐれもののアンチョコからちょっと言い方を変えて引いているだけであります。そんな調子ですから、お気楽に読み進めてくださるようお願いいたします。しばらく遊郭のお客にでもなったような心づもりでいてくだされば幸いです。ちなみに福田利子女史は、冒頭に登場した松葉屋の最後の女将です。
中見世・小見世についてもちょっとひとこと。往来に面した店先に遊女が居並び、格子の内側から自分の姿を見せて客を待つ張見世(はりみせ)があったころ、吉原には、登楼する客の何倍もの素見(ひやかし)の客がありましたが、張見世がなくなった昭和初年のころも、素見の客はずいぶんいたとの由。吉原大門(おうもん)をくぐり抜け、メインストリートの仲之町(なかのちょう)通りの植木柵を眺めたあと、通りから通りへ、露地から露地へと、不夜城といわれた廓のなかを、あの見世は高いとか、この見世にはいい妓(こ)がいるとか、男たちは好き放題を言いながらぶらぶらしたのでしょう。
そんないい加減な奴どもを見世に上げてしまうのが、妓夫(ぎゆう)太郎の腕の見せどころ。「ダンナ。いい妓が待っていますよ。素通りって手はありませんぜ」とかなんとか。
見世に入ると、正面に写真場があって、ショーケースのガラスの中に、花魁の上半身を写した写真が、見世の花魁の数だけ並べてありました。そのなかから、お客は好みの花魁を選ぶようになっていました。腕の良すぎる写真師の写真は、お客とお店とのトラブルの元になったそうですよ。「写真と実物とぜんぜん違うじゃないか」というわけで。
こうやって、往時の吉原の殷賑を延々と筆で描き続けるのも(少なくとも私にとっては)けっこう楽しいのですが、この文章の意図するところは、やや別のところにあるので、いささか話を転じましょう。
話は江戸時代にさかのぼります。徳川幕府公許の遊廓として吉原が誕生したのは、元和三年(一六一七年)と伝えられています。それ以前は野原のなかに、遊女屋があちらに二軒、こちらに三軒というふうに散らばっていたそうです。茶屋の主をしていた庄司甚内は、それらを一ヶ所に集めて遊廓を作ることを思いついたのでした。それで甚内は、″遊女屋が町の中に散らばっていると、自分の分際もわきまえずに遊興にふけり、身を持ち崩す者もでてくるが、遊女屋を一ヶ所に集め、長逗留ができないことにすれば放埒ができなくなる″とか、″遊女屋を一ヶ所に集めれば、娘をさらったり、養女にするからといって貧しい親から子どもをもらい受け、大きくめかけ奉公や遊女奉公に出すなどして世渡りをしている不届き者の、そのような悪行を防ぐことができる″とか、″遊女屋は世を乱す不穏分子の隠れ家になる危険がある。遊女屋を一ヶ所に集めてそれらを公許の遊廓にすれば身分の調べもでき、怪しい人物を挙げることもできる″などと理由を並べ立てて、幕府に許可願いを出しました。
この願いが出された七年後に、幕府から、いろいろな条件をつけたうえで、許可が下りました。あまり寄り道はしたくないのですが、「いろいろな条件」のなかでひとつだけ、とても面白いのがあるのでご紹介します。それは、″太夫三人を奉行所の式日ごとに奉仕に出すこと″です。これは、当番の太夫が奉行所に出向いて、琴や三味線の演奏をしたり、お茶の給仕をつとめることです。太夫というのは、容貌が人並み優れていて、諸芸にも堪能で「百人が中を十人にすぐり、十人の中より一人えらみ出すほどならでは太夫とはいひがたし」といわれたほどの、とび抜けて優れた遊女に与えられる尊称でした。奉行所に勤めるお役人たちの、取ってつけたような渋面から、あこがれの太夫を間近に見たいという可愛らしい本音が透けて見えるようですね。おのずとほほえましい光景が浮かんできます。
そのころの大見世の高級花魁は、歌舞音曲はもちろんのこと、話術に長け、生け花、茶の湯、書道、歌道、香道などの教養があって、その品格や教養などは、一般の女性が及ぶところではなかったようです。ちなみに香道とは、日本の伝統的な芸道で、一定の作法のもとに香木を焚き、立ち上る香りを鑑賞するものです。
また大見世には、江戸時代から″初会(しょかい)″″裏を返す″″馴染み″というしきたりがありました。″初会″というのは、お客が紹介者に連れられてこられた初めての日のことで、お客は芸者衆や幇間をあげて花魁の本部屋で遊びますが、寝所にまで入ることはなくそのまま帰ります。二度目を″裏を返す″と言い、初会と同じことをしてやはりそのまま帰ります。三度目ではじめて″馴染み″となって寝所に入ります。「惚れ」の機微を大切にしたのでしょう。高級花魁は、いわゆる娼婦とはかなりイメージが違う存在のようです。奉行所のお役人たちが、太夫を高嶺の花と見て無邪気に憧れた気持ちがそれなりに分かる気がします。
むろん太夫にとっても、奉行所出仕は大変に名誉なことだったので、当番に当たった前の晩は客を辞退し、翌日のお点前(てまえ)に使うためのお茶を挽きました。ここから転じて、遊女が客をとれないでいることを「お茶を引く」というようになったそうです。太夫は太夫なりに誠を尽くしたのですね。
さて、ずいぶん回り道をしたようです。遊廓設置の許可と同時に幕府から与えられた土地は、現在の日本橋堀留一丁目あたりの、葭(よし)や葦(あし)の茂る一面の湿地帯でした(一五九〇年、徳川家康が豊臣秀吉に江戸への転封を命じられて、江戸にたどり着いたとき、江戸全体が広大な湿地帯でした)。そこに続々と江戸の遊女屋が集まり、遊女屋一七軒、揚屋(あげや。引手茶屋の前身。客が遊女を呼んで遊んだ所)二四軒の遊廓ができあがりました。そこいら一帯は、葭の繁る土地であることから、″葭原″と名付けられ、縁起をかついで″葭″を″吉″に替え″吉原″となったそうです。
ご存知のように、その後江戸の人口はどんどん増えつづけました。それでいつのまにか、吉原遊廓のある場所が江戸の中心地になっていました。このままでは、風紀上も都市計画としても不都合が多いというので、幕府の命によって、移転する計画が立てられていたところ、別名振袖火事とも呼ばれる明暦の大火がおき、市中の大半が焼け、十万人以上の命が奪われました。そこで、いくつかあった候補地から浅草観音の裏地が選ばれて、移転することになりました。明暦三年(一六五七年)のことです。この″新吉原″は、昭和三十三年(一九五八年)三月三十一日、売春防止法施行前日までの約三〇〇年間、この地で遊廓としての道を歩み続けたのです。その後の吉原が、ソープランドのメッカとしていまに続いていることは、みなさまよくご存知のことでしょう。遊廓がなくなった後の吉原は、呼び名は同じでもかつての吉原とは別物と考えたほうがどうやらよさそうです。
遊廓がなくなった後のソープランドだらけの吉原で、冒頭に登場した松葉屋は、ずっと遊廓あっての松葉屋だったわけですから、経営がとてもむずかしくなりました。花魁道中、花魁ショウを企画したりして(ぜひ拝見したかったものです)、江戸初期から続く吉原文化を今日に伝え、魅力的な文化スポットとしての吉原を演出しようとして、できるだけのことはしたのですが、押し寄せる時流には勝てませんでした。基本的には、世間の無理解の壁を乗り超えることができなかったのでしょう。世間は、花魁道中や花魁ショウをいかがわしいものとして好奇の目で見たでしょうから。
話を戻しましょう。ここで注目したいのは、幕府はなぜ移転先として浅草観音の裏地の日本堤(にほんつつみ)を選んだのか、です。ここからの議論は、おおむね竹村公太郎氏の『日本史の謎は「地形」で解ける』に依拠します。
この疑問についてきちんと答えるために、私たちは、浅草の歴史について一通り押さえておく必要があります。そうすることで、「吉原の秘密」ににじり寄って行きたいと思っています。
「その1」を終えるにあたって、ひとつだけ申し上げておきたいことがあります。それは、吉原の花魁たちの身だしなみについてです。松葉屋の福田利子女史によれば、花魁たちはみな、お客にゆだねる我が身を常に清潔に保つためにまめに入浴するので、体臭がなくなってしまうそうです。女史は、そのことを当然のこととしてごく普通に言っています。私は、花魁たちに体臭がないという事実と女史の平静な語り口とに不意打ちを喰らったような衝撃を受けました。彼女たちは、体臭がなくなるほどに身を清潔に保つことで、無意識のうちに、心の清潔を保とうとしているのです。その自然体のけなげな心根に、私は日本女性のつつましさの原風景を見る思いがします。