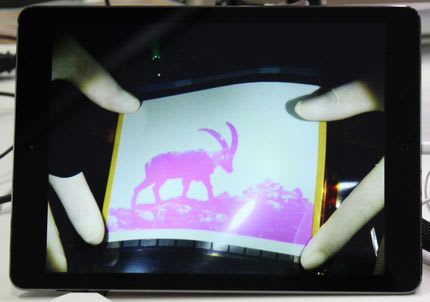先日、知的財産活用のフォーラムが開催された際に、その中の講演で、大阪大学発ベンチャー企業のクオンタムバイオシステムズ(Quantum Biosystems、大阪市)のお話を伺いました。
同社の代表取締役社長・COE(最高経営責任者)を務めている本蔵俊彦さんは熱烈に同社の製品開発とその事業化の独創性を語りました。

同社は、DNA(デオキシリボ核酸)の塩基配列を解析する第四世代のDNAシークエンサー(塩基配列解析装置)の装置開発を進めています。いくらかDNAシークエンサーのことをご存じの方は、日本はこの分野では後塵を拝していると思っています。
ところが本蔵さんによると、「製品開発中の第四世代のDNAシークエンサーは“破壊的イノベーション”を起こす可能性を秘めている」といいいます。「1990年代に製品化され始めたDNAの塩基配列を解析するDNAシークエンサーの進化は速く、解析の仕組みが異なる第3世代まで製品化されている。この第3世代までは、欧米が先行しました。しかし、「まだ決定打といえるDNAシークエンサーは登場していない」といい、そして「当社が現在開発中の解析装置が実用化されれば、一気に世界の先頭に立てる」と力説します。
DNAシークエンサーについては、「米国大手コンサルティング企業のマッキンゼー・アンド・カンパニーが効率的な次世代DNAシークエンサーが製品化されて、DNA塩基配列解析が1時間と短時間で100米ドルと低コストで可能になれば、1年当たりに2600万人に最適な治療を行うオーダーメイド治療に貢献でき、その経済効果は1年当たり70兆から160兆円との試算結果を発表している」と、“破壊的イノベーション”を起こす製品であると予想していると、本蔵さんは伝えます。
クオンタムバイオシステムズは2013年1月7日に創業されました。同社の技術シーズは、大阪大学産業科学研究所の川合知二特任教授や谷口正輝教授などが参加して2005年から始めた最先端研究開発支援プログラム(内閣府が推進)の「1分子解析技術を基盤とした革新ナノバイオデバイスの開発研究」プログラムが産み出したものです。
この技術シーズは、微細な空間でのトンネル電流を利用してDNAの塩基配列を解析する手法です。実は、これまでにも米国のIBMや韓国のサムソン電子、米国のインテルなどという蒼々たる企業が挑戦しましたたが成功していない難題です。
本蔵さんは「トンネル電流を実現する超微細電極と超微細電流測定が必須になる点が難しい課題になっていた」と説明します。
同社が製品化を図っている塩基配列解析の大まかな原理は、1本のDNAだけが流れる流路をつくり、その流れる速さを制御します。この1本のDNAが約1nm間隔の電極の間を通過する際に、1塩基分子の電気抵抗を連続的に測ることで、塩基配列を解析します。この基本原理を用いて、川合さんと谷口さんの大阪大の研究グループが2012年7月に塩基配列解析が可能であることを実証したことから、本蔵社長は「創業を決意した」と経緯を説明します。
本蔵さんは当時、経済産業省が中心になってつくった産業革新機構(東京都千代田区)の戦略投資部ディレクターとして、投資先を調査し投資する業務に従事していました。2012年5月に大阪大学の川合さんと谷口さんの研究開発グループが発表した開発成果を本蔵さんは知って、破壊的イノベーションを起こす可能性があると考えたそうです。、
本蔵さんは産業革新機構をすぐに退社し、クオンタムバイオシステムズ社を創業するための資金集めを始めたそうです。そして2013年1月7日に同社を創業しました。
本蔵さんによると、作製したプロトタイプは1台当たり200万円程度で製品化することを目指しています。その低価格化のカギとなる使い捨ての半導体チップは1個当たり約5000円をメドに実用化を図っているそうです。この半導体チップは「最終的には1個50円を目指している」とのことです。
現在、製品化されているDNAシークエンサーは日本円換算で6000万円から1億円程度と高価なので、製品化すればかなりの価格破壊をもたらすとも、付け加えます。
同社の創業時から日本市場を含めたグローバル市場向けの事業戦略を立てています。製品開発メンバーも国籍、年齢などに制限を設けず、実力がある人材を集めて進めているそうです。このため、同社での主要言語は英語で、Webサイトも英語表記にして、全世界に情報を発進しています。

また、測定器メーカーや半導体メーカー、名古屋大学などと連携するなどの外部リソースを活用し、製品化・事業化を早める工夫をこらしているそうです。
同社の代表取締役社長・COE(最高経営責任者)を務めている本蔵俊彦さんは熱烈に同社の製品開発とその事業化の独創性を語りました。

同社は、DNA(デオキシリボ核酸)の塩基配列を解析する第四世代のDNAシークエンサー(塩基配列解析装置)の装置開発を進めています。いくらかDNAシークエンサーのことをご存じの方は、日本はこの分野では後塵を拝していると思っています。
ところが本蔵さんによると、「製品開発中の第四世代のDNAシークエンサーは“破壊的イノベーション”を起こす可能性を秘めている」といいいます。「1990年代に製品化され始めたDNAの塩基配列を解析するDNAシークエンサーの進化は速く、解析の仕組みが異なる第3世代まで製品化されている。この第3世代までは、欧米が先行しました。しかし、「まだ決定打といえるDNAシークエンサーは登場していない」といい、そして「当社が現在開発中の解析装置が実用化されれば、一気に世界の先頭に立てる」と力説します。
DNAシークエンサーについては、「米国大手コンサルティング企業のマッキンゼー・アンド・カンパニーが効率的な次世代DNAシークエンサーが製品化されて、DNA塩基配列解析が1時間と短時間で100米ドルと低コストで可能になれば、1年当たりに2600万人に最適な治療を行うオーダーメイド治療に貢献でき、その経済効果は1年当たり70兆から160兆円との試算結果を発表している」と、“破壊的イノベーション”を起こす製品であると予想していると、本蔵さんは伝えます。
クオンタムバイオシステムズは2013年1月7日に創業されました。同社の技術シーズは、大阪大学産業科学研究所の川合知二特任教授や谷口正輝教授などが参加して2005年から始めた最先端研究開発支援プログラム(内閣府が推進)の「1分子解析技術を基盤とした革新ナノバイオデバイスの開発研究」プログラムが産み出したものです。
この技術シーズは、微細な空間でのトンネル電流を利用してDNAの塩基配列を解析する手法です。実は、これまでにも米国のIBMや韓国のサムソン電子、米国のインテルなどという蒼々たる企業が挑戦しましたたが成功していない難題です。
本蔵さんは「トンネル電流を実現する超微細電極と超微細電流測定が必須になる点が難しい課題になっていた」と説明します。
同社が製品化を図っている塩基配列解析の大まかな原理は、1本のDNAだけが流れる流路をつくり、その流れる速さを制御します。この1本のDNAが約1nm間隔の電極の間を通過する際に、1塩基分子の電気抵抗を連続的に測ることで、塩基配列を解析します。この基本原理を用いて、川合さんと谷口さんの大阪大の研究グループが2012年7月に塩基配列解析が可能であることを実証したことから、本蔵社長は「創業を決意した」と経緯を説明します。
本蔵さんは当時、経済産業省が中心になってつくった産業革新機構(東京都千代田区)の戦略投資部ディレクターとして、投資先を調査し投資する業務に従事していました。2012年5月に大阪大学の川合さんと谷口さんの研究開発グループが発表した開発成果を本蔵さんは知って、破壊的イノベーションを起こす可能性があると考えたそうです。、
本蔵さんは産業革新機構をすぐに退社し、クオンタムバイオシステムズ社を創業するための資金集めを始めたそうです。そして2013年1月7日に同社を創業しました。
本蔵さんによると、作製したプロトタイプは1台当たり200万円程度で製品化することを目指しています。その低価格化のカギとなる使い捨ての半導体チップは1個当たり約5000円をメドに実用化を図っているそうです。この半導体チップは「最終的には1個50円を目指している」とのことです。
現在、製品化されているDNAシークエンサーは日本円換算で6000万円から1億円程度と高価なので、製品化すればかなりの価格破壊をもたらすとも、付け加えます。
同社の創業時から日本市場を含めたグローバル市場向けの事業戦略を立てています。製品開発メンバーも国籍、年齢などに制限を設けず、実力がある人材を集めて進めているそうです。このため、同社での主要言語は英語で、Webサイトも英語表記にして、全世界に情報を発進しています。

また、測定器メーカーや半導体メーカー、名古屋大学などと連携するなどの外部リソースを活用し、製品化・事業化を早める工夫をこらしているそうです。