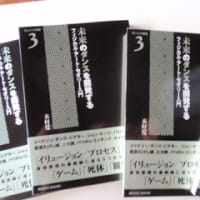30日、Aと一年ぶりくらいに一泊の小旅行。伊東の旅館「三浜館」を宿にする。
翌日、レンタカーで小刻みに一碧湖やその近くの宇宙美術館(?!)、城ヶ崎海岸などまわって、昼は、北川(ほっかわ)温泉で、海の見えるというか海岸にある黒根岩温泉へ。
そして最後に、まだ時間があるので「伊豆バイオパーク」なる不思議なテーマパークへ不意に行ってみたのだった。
ここまでは個人的にはきわめて楽しかったのだけれど前フリ。
そこで、久しぶりに沢山の種類の動物を見た、ということが書きたかった。
動物というのは、よく見るときわめて異常だ。気づくとツノとか生えてる。キリンの頭にもへんな突起物が二つある、そんなこと普段は見過ごして「かわいい」って無邪気に思ってたりするのだけれど。キリンならば、そもそもなんだ?あの皮の変なタイルみたいな模様は?あんな模様とか、へんな突起物のある人間があらわれたらそりゃホラーだ。別のところに眼を向ければ、ラクダはいつまでたっても左右に揺れ続けているけれど、いったい何を考えているのだ?
人間の子供たちは彼らを見てはしゃぐ。「かわいいー、ぎゃーっ!」って叫びがサファリバスに響く。けれど、まだ言葉の話せない人間の幼児の場合、巨大なキリンにキョトンとしてただただ驚いていたりする。そう、「かわいい」と思えるには人間化していなくちゃならない、のだ。で、その人間化の装置をちょっと外して彼らを見つめると、その幼児のように得体の知れない異形に驚かずにはおられなくなる。
ディズニーの『バンビ』みたいな人間に都合のよい動物と人間との適合的関係は、現実には基本成立するわけはないのだ。ゾウはダンボではない。だから、いくら呼びかけても徹底的にこちらを無視し続ける。それでも、人間というのはどうしても動物たちに応えてもらいたがるものなのだ、「ふれあいランド」と称する小スペースでは、子供たちがウサギやアルマジロ(昆虫みたいな背中!)を抱えたり、追いかけたりしているけれど、ともかく子供たちは動物に応答して欲しいので、いつの間にか暴力的になったりしている。
えっと、何が言いたいかというと。
動物はぼくたちにとって(身勝手な)ファンタジーの存在なのだ、まず。「かわいい!」と思いこみ、空想と妄想を勝手に投げかけるものなのだ。けれども、本当の動物はそんな人間の都合のために生きているわけではないので、その妄想の暴力から逃げたり無視したりしている。でそういう一方的恋愛から少し距離を取ってじっくり見始めると、実は本当の動物はかなりグロテスク。ひとはグロテスクなところを無視したいために動物を「かわいい!」と思い込んでいるのかも知れない、と考えたくもなる、それくらい本当はグロテスク。人間の身体をベースに考えれば、ツノとかシッポとかシマシマとかハネとか、よくみれば動物のパーツはすべてイレギュラーであって、いわば怪獣なのだ、キモイ怪獣。それでも、そのキモさを露出する怪獣というのは「かわいい」とは別の魅力を人間に発散してもいるわけ、で。あえていえばそれは奇想の魅力だ。
コスプレでうさぎの耳とかあるけれども、そのあたりのアイディアは「かわいい」に逃げ込もうとしている奇想なわけで、むしろ「サイ角」とかがコスプレの一アイテムとして流行出したりなんかすると(額につけちゃったり)、「かわいい」よりも「奇想」が上回る事態発生ということになるのではないだろうか。怪獣が人間の抱くイメージの錯綜を基にしているとすれば、動物は神の気まぐれの産物。そんな奇想への耽溺を経験する場として動物園はあるようにさえ思ったのだ。
翌日、レンタカーで小刻みに一碧湖やその近くの宇宙美術館(?!)、城ヶ崎海岸などまわって、昼は、北川(ほっかわ)温泉で、海の見えるというか海岸にある黒根岩温泉へ。
そして最後に、まだ時間があるので「伊豆バイオパーク」なる不思議なテーマパークへ不意に行ってみたのだった。
ここまでは個人的にはきわめて楽しかったのだけれど前フリ。
そこで、久しぶりに沢山の種類の動物を見た、ということが書きたかった。
動物というのは、よく見るときわめて異常だ。気づくとツノとか生えてる。キリンの頭にもへんな突起物が二つある、そんなこと普段は見過ごして「かわいい」って無邪気に思ってたりするのだけれど。キリンならば、そもそもなんだ?あの皮の変なタイルみたいな模様は?あんな模様とか、へんな突起物のある人間があらわれたらそりゃホラーだ。別のところに眼を向ければ、ラクダはいつまでたっても左右に揺れ続けているけれど、いったい何を考えているのだ?
人間の子供たちは彼らを見てはしゃぐ。「かわいいー、ぎゃーっ!」って叫びがサファリバスに響く。けれど、まだ言葉の話せない人間の幼児の場合、巨大なキリンにキョトンとしてただただ驚いていたりする。そう、「かわいい」と思えるには人間化していなくちゃならない、のだ。で、その人間化の装置をちょっと外して彼らを見つめると、その幼児のように得体の知れない異形に驚かずにはおられなくなる。
ディズニーの『バンビ』みたいな人間に都合のよい動物と人間との適合的関係は、現実には基本成立するわけはないのだ。ゾウはダンボではない。だから、いくら呼びかけても徹底的にこちらを無視し続ける。それでも、人間というのはどうしても動物たちに応えてもらいたがるものなのだ、「ふれあいランド」と称する小スペースでは、子供たちがウサギやアルマジロ(昆虫みたいな背中!)を抱えたり、追いかけたりしているけれど、ともかく子供たちは動物に応答して欲しいので、いつの間にか暴力的になったりしている。
えっと、何が言いたいかというと。
動物はぼくたちにとって(身勝手な)ファンタジーの存在なのだ、まず。「かわいい!」と思いこみ、空想と妄想を勝手に投げかけるものなのだ。けれども、本当の動物はそんな人間の都合のために生きているわけではないので、その妄想の暴力から逃げたり無視したりしている。でそういう一方的恋愛から少し距離を取ってじっくり見始めると、実は本当の動物はかなりグロテスク。ひとはグロテスクなところを無視したいために動物を「かわいい!」と思い込んでいるのかも知れない、と考えたくもなる、それくらい本当はグロテスク。人間の身体をベースに考えれば、ツノとかシッポとかシマシマとかハネとか、よくみれば動物のパーツはすべてイレギュラーであって、いわば怪獣なのだ、キモイ怪獣。それでも、そのキモさを露出する怪獣というのは「かわいい」とは別の魅力を人間に発散してもいるわけ、で。あえていえばそれは奇想の魅力だ。
コスプレでうさぎの耳とかあるけれども、そのあたりのアイディアは「かわいい」に逃げ込もうとしている奇想なわけで、むしろ「サイ角」とかがコスプレの一アイテムとして流行出したりなんかすると(額につけちゃったり)、「かわいい」よりも「奇想」が上回る事態発生ということになるのではないだろうか。怪獣が人間の抱くイメージの錯綜を基にしているとすれば、動物は神の気まぐれの産物。そんな奇想への耽溺を経験する場として動物園はあるようにさえ思ったのだ。