
現在進めている私のPhD論文のテーマの舞台設定としてかなり有益だとの指導教授のアドバイスを受けて最近読んでいたのがこの本です。もともとは、Collingwood Studiesの編集者の一人を務める指導教授が、次号のための書評の一つとして投稿されてきた原稿を読んで知ったのが私へのアドバイスへのきっかけだったそうで、ちょうど運よく先月その書評自体の執筆者・ヨーク大のB准教授がカーディフを訪れた際にいろいろ話をしてもらったときも、この本はお勧めだと言われてもいました。
* *
いわゆる分析哲学の伝統は、20世紀哲学の一大潮流のひとつであり、とりわけ英米圏では時に「分析哲学にあらずば哲学にあらず」というほどの隆盛を未だに誇っている。このことはここ英国でも同様で、大学の哲学科では分析系が圧倒的多数を占め、観念論の伝統は細々と息づいているに過ぎない。しかし、これほどまでに優勢を誇る分析哲学の起源についての哲学史的研究はつい1980年代後半になって本格的に始まったに過ぎず、このことも関係してか、20世紀英米哲学における観念論的伝統の存在はほとんど省みられてこなかった。この本は、そんな分析哲学の起源へ遡及し、分析哲学の始祖の一人であるバートランド・ラッセルと、当時落日を迎えつつあったイギリス観念論の最後の巨人・F.H.ブラッドリーの間の論争に焦点を当てることによって、(著者によれば)不当に無視・軽視されてきた20世紀における観念論の意義についてより公平な再評価を試みた作品である。
著者は、ラッセルが初期の観念論から実在論へと舵を切った1903年頃から1924年のブラッドリーの死まで二人の間で行なわれた論争を、英米哲学における一元論・観念論から多元論・実在論への広範な移行における歴史・哲学的な核心と位置づける。そして、この論争の中心論題としてjudgmentをめぐる議論を抽出する。すなわち、「A is B」という判断をするときに前提となるAとBの間の論理的結合の性質をめぐって、ラッセルは当初、この論理的関係(relation)は命題の本来的属性であるとの立場から、この関係性はrealであると主張するが、一方ブラッドリーはそれに異議を唱えるのである。つまり、この問題の焦点は、「relationはrealかidealか」という実在論/観念論論争にあることになる。
著者は、1900年代から1910年代にかけてのラッセルの著作を丹念に読み込むことにより、ラッセルがブラッドリーとの論争のなかで当初の素朴実在論の修正を余儀なくされ、最終的には1919年、ウィトゲンシュタインの『論考』の影響もあって素朴実在論の完全な断念に追い込まれたことを描き出している。このラッセルの素朴実在論の断念の一因として、著者はfalse judgmentの問題を指摘する。すなわち、relationがrealであるならば、誤った命題における推論もrealだということになってしまうからである。ブラッドリーは、このfalse judgmentの問題に対応するために、当時大方の哲学者がどちらかにコミットしていた真理対応説も妥当説もとらず、真理の程度(degree of truth)を認めることによって独自の真理説を模索したようである。この点で、ブラッドリーが真理妥当説を取っていたという従来の哲学史的常識はステレオタイプでありいかなる文献的根拠もないと著者は断言する。
また、初期ラッセルの素朴実在論のもう一つの問題として著者は、realな命題構成要素と、文法は言語が記述するrealityにいかなる影響も及ぼさないとする彼の文法の透明性の主張との組み合わせは存在論的問題を招来すると指摘する。つまり、日常言語における真実は、けっして言語の記述が現実世界をあるがままに表現しているとは言えないからである。この文法と存在論の問題においても、ラッセルはブラッドリー側の観念論的教義に戻ることを余儀なくされていると指摘するのである。このように、ラッセルが対決を試みていたまさにその観念論への回帰を余儀なくされている点があることを通して著者は、従来の分析哲学vs観念論哲学という20世紀初期の英米哲学の対決図式は、再考されるべきだと示唆するのである。もちろんこれは、あくまでこれまでの図式が余りに単純すぎてブラッドリーらの観念論が過小評価されていたことを再考するべきだという主張であって、いかなる意味でも観念論の復興を主張するものではないことは付言しておく。
最後に、コリングウッドとのかかわりにおいて、自身のテーマの「舞台設定」として示唆深いと思われる点を列挙しておく。
(1)コリングウッドが素朴実在論との対決を通して自らの哲学思考を開始し模索していたまさに同時期に、実在論者ラッセルと観念論者ブラッドリーという両陣営の巨人が論争をしていたという事実。
(2)この両者の論争の争点は、relationがrealかidealかというまさに実在論/観念論論争であり、素朴実在論者ラッセルが行き詰るのは存在論的問題であった。この点、コリングウッドの葛藤の争点も当時まさにこの実在論/観念論という軸であり、存在論的問題を(また違う形であるものの)抱えている点でも共通している。
(※1916年のコリングウッドの初めての単行本Religion and Philosophyでは、judgmentについてブラッドリーの定義に暫定的なから従う旨の脚注があり、またその後の1917~1923年の間の初期草稿群にも、judgmentについて論じたものが少なからず含まれていることから、コリングウッド自身も、このラッセルとブラッドリーの論争に意識的であった蓋然性が高い)
(3)コリングウッドが当時克服を試みていたいわゆるNew Realismは、1900年代から1920年頃まで盛んだった素朴実在論であり、1919年のラッセルによるこの立場の放棄などもありその後は一種のEmpiricismへのシフトし取って代わられた短命の哲学的潮流だった。コリングウッドはこの流れにユニークな仕方で克服を試みた一人と位置づけることもできる。
(4)著者がラッセルの若き日の書簡を引用しつつ述べるように、もしもラッセルの観念論への恐れが彼がある意味魅せられていた数学の完全な理論性が'life, death, human sordidness'によって汚染されることへの恐れだとすれば、コリングウッドはむしろ、この人間的なるものを積極的に哲学に取り込むべくhistoryを中心とした形而上学体系の構想へと歩を進めたと説明することもできるかもしれない。
また、この本の構成自体も、論争史という点で私のテーマにも通じるところがあり、自身の論文の構成にも大いに参考になる本であった。
* * *
いずれにしてもこの本は、指導教授やB准教授の示唆の通り、私の論文の舞台設定という点で、かなり私の無知を救ってくれ更なる問題意識の深化の手がかりとして実に興味深いものであり、短期間で一気に読んでしまいました。今後は、この本が参照している先行研究などにも目を通しつつ、舞台設定を行なう論文の第1章の構成をもっともっと堅固なものとしていきたいと思います。
* *
いわゆる分析哲学の伝統は、20世紀哲学の一大潮流のひとつであり、とりわけ英米圏では時に「分析哲学にあらずば哲学にあらず」というほどの隆盛を未だに誇っている。このことはここ英国でも同様で、大学の哲学科では分析系が圧倒的多数を占め、観念論の伝統は細々と息づいているに過ぎない。しかし、これほどまでに優勢を誇る分析哲学の起源についての哲学史的研究はつい1980年代後半になって本格的に始まったに過ぎず、このことも関係してか、20世紀英米哲学における観念論的伝統の存在はほとんど省みられてこなかった。この本は、そんな分析哲学の起源へ遡及し、分析哲学の始祖の一人であるバートランド・ラッセルと、当時落日を迎えつつあったイギリス観念論の最後の巨人・F.H.ブラッドリーの間の論争に焦点を当てることによって、(著者によれば)不当に無視・軽視されてきた20世紀における観念論の意義についてより公平な再評価を試みた作品である。
著者は、ラッセルが初期の観念論から実在論へと舵を切った1903年頃から1924年のブラッドリーの死まで二人の間で行なわれた論争を、英米哲学における一元論・観念論から多元論・実在論への広範な移行における歴史・哲学的な核心と位置づける。そして、この論争の中心論題としてjudgmentをめぐる議論を抽出する。すなわち、「A is B」という判断をするときに前提となるAとBの間の論理的結合の性質をめぐって、ラッセルは当初、この論理的関係(relation)は命題の本来的属性であるとの立場から、この関係性はrealであると主張するが、一方ブラッドリーはそれに異議を唱えるのである。つまり、この問題の焦点は、「relationはrealかidealか」という実在論/観念論論争にあることになる。
著者は、1900年代から1910年代にかけてのラッセルの著作を丹念に読み込むことにより、ラッセルがブラッドリーとの論争のなかで当初の素朴実在論の修正を余儀なくされ、最終的には1919年、ウィトゲンシュタインの『論考』の影響もあって素朴実在論の完全な断念に追い込まれたことを描き出している。このラッセルの素朴実在論の断念の一因として、著者はfalse judgmentの問題を指摘する。すなわち、relationがrealであるならば、誤った命題における推論もrealだということになってしまうからである。ブラッドリーは、このfalse judgmentの問題に対応するために、当時大方の哲学者がどちらかにコミットしていた真理対応説も妥当説もとらず、真理の程度(degree of truth)を認めることによって独自の真理説を模索したようである。この点で、ブラッドリーが真理妥当説を取っていたという従来の哲学史的常識はステレオタイプでありいかなる文献的根拠もないと著者は断言する。
また、初期ラッセルの素朴実在論のもう一つの問題として著者は、realな命題構成要素と、文法は言語が記述するrealityにいかなる影響も及ぼさないとする彼の文法の透明性の主張との組み合わせは存在論的問題を招来すると指摘する。つまり、日常言語における真実は、けっして言語の記述が現実世界をあるがままに表現しているとは言えないからである。この文法と存在論の問題においても、ラッセルはブラッドリー側の観念論的教義に戻ることを余儀なくされていると指摘するのである。このように、ラッセルが対決を試みていたまさにその観念論への回帰を余儀なくされている点があることを通して著者は、従来の分析哲学vs観念論哲学という20世紀初期の英米哲学の対決図式は、再考されるべきだと示唆するのである。もちろんこれは、あくまでこれまでの図式が余りに単純すぎてブラッドリーらの観念論が過小評価されていたことを再考するべきだという主張であって、いかなる意味でも観念論の復興を主張するものではないことは付言しておく。
最後に、コリングウッドとのかかわりにおいて、自身のテーマの「舞台設定」として示唆深いと思われる点を列挙しておく。
(1)コリングウッドが素朴実在論との対決を通して自らの哲学思考を開始し模索していたまさに同時期に、実在論者ラッセルと観念論者ブラッドリーという両陣営の巨人が論争をしていたという事実。
(2)この両者の論争の争点は、relationがrealかidealかというまさに実在論/観念論論争であり、素朴実在論者ラッセルが行き詰るのは存在論的問題であった。この点、コリングウッドの葛藤の争点も当時まさにこの実在論/観念論という軸であり、存在論的問題を(また違う形であるものの)抱えている点でも共通している。
(※1916年のコリングウッドの初めての単行本Religion and Philosophyでは、judgmentについてブラッドリーの定義に暫定的なから従う旨の脚注があり、またその後の1917~1923年の間の初期草稿群にも、judgmentについて論じたものが少なからず含まれていることから、コリングウッド自身も、このラッセルとブラッドリーの論争に意識的であった蓋然性が高い)
(3)コリングウッドが当時克服を試みていたいわゆるNew Realismは、1900年代から1920年頃まで盛んだった素朴実在論であり、1919年のラッセルによるこの立場の放棄などもありその後は一種のEmpiricismへのシフトし取って代わられた短命の哲学的潮流だった。コリングウッドはこの流れにユニークな仕方で克服を試みた一人と位置づけることもできる。
(4)著者がラッセルの若き日の書簡を引用しつつ述べるように、もしもラッセルの観念論への恐れが彼がある意味魅せられていた数学の完全な理論性が'life, death, human sordidness'によって汚染されることへの恐れだとすれば、コリングウッドはむしろ、この人間的なるものを積極的に哲学に取り込むべくhistoryを中心とした形而上学体系の構想へと歩を進めたと説明することもできるかもしれない。
また、この本の構成自体も、論争史という点で私のテーマにも通じるところがあり、自身の論文の構成にも大いに参考になる本であった。
* * *
いずれにしてもこの本は、指導教授やB准教授の示唆の通り、私の論文の舞台設定という点で、かなり私の無知を救ってくれ更なる問題意識の深化の手がかりとして実に興味深いものであり、短期間で一気に読んでしまいました。今後は、この本が参照している先行研究などにも目を通しつつ、舞台設定を行なう論文の第1章の構成をもっともっと堅固なものとしていきたいと思います。














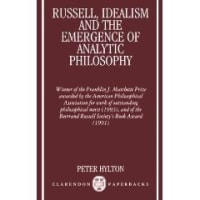
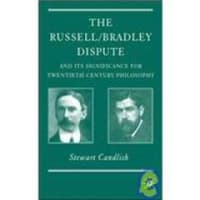




確かに、この舞台設定を知るか知らないかで、論文の切り口とか説得力はだいぶ変わってきそうですねー。
実在論/観念論論争ってベーシックなところだと思いますが、僕やっぱよくわかってないんですよね。読んでて、「あーあれか」と思っても「あれ」から先が出てこない、この不甲斐なさ…。
いや~、僕も日本でアプライのための研究計画書を書いていたときは結構気軽にテーマにしちゃった感がありましたが、じっさい、中世の普遍論争とかにも遡る哲学上の大問題だよね。あらゆる哲学の諸分野のあらゆる局面で、この実在論/観念論という軸は考えることができるので、広げたらきりがありません(汗 実際、形而上学から論理学、道徳哲学、歴史哲学、神学に至るまで、この時期のコリングウッドも縦横にこれを軸に論じちゃってます。また、idealism/materialismなんちゅう類似の軸もあったりして…。(これはより存在論的と思われますが)
あと、コンテクスト的にも、当時この実在論/観念論という軸はかなりホットな論争の的だったみたいです。
まあでも、メジャーな論点だけに、これを取っ掛かりにすれば他の全然関係ない哲学者の言うことも以前よりは分かるようになったので、こういうテーマを選んだのはよかったんだろうね。