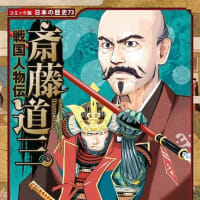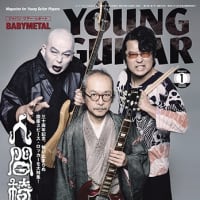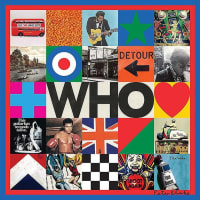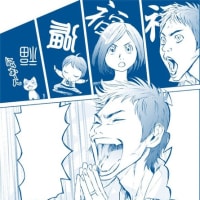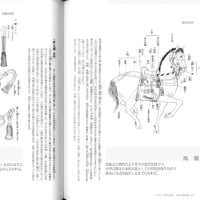「イメージ(=妄想)」が最優先された作品というのは概して、大衆の関心をよばない。
ゴダールや、カサベテスや、キアロスタミの腰の抜けるような凄い映画が、『踊るなんとか』よりヒットしないのが市場の理というものだ。
しかし、「イメージ」だけで出来上がったような『ハウルの動く城』はあれだけのヒットをした。
一般のお客が喜びそうな「えさ」が、作品の内外にちりばめられていたとはいえ、やはりそれはすんばらしいことといえる。
『ハウル』の代表的「イメージ」は、やはり「星にぶつかった少年」だろうが、そのちょっと前の、ソフィーが時間を逆行し、水車小屋(でしたっけ?)の室内に到着したそのBG(背景)にも、おれはどきりとした。
これは、おれが何度観ても号泣してしまう(笑)『アルプスの少女ハイジ』の第33話「ゆうれい騒動」で、うつ病に追い詰められたハイジがフランクフルトで幻視するアルムの山小屋の室内BGとだぶったからだ。
この辺からこの映画、わたくしずっと泣きっぱなしでした。
それは、宮崎監督の「イメージ」の、衒いのない強靭なロマンチシズムに打ちのめされて泣いたのデス。
‥‥‥‥‥‥
泣いてばかりでもどうかと思うので、ハウルの「イメージ」で重要なもう一つが、「戦争」である。
空襲シーンの異常なテンションは、宮崎氏の幼少期の記憶に直結しているのだろうが、登場人物のハウルをさえ、素朴な特攻少年に変質させた。
あの、アイロニー以外の何ものでもない「ぼくには守るものができた。きみだ!」(でしたっけ?)というハウルの台詞に、背筋が寒くなったのはどうも少数な気がして不思議だ。
ハウルが守ろうとしているもの(ソフィーの部屋)を無くすために、ソフィーが頑張るというその後のアナーキーな展開を、どれだけのお客が理解し、得心したんだろうか(謎)。
要するにこれは『ハウル』制作中に勃発したイラク戦争への、宮崎氏の痛烈な異議申し立てに他ならず、氏の面目躍如といったところだろう。
戦争への言及は宮崎作品には必須の条項だが、『ハウル』ほど戦争に対して、冷笑的で唾棄するように描いた作品はなかったように思う。
宮崎駿氏がイラク戦争をどうみていたか───それがラストシーンの、「このくだらない戦争を終わらせましょう」(うろ覚え)という、唖然とする台詞にあらわれているのだろう。
つづく?