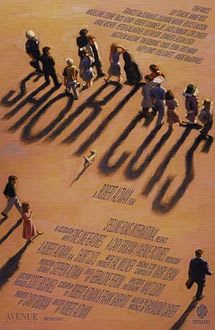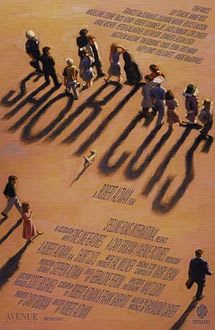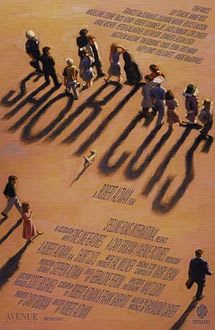世間では、1985年の『バック・トゥ・ザ・フューチャー』30周年の話題が語られている。正確には、89年の『2』に描かれた「2015年」と現在を比較する話題なのだが、この影に隠れてると思うのが、テリー・ギリアムの『未来世紀ブラジル』(85/日本公開は86年)だ。
近未来の超管理社会を舞台に、個人性の剥奪と自由の希求、テロリズムと飛翔願望をドス黒い風刺と共に描破する悪夢の造形美術。そんな『ブラジル』が予見した悪夢の未来こそ実は「いまっぽい」のではないか。21世紀は『バック・トゥ・ザ・フューチャーPART2』が描いた2015年は、まるでつくば万博(1985年だ)かユニバーサル・スタジオやディズニーランドにでもありそうなテーマパーク。つまり「楽しい未来」で、視角的には『バック・トゥ・ザ・フューチャーPART2』に登場する「未来像」がテーマパーク的な清潔さにおいて「いま」に近いかもしれないが、いまの内実はテロ対策と称した管理体制ばかりが進んでちっとも「楽しく」はない。
だから『ブラジル』の30周年にも注目してあげたいわけで、今年はギリアムの新作『ゼロの未来』が観れたけども、どういうわけかあまり印象に残らなかったし、『ブラジル』は多分、もう2度と再現出来ないだろうギリアムのアナーキーな空想力が最も美しく羽ばたいた異能の大作だったのだから。

『ブラジル』は、ロバート・アルトマンの『バード★シット』(70)との繋がりも見られる。が、いかにも70年代初頭的な『バード★シット』の飛翔願望とその失墜と比較したとき、『ブラジル』に描かれた極度の閉塞状況はやはり80年代に似つかわしかったと思える。なぜなら、81年に『ニューヨーク1997』があり、82年に『ブレードランナー』、84年にジョージ・オーウェルの小説をマイケル・ラドフォードが映画化した『1984』が公開されたあと真打ち的に登場してきたからだ。アルトマンのカラフルなポップアートは閉塞は閉塞でも笑いのめして打ち破らんとする不遜で軽やかなエネルギーが横溢していたが、スコットやギリアムのそれはより重たく、うんざりするほど辛気臭く、よって絶望的だった。
絶望を絶望として認識し、誇張された想像力を駆使し表現することこそ、レーガンの能天気で非現実的な政治観、社会観、世界観を前にした表現者たちに出来る唯一の抵抗術だったのかも知れない。
『バック・トゥ・ザ・フューチャー』と『未来世紀ブラジル』は対照的な未来映画で、前者がすこぶる陽性であるのに対して後者は陰性。『ブラジル』が提示する未来は悪夢そのもの、なにか悪い冗談でも見ているかのようなブラックユーモアが横溢する作品であった(その点でキューブリックの先駆的な『時計じかけのオレンジ』を連想する)。


80年代は光と影のコントラストで、その落差があまりにもハッキリしているのでその性格が分かりやすい(その分かりやすさゆえに分かりにくくもあるところが面妖な時代だ)。
日本では85~86年のあいだに公開された『バック・トゥ・ザ・フューチャー』と『未来世紀ブラジル』が示した個性の落差はあまりにも大きく、ゆえに鮮烈な印象だった。82年の『E.T.』と『ブレードランナー』の好対照を思わせる。翌86年の『トップガン』(トニー・スコット)と『プラトーン』(オリヴァー・ストーン)もそうだが、いかにもロナルド・レーガン政権時代の80年代を代表する2本の映画『バック・トゥ・ザ・フューチャー』のマイケル・J・フォックスと『トップガン』のトム・クルーズが、大スターの座につくとそれぞれ、むしろアンチ・レーガンのシリアスなベトナム戦争映画『カジュアリティーズ』(89、ブライアン・デ・パルマ)と『7月4日に生まれて』(89、オリヴァー・ストーン)にも出演したことも興味深い出来事だった(80年代における60年代的なるものとはベトナムだった)。単なる賞狙いや批評家への目配せと捉える向きもあったが、『プラトーン』に出たチャーリー・シーンなど逆に『メジャーリーグ』(89)みたいなコメディでヒットを飛ばすわけで、この時代はスターは映画的・政治的な左右(=光と影)のバランスに目配せして出演作を選んでおく必要があったのかもしれない。
80年代半ばはベトナム戦争終結から10年ほどで、あらためてあの戦争を検証する機運が出てきていた。そんななか「ベトナム戦争映画」は流行のひとつとなり――米兵によるベトナム人少女強姦殺人事件を題材にした『カジュアリティーズ』を除けば――興行的な成功を収めていたし、別の言い方をすれば、いずれも明暗のハッキリした分かりやすい作品であり、その限りにおいて受け入れられることも多かった。(ちなみに86年の年間ボックスオフィス・チャートの1位は『トップガン』、2位は『クロコダイル・ダンディ』、3位は『プラトーン』である。当時『プラトーン』は「プラトーン現象」と呼ばれる大ロングラン作となった)。


そんな80年代という時代には、例えばロバート・アルトマン的な「灰色の世界」が馴染まなかったのも致し方ないことであった。マイケル・チミノの『天国の門』(80)がユナイテッド・アーティスツ社を倒産に追い込んで以来、ほとんどの70年代ニューシネマ勢の監督が失速、ハリウッドは保守化して、アルトマンは『ポパイ』(80)以降パリに移住、マイク・ニコルズはうまくハリウッド風を取り込み、アーサー・ペン、ボブ・ラフェルソンらはうまく転向出来ないまま低調な作品づくりに終始、サム・ペキンパー、ハル・アシュビー、ボブ・フォッシー、ジョン・カサヴェテスは80年代の後半にみな死去した。
そして冷戦が終結し、左右、白黒が曖昧で捉えどころない90年代が始まると、途端にアルトマンが復活してきたのも、また分かるような気がする。『ショートカッツ』(93)を代表とするアルトマンの白茶けて曖昧な奥行きを欠いた画面空間というか世界観が、改めてリアリティを増してきたと感じられたものである。
逆に90年代はテリー・ギリアム的な造形美学に凝りまくる大がかりな悪ノリの方向がちょっと馴染まなくなってきて、もっとゲリラ的な安いやり方で、白茶けて刹那的な日常を日常のまま細切れにして異化することのできる悪ノリの才能が求められてくる。例えば、クエンティン・タランティーノやポール・トーマス・アンダーソン、日本なら北野武や黒沢清の観念的な暴力映画に日常感覚のリアリティを感じる、そういう時代が始まったのである。