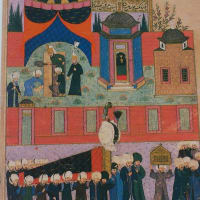♤A屈原(BC340-BC278)「楚辞」「離騒 」を残したとされる楚の時代の詩人・政治家。秦の張儀の策略を見抜けない楚の無能な王に絶望し、入水したとされる。この理由でドラゴンボートの起因となったり、水の神様として祀られる。楚は現在の揚子江中央部辺りに位置し、当時では地方の特異な風習やシャーマニズムなどもあり、詩にも影響がみられるようだ。今世紀では文学において屈原は国民的愛国詩人の位置にあり、切手にもなった。学究的な検証が残されているようだ。
♤2司馬遷
8月28日 ここまで
♤2司馬遷(BC145-BC87)秦の暦を改変し新たに正確な暦の制作に携わる。多くが知る「史記」ー黄帝(BC 2697–2597 or 2698)から司馬遷が生きていた頃までの歴史を記す。記述手法はアジア諸国(韓国・日本・ベトナム)にも20世紀まで影響を与えた。歴史家の努めは、記述により悪を打ち勝つ善の勝利とある。歴史事例について発生した場所・見聞した証言者・関連した周辺の様々な地域と時空を考慮した記録に努める。卓越した人物の自伝・統治者の家族系譜を時間軸で残す。論考は天文・音楽・宗教・土木工学技術・経済等の章に及び、個人の見解として男性・貴族主義を超え男女問わず、詩人・官僚・商人・道化者・暗殺者・哲学者についても網羅。人間社会の発展のパタンーを探ろうとしていた。出自や親・遺言の話題その他は各自で楽しみ、「史記」についてのここでの説明は英語wikiに因ります。
夏休みの課題、久しぶりに学生の気持ちになれます。
♤3李白’701-762)唐代の詩人。4歳の頃に父親とともに成都近くの四川に移り隋の時代を過ごす。当時は家柄の習慣でもある読書に親しみ、古典・詩経(舞踊・楽曲などの歌謡体系)・書経等を読み、青蓮居士というペンネームで詩を創作していたそうだ。若者の李白は自然探索・旅・狩り・弱者救済や、剣術等の活動を広め、騎士道にも及ぶ。725年、20代半ば、旅を始め、時の首相でもある孫と結ばれた。730年、仕官を試みていた。740年頃、有名な道教の僧に遭い、742年、僧が皇帝に召喚された際に、李白の創作が認められた。酒仙・摘仙人・詩狭他のニックネームなどがあり、楊貴妃を讃えたにもかかわらず、酒の禍で宮廷から遠ざけられた。創作は栄華を極めていた唐の繁栄・平和並びに懐古が現れる。酒は饒舌な語り手に導き、苦も無く詩が現れ、民衆への同情や不必要な戦いへの反感等もあるが、懐古感から渇望する将来への発展を期待する心情でもあろう。←バートン=ワトソン
いろいろな偉人の一生を知るのは楽しみでもある。
♤4杜甫(710-770)生後すぐに母親が亡くなり、父方の子だくさんの伯父に養われ、詩作にも登場する。普通の学者の息子として育てられ、青年期には役人になる将来に備え、歴史・儒学・哲学などを学ぶが、後に多くを創作に費やしたかったそうだ。730年詩のコンテスト、735年、科挙などあったが、旅にいそしむ結果になる。744年、李白、隆盛期の詩人との関りに、若い杜甫はひとり遠い星としてあこがれていた。その後の科挙の失敗、子供の喪失、我が身の病などに見まわれる。755年の人口52.9milが10年で三分の一ほどになる戦況と殺戮などを経験し、杜甫の創作のテーマの根幹となった。759年、飢饉・飢餓に見まわれた時期には理性が旺盛に働いて多くの創作を残している。役職にも就くが、窮地の際に友人からの援助を受け、安定し幸せな時機で、友人に捧げる詩を多く創作。762年から郷里から旅を始め766年頃まで、弱視・難聴・糖尿病・結核などの状態だったが、創作は黄金時代で、多い。770年、58歳で没。
人が生きた社会環境で(生い立ちをも含め)、一生の人生の推移に、精神と脳は肉体や家族を伴い、どう感じ、残したか、つくづく感じ入ります。
詩は読んでいないのに。
今日はここまで
♤5 白居易(772-846)安史の乱以降の唐が回復する時期(8,9代の皇帝が交代)を生きる。家族は貧しいが学者の家の生まれ。10歳頃、戦禍を避けるために親戚に預けられる。800年に科挙合格の後、長安で職につくが、804年に父親の喪のために儒教の慣習により職を離れ、再び復帰するものの母親の喪でも慣例に従う。広州に赴任した時には西湖にダムと堤防を築き、白居易に因んだ名前が堰についたそうだ。洛陽・蘇州
に赴任し、引退。創作は一般の民衆にもわかりやすい漢の形式のようで、(そのために批判に上がったりもし、日本にも影響をもたらす。)楽府に収められた作品もある。西域の影響があった時代に、音楽や詩も同様に宮廷に取り入られていたが、口承文芸には相応の道徳や社会に向けた制限も必要だと主張していた。
♤6韓愈(768-824)有名な貴族家系の家に生まれるが、2歳の時に父親と死別し、哲学や儒学を身につけた伯父家族の中で育つ。781年伯父が亡くなり、韓愈は792年に科挙を通過し、802年頃には中央の役職に就くが、批判を受けて左遷されたり、洛陽、長安で服務が819年ごろまで続く。皇帝の講義役をも務め、824年に没。古典儒学の復興を唱え、唐で盛んであった仏教・道教は、経済を発展させるためには社会的に劣ると主張。孟子の説いた理論-政策は学究的な宋理学を基盤として後に形成されるーを強調。が、韓愈自身の哲学には仏教・道教からの影響が根付いている。討論したり、考えを伝えるのは漢の時代の装飾によらない古文復興による完結・正確・有益性を根差す。エッセイ・散文・詩詞などあり、客観的に自分の一生を図りながらも機知にとんだ作り話も数多い。話好きで発想力のある胸襟の開いたまっすぐな性格で、ユーモアある人がらのようで、受講生や友からの回想があったようだ。
中国語の言葉の概念には届かないので、自分学習という意味合いになります。
♤7柳宗元(773-819)唐の時代の政治家・著述家・詩人。793年21歳で科挙を通過し、有名になった。26歳で宮廷の試験を受け,昇級。韓愈同様、古典復古の表現活動。たいていの識者が経験しているように権力の考え・指向が反感に遭うと左遷される。永州・柳州で職に就き、様々なジャンルの散文や寓話(短く洗練され、比喩は意味が深い)を書いたり、紀行回想文(優雅かつ科学的に的確で深い狙いが込められている)・儒教・道教・仏教などに見出される随筆などを生みだす文学的な経験となった。
♤8王安石(1021-1086)宋の時代に生きた経済学者・政治家・詩・詞人で、社会経済学で新しい改革を宋に導く。宮廷職に就く科挙で1042年、4位で通過し、初めの20年は地方の下級官僚の仕事に就き、実践を積み、経験が国庫改革の分析に繋がっていった。貨幣の流通を良くし、独占的な停滞を失くし、国の規則と社会福祉を形成するのがその考え。改革は地方兵士の拡大・仕官制度の改革(法律・軍事・薬学に加え1104年に数学が入った)・朝廷官僚の旧体質改革の縁故抑制などに及んだ。(宋の時代に領土の拡大や飢饉に伴う課税逃亡や重い課税で国庫は困難が続き、インフレが進んでいたため、皇帝が王安石に意見を求めた。)晩年になって皇帝に招かれたが、研究に就きたい希望で辞退。1086年に没。
♤9蘇軾(1037-1101)眉山で生まれ、道教僧が運営する村の学舎で学ぶ。著述・詩・詞・書画・薬理学。17歳で知的で物静かな女性と結婚するが、1065年には子供を生んで没。10年後に忍んで「江城子」を残す。2番目、3番目の女性との永別にも詩を残している。19歳で兄弟とともに科挙通過し、1060年から20年の間は各地で様々な役職に就く。王安石とは政策論で対立し、訴追され、困窮に瀕しては仏教の瞑想にふけり、この時期に多くの詩を残している。左遷された途上の1101年に64歳で没。生前に描かれた書画・訪問先の碑文など赤壁を含め多くが有名になった。
♤10 司馬光(1019-1086)宋の時代を生きた歴史家・著述家「資治通鑑」・政治家(王安石とは反対の意見)6歳の時の逸話(紀元前4世紀の春秋時代の歴史書講義を家に帰って家族に暗唱するほど)があるほどに聡明で学者・官吏を約束されたように、20歳で都の科挙を通過し、仕事に就く。BCE403(戦国時代から唐が分裂するまで)から959年(秦が起こり五代十国が終わり宋の始まりまで)の歴史書5巻(書き手は当時の専門家・史学研究者)を編纂。王安石と対立した点は、性急すぎる新改革の危険性であり、王安石の主張由来には、地理的な要素がありそうだと、吐いている。“閩人狹險,楚人輕易,今二相皆閩人,二參政皆楚人,必將援引鄉黨之士,充塞朝廷,風俗何以更得淳厚 ?」
♤J李清照(1084-1151)蘇軾に学んだ学者一家に生まれる女性詩人・随筆家。中国史では、偉大な詩人。一家の所蔵本は膨大で、幼いころから蔵書に親しみ、学究一門としては女子でも、外交的。創作詩は仲間内でも知られていた。1101年3歳年上の書画書籍の研究・碑文研究に情熱を寄せる者同士が結婚。1127年開封(宋の都)陥落する頃に家が消失し、所蔵品を携えて南京に移り、1年ばかり暮らした後の1129年、夫は役職に就く予定だったが、亡くなる。二度目の結婚をするが、数か月で離縁。詩・詞を書き続け、夫が執筆した「金石録」を完成させる。数百が知られている詩は、夫への愛であったり、戦争の憎悪や彼女自身の愛国心だったりする。
♤Q辛棄疾(1140-1207)偉大な詞人・南宋の軍指揮官。金が北方から侵入する頃、祖父が霍去病(漢の武将)にあやかり、病封じに命名。祖父の語りに影響され、愛国心が育つ。軍事経験は22歳。詞は蘇軾と比較されるほどで、作風は広大な世界で暗喩を用い、600の作品が現存しているそうだ。
♤K 曹雪芹【-1762/64)中国四大小説のひとつ「紅楼夢」の著者。漢民族で、清朝の康熙帝治世下では祖父曹寅はお抱えの遊び相手で、18世紀には絶頂期で、巡礼のホスト役を務めたり、唐代の詞‣詩編纂を曹寅は皇帝から命じられた。雪芹の曽祖父は皇帝から織物製造を命じられ、南京に移る。1715年に没。康熙帝没後の雍親王帝に粛清を受け、一家は北京に移り住むころ、雪芹はまだ幼く、貧しくて、自分の絵を売っていた。酒の常習者で才能があると認められていた。「紅楼夢」執筆に情熱を注ぎ、80章まで書き上げ、亡くなる。息子の死が引き金になったようでもある。