え゛,もう池田屋ですか・・・,ということで終わった前回。
文久3(1863)年8月の長州藩の京都失脚(八月十八日の政変)と天誅組の変から翌元治元年6月5日の池田屋の変,同7月19日の禁門の政変(蛤御門の変),同8月5日の四国艦隊下関砲撃事件・・・といった具合に長州藩が踏んだり蹴ったりの状況になります。
その間,龍馬は神戸海軍塾の塾頭として多忙な日々を送っていた筈で,言うなれば世間の動き(というか長州の暴発と,それを誘引した薩摩の動き)からは距離を置いた存在だった筈です。
まずは饅頭屋の祝言から始まりました。
どうなんでしょうね,このあたり・・・。
根多ばれになりますから,今後の饅頭屋こと上杉宋次郎(近藤長次郎)のことは敢えて書きませんが,後に龍馬とともに長崎で亀山社中(後の海援隊)の旗揚げをすることになる訳ですから,妻帯したというのはどんなものでしょう・・・。
で,その長次郎とイケメン沢村は分かるのですが(先週まで要さんが主役のCX系ドラマの再放送やってました・・・),望月亀弥太と北添佶摩はどっちがどっちかさっぱり分かりませんでした。
分からんと言えば,桂役の谷原「義元」章介(磯次郎さんとも云う)も今回はどうも役所が不明瞭です。
3年前の「風林火山」でのダークサイド今川義元役や,それが終わるとすぐに民放系で始まった「エラいところに嫁いでしまった」でのマザコン前回のお莫迦駄目亭主役は見事としか言いようのない演技だったのですが,今回は全くキャラが立っていません。
器用な俳優さんと思ってきただけに残念です・・・。
で,ようやく陸奥陽之助が出てきましたね。
多分,ああした高ビーな若者だったことでしょう。
その意味ではぴったりな俳優さんだったと思います。
ただ,家老の息子である陸奥(当時は伊達小次郎か)が何故脱藩したのか(否せざるを得なかったのか)が全く語られなかったのが残念です。
あれでは,脱藩したただの物好きでしか無いような気がします・・・。
そうしているうちに,亀弥太が神戸を脱走します。
・・・ということは,いよいよ池田屋か・・・となります。
文久3年9月と言ったばかりなのに・・・。
尤も同月は武市が捕縛されていますし,龍馬自身獅子奮迅の動きをしていますので,どうしても時系列の甘さが気になります。
まず龍馬の動きを見ると,文久3年には江戸へ下っています。
佐那に形見として片袖をちぎって与えたのがこの時と思われますし,年末~年始には上坂して神戸へ。
そして勝とともに長崎へ行き,熊本に横井小楠を訪ねているはずです。
さらには神戸海軍塾のメンバーによる蝦夷地探索を行ったのもこの時期でした。
北添佶摩らが行った筈ですが,これこそ明治政府が後年推し進めた屯田兵計画のはしりだと思います。
そうした史実が脇に追いやられ,龍馬が池田屋に向かう・・・というよく分からん内容になっていました。
池田屋の変の際,龍馬は人生最後の江戸行きの最中と思われますし,だいたい不逞浪士狩りをしている新撰組が目を光らせている,さらには池田屋を十重二重に会津・桑名両藩が包囲しているでしょうから,近づけるはずがありません。
都合良く瀕死の亀弥太と遭うシーンに至っては何をか況んやです・・・。
腹に刀突き立てたら痛みと出血で苦しんでいる筈で,朦朧としている筈はありません・・・。
池田屋の変に関しては,来週詳しく語られるのでしょうか・・・。
では,何故長州系の過激志士たちが池田屋に集うことが新撰組にばれたのか,何故あっさりと斬られたのか(宮部鼎三役は小西博之だったんですね),そして新撰組はどういう布陣だったのか・・・。
できれば来週語って欲しいものです。
でないと,何で起きたのかあれじゃ全く分からないので・・・。
(お登世は出ない設定ですかね・・・)










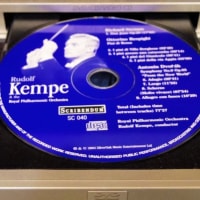
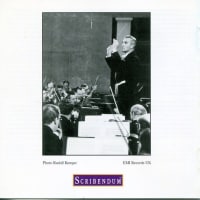
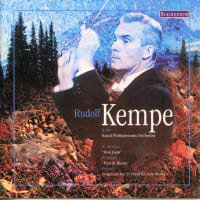







返答コメのペースもわかってきました(笑)。
そんなに仰々しく構えてもらうとこちらのほうが恐縮してしまいます。 たいしたことはありません。
非常に謙虚な方なんですね。(多少自虐気味? 笑)
ところで今回神戸の今、昔が多く出てましたね。
神戸海軍操練所に関してはこれまで私が見ていた幕末、龍馬関係でも今回ほど長く描写したドラマはなかったので感動しています。
同じ景色を150年前、坂本龍馬も見ていたんだと思うと・・・。
傍のメリケンパークには「神戸海援隊」と名をうった大きなモニュメント(1991年建設)もあります。 是非またおこしやす。
さて、いきなりの池田屋騒動でしたね。
亀弥太は神戸の寮にいたのにどのようにしてそんな情報を得ていたのでしょう? 電話もないのに(笑)・・・。
でもああいう心情になるのはわかります。
三条大橋にその時戦った刀傷が残っているというので4月に京都に行った時見に行ってきましたがわかりませんでした。
陸奥陽之助はああいう若者だったんですか?
秀才だけれども・・と人物像のサイトに「ひととなり」がでてました。
そうです。彼がなぜ脱藩せざるを得なかったのかわかりません。
koshiさんはよくご存じのようですね。
また教えてください。
お出でくださいましてありがとうございます。
こうして読んでくださる方が居られるのみならず,コメントまでいただけると本当に嬉しい限りです。
亀弥太と佶摩が脱走したのは,やはり土佐浪士は長州藩を媒介としたネットワークを持っていたからではないかと予想されます。
龍馬と沢村の脱藩も,直接的なきっかけは(龍馬は全面的に賛同していなかったでしょうが),吉村寅太郎らによる京都義挙への参加でしょうから(薩摩藩による第一次寺田屋事件により頓挫),何らかの横のつながりはあったと思われます・・・。
因みに,池田屋の犠牲者第一号はこの佶摩だったようです・・・。
伊達小次郎こと陸奥陽之助の脱藩は,一言で言えば家老であった父宗広が政争で敗れて失脚したための困窮が原因であったと思われます。
勿論,国学者でもあった父の影響で尊攘思想にのめり込んでいったのでしょうが・・・。
明治以後も,外務相となるまでに結構ドラマチックな人生を歩んでいます。
以前も述べたとおり,神戸は一度仕事でいったきりです・・・。
ぜひ採訪して史跡をあれこれ見てみたいものです。
今後の舞台となる長崎で亀山社中跡(司馬遼太郎氏が訪れたときは人が住んでいたそうです)を見て,その上の風頭公園の龍馬像の下で東シナ海を眺めたとき,私も同じ景色を龍馬も見たのか・・・と感慨に浸りました・・・。
次回も頑張って感想を書きたいと思いますので,ぜひお読みいただけると有り難いです・・・