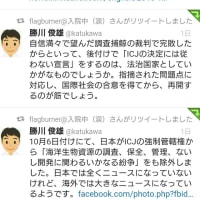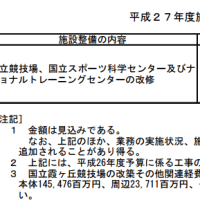昨日、日本政府が行ってる南極海「調査捕鯨」について、オーストラリア政府が差し止めを求めてる裁判の第1回目口頭弁論が国際司法裁判所(ICJ)で行われた。
・調査捕鯨:南極海対象訴訟 豪「実態は商業捕鯨」 国際司法裁で口頭弁論(2013年6月27日 毎日jp)
・(2013年6月26日 guardian.co.uk)
オーストラリア政府が ICJ に提訴すると言いだしてから口頭弁論までに約3年かかったのは何故か・・・。
ってのはともかく。
昨日は、オーストラリア政府が自らの主張を行っていた。
以下、2013年6月27日分毎日jp『調査捕鯨~』を全文(略
---- 以下引用 ----
【ブリュッセル 斎藤 義彦】
国際司法裁判所(オランダ・ハーグ)は26日、日本の調査捕鯨が国際法に違反するとしてオーストラリアが日本を相手に起こした訴訟の口頭弁論を始めた。
26日は豪州が、調査捕鯨は商業捕鯨にあたり国際捕鯨取締条約に違反すると主張、南極海での調査捕鯨禁止を求めた。
日本は7月2日から反論。
弁論は16日までで、判決は早ければ半年後。
日本が勝訴すれば調査捕鯨の正当性が認められ、反捕鯨勢力は批判の法的根拠を失う。
敗訴すれば南極海での調査捕鯨を中止せざるをえず、北西太平洋での調査捕鯨にも深刻な影響が出そうだ。
口頭弁論で豪州は、日本の調査捕鯨が「継続し大規模」で実態は商業捕鯨だと指摘。
商業捕鯨数を86年からゼロにすると定め、南極海での商業捕鯨を禁止した同条約違反だと主張した。
さらに、日本が条約を「曲解」し「毎年数百頭のクジラを殺すのは科学ではない」と断言。
絶滅の恐れがある野生動植物の国際取引を規制するワシントン条約にも違反すると指摘、南極海での調査捕鯨中止を求めた。
日本はこれまで、科学調査目的の捕鯨とその鯨肉の利用は国際捕鯨取締条約8条で認められ「商業捕鯨でなく条約に違反しない」と指摘。
調査捕鯨の対象鯨種は日本に関してワシントン条約の適用外で、商業目的でもなく合法と主張してきた。
豪州は10年5月に提訴。
国際司法裁判所は1審制で判決には従う義務がある。
---- 引用以上 ----
厳密に言うと、ICJ の判決に従う義務はないらしいのよね。
・国際司法裁判所の判決、拘束力はどのくらい?(2012年8月29日 nikkei.com)
参考までに、2012年8月29日分 nikkei.com『国際司法裁判所~』からその部分を(略
---- 以下引用 ----
(中略)
からすけ 結論(けつろん)に従(したが)わない国もあるんじゃない?
イチ子 一方の国が判決に従わない場合は安保理が従うように「勧告(かんこく)」をするの。
そもそもICJの出した判決や意見は国際社会で権威(けんい)あるものと認(みと)められているわ。
アメリカと旧ソ連を中心とした「冷戦(れいせん)」があった60~80年代にはICJでの裁判を求(もと)める件数(けんすう)も年平均(へいきん)1つぐらいだったけど、90年代以降(いこう)は増(ふ)えているのよ。
(以下略)
---- 引用以上 ----
安保理の勧告、か。
こいつを無視すると、流石に日本の対外イメージ悪化は避けられないだろうが・・・。
・ICJ調査捕鯨訴訟解説/キツネとクジラ(2013年6月26日 クジラ・クリッピング)
上の記事では、国際交渉の場で「豪腕」との呼び名が高い鶴岡 公二(Koji TSURUOKA)外務審議官(来月22日に退任予定→TPPの首席交渉官専任予定)が今回の裁判も担当してることに触れた後で、その問題点について触れていた。
以下、2013年6月26日分 クジラ・クリッピング『ICJ~』からその部分を(略
---- 以下引用 ----
(中略)
確かに、オーストラリアも、日本にとって経済・防衛両面で重要なパートナーであり、米国の次に大切なトモダチのハズ。
しかし、ことこの問題に関しては、文字どおり対決であり、交渉の二字が出る幕はありません。
残念ながら、その段階はすでに過ぎ去ってしまったのです。
実際には、国際捕鯨委員会(IWC)の場で、米国と外部専門家のデソト氏を仲介役に現実的な落としどころを探る交渉は進められていたのです。
しかし、日本側はその時点で調整能力の高い人材を充てることをせず、終始内向きで歩み寄りの姿勢を欠いていたため、折り合いをつけることができなかったのです。
国際法廷で、豪腕の利害調整役が一体どのように腕を振るう余地があるのでしょう?
「本当は殺さなきゃならない南のザトウを、わざわざ殺さないでやるっつってんのに、豪がごねてやがるんだ」なんて口にしようものなら、判事の心象を悪くすることは請け合いでしょうに。
(以下略)
---- 引用以上 ----
日本政府は、南極海「調査捕鯨」に関して折り合いをつける気なんて一切なかったんだろうけど・・・。
その意味では、今回の裁判ってのは、日本政府が望んだ展開とも言える。
ただし、その判決が日本政府の望み通りになるかどうか知らんが。
一方、今回の裁判で日本政府が訴えるべきことについて、妙なことを語ってる人がいた。
・調査捕鯨中止訴訟で日本が訴えるべきこと(2013年6月26日 経済ニュースゼミ)
↑では、日本外務省が主張してた南極海「調査捕鯨」の根拠について「説得力が感じられることがない」と述べていた。
その後、裁判でこんな主張をすれば(略)という話をしてたのだが・・・。
以下、2013年6月26日分経済ニュースゼミ『調査捕鯨~』から問題の部分を(略
読む前に、コンサートチケットの代金振り込みを忘れないように!
久しぶりに、ひと月分の振り込み額が3万を超えたのは内緒。
---- 以下引用 ----
(中略)
先ず、人類の捕鯨の歴史というものをオーストラリアを始めとする世界の人々にしっかりと認識してもらうことが必要なのです。
オーストラリアの人々の元々の母国は英国です。
例えば、アダムスミスが国富論の中でも書いているように、昔の英国人たちは盛んに捕鯨活動にいそしんでいたのです。
だから、少し知識のある人々なら、自分たちの祖先がクジラをガンガン捕獲していたことをよく知っているのです。
白鯨という小説もあります。
それに日本に開国を求めたペリーが何故日本に来たかと言えば、元はと言えば、捕鯨船への燃料と水の補給が目的だったではありませんか。
では、彼らはそれほどクジラの肉が好きだったのか?
しかし、クジラを捕る主たる目的は別にあったのです。
つまり、肉よりも鯨油が目的だった、と。
鯨油は、温度が下がっても固まらないので、ランプの燃料や潤滑油として人気があったのです。
それに、クジラの髭や骨は、コルセットやペチコートの材料になった、と。
でも、20世紀に入ると、石油精製の発展と共に、そのような需要が激減し、クジラを捕獲する意味が失われてしまったのです。
どんな目的であろうと、過去大々的に捕鯨をしていた英国人の子孫であるオーストラリアなどの人々が、どんな顔をして捕鯨が残酷だなどと言えるのでしょうか?
繰り返しになりますが、漁の対象にされたクジラさんは、かわいそう。
それはそのとおり。
但し、日本人は、自分たちが食する生き物に対する感謝の念を持っているから、「頂きます」とちゃんと食事の前に言う訳ですし、捕鯨の基地にはクジラ塚なるものがあるところもあると聞きます。
それに比べて、西洋の人々はどれだけ慈悲深いと言うのか?
オーストラリア人がカンガルーを棒で叩くという反論は、この際置いておくとして‥
例えば、英国人のキツネ狩りやスペイン人の闘牛という行いについて指摘してみたら如何でしょう?
どうしてキツネ狩りなんかするのですか?
キツネの肉を食べる必要があるからですか?
否、彼らはスポーツというか娯楽でやっているのです。
どうして鴨を撃ち落とすのですか?
これも、食べるためというよりも、娯楽なのです。
闘牛にしてもそのとおり。何故おとなしい牛を興奮させるようなことをするのか?
そして、興奮して向かってきた牛に一撃を加える。それ、おかしくないですか?
誰が一番残酷なのか?
私は、今回の裁判で日本が一番主張すべきなのは、そのような西洋人にとって都合の悪い事実を指摘することだと思うのです。
(以下略)
---- 引用以上 ----
上の主張って、最近従軍慰安婦に関して「日本以外の国も同じことをやってた」云々って主張をして豪快にスベった某市長に通じるものがあるとしか(呆)
だいたい、判事の前で上の主張を行っても、心の中で笑われるのがオチ(下手すると「政治的主張の場所じゃない」と注意される)だろうに。
こういう主張を裁判の場でしたらダメってことくらい、いくら日本政府が(放送禁止用語)だからってわかるだろうに・・・。
にしても。
来月行われる口頭弁論で、日本政府はどういう主張をするのやら(←わかってるくせに)。
・調査捕鯨:南極海対象訴訟 豪「実態は商業捕鯨」 国際司法裁で口頭弁論(2013年6月27日 毎日jp)
・(2013年6月26日 guardian.co.uk)
オーストラリア政府が ICJ に提訴すると言いだしてから口頭弁論までに約3年かかったのは何故か・・・。
ってのはともかく。
昨日は、オーストラリア政府が自らの主張を行っていた。
以下、2013年6月27日分毎日jp『調査捕鯨~』を全文(略
---- 以下引用 ----
【ブリュッセル 斎藤 義彦】
国際司法裁判所(オランダ・ハーグ)は26日、日本の調査捕鯨が国際法に違反するとしてオーストラリアが日本を相手に起こした訴訟の口頭弁論を始めた。
26日は豪州が、調査捕鯨は商業捕鯨にあたり国際捕鯨取締条約に違反すると主張、南極海での調査捕鯨禁止を求めた。
日本は7月2日から反論。
弁論は16日までで、判決は早ければ半年後。
日本が勝訴すれば調査捕鯨の正当性が認められ、反捕鯨勢力は批判の法的根拠を失う。
敗訴すれば南極海での調査捕鯨を中止せざるをえず、北西太平洋での調査捕鯨にも深刻な影響が出そうだ。
口頭弁論で豪州は、日本の調査捕鯨が「継続し大規模」で実態は商業捕鯨だと指摘。
商業捕鯨数を86年からゼロにすると定め、南極海での商業捕鯨を禁止した同条約違反だと主張した。
さらに、日本が条約を「曲解」し「毎年数百頭のクジラを殺すのは科学ではない」と断言。
絶滅の恐れがある野生動植物の国際取引を規制するワシントン条約にも違反すると指摘、南極海での調査捕鯨中止を求めた。
日本はこれまで、科学調査目的の捕鯨とその鯨肉の利用は国際捕鯨取締条約8条で認められ「商業捕鯨でなく条約に違反しない」と指摘。
調査捕鯨の対象鯨種は日本に関してワシントン条約の適用外で、商業目的でもなく合法と主張してきた。
豪州は10年5月に提訴。
国際司法裁判所は1審制で判決には従う義務がある。
---- 引用以上 ----
厳密に言うと、ICJ の判決に従う義務はないらしいのよね。
・国際司法裁判所の判決、拘束力はどのくらい?(2012年8月29日 nikkei.com)
参考までに、2012年8月29日分 nikkei.com『国際司法裁判所~』からその部分を(略
---- 以下引用 ----
(中略)
からすけ 結論(けつろん)に従(したが)わない国もあるんじゃない?
イチ子 一方の国が判決に従わない場合は安保理が従うように「勧告(かんこく)」をするの。
そもそもICJの出した判決や意見は国際社会で権威(けんい)あるものと認(みと)められているわ。
アメリカと旧ソ連を中心とした「冷戦(れいせん)」があった60~80年代にはICJでの裁判を求(もと)める件数(けんすう)も年平均(へいきん)1つぐらいだったけど、90年代以降(いこう)は増(ふ)えているのよ。
(以下略)
---- 引用以上 ----
安保理の勧告、か。
こいつを無視すると、流石に日本の対外イメージ悪化は避けられないだろうが・・・。
・ICJ調査捕鯨訴訟解説/キツネとクジラ(2013年6月26日 クジラ・クリッピング)
上の記事では、国際交渉の場で「豪腕」との呼び名が高い鶴岡 公二(Koji TSURUOKA)外務審議官(来月22日に退任予定→TPPの首席交渉官専任予定)が今回の裁判も担当してることに触れた後で、その問題点について触れていた。
以下、2013年6月26日分 クジラ・クリッピング『ICJ~』からその部分を(略
---- 以下引用 ----
(中略)
確かに、オーストラリアも、日本にとって経済・防衛両面で重要なパートナーであり、米国の次に大切なトモダチのハズ。
しかし、ことこの問題に関しては、文字どおり対決であり、交渉の二字が出る幕はありません。
残念ながら、その段階はすでに過ぎ去ってしまったのです。
実際には、国際捕鯨委員会(IWC)の場で、米国と外部専門家のデソト氏を仲介役に現実的な落としどころを探る交渉は進められていたのです。
しかし、日本側はその時点で調整能力の高い人材を充てることをせず、終始内向きで歩み寄りの姿勢を欠いていたため、折り合いをつけることができなかったのです。
国際法廷で、豪腕の利害調整役が一体どのように腕を振るう余地があるのでしょう?
「本当は殺さなきゃならない南のザトウを、わざわざ殺さないでやるっつってんのに、豪がごねてやがるんだ」なんて口にしようものなら、判事の心象を悪くすることは請け合いでしょうに。
(以下略)
---- 引用以上 ----
日本政府は、南極海「調査捕鯨」に関して折り合いをつける気なんて一切なかったんだろうけど・・・。
その意味では、今回の裁判ってのは、日本政府が望んだ展開とも言える。
ただし、その判決が日本政府の望み通りになるかどうか知らんが。
一方、今回の裁判で日本政府が訴えるべきことについて、妙なことを語ってる人がいた。
・調査捕鯨中止訴訟で日本が訴えるべきこと(2013年6月26日 経済ニュースゼミ)
↑では、日本外務省が主張してた南極海「調査捕鯨」の根拠について「説得力が感じられることがない」と述べていた。
その後、裁判でこんな主張をすれば(略)という話をしてたのだが・・・。
以下、2013年6月26日分経済ニュースゼミ『調査捕鯨~』から問題の部分を(略
読む前に、コンサートチケットの代金振り込みを忘れないように!
久しぶりに、ひと月分の振り込み額が3万を超えたのは内緒。
---- 以下引用 ----
(中略)
先ず、人類の捕鯨の歴史というものをオーストラリアを始めとする世界の人々にしっかりと認識してもらうことが必要なのです。
オーストラリアの人々の元々の母国は英国です。
例えば、アダムスミスが国富論の中でも書いているように、昔の英国人たちは盛んに捕鯨活動にいそしんでいたのです。
だから、少し知識のある人々なら、自分たちの祖先がクジラをガンガン捕獲していたことをよく知っているのです。
白鯨という小説もあります。
それに日本に開国を求めたペリーが何故日本に来たかと言えば、元はと言えば、捕鯨船への燃料と水の補給が目的だったではありませんか。
では、彼らはそれほどクジラの肉が好きだったのか?
しかし、クジラを捕る主たる目的は別にあったのです。
つまり、肉よりも鯨油が目的だった、と。
鯨油は、温度が下がっても固まらないので、ランプの燃料や潤滑油として人気があったのです。
それに、クジラの髭や骨は、コルセットやペチコートの材料になった、と。
でも、20世紀に入ると、石油精製の発展と共に、そのような需要が激減し、クジラを捕獲する意味が失われてしまったのです。
どんな目的であろうと、過去大々的に捕鯨をしていた英国人の子孫であるオーストラリアなどの人々が、どんな顔をして捕鯨が残酷だなどと言えるのでしょうか?
繰り返しになりますが、漁の対象にされたクジラさんは、かわいそう。
それはそのとおり。
但し、日本人は、自分たちが食する生き物に対する感謝の念を持っているから、「頂きます」とちゃんと食事の前に言う訳ですし、捕鯨の基地にはクジラ塚なるものがあるところもあると聞きます。
それに比べて、西洋の人々はどれだけ慈悲深いと言うのか?
オーストラリア人がカンガルーを棒で叩くという反論は、この際置いておくとして‥
例えば、英国人のキツネ狩りやスペイン人の闘牛という行いについて指摘してみたら如何でしょう?
どうしてキツネ狩りなんかするのですか?
キツネの肉を食べる必要があるからですか?
否、彼らはスポーツというか娯楽でやっているのです。
どうして鴨を撃ち落とすのですか?
これも、食べるためというよりも、娯楽なのです。
闘牛にしてもそのとおり。何故おとなしい牛を興奮させるようなことをするのか?
そして、興奮して向かってきた牛に一撃を加える。それ、おかしくないですか?
誰が一番残酷なのか?
私は、今回の裁判で日本が一番主張すべきなのは、そのような西洋人にとって都合の悪い事実を指摘することだと思うのです。
(以下略)
---- 引用以上 ----
上の主張って、最近従軍慰安婦に関して「日本以外の国も同じことをやってた」云々って主張をして豪快にスベった某市長に通じるものがあるとしか(呆)
だいたい、判事の前で上の主張を行っても、心の中で笑われるのがオチ(下手すると「政治的主張の場所じゃない」と注意される)だろうに。
こういう主張を裁判の場でしたらダメってことくらい、いくら日本政府が(放送禁止用語)だからってわかるだろうに・・・。
にしても。
来月行われる口頭弁論で、日本政府はどういう主張をするのやら(←わかってるくせに)。