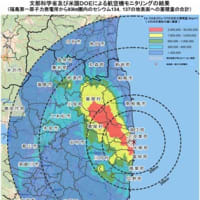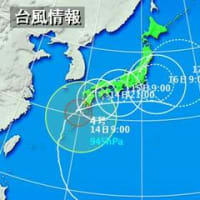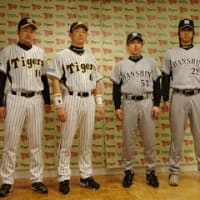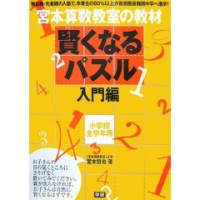本日早朝ご遷化の報に接し、深い悲しみのもと當寮にて弔意を表しました。
日中、多くの法友からも連絡を頂き、報道でも遷化の訃報を目の当たりにし、改めてその存在の大きさに気付かされた次第です。
前回の記事にも記した様に、私は安居中、直接お世話をさせて頂いた事もなく、あくまでも間接的にご指導を賜った立場の者でしかありません。
その私でさえ斯様ですから、身近でお世話に当たっていた隨身の方々の悲しみは察するところ余りあります。
改めて、衷心より弔意を表したいと存じます。
しかし、今回の訃報は想像以上に応えました。
宗門が社会の変革の波に曝されながらも、安心して我々が檀信徒教化に励む事ができるのも、全ては御山の存在があり、猊下の様な禅師家の存在があったからだと思います。
少なくとも私の場合はそうでした。
深山幽谷にて綿密なる法の実践が行じられている現実が、社会に出ても安心して頑張ってこれた一つの要因でもありました。
意思が弱く融通が効かない私は、今でも定期的に自らの確認作業をしに御山に出向きます。
その際に、法の実践を地でいく禅師様の存在に何度心救われたことか。
非常に恥ずかしい話でもありますが、私にとって定期的に御山にご奉公に出向くことは、一種の身心の矯正作業みたいなものでした。
知らず知らずのうちに人の体の骨が歪んでいくように、私の身と心も知らず知らずのうちに社会の荒波にて歪みが生じます。
その歪んだ身と心の矯正作業を御山に求めていたのです。
私は安居中、お二人の禅師様のもとで修行に励む事ができましたが、それぞれの禅師様の家風が弁道に反映される、大変ありがたい環境で安居を送る事ができました。
どこの世界でもそうでしょうが、修行環境というのはその時の指導者のカラーや個性で一変するものだと思います。
それは、時に良い意味でも悪い意味でも変化をもたらす事がありましょう。
しかし、私が安居していた頃の御山は、前者が「柔」で後者が「剛」といった「柔・剛」併せ持つ非常に恵まれた修行環境にあったと思います。
前の禅師様からは衆生縁のありがたさを学び、今の禅師様からは坐堂に居るだけで雰囲気が一変する禅師家の醍醐味というものを肌で体感できました。
これら「柔・剛」ともに交えた経験は、私の僧侶としてのかけがえのない財産となっております。
そういう意味で、私は良い意味で未だに御山を引きずっているのだと感じます。御山を引きずる事に対して、たまに懐疑的な意見を耳にする時がありますが、逆に引きずれない安居生活である事の方が寂しく感じる時もあります。
これからも私は、愛山護法の精神を自らの糧にしながら、僧として人生を全うしていきたいと思っております。
改めて、焚香夜坐の報恩行を以て、永平78世旃崖奕保大和尚の慈恩に酬い給わんことを祈念申し上げます。