ドイツ系ユダヤ人の哲学者ハンナ・アーレントが「アイヒマン裁判」に関わり、論争を巻き起こした前後4年の出来事を描く。
内容の紹介
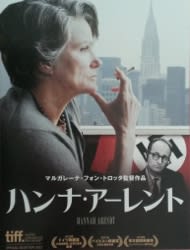
1960年、ニューヨーク。
ハンナ・アーレントは第二次大戦中、反ナチス活動に携わり、強制収容所に連行されたが脱出した過去を持つ。その後、夫と母を連れてアメリカに亡命し、無国籍のまま英語を学んでジャーナリストとして活動。1951年にはアメリカ国籍を取得し、ナチズムとスターリン主義を批判した大著『全体主義の起源』を出版して一躍有名になる。
現在は、共に大学教授の夫・ハインリヒと、信頼と愛情にあふれた日常生活を送っており、その交遊関係から、自宅には多くの知識人や言論人が集う。

その頃、元ナチス高官のアイヒマンが潜伏先のアルゼンチンで捕らえられ、大々的に報道される。アイヒマンは、多くのユダヤ人を強制収容所に移送した責任者であり、ハンナは過去に自分が連行された経験や、初めてアウシュビッツの惨劇を知った時の衝撃が蘇る。そして、なぜ、どのように、「人類に対する犯罪」ともいうべき大量殺戮が起こったのかを明らかにするために、ハンナは戦犯裁判の行われるエルサレムに行き、傍聴したいと願う。そこで、雑誌『ニューヨーカー』の編集部に手紙を書き、貴誌にぜひ傍聴レポートを寄稿したいと売り込む。

周囲の友人たちが、“歴史的裁判”に立ち会うハンナを讃える中、夫のハインリヒは、ハンナが過去の暗い歴史と向かい合うことを心配し、「行かせたくない、分かってくれ。」と反対するが、ハンナはそれを退けてエルサレムに向かう。

ところが、国際裁判が始まってみると、元SS(ヒトラー親衛隊)中佐としてナチスのユダヤ人殲滅計画を遂行してきた中心人物であったはずのアイヒマンは、実は、権力機構の一端として、上からの命令を事務的に処理するだけの存在にしか過ぎなかったと自己認識していることが明らかになる。
内容の紹介
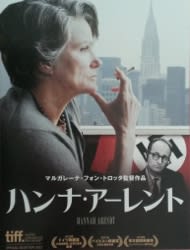
1960年、ニューヨーク。
ハンナ・アーレントは第二次大戦中、反ナチス活動に携わり、強制収容所に連行されたが脱出した過去を持つ。その後、夫と母を連れてアメリカに亡命し、無国籍のまま英語を学んでジャーナリストとして活動。1951年にはアメリカ国籍を取得し、ナチズムとスターリン主義を批判した大著『全体主義の起源』を出版して一躍有名になる。
現在は、共に大学教授の夫・ハインリヒと、信頼と愛情にあふれた日常生活を送っており、その交遊関係から、自宅には多くの知識人や言論人が集う。

その頃、元ナチス高官のアイヒマンが潜伏先のアルゼンチンで捕らえられ、大々的に報道される。アイヒマンは、多くのユダヤ人を強制収容所に移送した責任者であり、ハンナは過去に自分が連行された経験や、初めてアウシュビッツの惨劇を知った時の衝撃が蘇る。そして、なぜ、どのように、「人類に対する犯罪」ともいうべき大量殺戮が起こったのかを明らかにするために、ハンナは戦犯裁判の行われるエルサレムに行き、傍聴したいと願う。そこで、雑誌『ニューヨーカー』の編集部に手紙を書き、貴誌にぜひ傍聴レポートを寄稿したいと売り込む。

周囲の友人たちが、“歴史的裁判”に立ち会うハンナを讃える中、夫のハインリヒは、ハンナが過去の暗い歴史と向かい合うことを心配し、「行かせたくない、分かってくれ。」と反対するが、ハンナはそれを退けてエルサレムに向かう。

ところが、国際裁判が始まってみると、元SS(ヒトラー親衛隊)中佐としてナチスのユダヤ人殲滅計画を遂行してきた中心人物であったはずのアイヒマンは、実は、権力機構の一端として、上からの命令を事務的に処理するだけの存在にしか過ぎなかったと自己認識していることが明らかになる。
「それが命令でした。殺害するか否かはすべて命令次第です。事務的に処理したんです。私は一端を担ったにすぎません。」
「なにしろ戦時中の混乱期でしたから、皆思いました。“上に逆らったって状況は変わらない。抵抗したところで、どうせ成功しない”と。仕方なかったんです。そういう時代でした。皆そんな世界観で教育されていたんです。たたき込まれていたんです。」
といった被告の言葉を聞き、ハンナはその恐るべき凡庸さと、行われた暴虐とのあまりの対照に戦慄する。








