自転車キンクリートSTOREによるテレンス・ラティガン3作連続公演の第2弾である。
第1弾『ウィンズロウ・ボーイ』(演出=坂手洋二)がとても面白かったので、迷わず観るつもりだったラティガン作品。
今回の第2弾『ブラウニング・バージョン』(訳・演出=鈴木裕美)も、期待に違わぬ面白さで大満足。
英国のパブリックスクールにある教職員住宅のリビングルーム兼書斎(美術=横田あつみ)で展開される1幕劇(1時間50分)である。
心臓病のために明日の終業式で退職することになっているアンドルウ・クロッカーハリス先生(浅野和之)は、ギリシャ悲劇を教える優れた古典学者だが、生徒や同僚に好かれる柄ではない。開幕後、彼が最初に登場するまでに彼の部屋に入ってくる教え子(池上リョウマ)、後輩の教師ハンター(今井朋彦)、妻ミリー(内田春菊)の3人によって、アンドルウの人物像と対人関係が浮き彫りにされ、観客に明らかにされる見事な幕開けである。
そして、先生の登場となる。私はこの登場の第一印象で浅野和之起用の成功を確信した。
謹厳実直だが人気のない教師像を、抑制の効いた演技で見せた浅野和之が見事であった。
妻との性的に微妙な関係、校長(岡田正)からの無神経な発言、その発言を間接的に伝える後任教師、教え子からのプレゼントの本(題名になっている)等など、見せ場となる彼の感情の揺らぎと反応が素晴らしい。
なかでも、自分がヒムラーに例えられたショックによる慟哭は、誰にも殆ど感情を露わにしなかった彼の唯一の小爆発であり涙を誘う。
最も劇的で緊張感を孕んだのは、アンドルウとハンターとの二人場面での遣り取りで、浅野と今井の見ごたえのある場面となった。
また、妻のミリーはテネシー・ウイリアムズの『やけたトタン屋根の上の猫』のマーガレットや『欲望という名の電車』のブランチにも通じるキャラクターで哀れである。ラティガンとウィリアムズの類似性が見えたのも今回の収穫であった。
ラティガンの作劇術の優れているところは、アンドルウを単に哀れな先生とせずに、最後にきっちりと自己主張させたとこに表れている。
人間性の素晴らしさと、その人が置かれた状況とは往々にして比例しないのが現実である。その現実の中で、痩せ我慢しながら生きているのがラティガン作品の主人公である。
明日の終業式で、彼は「チップス先生」になれるかも知れないという、ささやかな期待を持たせてくれる幕切れに快哉を叫び、安堵し、劇場を後にする喜びに浸れたのであった。
(2005-10-22 六本木・俳優座劇場にて butler)
第1弾『ウィンズロウ・ボーイ』(演出=坂手洋二)がとても面白かったので、迷わず観るつもりだったラティガン作品。
今回の第2弾『ブラウニング・バージョン』(訳・演出=鈴木裕美)も、期待に違わぬ面白さで大満足。
英国のパブリックスクールにある教職員住宅のリビングルーム兼書斎(美術=横田あつみ)で展開される1幕劇(1時間50分)である。
心臓病のために明日の終業式で退職することになっているアンドルウ・クロッカーハリス先生(浅野和之)は、ギリシャ悲劇を教える優れた古典学者だが、生徒や同僚に好かれる柄ではない。開幕後、彼が最初に登場するまでに彼の部屋に入ってくる教え子(池上リョウマ)、後輩の教師ハンター(今井朋彦)、妻ミリー(内田春菊)の3人によって、アンドルウの人物像と対人関係が浮き彫りにされ、観客に明らかにされる見事な幕開けである。
そして、先生の登場となる。私はこの登場の第一印象で浅野和之起用の成功を確信した。
謹厳実直だが人気のない教師像を、抑制の効いた演技で見せた浅野和之が見事であった。
妻との性的に微妙な関係、校長(岡田正)からの無神経な発言、その発言を間接的に伝える後任教師、教え子からのプレゼントの本(題名になっている)等など、見せ場となる彼の感情の揺らぎと反応が素晴らしい。
なかでも、自分がヒムラーに例えられたショックによる慟哭は、誰にも殆ど感情を露わにしなかった彼の唯一の小爆発であり涙を誘う。
最も劇的で緊張感を孕んだのは、アンドルウとハンターとの二人場面での遣り取りで、浅野と今井の見ごたえのある場面となった。
また、妻のミリーはテネシー・ウイリアムズの『やけたトタン屋根の上の猫』のマーガレットや『欲望という名の電車』のブランチにも通じるキャラクターで哀れである。ラティガンとウィリアムズの類似性が見えたのも今回の収穫であった。
ラティガンの作劇術の優れているところは、アンドルウを単に哀れな先生とせずに、最後にきっちりと自己主張させたとこに表れている。
人間性の素晴らしさと、その人が置かれた状況とは往々にして比例しないのが現実である。その現実の中で、痩せ我慢しながら生きているのがラティガン作品の主人公である。
明日の終業式で、彼は「チップス先生」になれるかも知れないという、ささやかな期待を持たせてくれる幕切れに快哉を叫び、安堵し、劇場を後にする喜びに浸れたのであった。
(2005-10-22 六本木・俳優座劇場にて butler)










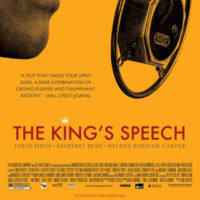


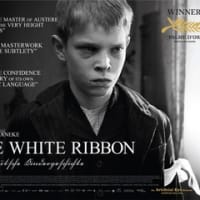

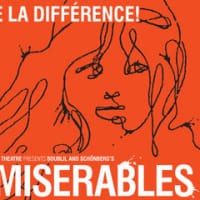
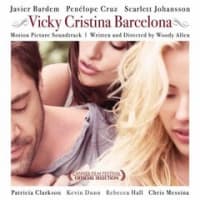
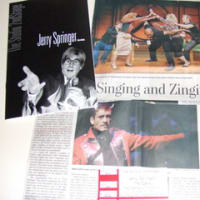
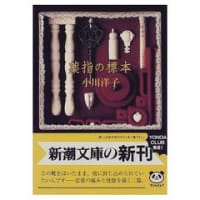
私とは異なった視点での感想を読み、楽しませていただいております。
よろしくお願い致します。
私は他の観劇の為上京し、空時間に何かと思い、当公演をさほど期待もせずに観ました。
しかし、アンドルウの姿に打ちのめされ、今もふと気が付くとこの芝居の様を思い浮かべ、タプロウ少年の純粋な行動を願わずにはいられない気持ちになっております。浅野さんの上手さがあればこその舞台だから、其処まで考えが到るのだと自己分析しております。
あとは照明について、細かい照明プランをたてられる方とは存じ上げておりましたが、ケレン味のある明かりが持て囃される昨今、一幕物をこんなにも美しく効果的に表現されたことに感動いたしました。
男性の考え方(私にとっては想像ですが…)、女性の考え方の温度差、時間では埋められないもどかしさが心に残ります。
こういった佳作の舞台が地方でも公演されることを願わずにはおられません。
コメントをどうもありがとうございます。
一作目の『ウインズロウ・ボーイ』で感動し、今回の『ブラウニング・バージョン』も期待を裏切らないものでした。
私はタブロウ少年の行動は純粋なものだと信じています。
そして卒業式でアンドルウは立派にトリを務めて、生徒達から暖かい感謝の拍手を受けると確信します。
アンドルウに対する考え方は、女性ならずとも男性でも温度差はあると思います。テネシー・ウイリアムズを引き合いに出したのはその為です。
来月上演の第三作目『セパレート・テーブルズ』も大いに楽しみです。
仰られるように、こういうウエル・メイドの芝居こそ地方のこじんまりしたホールでどしどし上演されるといいですね。地味でも感動できる演劇のお手本だと思います。