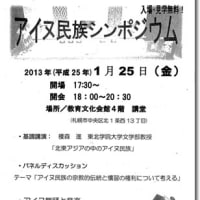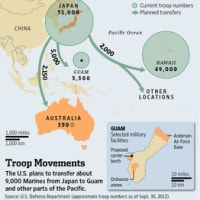アイヌを愛した国語学者、じゃなかったの?~『金田一京助と日本語の近代』
安田敏朗著(評:尹雄大)
平凡社新書、880円(税別)
2008年10月7日 火曜日 尹 雄大
本 金田一京助 国語 アイヌ 帝国主義 4時間00分
『金田一京助と日本語の近代』 安田敏朗著、平凡社新書、880円(税別)
「金田一」と聞いて思い起こされるのは、まずは名探偵の金田一耕助であり、その孫という設定の一(はじめ)少年だろうか。いまでは京助の名をあげる人は少ないかもしれない。
作家の横溝正史は、金田一京助を捩って「耕助」とつけたというから、文化勲章を受賞した東京帝大の文学博士といえば、戦後のある時期まで名の通った人物であったのは間違いなさそうだ。
金田一京助の功績はざっと三つ。アイヌ語を調査し、アイヌに伝わる叙事詩「ユーカラ」を筆録、研究した。石川啄木の親友であり、自身も貧困に喘ぎながら原稿料をはたいて薬を買い与えるなど親身の世話をした。そして、アイヌ語の音韻体系をまとめたことを認められ、戦後の国語政策に深く関わっていった。実は私たちが使っている日本語にも大きな影響を及ぼしているのだ。
そうでありながら金田一自身は、「国語」という国民国家の成立過程でつくられた言語について深く考えていたわけではないという。著者は彼のアイヌへの研究姿勢に言語観そのものの偏りを見てとり、こう述べる。
〈言語と民族について金田一は精緻に考えていたようではない。アイヌはアイヌ語を捨てて帝国日本の言語である国語へと同化せよという金田一の主張は、論理ではない〉
かつて日本を席巻した自民族中心主義が金田一の行ったアイヌ研究や近代日本語の整備にどう関わったのか。本書は、この問題意識を軸に金田一の功績に迫っていく。
著者はまず、金田一のアイヌ研究を俎上に載せる。
アイヌ研究は嫌々やった
アイヌ研究の第一人者である金田一はアイヌに親身であり、彼らから慕われたというイメージはいまもって強固だが、著者の明らかにするエピソードはそれを見事に裏切る。
自身もアイヌ民族であり、アイヌ文化研究者でもあり、また自ら政治家となりアイヌ文化振興法の成立に奔走した萱野茂は、金田一の名を出しはしなかったものの、その死に際しこう述べたという。
〈有名なアイヌの研究家が最近死んだよね。アイヌの人々のあいだから、一つとして悲しみの声は聞かれなかったよ〉
さらに、親友であった石川啄木から「なぜアイヌ語を研究するのか?」と問われ、金田一は以下のように返したと自ら明かしている。
〈あんな哀れなアイヌ語の調べでも、もともと国語の研究の為であり、国語の研究は、日本文化の再認識であり、日本文化の再認識は、吾々の現実生活を深く正しく解釈する所以であつて、即ち吾々の明日の生活を考へる唯一の道だ〉
ダメ押しは文化勲章受賞の翌1954年に発表した「私の仕事」で、金田一は〈自分がひとり、未開人の世界へ後もどりをして、蒙昧な、低級文化の中にいつまでも、いつまでも、さまよつて暮らすのかと、さびしさが込み上げる〉と綴っている。
ここまでくると、「アイヌを愛した金田一」といった像が形成されたのが不思議である。著者は金田一のイノセントさが、彼の学知の質を問う批判を鈍らせていた可能性を示唆する。
だが、〈無邪気であることが、無知であることの責任を回避させる回路だったとしたら、それは大問題である〉。
金田一の人生は、領有した台湾の経営にはじまり樺太の編入、関東州の租借、韓国併合と、日本が世界に伍する帝国にならんとした意気軒昂な時代に重なっていた。
時代の煽りをうけてか、金田一の師であり、日本の言語学の鼻祖である上田万年もまた「日本帝国大学言語学」という構想を標榜。統一した国語を定め、それを制度にのせて敷衍するプロジェクトを抱いていた。
そのためには、「日本語は世界の諸言語の語族のなかのどこに属するか」を示す必要があった。
上田の門下生らは朝鮮語に琉球語と、「日本帝国大学言語学」の見取り図の中で着々と研究を進めていくのだが、金田一はといえば、〈上田からみればアイヌ語研究を金田一がおこなう必然性はなかったともいえる〉といったような成り行きで、彼はアイヌ語を消去法で選ぶほかなかった様子だ。
さらに彼の意気を沮喪させたのは、アイヌ語が、日本語の系統に直接関係ないことが次第に明らかになったことだ。金田一は、せめて科学的な研究であろうとし、アイヌ語の古形を構築する有効な手段として叙事詩のユーカラに着目、採録に努めたという。
そこで彼は、研究の過程でユーカラは現在使われている口語とは違うこと、またアイヌの若者は、伝承されている詩句の意味が理解できないことに気付く。加えて、お互いの口語が通じない樺太アイヌと北海道アイヌ間でも、叙事詩の言葉は通じたことに驚いた。いわく〈叙事詩の言語が今の口語よりも古いものである証拠である。この事を発見したのが私の研究の出発点なのである〉。
金田一にとって叙事詩こそがアイヌ語研究を続ける生命線となり、彼はユーカラを古代ギリシャの『イリアス』、『オデュッセイア』になぞらえた。
牽強付会にも見えるが、その意味合いを著者は〈アイヌに「文芸」をみいだすことによって「社会生活における個別的な利害・経験といった日常的な部分を捨象」することに成功〉したと表している。
こうした「捨象」は、金田一の研究の根底に流れていたとみえ、〈金田一のアイヌ語学が欲したのは、アイヌ語話者ではなく、アイヌ語そのもの〉であったと著者は続ける。さらには、金田一のアイヌ語研究者としての地歩は、現地ではなく東京で固められたということに論は及ぶ。
1912年、上野公園で拓殖博覧会が催され、台湾のタイヤル族やアイヌが会場に「展示」された。金田一は、博覧会場で故郷の生活ぶりを展示していたアイヌと知己を得たことをきっかけに「アイヌのホメロス」ことワカルパ、コポアヌを東京に呼び、筆録を行った。
つまり、彼のアイヌ研究は、「拓殖博覧会がなかったならば完成しえない」ものであり、また「フィールドから切り離された言語学として成立」している側面もあるというのだ。
同様の眼差しと調査手法が、同国人の話す言語にも向けられていたという。
東京の言葉は美しい、地方の言葉は可笑しい
金田一にって、地方人の話す方言とは、〈文運の進みにつれて、漸くその影の薄れてゆくのは必至の運命であり、(略)さうなつて早く全国が中央共通語に統一されべきもの〉であった。したがって、〈無くなる前に、この貴重な資料を、是非とも、完全に調査記録して置かなければならない〉と、誰もが話して通じる国語の前には、方言はあくまで資料だとの考えを崩さない。
ここから窺えるのは、アイヌに対する態度と同じく、生きてしゃべっている人がいるという事実にまったく配慮しない、乾いた言語観だ。
金田一にとっての生きた言語とは、あくまで近代国家の伸張を支えるものであった。だから著者はこんな構図を示す。
拓殖博覧会とは、植民地主義の獲得物を陳列する場にほかならず、そこに引き出されたアイヌを利用した東京での研究とは、植民地支配領域の拡大を前提にしたものである。金田一は「そこにアイヌ語を配置していった」のだと。
太平洋戦争中、金田一は印度にまで達しようとする国家と国語の勢いは歴史の必然であり、〈潮のやうに瀰漫して行く世となつた〉と日本の支配領域の拡大が自然現象であるかのように述べた上で、こう続けている。
〈長幼序なり、男女別ある家族主義のこの暖かい国語を以て、八紘為宇の手をさしのべてやるのである〉
だが、敗戦により植民地という国語の波及先を日本は失った。
戦後、ほどなくして金田一は国語審議会に参加し、現代かなづかいや標準語の設定という、師の上田もかなわなかった国語の政策決定に関与していく。そこに金田一の言語観のクライマックスを見ることができそうだ。
〈全国隅々まで共通語に統一されて行くことは、文化国家の理想である〉
標準語に関する彼の持論は、文化国家では人為的に言葉を統一するのは当然である、というものだ。しかし、共通たるべき標準語の基準は何かというと、「東京の良識」である。
そして、その良識を担保するのは、〈立派な人のは立派に、立派でない人のが立派でない。都人士のいうのは美しく聞え、田舎人のみのいうのは可笑しく聞こえる。これを念頭に置くことが必要である〉という拍子抜けするような理由であることを著者は明らかにしている。
なぜか〈盛岡出身の金田一が自身も「東京の良識」のなかに入っていると思っていた〉らしい。イノセントだからか? 大日本帝国がアイヌを周縁として位置づけたのと同様の、中心から見下ろす視座の反復がここでも行われる。
〈ともあれ問題は、実際の言語調査を経ることなく、自らが決めた「良識」の自省のみで標準語か否かが決まっていく点にある〉
金田一は常に己の良識を疑わない人であった。だからこその邪気のなさだったのだろう。
本著でのいちいちの批判は言語学に門外漢であってもうなずけるところは多い。だが、そうであればなおのこと、日本語の近代化に寄与したと手放しで評価できないはずなのに、学界における金田一京助像にあまり揺らぎが見られないことに改めて訝しさを覚える。
金田一がいうところの良識の善導がもたらした標準語は、今日NHKを通じて聞くことができる。そう思ってキャスターの話す日本語を聞いてみるのもまた一興だろう。
(文/尹雄大、企画・編集/須藤輝&連結社)

安田敏朗著(評:尹雄大)
平凡社新書、880円(税別)
2008年10月7日 火曜日 尹 雄大
本 金田一京助 国語 アイヌ 帝国主義 4時間00分
『金田一京助と日本語の近代』 安田敏朗著、平凡社新書、880円(税別)
「金田一」と聞いて思い起こされるのは、まずは名探偵の金田一耕助であり、その孫という設定の一(はじめ)少年だろうか。いまでは京助の名をあげる人は少ないかもしれない。
作家の横溝正史は、金田一京助を捩って「耕助」とつけたというから、文化勲章を受賞した東京帝大の文学博士といえば、戦後のある時期まで名の通った人物であったのは間違いなさそうだ。
金田一京助の功績はざっと三つ。アイヌ語を調査し、アイヌに伝わる叙事詩「ユーカラ」を筆録、研究した。石川啄木の親友であり、自身も貧困に喘ぎながら原稿料をはたいて薬を買い与えるなど親身の世話をした。そして、アイヌ語の音韻体系をまとめたことを認められ、戦後の国語政策に深く関わっていった。実は私たちが使っている日本語にも大きな影響を及ぼしているのだ。
そうでありながら金田一自身は、「国語」という国民国家の成立過程でつくられた言語について深く考えていたわけではないという。著者は彼のアイヌへの研究姿勢に言語観そのものの偏りを見てとり、こう述べる。
〈言語と民族について金田一は精緻に考えていたようではない。アイヌはアイヌ語を捨てて帝国日本の言語である国語へと同化せよという金田一の主張は、論理ではない〉
かつて日本を席巻した自民族中心主義が金田一の行ったアイヌ研究や近代日本語の整備にどう関わったのか。本書は、この問題意識を軸に金田一の功績に迫っていく。
著者はまず、金田一のアイヌ研究を俎上に載せる。
アイヌ研究は嫌々やった
アイヌ研究の第一人者である金田一はアイヌに親身であり、彼らから慕われたというイメージはいまもって強固だが、著者の明らかにするエピソードはそれを見事に裏切る。
自身もアイヌ民族であり、アイヌ文化研究者でもあり、また自ら政治家となりアイヌ文化振興法の成立に奔走した萱野茂は、金田一の名を出しはしなかったものの、その死に際しこう述べたという。
〈有名なアイヌの研究家が最近死んだよね。アイヌの人々のあいだから、一つとして悲しみの声は聞かれなかったよ〉
さらに、親友であった石川啄木から「なぜアイヌ語を研究するのか?」と問われ、金田一は以下のように返したと自ら明かしている。
〈あんな哀れなアイヌ語の調べでも、もともと国語の研究の為であり、国語の研究は、日本文化の再認識であり、日本文化の再認識は、吾々の現実生活を深く正しく解釈する所以であつて、即ち吾々の明日の生活を考へる唯一の道だ〉
ダメ押しは文化勲章受賞の翌1954年に発表した「私の仕事」で、金田一は〈自分がひとり、未開人の世界へ後もどりをして、蒙昧な、低級文化の中にいつまでも、いつまでも、さまよつて暮らすのかと、さびしさが込み上げる〉と綴っている。
ここまでくると、「アイヌを愛した金田一」といった像が形成されたのが不思議である。著者は金田一のイノセントさが、彼の学知の質を問う批判を鈍らせていた可能性を示唆する。
だが、〈無邪気であることが、無知であることの責任を回避させる回路だったとしたら、それは大問題である〉。
金田一の人生は、領有した台湾の経営にはじまり樺太の編入、関東州の租借、韓国併合と、日本が世界に伍する帝国にならんとした意気軒昂な時代に重なっていた。
時代の煽りをうけてか、金田一の師であり、日本の言語学の鼻祖である上田万年もまた「日本帝国大学言語学」という構想を標榜。統一した国語を定め、それを制度にのせて敷衍するプロジェクトを抱いていた。
そのためには、「日本語は世界の諸言語の語族のなかのどこに属するか」を示す必要があった。
上田の門下生らは朝鮮語に琉球語と、「日本帝国大学言語学」の見取り図の中で着々と研究を進めていくのだが、金田一はといえば、〈上田からみればアイヌ語研究を金田一がおこなう必然性はなかったともいえる〉といったような成り行きで、彼はアイヌ語を消去法で選ぶほかなかった様子だ。
さらに彼の意気を沮喪させたのは、アイヌ語が、日本語の系統に直接関係ないことが次第に明らかになったことだ。金田一は、せめて科学的な研究であろうとし、アイヌ語の古形を構築する有効な手段として叙事詩のユーカラに着目、採録に努めたという。
そこで彼は、研究の過程でユーカラは現在使われている口語とは違うこと、またアイヌの若者は、伝承されている詩句の意味が理解できないことに気付く。加えて、お互いの口語が通じない樺太アイヌと北海道アイヌ間でも、叙事詩の言葉は通じたことに驚いた。いわく〈叙事詩の言語が今の口語よりも古いものである証拠である。この事を発見したのが私の研究の出発点なのである〉。
金田一にとって叙事詩こそがアイヌ語研究を続ける生命線となり、彼はユーカラを古代ギリシャの『イリアス』、『オデュッセイア』になぞらえた。
牽強付会にも見えるが、その意味合いを著者は〈アイヌに「文芸」をみいだすことによって「社会生活における個別的な利害・経験といった日常的な部分を捨象」することに成功〉したと表している。
こうした「捨象」は、金田一の研究の根底に流れていたとみえ、〈金田一のアイヌ語学が欲したのは、アイヌ語話者ではなく、アイヌ語そのもの〉であったと著者は続ける。さらには、金田一のアイヌ語研究者としての地歩は、現地ではなく東京で固められたということに論は及ぶ。
1912年、上野公園で拓殖博覧会が催され、台湾のタイヤル族やアイヌが会場に「展示」された。金田一は、博覧会場で故郷の生活ぶりを展示していたアイヌと知己を得たことをきっかけに「アイヌのホメロス」ことワカルパ、コポアヌを東京に呼び、筆録を行った。
つまり、彼のアイヌ研究は、「拓殖博覧会がなかったならば完成しえない」ものであり、また「フィールドから切り離された言語学として成立」している側面もあるというのだ。
同様の眼差しと調査手法が、同国人の話す言語にも向けられていたという。
東京の言葉は美しい、地方の言葉は可笑しい
金田一にって、地方人の話す方言とは、〈文運の進みにつれて、漸くその影の薄れてゆくのは必至の運命であり、(略)さうなつて早く全国が中央共通語に統一されべきもの〉であった。したがって、〈無くなる前に、この貴重な資料を、是非とも、完全に調査記録して置かなければならない〉と、誰もが話して通じる国語の前には、方言はあくまで資料だとの考えを崩さない。
ここから窺えるのは、アイヌに対する態度と同じく、生きてしゃべっている人がいるという事実にまったく配慮しない、乾いた言語観だ。
金田一にとっての生きた言語とは、あくまで近代国家の伸張を支えるものであった。だから著者はこんな構図を示す。
拓殖博覧会とは、植民地主義の獲得物を陳列する場にほかならず、そこに引き出されたアイヌを利用した東京での研究とは、植民地支配領域の拡大を前提にしたものである。金田一は「そこにアイヌ語を配置していった」のだと。
太平洋戦争中、金田一は印度にまで達しようとする国家と国語の勢いは歴史の必然であり、〈潮のやうに瀰漫して行く世となつた〉と日本の支配領域の拡大が自然現象であるかのように述べた上で、こう続けている。
〈長幼序なり、男女別ある家族主義のこの暖かい国語を以て、八紘為宇の手をさしのべてやるのである〉
だが、敗戦により植民地という国語の波及先を日本は失った。
戦後、ほどなくして金田一は国語審議会に参加し、現代かなづかいや標準語の設定という、師の上田もかなわなかった国語の政策決定に関与していく。そこに金田一の言語観のクライマックスを見ることができそうだ。
〈全国隅々まで共通語に統一されて行くことは、文化国家の理想である〉
標準語に関する彼の持論は、文化国家では人為的に言葉を統一するのは当然である、というものだ。しかし、共通たるべき標準語の基準は何かというと、「東京の良識」である。
そして、その良識を担保するのは、〈立派な人のは立派に、立派でない人のが立派でない。都人士のいうのは美しく聞え、田舎人のみのいうのは可笑しく聞こえる。これを念頭に置くことが必要である〉という拍子抜けするような理由であることを著者は明らかにしている。
なぜか〈盛岡出身の金田一が自身も「東京の良識」のなかに入っていると思っていた〉らしい。イノセントだからか? 大日本帝国がアイヌを周縁として位置づけたのと同様の、中心から見下ろす視座の反復がここでも行われる。
〈ともあれ問題は、実際の言語調査を経ることなく、自らが決めた「良識」の自省のみで標準語か否かが決まっていく点にある〉
金田一は常に己の良識を疑わない人であった。だからこその邪気のなさだったのだろう。
本著でのいちいちの批判は言語学に門外漢であってもうなずけるところは多い。だが、そうであればなおのこと、日本語の近代化に寄与したと手放しで評価できないはずなのに、学界における金田一京助像にあまり揺らぎが見られないことに改めて訝しさを覚える。
金田一がいうところの良識の善導がもたらした標準語は、今日NHKを通じて聞くことができる。そう思ってキャスターの話す日本語を聞いてみるのもまた一興だろう。
(文/尹雄大、企画・編集/須藤輝&連結社)