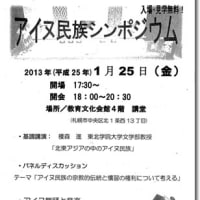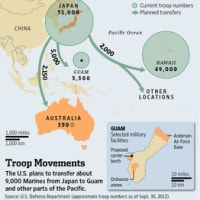アイヌの今:民族共生に向けて/上 文化 /北海道
◇振興法にほころびも--国の支援不十分、継承に不安
「イランカラプテー(こんにちは)」。日高管内平取町の中心部から車で約15分。アイヌ民族初の国会議員となった萱野茂さん(06年死去)が山あいに開いた私設図書館で、次男志朗さん(50)がマイクに語りかけた。志朗さんが主宰する国内唯一のアイヌ語ラジオ「FMピパウシ」の放送だ。
萱野茂さんは約30万円かけて中古機材を購入し、01年4月に免許のいらないミニFM局を開局した。父の遺志を継いだ志朗さんが毎月第2日曜日の午前11時から正午まで、アイヌ民話の朗読や簡単なアイヌ語講座など月1回の放送を続ける。語り手やスタッフ約10人はボランティアで、電波が届く範囲は半径約200メートル。受信可能な民家は3軒程度だが、放送はインターネットでも配信しており、平均300件のアクセスがある。
◇
97年施行のアイヌ文化振興法(アイヌ新法)は、国がアイヌ文化の継承者育成などに努めることをうたった。だが、差別を嫌ってアイヌ語を子どもに教えてこなかったアイヌの家庭も多く、アイヌ語の話し手は年々減少しているとみられる。佐藤幸治・京大名誉教授は「文化の継承・発展は『言葉』であり、これをどう展開していくかが大きな問題だ」と指摘する。
アイヌ新法に基づき設置されたアイヌ文化振興・研究推進機構は国の補助を受け、アイヌ語の普及事業などを実施している。しかし、民間への助成は単年度事業に限られる。ラジオ局のような複数年度にまたがる活動は対象外とされ、年間約20万円に上る機材の維持費などを負担している志朗さんは「手続きも煩雑で、使い勝手が悪い」と批判する。
◇
胆振管内白老町では06年度から、アイヌ民族が伝統的に生活を営んできた森や河川を整備する「伝統的生活空間(イオル)再生事業」が始まった。明治政府がアイヌの土地を収奪した歴史を踏まえ、政府の「ウタリ対策のあり方に関する有識者懇談会」が96年に提案した目玉事業。イオルでは、アイヌが生活用具に利用していたオヒョウなどの苗木が植樹され、成木は伝統工芸の素材となる予定だ。
ただ、オヒョウは近くの国有林にも多く自生している。地元の関係者からは「木が育つのを待つうちに伝承者がいなくなってしまう」と国有林の活用を求める声も出ているが、事業の実施主体が同機構のため「国有林は使えない」(胆振東部森林管理署)というのが国の見解。アイヌ民族博物館の前館長、中村斎(いつき)さん(76)は「国がアイヌのことを本当に考えているとは思えない」と不信感をぬぐえない。
× ×
アイヌ新法制定から間もなく12年。アイヌの文化振興をうたった新法に「ほころび」も見え隠れする中、08年6月にはアイヌ民族を先住民族と認定するよう求める初の国会決議が採択され、政府は新たな「アイヌ政策のあり方に関する有識者懇談会」を設置した。今夏にもまとめられる懇談会報告書を前に、アイヌの現場から今、必要な施策を考える。
==============
■ことば
◇アイヌ文化振興法
97年7月、アイヌ文化の振興・普及・啓発などを図ることを目的に施行された。差別法といわれた北海道旧土人保護法が同時に廃止されたことから、アイヌ新法とも呼ばれる。具体的な事業の実施主体として、財団法人「アイヌ文化振興・研究推進機構」(札幌市)が設立され、アイヌ関連の研究事業やアイヌ語教育・普及事業のほか、伝統的生活空間(イオル)再生事業などが行われている。同法はアイヌ政策の転換点となったが、アイヌを先住民族と認定することを避けたほか、内容も「文化」に特化され、アイヌ側が求めた生活支援策などは盛り込まれなかった。
毎日新聞 2009年1月9日 地方版

◇振興法にほころびも--国の支援不十分、継承に不安
「イランカラプテー(こんにちは)」。日高管内平取町の中心部から車で約15分。アイヌ民族初の国会議員となった萱野茂さん(06年死去)が山あいに開いた私設図書館で、次男志朗さん(50)がマイクに語りかけた。志朗さんが主宰する国内唯一のアイヌ語ラジオ「FMピパウシ」の放送だ。
萱野茂さんは約30万円かけて中古機材を購入し、01年4月に免許のいらないミニFM局を開局した。父の遺志を継いだ志朗さんが毎月第2日曜日の午前11時から正午まで、アイヌ民話の朗読や簡単なアイヌ語講座など月1回の放送を続ける。語り手やスタッフ約10人はボランティアで、電波が届く範囲は半径約200メートル。受信可能な民家は3軒程度だが、放送はインターネットでも配信しており、平均300件のアクセスがある。
◇
97年施行のアイヌ文化振興法(アイヌ新法)は、国がアイヌ文化の継承者育成などに努めることをうたった。だが、差別を嫌ってアイヌ語を子どもに教えてこなかったアイヌの家庭も多く、アイヌ語の話し手は年々減少しているとみられる。佐藤幸治・京大名誉教授は「文化の継承・発展は『言葉』であり、これをどう展開していくかが大きな問題だ」と指摘する。
アイヌ新法に基づき設置されたアイヌ文化振興・研究推進機構は国の補助を受け、アイヌ語の普及事業などを実施している。しかし、民間への助成は単年度事業に限られる。ラジオ局のような複数年度にまたがる活動は対象外とされ、年間約20万円に上る機材の維持費などを負担している志朗さんは「手続きも煩雑で、使い勝手が悪い」と批判する。
◇
胆振管内白老町では06年度から、アイヌ民族が伝統的に生活を営んできた森や河川を整備する「伝統的生活空間(イオル)再生事業」が始まった。明治政府がアイヌの土地を収奪した歴史を踏まえ、政府の「ウタリ対策のあり方に関する有識者懇談会」が96年に提案した目玉事業。イオルでは、アイヌが生活用具に利用していたオヒョウなどの苗木が植樹され、成木は伝統工芸の素材となる予定だ。
ただ、オヒョウは近くの国有林にも多く自生している。地元の関係者からは「木が育つのを待つうちに伝承者がいなくなってしまう」と国有林の活用を求める声も出ているが、事業の実施主体が同機構のため「国有林は使えない」(胆振東部森林管理署)というのが国の見解。アイヌ民族博物館の前館長、中村斎(いつき)さん(76)は「国がアイヌのことを本当に考えているとは思えない」と不信感をぬぐえない。
× ×
アイヌ新法制定から間もなく12年。アイヌの文化振興をうたった新法に「ほころび」も見え隠れする中、08年6月にはアイヌ民族を先住民族と認定するよう求める初の国会決議が採択され、政府は新たな「アイヌ政策のあり方に関する有識者懇談会」を設置した。今夏にもまとめられる懇談会報告書を前に、アイヌの現場から今、必要な施策を考える。
==============
■ことば
◇アイヌ文化振興法
97年7月、アイヌ文化の振興・普及・啓発などを図ることを目的に施行された。差別法といわれた北海道旧土人保護法が同時に廃止されたことから、アイヌ新法とも呼ばれる。具体的な事業の実施主体として、財団法人「アイヌ文化振興・研究推進機構」(札幌市)が設立され、アイヌ関連の研究事業やアイヌ語教育・普及事業のほか、伝統的生活空間(イオル)再生事業などが行われている。同法はアイヌ政策の転換点となったが、アイヌを先住民族と認定することを避けたほか、内容も「文化」に特化され、アイヌ側が求めた生活支援策などは盛り込まれなかった。
毎日新聞 2009年1月9日 地方版