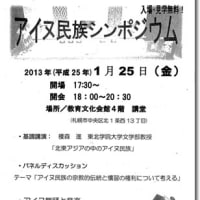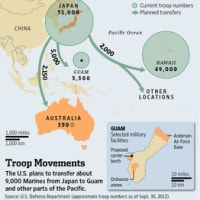高度な近世アイヌ農耕 遺跡から畝や鉄製農具
2008年01月22日10時28分
ヒグマ狩りやサケ漁などのイメージから、「狩猟・漁労の民」と見られることが多いアイヌの人々。そんな彼らが、近世以前にかなり高いレベルで農耕を営んでいたことが最近の研究で明らかになってきた。江戸時代の文献などに「畝(うね)も作らず、放置したままの粗雑な農業」と記された姿は、実は現地を支配していた松前藩などによって抑圧された結果である可能性が高いという。
研究をまとめたのは、北海道開拓記念館の山田悟郎・学芸部長。
サケや昆布を採り、それらを交易することで、米や漆器、刀、鉄鍋などを手に入れる――。私たちが考えているような、いわゆる「アイヌ文化」は、13世紀末(鎌倉時代後期)に生まれたと考えられている。
母体となったのは、ほぼ同じ地域に広がっていた「擦文(さつもん)文化」(7~13世紀)だ。表面にハケ目のある土器を使うのが特徴で、サケ・マス漁のかたわら、大麦、アワ、キビなどを栽培していた。
山田部長は、この擦文文化を調べていく過程で、アイヌのものと推定される畑が道内各地で出土していることに気づく。「最初の発見は97年。虻田町(現在は洞爺湖町)の高砂貝塚で、土層の断面に畑の畝らしい痕跡が確認されたのがきっかけ。その後、『似たものがうちにも』という報告があり、北海道全域で出土例が増えた」
現在確認されているアイヌ文化期の畑跡は、高砂貝塚のほか、ポンマ遺跡(伊達市)、オヤコツ遺跡(同)など十数カ所。
いずれも広さ数1000平方メートルで、幅70センチ~1メートルの畝が10列程度まとまり、一つの畑を構成している。周辺の集落で発掘された遺物や、畑に積もった火山灰などの年代から、「17世紀以前のアイヌ文化期のものである可能性が高い」という。
さらに出土した土を洗い、札幌国際大客員研究員の椿坂恭代さんらの協力を得て調べたところ、20カ所を超える遺跡から、大麦、ヒエ、アワ、キビ、ソバ、小豆など、十数種の作物の種子が確認された。
鉄製の農具も使われていたらしい。鋤(すき)先や鎌などが出土しており、「土掘り棒や木製の鍬(くわ)と併用されていた様子がうかがえる」。
さらに、「水はけをよくするための畝をつくる技術を持っていたことからみて、近世のアイヌたちがかなり進んだ農業をしていたことは間違いない」と指摘する。
だが、こうした状況は、文献に描かれたアイヌの姿とは大きく異なる。
18世紀末(江戸後期)に北海道を訪れた幕府の役人・近藤重蔵は当時のアイヌの農耕について、「木の枝やマキリ(小刀)で土地を耕し、畝を立てず肥料も使わず、鍬や鎌もなく……」と記している。
一体、どちらが正しいのか。
山田部長は「1669年(江戸中期)に起きたシャクシャインの戦いを境にアイヌの農業は大きく変質したのではないか」と推測する。松前藩の過酷な支配に抗議して起きたこの蜂起の後、同藩はアイヌに対して刀狩りを行い、農具をはじめとする、鉄製利器の入手を制限した。
「さらにアイヌの居住区を制限し、その場所を商人の支配に委ねる場所請負制が導入されたことで、アイヌの人々は、過酷な労働に駆り出されるようになります。その結果、従来のような農業を続けられなくなったのではないでしょうか」
これまでアイヌの生業については漁猟の側面が強調されてきたが、この研究をみる限り、むしろ半農半漁に近かった可能性が高い。
古代~中世の植物利用を研究している小畑弘己・熊本大准教授(考古学)は「ひたすら土を洗い、種子を同定するという地道な作業が結果につながった。文献の空白を埋める貴重な成果だ」と話している。
2008年01月22日10時28分
ヒグマ狩りやサケ漁などのイメージから、「狩猟・漁労の民」と見られることが多いアイヌの人々。そんな彼らが、近世以前にかなり高いレベルで農耕を営んでいたことが最近の研究で明らかになってきた。江戸時代の文献などに「畝(うね)も作らず、放置したままの粗雑な農業」と記された姿は、実は現地を支配していた松前藩などによって抑圧された結果である可能性が高いという。
研究をまとめたのは、北海道開拓記念館の山田悟郎・学芸部長。
サケや昆布を採り、それらを交易することで、米や漆器、刀、鉄鍋などを手に入れる――。私たちが考えているような、いわゆる「アイヌ文化」は、13世紀末(鎌倉時代後期)に生まれたと考えられている。
母体となったのは、ほぼ同じ地域に広がっていた「擦文(さつもん)文化」(7~13世紀)だ。表面にハケ目のある土器を使うのが特徴で、サケ・マス漁のかたわら、大麦、アワ、キビなどを栽培していた。
山田部長は、この擦文文化を調べていく過程で、アイヌのものと推定される畑が道内各地で出土していることに気づく。「最初の発見は97年。虻田町(現在は洞爺湖町)の高砂貝塚で、土層の断面に畑の畝らしい痕跡が確認されたのがきっかけ。その後、『似たものがうちにも』という報告があり、北海道全域で出土例が増えた」
現在確認されているアイヌ文化期の畑跡は、高砂貝塚のほか、ポンマ遺跡(伊達市)、オヤコツ遺跡(同)など十数カ所。
いずれも広さ数1000平方メートルで、幅70センチ~1メートルの畝が10列程度まとまり、一つの畑を構成している。周辺の集落で発掘された遺物や、畑に積もった火山灰などの年代から、「17世紀以前のアイヌ文化期のものである可能性が高い」という。
さらに出土した土を洗い、札幌国際大客員研究員の椿坂恭代さんらの協力を得て調べたところ、20カ所を超える遺跡から、大麦、ヒエ、アワ、キビ、ソバ、小豆など、十数種の作物の種子が確認された。
鉄製の農具も使われていたらしい。鋤(すき)先や鎌などが出土しており、「土掘り棒や木製の鍬(くわ)と併用されていた様子がうかがえる」。
さらに、「水はけをよくするための畝をつくる技術を持っていたことからみて、近世のアイヌたちがかなり進んだ農業をしていたことは間違いない」と指摘する。
だが、こうした状況は、文献に描かれたアイヌの姿とは大きく異なる。
18世紀末(江戸後期)に北海道を訪れた幕府の役人・近藤重蔵は当時のアイヌの農耕について、「木の枝やマキリ(小刀)で土地を耕し、畝を立てず肥料も使わず、鍬や鎌もなく……」と記している。
一体、どちらが正しいのか。
山田部長は「1669年(江戸中期)に起きたシャクシャインの戦いを境にアイヌの農業は大きく変質したのではないか」と推測する。松前藩の過酷な支配に抗議して起きたこの蜂起の後、同藩はアイヌに対して刀狩りを行い、農具をはじめとする、鉄製利器の入手を制限した。
「さらにアイヌの居住区を制限し、その場所を商人の支配に委ねる場所請負制が導入されたことで、アイヌの人々は、過酷な労働に駆り出されるようになります。その結果、従来のような農業を続けられなくなったのではないでしょうか」
これまでアイヌの生業については漁猟の側面が強調されてきたが、この研究をみる限り、むしろ半農半漁に近かった可能性が高い。
古代~中世の植物利用を研究している小畑弘己・熊本大准教授(考古学)は「ひたすら土を洗い、種子を同定するという地道な作業が結果につながった。文献の空白を埋める貴重な成果だ」と話している。