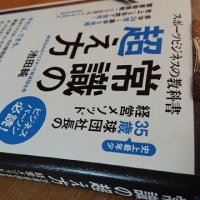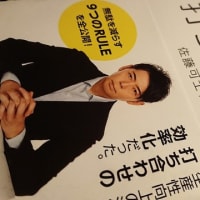具体的な企業名など一切出てこないのに、この本に描かれている組織にはとてもリアリティがある。
「ルーチンワークは創造性を駆逐する」(計画のグレシャムの法則)の通りにルーチンワークで忙殺されている組織は、忙しいことに満足して実際には背後にある構造的な問題に気づいていないという。「貧乏暇なし」や「木こりのジレンマ」(忙しくて、切れない斧を研ぐ時間もないという木こりの話)でも当てはまるが、実際によく出会う現象だ。
著者はマズローの欲求段階説の解釈の常識も疑っている。マズローの欲求段階説ではピラミッドの一番上に自己実現欲求があるが、これを裏付ける実証的研究の結果は出ていないらしい。しかし根強くこのピラミッドの上の自己実現欲求に人気があるのは、この考え方が美しく安上がりだからという。自己実現では報酬はいらないし、自己実現というとあいまいだが人を尊重しているようにみんなが思う。しかしモチベーション管理の有効性を考えると、自己実現欲求より「承認・尊厳欲求」が重要らしい。承認・尊厳欲求は本人が組織で必要だと自覚させる効果がある。これを満たすためには、たんにポストを与えるとかだけでなく、成功体験をさせるためにプロジェクトをまかせるとか、成果をほめるとか組織運営に重要であることを示すいくつかの方法がある。
この本で鋭い分析だと思ったのは、「組織のフリーライダー論」と「トラの権力、キツネの権力論」である。頑張る人の努力に乗っかって、自分は野党的に適当に批判したりして安全な楽な立場にいる人のことを「フリーライダー」という。これが増えると組織を腐らせるもとになる。この問題の解決法は責任感の強い人を採用し、企業の運命と自分の運命は一心同体だと思う人を育てることだ。
組織内の奇妙な権力の一つに「厄介者の権力」がある。これは「人前ですごんだり、大騒ぎしたりする」という育ちの悪さを基盤としている。こういう大人気ない行動をとる「厄介者」が権力をもつのは優等生の多い組織に特徴的だそうだ。大企業や省庁が典型。こういう厄介者が騒いだとき、そこで叱り飛ばす人がいれば厄介者が権力をもつことはないのだが、優等生たちが「騒ぎだされたら収拾がつかなくなる」と大人になればなるほど厄介者が権力を握ることになる。
キツネの権力とは「トラの威を借るキツネ」のことである。社長が好まないからとか、重要取引先が要求しているからとメンッセンジャーの役割を担う人がこの権力を握る。ひどい場合は架空のトラをつくることもできる。キツネの権力の温床も優等生の集まりだそうだ。本当に対決しなければならない権力との対決を避け、調整に委ねれば委ねるほど、トラの威を借るキツネが暗躍する。これらの奇妙な権力が育つのは組織が衰退しているときの象徴だそうだ。役員が多すぎて調整事項が多すぎたり、ヒソヒソ話が起きやすい環境ができるととくに奇妙な権力が生まれるという。これを防ぐためには役員数を減らし、面と向かって討論するようにすることだ。そうすれば根性のないキツネが権力を握ったりすることはない。
花形の成熟事業部に優秀な人材を集めることも内向きの仕事を増やすばかりだという。成熟事業部に優秀な人が集まると実際には成熟市場に対する仕事がないのに、余計な仕事(やたらと完成度の高いプレゼン資料や報告書など)ばかり作るようになる。これを外向きの組織にするためには、古いルールはトップダウンでなくしてしまい、成熟事業部から優秀な人を引き抜き、新規事業部につけるとか若手を抜擢することなどが有効らしい。
この本は組織をロジカルに分析した良書だ。ときどき読み返したい。
「ルーチンワークは創造性を駆逐する」(計画のグレシャムの法則)の通りにルーチンワークで忙殺されている組織は、忙しいことに満足して実際には背後にある構造的な問題に気づいていないという。「貧乏暇なし」や「木こりのジレンマ」(忙しくて、切れない斧を研ぐ時間もないという木こりの話)でも当てはまるが、実際によく出会う現象だ。
著者はマズローの欲求段階説の解釈の常識も疑っている。マズローの欲求段階説ではピラミッドの一番上に自己実現欲求があるが、これを裏付ける実証的研究の結果は出ていないらしい。しかし根強くこのピラミッドの上の自己実現欲求に人気があるのは、この考え方が美しく安上がりだからという。自己実現では報酬はいらないし、自己実現というとあいまいだが人を尊重しているようにみんなが思う。しかしモチベーション管理の有効性を考えると、自己実現欲求より「承認・尊厳欲求」が重要らしい。承認・尊厳欲求は本人が組織で必要だと自覚させる効果がある。これを満たすためには、たんにポストを与えるとかだけでなく、成功体験をさせるためにプロジェクトをまかせるとか、成果をほめるとか組織運営に重要であることを示すいくつかの方法がある。
この本で鋭い分析だと思ったのは、「組織のフリーライダー論」と「トラの権力、キツネの権力論」である。頑張る人の努力に乗っかって、自分は野党的に適当に批判したりして安全な楽な立場にいる人のことを「フリーライダー」という。これが増えると組織を腐らせるもとになる。この問題の解決法は責任感の強い人を採用し、企業の運命と自分の運命は一心同体だと思う人を育てることだ。
組織内の奇妙な権力の一つに「厄介者の権力」がある。これは「人前ですごんだり、大騒ぎしたりする」という育ちの悪さを基盤としている。こういう大人気ない行動をとる「厄介者」が権力をもつのは優等生の多い組織に特徴的だそうだ。大企業や省庁が典型。こういう厄介者が騒いだとき、そこで叱り飛ばす人がいれば厄介者が権力をもつことはないのだが、優等生たちが「騒ぎだされたら収拾がつかなくなる」と大人になればなるほど厄介者が権力を握ることになる。
キツネの権力とは「トラの威を借るキツネ」のことである。社長が好まないからとか、重要取引先が要求しているからとメンッセンジャーの役割を担う人がこの権力を握る。ひどい場合は架空のトラをつくることもできる。キツネの権力の温床も優等生の集まりだそうだ。本当に対決しなければならない権力との対決を避け、調整に委ねれば委ねるほど、トラの威を借るキツネが暗躍する。これらの奇妙な権力が育つのは組織が衰退しているときの象徴だそうだ。役員が多すぎて調整事項が多すぎたり、ヒソヒソ話が起きやすい環境ができるととくに奇妙な権力が生まれるという。これを防ぐためには役員数を減らし、面と向かって討論するようにすることだ。そうすれば根性のないキツネが権力を握ったりすることはない。
花形の成熟事業部に優秀な人材を集めることも内向きの仕事を増やすばかりだという。成熟事業部に優秀な人が集まると実際には成熟市場に対する仕事がないのに、余計な仕事(やたらと完成度の高いプレゼン資料や報告書など)ばかり作るようになる。これを外向きの組織にするためには、古いルールはトップダウンでなくしてしまい、成熟事業部から優秀な人を引き抜き、新規事業部につけるとか若手を抜擢することなどが有効らしい。
この本は組織をロジカルに分析した良書だ。ときどき読み返したい。