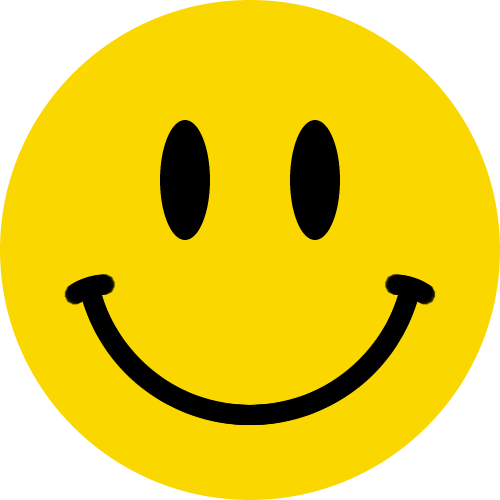この度は東京都東大和市の多摩湖(村山貯水池)、
埼玉県の狭山湖(山口貯水池)に行ってきました。
東京都の安定した水源を確保するため狭山丘陵に造られた人口湖で、
大正13年完成の村山上貯水池と、昭和2年完成の村山下貯水池の
二つの池からできており、旧地名である「村山郷」から名付けられている。
また、埼玉県側に昭和9年完成の山口貯水池が隣接していて、
埼玉県所沢市・入間市にあるが、東京都水道局が管理している。
多摩川水系施設として、東京都羽村市の小作取水堰や羽村取水堰を水源とし、
東村山市の東村山浄水場及び武蔵野市の境浄水場、埼玉県の朝霞浄水場への
供給経路として、東京都の上水道として供給されている。
昭和30年代までは、水道水源の多くを多摩川水系に依存してきましたが、
東京都は利根川水系の水資源開発に合わせて、利根川水系への依存度を高め、
現在は78%が利根川・荒川水系、19%が多摩川水系、地下水0.2%の比率で
水源を確保しており、多摩川系貯水池は緊急時に備えて貯水に努めている。
東京都の特別区を除いた現在の多摩地域は、かつては神奈川県に属していたが、
東京市の水源地である玉川上水の管理、水道拡張の早急な計画の必要性に迫られ、
明治26年(1893年)に神奈川県から東京府へ編入されたと言われている。しかし真相は
政治的な問題で、多摩地域を地盤としていた政党を壊滅するのが目的だったと言われる。
徳川幕府入府後、川の流れを変えたり、関東ローム層の武蔵野台地の開削など、
東京都は水との闘いなしでは語れない土地である。

埼玉県側に湖底の村広場があり、ダムに沈んだ村の歴史の一端を紹介している。
縄文時代から2万年に及ぶ歴史を持ち、発掘調査で掘り出された遺跡は東大和市
郷土博物館に展示されている。写真は慶性院の山門(慶性門)。
埼玉県の狭山湖(山口貯水池)に行ってきました。
東京都の安定した水源を確保するため狭山丘陵に造られた人口湖で、
大正13年完成の村山上貯水池と、昭和2年完成の村山下貯水池の
二つの池からできており、旧地名である「村山郷」から名付けられている。
また、埼玉県側に昭和9年完成の山口貯水池が隣接していて、
埼玉県所沢市・入間市にあるが、東京都水道局が管理している。
多摩川水系施設として、東京都羽村市の小作取水堰や羽村取水堰を水源とし、
東村山市の東村山浄水場及び武蔵野市の境浄水場、埼玉県の朝霞浄水場への
供給経路として、東京都の上水道として供給されている。
昭和30年代までは、水道水源の多くを多摩川水系に依存してきましたが、
東京都は利根川水系の水資源開発に合わせて、利根川水系への依存度を高め、
現在は78%が利根川・荒川水系、19%が多摩川水系、地下水0.2%の比率で
水源を確保しており、多摩川系貯水池は緊急時に備えて貯水に努めている。
東京都の特別区を除いた現在の多摩地域は、かつては神奈川県に属していたが、
東京市の水源地である玉川上水の管理、水道拡張の早急な計画の必要性に迫られ、
明治26年(1893年)に神奈川県から東京府へ編入されたと言われている。しかし真相は
政治的な問題で、多摩地域を地盤としていた政党を壊滅するのが目的だったと言われる。
徳川幕府入府後、川の流れを変えたり、関東ローム層の武蔵野台地の開削など、
東京都は水との闘いなしでは語れない土地である。

埼玉県側に湖底の村広場があり、ダムに沈んだ村の歴史の一端を紹介している。
縄文時代から2万年に及ぶ歴史を持ち、発掘調査で掘り出された遺跡は東大和市
郷土博物館に展示されている。写真は慶性院の山門(慶性門)。