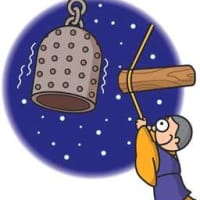【緑茶の日】= 日本茶業中央会が制定。八十八夜は茶摘みの最盛期であることから。八十八夜は年によって日が変わるのが、5月2日(閏年は5月1日)に固定して実施している。
http://www.meisetudo.com/topics/chishiki.html
「新茶」= その年の最初に生育した新芽を摘み採ってつくったお茶のことをいいます。
鹿児島などの温暖な地域から摘み採りが始まり、桜前線と同様に徐々に北上していきます。
「新茶」と「一番茶」とは基本的に同じお茶のことで、呼び方が異なるだけです。その使い分けとしては、「一番茶」はその後に摘み採られる「二番茶」「三番茶」などと対比して使われることが多く、「新茶」は一年で最初に摘まれる「初物(はつもの)」の意味を込めて、また「旬」のものとして呼ばれる際などに使われます。
茶樹は、冬の間に養分を蓄え、春の芽生えとともにその栄養分をたくさん含んだみずみずしい若葉を成長させます。それが新茶となるのです。立春(2月4日)から数えて88日目の日を「八十八夜」といい、昔から、この日に摘み採られたお茶を飲むと、一年間無病息災で元気に過ごせると言い伝えられています。
新茶の特徴は、何といっても若葉の「さわやかですがすがしい香り」にあります。また、新茶は「二番茶」「三番茶」に比べて苦渋いカテキンやカフェインが少なく、旨み、甘みの成分であるアミノ酸(テアニン)が多いといわれます。
” 茶摘(ちゃつみ)(唱歌)
夏も近づく八十八夜
野にも山にも若葉が茂る
あれに見えるは
茶摘ぢやないか
あかねだすきに菅(すげ)の笠
日和つづきの今日此の頃を、
心のどかに摘みつつ歌ふ
摘めよ 摘め摘め
摘まねばならぬ
摘まにや日本の茶にならぬ ”
茶摘(ちゃつみ)〔文部省唱歌〕
夏も近づく八十八夜 野にも山にも若葉が茂る・・・
日本の茶摘の様子を歌った『茶摘(ちゃつみ)』は、1912年(明治45)年に『尋常小学唱歌 第三学年用』として発表された文部省唱歌。
京都の宇治田原村の茶摘歌を元に作られたとされ、歌詞の二番にある「日本」は元々は「田原」だったといいます。八十八夜(はちじゅうはちや)とは雑節の一つで、立春から数えて88日目の日を指し、毎年5月2日頃がこの日にあたります。
私が若い頃、京都の宇治田原の近くのゴルフ場のメンバー(協和GC)でしたので、毎週程行きました。茶畑の中にあるようなゴルフ場でOBを出すと茶畑に飛び込みました。
今では、京都の知人が旬のこの頃、新茶を送ってくれます。本人も茶園へボランティアにいくそうで、家内は宇治の新茶が毎年くるのを大変楽しみにしております。今年ももうすぐです。
<川柳> * 齢重ね アイアンと同じ ドライバー
* いっせいに 茶葉芽吹いて 八十八夜
* 花曇り 蛍の光 忘れおり
* 来たよ~ 孫の一声 つかれとぶ
* お茶の香 日本の政治 ちょっと待て
* 草花が 足の下から 顔を出す
* 田の土手で 議員が競う 新芽時
* 花もない 実もない施策 ヤメトケヨ
* 老齢で 声が拾えぬ 障害人
* 後遺症 介護がない日は 日曜日
* 春連休 議員はTVで 背(政)くらべ
* 善人と 見せてる人が ボランティア
* スゴイ人 イチロー・金本 みな野球
* 党が出来 頭ばかりで 生徒ナシ
* 爺に似て 孫はサッカー 休みナシ
* 絵に描いた 餅を見せても 沖縄県
* テレビって 一家に一台 二人だけ
* 食べるより 持ち帰り多い 宴会あと
* 食べ残す 高価な料理 持ち帰り
* お母さん 何歳までが 期限です?
* 言い訳は 何回聞くの カンニンャ
* 改革の 御旗ほころび 買い替えか
* 201Qを 村上さんに 小説化
* 宝くじ 夢を買ったが 夢は夢
* どぶろく祭 酒まんじゅうが 精一杯
* 宝くじ 当たらないのが 多空くじ
高齢者は連休は暇らしい。多数の応募アリガトウ・・・生活・時事・趣味・政治・家族・・・思っているようにいかないのが世の中ですね。
http://www.meisetudo.com/topics/chishiki.html
「新茶」= その年の最初に生育した新芽を摘み採ってつくったお茶のことをいいます。
鹿児島などの温暖な地域から摘み採りが始まり、桜前線と同様に徐々に北上していきます。
「新茶」と「一番茶」とは基本的に同じお茶のことで、呼び方が異なるだけです。その使い分けとしては、「一番茶」はその後に摘み採られる「二番茶」「三番茶」などと対比して使われることが多く、「新茶」は一年で最初に摘まれる「初物(はつもの)」の意味を込めて、また「旬」のものとして呼ばれる際などに使われます。
茶樹は、冬の間に養分を蓄え、春の芽生えとともにその栄養分をたくさん含んだみずみずしい若葉を成長させます。それが新茶となるのです。立春(2月4日)から数えて88日目の日を「八十八夜」といい、昔から、この日に摘み採られたお茶を飲むと、一年間無病息災で元気に過ごせると言い伝えられています。
新茶の特徴は、何といっても若葉の「さわやかですがすがしい香り」にあります。また、新茶は「二番茶」「三番茶」に比べて苦渋いカテキンやカフェインが少なく、旨み、甘みの成分であるアミノ酸(テアニン)が多いといわれます。
” 茶摘(ちゃつみ)(唱歌)
夏も近づく八十八夜
野にも山にも若葉が茂る
あれに見えるは
茶摘ぢやないか
あかねだすきに菅(すげ)の笠
日和つづきの今日此の頃を、
心のどかに摘みつつ歌ふ
摘めよ 摘め摘め
摘まねばならぬ
摘まにや日本の茶にならぬ ”
茶摘(ちゃつみ)〔文部省唱歌〕
夏も近づく八十八夜 野にも山にも若葉が茂る・・・
日本の茶摘の様子を歌った『茶摘(ちゃつみ)』は、1912年(明治45)年に『尋常小学唱歌 第三学年用』として発表された文部省唱歌。
京都の宇治田原村の茶摘歌を元に作られたとされ、歌詞の二番にある「日本」は元々は「田原」だったといいます。八十八夜(はちじゅうはちや)とは雑節の一つで、立春から数えて88日目の日を指し、毎年5月2日頃がこの日にあたります。
私が若い頃、京都の宇治田原の近くのゴルフ場のメンバー(協和GC)でしたので、毎週程行きました。茶畑の中にあるようなゴルフ場でOBを出すと茶畑に飛び込みました。
今では、京都の知人が旬のこの頃、新茶を送ってくれます。本人も茶園へボランティアにいくそうで、家内は宇治の新茶が毎年くるのを大変楽しみにしております。今年ももうすぐです。
<川柳> * 齢重ね アイアンと同じ ドライバー

* いっせいに 茶葉芽吹いて 八十八夜
* 花曇り 蛍の光 忘れおり
* 来たよ~ 孫の一声 つかれとぶ
* お茶の香 日本の政治 ちょっと待て
* 草花が 足の下から 顔を出す
* 田の土手で 議員が競う 新芽時
* 花もない 実もない施策 ヤメトケヨ
* 老齢で 声が拾えぬ 障害人
* 後遺症 介護がない日は 日曜日
* 春連休 議員はTVで 背(政)くらべ
* 善人と 見せてる人が ボランティア
* スゴイ人 イチロー・金本 みな野球
* 党が出来 頭ばかりで 生徒ナシ
* 爺に似て 孫はサッカー 休みナシ
* 絵に描いた 餅を見せても 沖縄県
* テレビって 一家に一台 二人だけ
* 食べるより 持ち帰り多い 宴会あと
* 食べ残す 高価な料理 持ち帰り
* お母さん 何歳までが 期限です?
* 言い訳は 何回聞くの カンニンャ
* 改革の 御旗ほころび 買い替えか
* 201Qを 村上さんに 小説化
* 宝くじ 夢を買ったが 夢は夢
* どぶろく祭 酒まんじゅうが 精一杯
* 宝くじ 当たらないのが 多空くじ
高齢者は連休は暇らしい。多数の応募アリガトウ・・・生活・時事・趣味・政治・家族・・・思っているようにいかないのが世の中ですね。