どんなに頭の良い人でもこれを知らないと"カモ"になる…情報と時間に追われる現代人に必要な「心理学の知識」「起業家の成功物語」に踊らされてはいけない25/03/26 8:00栗山 直子様記事抜粋<現代社会は情報に溢れている。どうすれば情報に振り回されずに生きていけるのか。東京科学大学講師で認知心理学者の栗山直子さんは「どんなに頭の良い人でも、思い込みに囚われていては失敗をする。現代を生きる私たちは『認知バイアス』について知る必要がある」という―
認知バイアスを知らない者がカモになる時代
「情報の豊かさは注意の貧困をもたらす」
ノーベル経済学賞受賞者で人工知能(AI)の生みの親でもあるハーバート・サイモン(1916~2001)は、生前にこのような言葉を残しました。情報が増えれば増えるほど、一つひとつの情報に振り向けられる注意が減るというトレードオフの状態になるということです。なぜなら、人間の脳のキャパシティは昔も今も変わらないからです。注意力を失った人間はどうなるか。ますます「バイアス(=思い込み)」に囚われやすくなります。
ITの発展により情報は指数関数的に増えています。そんな「情報氾濫の時代」において、「思い込みに囚われた人類」が情報に踊らされ、大統領選、ネット炎上、株価暴落、大ブームなど、世界を大きく動かしています。
情報が氾濫している時代だからこそ、情報にアクセスするだけの能力にはあまり意味はありませんし、どんなに頭の良い人でも、思い込みに囚われていては失敗をします。そして、思い込みは直感的であり、感情的なものです。意識をしなければ、自分でもコントロールできるものではありません。現代を生きる私たちにとって、認知バイアスを知らないことは、ことのほかヤバいことなのです。
認知バイアスがもたらした「イタリアの53番」の悲劇
ここでは私の恩師である故・山岸侯彦先生からご教示いただいた事例を紹介していきましょう。卑近な例でいえば、「イタリアの53番」と呼ばれる認知バイアスがもたらした悲劇があります。
2005年、イタリアでは数字を当てるナンバーズくじで「53番」が2年にわたって、あたり目になっていませんでした。このくじは一カ月の売り上げが7億ユーロ近く(当時の為替レートで900億円以上)あることもあり、多くの人が関心を寄せていました。
当然、くじを買う人の中には「次は53番が絶対に出るはず」と考え、多くのお金を投じる人もいましたが、そのことでいくつかの悲劇が生まれます。大損して妻と息子を射殺した後に自殺したり、家族の全貯金を使い込んで入水自殺したり、少なくとも4件の自殺・殺人が確認されています。
確かに2年も出ていない番号であれば、「次こそ53番が出る」と興奮する気持ちはわかります。ただ、くじの結果はランダムです。続けて53番が出ることもあれば、2年どころか5年、10年にわたって53番が出なくても全く不思議ではありません。
くじでは当たり前ですが、結果は一回ごとに常にリセットされるので、これまでの出目によって次の結果を修正する機能はありません。それにもかかわらず、賭ける側はあたかも法則があるように考えてしまいます。同じように、ルーレットが続けて偶数を出していると、「次は奇数が出るのでは」と思いがちですが、次に奇数が出るか偶数が出るかの確率は同じです。
これらは認知バイアスのひとつで「賭博者の誤謬」と呼びます。もし、当時この認知バイアスが広く知れ渡っていれば、そこまで熱くならず、悲劇も防げたはずです。
認知バイアスがもたらした「イタリアの53番」の悲劇
ここでは私の恩師である故・山岸侯彦先生からご教示いただいた事例を紹介していきましょう。卑近な例でいえば、「イタリアの53番」と呼ばれる認知バイアスがもたらした悲劇があります。
2005年、イタリアでは数字を当てるナンバーズくじで「53番」が2年にわたって、あたり目になっていませんでした。このくじは一カ月の売り上げが7億ユーロ近く(当時の為替レートで900億円以上)あることもあり、多くの人が関心を寄せていました。
当然、くじを買う人の中には「次は53番が絶対に出るはず」と考え、多くのお金を投じる人もいましたが、そのことでいくつかの悲劇が生まれます。大損して妻と息子を射殺した後に自殺したり、家族の全貯金を使い込んで入水自殺したり、少なくとも4件の自殺・殺人が確認されています。
確かに2年も出ていない番号であれば、「次こそ53番が出る」と興奮する気持ちはわかります。ただ、くじの結果はランダムです。続けて53番が出ることもあれば、2年どころか5年、10年にわたって53番が出なくても全く不思議ではありません。
くじでは当たり前ですが、結果は一回ごとに常にリセットされるので、これまでの出目によって次の結果を修正する機能はありません。それにもかかわらず、賭ける側はあたかも法則があるように考えてしまいます。同じように、ルーレットが続けて偶数を出していると、「次は奇数が出るのでは」と思いがちですが、次に奇数が出るか偶数が出るかの確率は同じです。
これらは認知バイアスのひとつで「賭博者の誤謬」と呼びます。もし、当時この認知バイアスが広く知れ渡っていれば、そこまで熱くならず、悲劇も防げたはずです。
起業家の成功物語」に踊らされてしまう理由
もうひとつ、知らないと判断を誤りかねないバイアスもお伝えしておきます。ビジネスの世界で多くの人が陥りがちなのが「生存者バイアス」です。人は判断する際に失敗したケースを無視して、成功した事例のみに注目して、誤った結論を導いてしまう現象です。
たとえば、メディアではスティーブ・ジョブズやビル・ゲイツなど起業家の成功物語を盛んに取り上げます。彼らが起業によって世の中を大きく変えたのは事実ですが、起業して彼らのようになれなかった人たちも当然います。むしろ、99.9%はなれません。
ただ、失敗事例にはあまり焦点が当たらないので、成功事例だけに注目して過大評価してしまい、リスクを見落としがちです。企業が新しい商品を開発したり、新規事業に参入したりするときもこの罠によくはまります。
たとえば、あなたの会社が社運を賭けて新商品を開発する際、既存商品を買ってくれた人にアンケート調査をして、高評価を得たとします。しかし、だからといって、「よし、イケる」と判断するのは早計です。これこそ「生存者バイアス」だからです。
確かに、この結果はかつてあなたの会社の商品を買ってくれた人がもう一回買ってくれるかどうかの参考にはなるかもしれませんが、新規顧客の獲得につながるかどうかはわかりません。そもそもこの調査では買おうと思わない人がなぜ買わないかがわかりません。この買った人だけの調査で社運を賭けるのはあまりにも危険です。
「減税」を「税の恵み」と表現した大統領
認知バイアスは私たちの生活のあらゆる場面に潜んでいます。あらゆる決断には認知バイアスが関わっているといっても言い過ぎではありません。知らないことで悲惨な結果を招くことはありますが、知っていれば自分の強みにすることができます。
認知バイアスをうまく使っているのが政治家です。政治家が使うバイアスで有名なのが「フレーミング効果」です。これは情報の発信側が現実を切り取り、認識の枠組みをつくる効果です。受け手はその切り取られた枠組みで評価をせざるを得なくなります。
たとえば、2001年、米国のジョージ・ブッシュ大統領は一般教書演説で減税について語りましたが、彼はスピーチ中、「減税」をそのまま「減税」とは呼ばずに、「税の恵み」と表現しました。それも5回もです。
聞き心地のよい言葉に言い換えることで、「減税して当たり前だろ」と思っていた人たちに対して「ブッシュ大統領にありがたいことをしてもらっている」と印象を変えることができたのです。
認知バイアスの活用で納税率を向上
また、政治家以外にも、最近、行政の政策立案者は認知バイアスを活用しています。英国では他国に先駆けて行政サービスの改善に認知バイアスの理論を活用しようとして2010年に「行動洞察チーム」を設置しました。
チームでは納税率を上げるために未納者に新しい通知書を作成し、そこに「あなたの近隣の90%の人々はすでに税金を納めています」と記載しました。こう書くことで多くの人は「近所の人が払っているならば、自分も払わなければ」という気になります。厳しい罰則を新たに定めたわけではなく、文書の内容を工夫することで、納税率が向上し、納税の遅延も大幅に減少したのです。
「人はみんなが選択した判断を好む」という社会的証明と呼ばれる認知バイアスをうまく用いています。「みんな払っていること」を認識させることで、何も強制せずに、行動を促したわけです
時間に追われる現代人にこそ必要な教養
私たちが生きている現代は常に時間に追われています。多くの情報から必要な情報を取捨選択したり、その情報に基づいて判断したり意思決定したりする際にも、時間をかけないで情報を精査しなければいけません。
人間の思考は合理的ではありません。経験則で判断します。理屈ではなく、過去の経験に依存しがちです。実際、素早く決めなければいけない場合は、あまり考えている時間がないので、経験則による判断が必要になります。これは人間の生きる知恵でもあります。
ただ、時間がないからと経験則で判断してばかりいると、認知バイアスの落とし穴に気づけず、痛い目に遭う可能性もあります。そして、ときには生命や財産がリスクにさらされたり、人間関係を壊しかねなかったりするほどのダメージを負うこともあります。情報があふれ、時間がない今の時代こそ、「教養としての認知バイアス」を知る必要があります。
実際、最近は認知バイアスへの関心の高さから、海外では大学も教育に力を入れています。ハーバード大学はオンラインコースで、認知バイアスに関する講義を2024年の9月に実施しており、それは認知バイアスに関する科学的知見や職場でのバイアスの影響を軽減するための戦略を学べる内容になっていました。ペンシルベニア大学やスタンフォード大学でもこれまで認知バイアスに関連する授業が開かれていて、もはや認知バイアスは「必須の教養」となりつつあるのです。












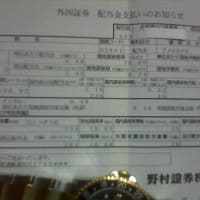

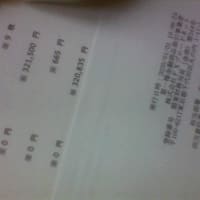
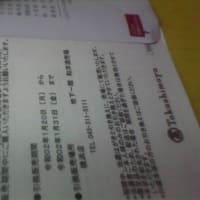

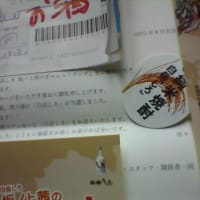

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます