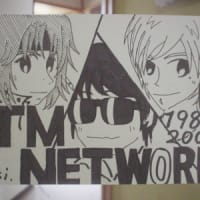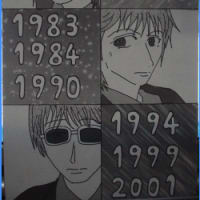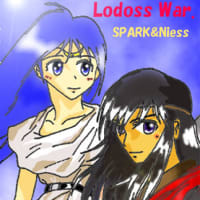第1章…『大衆革命①~上からの革命、
下からの革命』
:食糧革命~“パンを求めて”~サン・キュロット運動の隆盛
■大衆は何のために革命に身を投じたのか。いや、それ以前に、彼らのその示威行動の中には何らかの政治的思想があったのか。
その答えは「No」である。
たしかにサン・キュロット運動の後半、彼らは様々な社会的要求をするに至る。だが、本質的には彼らは元来、政治というものにさしたる関心を持っていたわけではなかった。
歴史上、あるいは本考察においても便宜上、ブルジョワ層との対立軸として「大衆」=『サン・キュロット層』とまとめてはいるものの、それがパリの人口の約90%をも占める以上、実際はその範疇でさらに雑多な社会的立場が構成されていることは明らかである。そうである以上、「サン・キュロット層としての1つの確固たる社会的定義・政治的定義」的なイデオロギーを展開することは非常に困難であると言わざるをえない。それは当時のパリにおいても、現在の学問的見地からいっても同様である。
では、イデオロギー的には必ずしも1つにまとまっていたわけではない彼らは、何をもって『サン・キュロット層』としての運動を確立するに至ったのであろうか。
■“食糧危機”―――。
凶作や物価上昇などさまざまな要因があるが、彼らは唯一「安定した食糧(パン)供給を要求する」ことで考えが一致し、それが大きな革命エネルギーとなったといえる。
1780年代後半、財政危機もさることながら、同時にフランスは未曾有の凶作にも見舞われていた。天候不順による作物不作は、やがて何千人単位での地方農民のパリへの流入を招くに至る。自然パリは失業者が増え続け、その数は1788年末には8万人も及んだともいわれる。全国的な凶作、パリへの人口一点集中、失業者の増加……、これは当然の結果として食糧をはじめとする物価上昇に直結する。
本論文末の資料『1789年パリ労働者の収入における、パンに消費された割合(%)』によると、当時の一般的な工場労働者においては、実にその収入の9割がパンに消費されてしまうという異常な事態となっていることがわかる。では「それ以下」の人々、つまりパリに何万といた失業者やその家族はどうであろうか。数的な資料がない故に推測の域を脱しないが、おそらくそれは「想像を絶する貧困ぶり」であろう。彼らサン・キュロット層の不満は当然、国王(政府)へと向いていく。王室も財政破綻に近い状態とはいえ、未だ大衆に向かって「パンが食べられないならばケーキを食べればいい」と言ってのけるだけの生活をしていたのだから。
このような理由から、食糧危機による問題をすべて国王(政府)のせいとする立場をとるサン・キュロット層たちは、パリにおいて様々な暴動を起こすようになる。当時のパリは“フォーブール”という48の区に分かれていたが、革命がはじまると、彼らはその区を基本単位として行動を起こすのであった。
■しかし、いかにサン・キュロット層の不満が高まっていたとはいえ、1789年の初期段階においてはその行動はあくまでも散発的な暴動レベルのものでしかなかった。彼らは終始「大衆」であったが故に、「明日のパンを求める」という日常的レベルでの具体的な要求はあれども、もう一段階上の政治的レベルにまでは自らを政治思想的に理論武装することができなかった。
後に革命が進行するにしたがって、革命指導家やジャーナリストなどによって大衆も“教育”されてはいく。その代表的な例としてはシェイエスによる『第3身分とは何か』などが挙げられるであろう。
だが、あくまでも「大衆」として基本的には「より安価で豊富なパン」「食糧暴動」という本能的欲求が「より高い賃金・労働条件」「民衆抗議・ストライキ」という政治的欲求にはるかに勝っていた。即物的ではある。そしてこの性質は、この後も本質的には変わることはなかった。
その意味においても現実的な食糧の危機(凶作・物価上昇など)に直面しなければ、彼らは進んで革命(政治)に参加しようという意識をもってはいなかった。また、『サン・キュロット層』として「下からの革命」を起こすだけの巨大なエネルギーを持ちながらも、前述のような理由から、彼ら自身を導く「思想的リーダー」というものの存在が、彼ら「大衆」の中からは登場することもなかった。
この2つのジレンマは、やがてサン・キュロット運動を崩壊に向かわせる大きな要因にもなっていく。
■1789年初夏、サン・キュロット層の国王(政府)に対する不満が高まり続けるのと並行し、パリの町自体も、三部会開催後の6月には国民議会の成立するなど政治的な緊迫も最高潮に達しようとしていた。
そして1789年7月14日、ついに『バスティーユ牢獄襲撃』事件が発生―――。
前回にも述べたことではあるが、当時ブルジョワ層は資本主義的自由を勝ち取るために特権階級との対立を深めていた。そこにはサン・キュロット層のそれとは違い、政治的にも明らかな階級闘争的な側面が存在していた。明確に「目指す社会」があるという点では「上からの革命」ともいえる。しかし、ブルジョワ層が強大な既存の特権階級の壁を打破するためには、「自らの手足となる力」が必要であった。その力こそが、潜在的には社会を変えるだけの強大なエネルギーを有しているものの、政治思想的指導者不在のために暴動レベルでの行動に止まっていたサン・キュロット層である。このことはいわば、バスティーユ牢獄襲撃やヴェルサイユ行進など、それら「明日のパンを求める」という日常生活レベルの欲求の矛先が、ブルジョワ層、あるいは一部の革命指導家の思惟、そのアジテーション的行動と一致した結果だと言い換えることもできる。
だが、「対等であっては困る」―――。
「大衆」の持つ膨大なエネルギーは重要視しながらも、ブルジョワ層は本音として「大衆」の力を恐れていてもいたのも事実である。そのことは、ブルジョワ層が一連の事件において、サン・キュロット層を統率・指導する一方で「ブルジョワ民兵(パリ市民軍)」という自らの武力組織をも創設していることからも見て取れる。ちなみにこの組織には後に一部の貴族・軍隊も合流している。
ところで、逆にサン・キュロット側から見た場合、彼らにはブルジョワ層に「利用されている」という感覚があったのだろうか。両者は同じ第3身分ではあるものの、性質的には本来相容れないものをもっている。だが「敵の敵は味方」という言葉ではないが、この段階では特権階級という「共通の敵」を目前にして、サン・キュロット層はブルジョワ層を素直に協力者として捉えていたのではないだろうかと私は考える。
また、その一方で当時のサン・キュロット層、あるいはフランス革命だけに限らず「大衆というモノ」を考察する場合、「権力に対する反発」と「権力への従順」というある種の矛盾した性質が同居しているように思われる。
すでに前述したように、「大衆」にはそれを導くリーダーが必要ではある。リーダーといっても一個人を指すとは限らない。「自らの社会的価値観の精神的主柱」と考えてもよい。それが1789年の革命当時の大衆にとっては、国王であるルイ16世(を含む絶対王政)であったのではないだろうか。
大衆の生活を苦しめる存在のある種の象徴が、国王その人であること明らかである(例えばマリー・アントワネット等の個人名も挙がるではあろうが、あくまでも象徴的な話として)。
だが、国王を失うことは同時に当時の「フランス社会」という既成価値観が崩壊することをも意味する。「権力への従順」という点では大衆とは異なるが、「権力に対する反発」、資本主義的自由(ブルジョワ的秩序社会)という明確な目標があったブルジョワ層でさえ「秩序の維持のため」には王権の必要性を認めざるを得なかった。無意識での「畏れ」のようなものがあったといってもいいかもしれない。
であるならば、明確な思想的目標がない大衆はなおのこと、ヴェルサイユ行進など心情的には国王ルイ16世を批判の対象にはするものの、現実下の行動としては、国王よりは漠然とした特権階級全体をより敵視していた感があることは否めなであろう。
だが、このような「畏れ」がある一方で、リーダーが自分達を明確に裏切ったとき、その「畏れ」を凌駕する怒りを大衆がもつことも歴史が証明するとおりである。
1791年6月のヴァレンヌ逃亡事件以後、大衆はルイ16世を「国民を裏切った男」として明らかに敵視するように至る。その後、1792年8月に王権停止に至るまでの過程は、本章第1節に既述のとおりである。
次回へ続く
下からの革命』
:食糧革命~“パンを求めて”~サン・キュロット運動の隆盛
■大衆は何のために革命に身を投じたのか。いや、それ以前に、彼らのその示威行動の中には何らかの政治的思想があったのか。
その答えは「No」である。
たしかにサン・キュロット運動の後半、彼らは様々な社会的要求をするに至る。だが、本質的には彼らは元来、政治というものにさしたる関心を持っていたわけではなかった。
歴史上、あるいは本考察においても便宜上、ブルジョワ層との対立軸として「大衆」=『サン・キュロット層』とまとめてはいるものの、それがパリの人口の約90%をも占める以上、実際はその範疇でさらに雑多な社会的立場が構成されていることは明らかである。そうである以上、「サン・キュロット層としての1つの確固たる社会的定義・政治的定義」的なイデオロギーを展開することは非常に困難であると言わざるをえない。それは当時のパリにおいても、現在の学問的見地からいっても同様である。
では、イデオロギー的には必ずしも1つにまとまっていたわけではない彼らは、何をもって『サン・キュロット層』としての運動を確立するに至ったのであろうか。
■“食糧危機”―――。
凶作や物価上昇などさまざまな要因があるが、彼らは唯一「安定した食糧(パン)供給を要求する」ことで考えが一致し、それが大きな革命エネルギーとなったといえる。
1780年代後半、財政危機もさることながら、同時にフランスは未曾有の凶作にも見舞われていた。天候不順による作物不作は、やがて何千人単位での地方農民のパリへの流入を招くに至る。自然パリは失業者が増え続け、その数は1788年末には8万人も及んだともいわれる。全国的な凶作、パリへの人口一点集中、失業者の増加……、これは当然の結果として食糧をはじめとする物価上昇に直結する。
本論文末の資料『1789年パリ労働者の収入における、パンに消費された割合(%)』によると、当時の一般的な工場労働者においては、実にその収入の9割がパンに消費されてしまうという異常な事態となっていることがわかる。では「それ以下」の人々、つまりパリに何万といた失業者やその家族はどうであろうか。数的な資料がない故に推測の域を脱しないが、おそらくそれは「想像を絶する貧困ぶり」であろう。彼らサン・キュロット層の不満は当然、国王(政府)へと向いていく。王室も財政破綻に近い状態とはいえ、未だ大衆に向かって「パンが食べられないならばケーキを食べればいい」と言ってのけるだけの生活をしていたのだから。
このような理由から、食糧危機による問題をすべて国王(政府)のせいとする立場をとるサン・キュロット層たちは、パリにおいて様々な暴動を起こすようになる。当時のパリは“フォーブール”という48の区に分かれていたが、革命がはじまると、彼らはその区を基本単位として行動を起こすのであった。
■しかし、いかにサン・キュロット層の不満が高まっていたとはいえ、1789年の初期段階においてはその行動はあくまでも散発的な暴動レベルのものでしかなかった。彼らは終始「大衆」であったが故に、「明日のパンを求める」という日常的レベルでの具体的な要求はあれども、もう一段階上の政治的レベルにまでは自らを政治思想的に理論武装することができなかった。
後に革命が進行するにしたがって、革命指導家やジャーナリストなどによって大衆も“教育”されてはいく。その代表的な例としてはシェイエスによる『第3身分とは何か』などが挙げられるであろう。
だが、あくまでも「大衆」として基本的には「より安価で豊富なパン」「食糧暴動」という本能的欲求が「より高い賃金・労働条件」「民衆抗議・ストライキ」という政治的欲求にはるかに勝っていた。即物的ではある。そしてこの性質は、この後も本質的には変わることはなかった。
その意味においても現実的な食糧の危機(凶作・物価上昇など)に直面しなければ、彼らは進んで革命(政治)に参加しようという意識をもってはいなかった。また、『サン・キュロット層』として「下からの革命」を起こすだけの巨大なエネルギーを持ちながらも、前述のような理由から、彼ら自身を導く「思想的リーダー」というものの存在が、彼ら「大衆」の中からは登場することもなかった。
この2つのジレンマは、やがてサン・キュロット運動を崩壊に向かわせる大きな要因にもなっていく。
■1789年初夏、サン・キュロット層の国王(政府)に対する不満が高まり続けるのと並行し、パリの町自体も、三部会開催後の6月には国民議会の成立するなど政治的な緊迫も最高潮に達しようとしていた。
そして1789年7月14日、ついに『バスティーユ牢獄襲撃』事件が発生―――。
前回にも述べたことではあるが、当時ブルジョワ層は資本主義的自由を勝ち取るために特権階級との対立を深めていた。そこにはサン・キュロット層のそれとは違い、政治的にも明らかな階級闘争的な側面が存在していた。明確に「目指す社会」があるという点では「上からの革命」ともいえる。しかし、ブルジョワ層が強大な既存の特権階級の壁を打破するためには、「自らの手足となる力」が必要であった。その力こそが、潜在的には社会を変えるだけの強大なエネルギーを有しているものの、政治思想的指導者不在のために暴動レベルでの行動に止まっていたサン・キュロット層である。このことはいわば、バスティーユ牢獄襲撃やヴェルサイユ行進など、それら「明日のパンを求める」という日常生活レベルの欲求の矛先が、ブルジョワ層、あるいは一部の革命指導家の思惟、そのアジテーション的行動と一致した結果だと言い換えることもできる。
だが、「対等であっては困る」―――。
「大衆」の持つ膨大なエネルギーは重要視しながらも、ブルジョワ層は本音として「大衆」の力を恐れていてもいたのも事実である。そのことは、ブルジョワ層が一連の事件において、サン・キュロット層を統率・指導する一方で「ブルジョワ民兵(パリ市民軍)」という自らの武力組織をも創設していることからも見て取れる。ちなみにこの組織には後に一部の貴族・軍隊も合流している。
ところで、逆にサン・キュロット側から見た場合、彼らにはブルジョワ層に「利用されている」という感覚があったのだろうか。両者は同じ第3身分ではあるものの、性質的には本来相容れないものをもっている。だが「敵の敵は味方」という言葉ではないが、この段階では特権階級という「共通の敵」を目前にして、サン・キュロット層はブルジョワ層を素直に協力者として捉えていたのではないだろうかと私は考える。
また、その一方で当時のサン・キュロット層、あるいはフランス革命だけに限らず「大衆というモノ」を考察する場合、「権力に対する反発」と「権力への従順」というある種の矛盾した性質が同居しているように思われる。
すでに前述したように、「大衆」にはそれを導くリーダーが必要ではある。リーダーといっても一個人を指すとは限らない。「自らの社会的価値観の精神的主柱」と考えてもよい。それが1789年の革命当時の大衆にとっては、国王であるルイ16世(を含む絶対王政)であったのではないだろうか。
大衆の生活を苦しめる存在のある種の象徴が、国王その人であること明らかである(例えばマリー・アントワネット等の個人名も挙がるではあろうが、あくまでも象徴的な話として)。
だが、国王を失うことは同時に当時の「フランス社会」という既成価値観が崩壊することをも意味する。「権力への従順」という点では大衆とは異なるが、「権力に対する反発」、資本主義的自由(ブルジョワ的秩序社会)という明確な目標があったブルジョワ層でさえ「秩序の維持のため」には王権の必要性を認めざるを得なかった。無意識での「畏れ」のようなものがあったといってもいいかもしれない。
であるならば、明確な思想的目標がない大衆はなおのこと、ヴェルサイユ行進など心情的には国王ルイ16世を批判の対象にはするものの、現実下の行動としては、国王よりは漠然とした特権階級全体をより敵視していた感があることは否めなであろう。
だが、このような「畏れ」がある一方で、リーダーが自分達を明確に裏切ったとき、その「畏れ」を凌駕する怒りを大衆がもつことも歴史が証明するとおりである。
1791年6月のヴァレンヌ逃亡事件以後、大衆はルイ16世を「国民を裏切った男」として明らかに敵視するように至る。その後、1792年8月に王権停止に至るまでの過程は、本章第1節に既述のとおりである。
次回へ続く