ついに釣り研ブログコンテストの結果が出ました!!
結果は箸にも棒にもかかりませんでしたが・・・
審査員の方々の総評を読ませて頂くと、反省点が多く学ばされました。
その総評をコピーしたものを添付します!!
釣研フィールドテスター:池永祐二さん
今回送られてきたブログを拝見させていただきました。
どのブログも、作者の人柄や釣仲間達とのコミュニケーションに満ちた記事・写真にあふれており、楽しく審査することが出来ました。
内容は釣りに関する記事を主体に、日常生活の色々な出来事を題材にしており、当たり前の事かもしれませんが、ブログ更新に対する意識の強いものが数多くありました。
写真技術の高さ・構成や編集のやり方・文字の表現力・動画機能の併用など、情報発信力の凄さに驚いています。
更新頻度も、感心するくらい多い方、少ない更新で釣りの楽しさやアイディアに満ちたもの、ブログコンテストに登録する前から精力的に情報発信し、すでに完熟期に達したブログなどは、ブロガーとして、私も見習いたい事が沢山ありました。
コンテストが終了しても、それぞれが自分のブログの顔を持ち、今後も楽しく、役立つ記事を更新し続けて欲しいと思いました。
素晴らしいブログを沢山拝見し、とても勉強になりました。ありがとうございました。
釣研フィールドテスター:山口 雅三さん
この度ブログコンテストの審査を依頼され、その責務が如何に重要か知りつつもお受けして、着目点はブログらしさ、つまり生活感や書いている方の人柄などが出ているもの、その方ならではの印象が良く出ているものを選択させていただきました。予選を通過した作品を眺めながら内容の濃さに驚きました。
情報通の方から、身近な不思議や疑問を素直に書き綴られた方、生活の中で釣りの位置づけが良くわかるものなど皆さんそれぞれが無理なく綴ってあるあところに感動すら覚えるほどでした。この時代ならではのコンテスト。で初めての試み。先陣を切って開催されたこのコンテストで優良なブログが多く作られていることがわかりました。これからも読者参加型で楽しい分野が開拓確立されて行くことを期待したいと思います。非常に難しい選択に頭を悩ませましたがこれを通じて、釣りの世界がより広がったような気がいたします。
(株)スパローハウス
(Web釣りサンデー):代表取締役細谷 洋介さん
思わず熟読して再訪するブログと、斜めに読み飛ばしてそれっきりになってしまうブログ。2者を分ける大きな要因のひとつに、ビジュアルの巧拙が挙げられます。
不特定多数に見てもらうためには、まずは「見やすいこと」が前提となりますが、さらに魅力的に見せるためには、画像のクオリティにもこだわることが大切です。今回拝見したブログの中にもいろんな画像が貼り込まれていましたが、残念なことに「適当に撮って、適当に並べただけ」といった印象のものが少なくありません。テキスト(文章)を読んでみると、なかなか面白かったりするだけにとても惜しまれます。
フイルムで写真を撮っていた時代とは違い、デジカメでは撮った画像はその場で確認でき、しかもコストを気にせず何枚でも撮ることができます。ですからひとつの被写体に対し、アングルやホワイトバランスを変えて数枚を撮り、その中からもっともよく撮れているものを選ぶといった努力は最低でもすべきでしょう。さらに、適当な立ち位置から適当に撮るのではなく、どのポジションから何を強調して撮るかといったフレーミング。そしてパソコンのモニター上で、余計な部分を切り取るトリミングの作業。もっと欲をいうなら、色調や明るさなどもアップロードの前に調整しておきたいところです。
このようにして、いい「絵作り」ができるようになれば、ブログの魅力はよりアップするに違いありません。他方でも書きましたが、ブログを見知らぬたくさんの人に見てもらいたいと思うのなら、見る側に立った気配りも必要です。今よりほんの少し手間をかければ、もっと大勢の人々に釣りの素晴らしさを伝えられるのではないかと思います。
編集という仕事柄、まずは内容よりもテキスト(文章)や写真のバランスを見ます。これは「読んでもらえるかどうか」という点において非常に重要なポイントのひとつです。特にウェブの世界では、読みづらかったり、表示に時間を要したりといったことは大きなマイナスポイントとなり、読み終わらないうちにページを閉じられてしまうことにもなりかねません。
今回拝見した審査対象のブログの中にも、無意味に行間が空いていたり、大フォントや絵文字を多用しすぎることによって読みづらくなっていたり、画像や素材の重いものが見受けられました。テキストをよく読み込んでみると面白く興味深い内容だったりするだけに、残念なところです。
ブログを自分や親しい知人だけに限定して見せるのではなく、見知らぬ人にも広く発信したいという意図があるなら、「いかに早く、読みやすく、美しく見せるか」という点について、もっと配慮すべきでありましょう。テキストは段落ごとにまとめる、本文とキャプション(写真の説明文)でフォントのサイズを変える、役に立たないブログパーツは削除する、そしてあまり重要でない画像は縮小するか、GIFファイルに変換する…といった工夫をするだけでも見栄えはずいぶん変わり、また表示速度も上がるはずです。そして、ただ漫然とダラダラ書いたり、適当に貼りつけたりするのではなく、文章をうまく書く、写真を上手に撮るといった努力もすべきであり、こうした工夫や努力を重ることによって媒体としてのクオリティが高まれば、今よりもっと多くの人に読んでもらえるはずです。
ふくだあかりさん
コンテストに応募するだけあって、みなさん本当に釣り好き!!っていうのがブログを通して伝わってきます。みなさん毎日毎日釣りの事を考えていて、隙あらば釣りに行っちゃう釣りキチなんだなって感じました。いろんな釣りの目線があって、いろんな感性で釣りをしているのがすごく伝わってきました。みなさんのブログを通して、なかなか行けない地域の写真、キレイな風景が見れるのはすごく新鮮。そこでの釣果が細かく乗っていると自分が釣りに行った気分になれるのがいいですね。自分の釣りジャンルとは違う魚が見られたり、釣り方、タックルが紹介されていて、どのブログもとっても楽しく見せて頂きました。特に、釣った魚の写真が多かったり、魚をキープした記事があった後に、お魚料理が紹介してあるととっても好感度が高かったです。みなさんがこれからもどんどん釣りの楽しさをブログで伝えていって頂いて、「いい釣り人」がどんどん増えて行ってくれると嬉しいと思います。
オーシャンルーラーインストラクター:金丸竜児さん
ブログというツールは雑誌やテレビ等と違って、基本的には自分自身でプロデューサーとなり作り上げる媒体である為、良い意味でも悪い意味でも非常に個性が表れてしまいます。だからこそ、面白いブログや逆に面白みが欠けているもの、具体的には、誰から見られても分かってもらえるよう客観的な立場から面白おかしく作り上げているもの、あるいは、完全に自己満足だけで完結しているもの等、実に多用なブログが存在しています。
その中でも、今回ご応募頂けたブログは、比較的第三者に見てもらおうという目的のもとに作られているものが多く、実に楽しく閲覧させて頂きました。
もちろん、項目別に観察していくと、スキル面での差は其々見られますが、それはそれで今後少しずつさらに良いものにレベルアップしていけば良いかと思います。
インドアブームの到来で、釣り業界は以前ほどの勢いは無くなりましたが、それでも、何とかここまで盛り返せたのは、メーカーやメディアだけの力だけではなく、皆様方の協力や力があってこそだと考えております。
今後、釣り業界がさらに盛り上がるよう、これからもブログというツールを使って、ドシドシ新鮮な釣情報やマル秘メソッド等、発表して頂ければと願っております。
(株)釣研 代表取締役社長 :楠根丈司さん
今回の釣りブログコンテストは業界初の試みということもあり、どれだけの方がエントリーされるのか見当がつかない状態での開催となりました。しかし、いざスタートしてみると、そんな不安を吹き飛ばすかのように、おかげさまで数多くのエントリーをいただくことができました。皆様方には心より厚く御礼申し上げます。 審査に当たって開催主旨にもありますように、地域の優良釣り情報や釣りの楽しみ、釣り技術の向上に繋がる情報を発信しているか、また釣り場の美化運動を積極的に啓蒙しているか、それらにプラスして更新頻度も審査の基準とさせていただきました。また、応募資格の取消し事項に触れていないかも審査の対象とし、著作権を侵害した画像の掲載や公序良俗に反するサイトにリンクを貼ったブログが残念ながら数件ありました。それさえなければ最終審査にノミネートと思われる内容の物もありました。次回は是非改善して再度エントリーしていただきたいものです。
エントリーされた皆様のブログを拝見すると、本当に釣りを愛されている方ばかりで、生活の中心に釣りがあるのが感じ取れました。また、訪問された方に釣りの楽しみを伝えたいという思いが心から感じられものも数多くありました。一言で釣りの楽しみと言っても種々様々で、大物を釣る楽しみ、より多くの魚を釣る楽しみ、釣った魚を味わう楽しみ、釣り場で仲間と語らう楽しみ、家族で釣りをして面白さを分かち合う楽しみ、工夫して釣具を作る楽しみ等々。それらの楽しみを共有できる方々が訪問してコメントを残し、またその楽しみを感じたくて再訪し、そして仲間がどんどん増えていく。それもまた楽しみ。これからもブログという素晴らしいツールを活用して、より多くの方々にさらなる釣りの楽しさをプラスして情報発信していただけますようお願い申し上げます。
この総評を読ませて頂いて、更新頻度や写真etc
自分に言っているのでは??っと思わせれるような1文もあり・・・
4・5年ブログをしていて未だに甘い点があるきがします!!
釣りにおいても一緒です!!
まだまだ未熟です!!
グランプリを獲得された方のブログを拝見していると・・・
総評の模範となるようなのもでした!!
またコンテストが開かれると嬉しいです!!
反省を十分生かし今度こそ目指せ上位!!!!!!!!!!!!
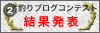
是非ご覧になってください
結果は箸にも棒にもかかりませんでしたが・・・
審査員の方々の総評を読ませて頂くと、反省点が多く学ばされました。
その総評をコピーしたものを添付します!!
釣研フィールドテスター:池永祐二さん
今回送られてきたブログを拝見させていただきました。
どのブログも、作者の人柄や釣仲間達とのコミュニケーションに満ちた記事・写真にあふれており、楽しく審査することが出来ました。
内容は釣りに関する記事を主体に、日常生活の色々な出来事を題材にしており、当たり前の事かもしれませんが、ブログ更新に対する意識の強いものが数多くありました。
写真技術の高さ・構成や編集のやり方・文字の表現力・動画機能の併用など、情報発信力の凄さに驚いています。
更新頻度も、感心するくらい多い方、少ない更新で釣りの楽しさやアイディアに満ちたもの、ブログコンテストに登録する前から精力的に情報発信し、すでに完熟期に達したブログなどは、ブロガーとして、私も見習いたい事が沢山ありました。
コンテストが終了しても、それぞれが自分のブログの顔を持ち、今後も楽しく、役立つ記事を更新し続けて欲しいと思いました。
素晴らしいブログを沢山拝見し、とても勉強になりました。ありがとうございました。
釣研フィールドテスター:山口 雅三さん
この度ブログコンテストの審査を依頼され、その責務が如何に重要か知りつつもお受けして、着目点はブログらしさ、つまり生活感や書いている方の人柄などが出ているもの、その方ならではの印象が良く出ているものを選択させていただきました。予選を通過した作品を眺めながら内容の濃さに驚きました。
情報通の方から、身近な不思議や疑問を素直に書き綴られた方、生活の中で釣りの位置づけが良くわかるものなど皆さんそれぞれが無理なく綴ってあるあところに感動すら覚えるほどでした。この時代ならではのコンテスト。で初めての試み。先陣を切って開催されたこのコンテストで優良なブログが多く作られていることがわかりました。これからも読者参加型で楽しい分野が開拓確立されて行くことを期待したいと思います。非常に難しい選択に頭を悩ませましたがこれを通じて、釣りの世界がより広がったような気がいたします。
(株)スパローハウス
(Web釣りサンデー):代表取締役細谷 洋介さん
思わず熟読して再訪するブログと、斜めに読み飛ばしてそれっきりになってしまうブログ。2者を分ける大きな要因のひとつに、ビジュアルの巧拙が挙げられます。
不特定多数に見てもらうためには、まずは「見やすいこと」が前提となりますが、さらに魅力的に見せるためには、画像のクオリティにもこだわることが大切です。今回拝見したブログの中にもいろんな画像が貼り込まれていましたが、残念なことに「適当に撮って、適当に並べただけ」といった印象のものが少なくありません。テキスト(文章)を読んでみると、なかなか面白かったりするだけにとても惜しまれます。
フイルムで写真を撮っていた時代とは違い、デジカメでは撮った画像はその場で確認でき、しかもコストを気にせず何枚でも撮ることができます。ですからひとつの被写体に対し、アングルやホワイトバランスを変えて数枚を撮り、その中からもっともよく撮れているものを選ぶといった努力は最低でもすべきでしょう。さらに、適当な立ち位置から適当に撮るのではなく、どのポジションから何を強調して撮るかといったフレーミング。そしてパソコンのモニター上で、余計な部分を切り取るトリミングの作業。もっと欲をいうなら、色調や明るさなどもアップロードの前に調整しておきたいところです。
このようにして、いい「絵作り」ができるようになれば、ブログの魅力はよりアップするに違いありません。他方でも書きましたが、ブログを見知らぬたくさんの人に見てもらいたいと思うのなら、見る側に立った気配りも必要です。今よりほんの少し手間をかければ、もっと大勢の人々に釣りの素晴らしさを伝えられるのではないかと思います。
編集という仕事柄、まずは内容よりもテキスト(文章)や写真のバランスを見ます。これは「読んでもらえるかどうか」という点において非常に重要なポイントのひとつです。特にウェブの世界では、読みづらかったり、表示に時間を要したりといったことは大きなマイナスポイントとなり、読み終わらないうちにページを閉じられてしまうことにもなりかねません。
今回拝見した審査対象のブログの中にも、無意味に行間が空いていたり、大フォントや絵文字を多用しすぎることによって読みづらくなっていたり、画像や素材の重いものが見受けられました。テキストをよく読み込んでみると面白く興味深い内容だったりするだけに、残念なところです。
ブログを自分や親しい知人だけに限定して見せるのではなく、見知らぬ人にも広く発信したいという意図があるなら、「いかに早く、読みやすく、美しく見せるか」という点について、もっと配慮すべきでありましょう。テキストは段落ごとにまとめる、本文とキャプション(写真の説明文)でフォントのサイズを変える、役に立たないブログパーツは削除する、そしてあまり重要でない画像は縮小するか、GIFファイルに変換する…といった工夫をするだけでも見栄えはずいぶん変わり、また表示速度も上がるはずです。そして、ただ漫然とダラダラ書いたり、適当に貼りつけたりするのではなく、文章をうまく書く、写真を上手に撮るといった努力もすべきであり、こうした工夫や努力を重ることによって媒体としてのクオリティが高まれば、今よりもっと多くの人に読んでもらえるはずです。
ふくだあかりさん
コンテストに応募するだけあって、みなさん本当に釣り好き!!っていうのがブログを通して伝わってきます。みなさん毎日毎日釣りの事を考えていて、隙あらば釣りに行っちゃう釣りキチなんだなって感じました。いろんな釣りの目線があって、いろんな感性で釣りをしているのがすごく伝わってきました。みなさんのブログを通して、なかなか行けない地域の写真、キレイな風景が見れるのはすごく新鮮。そこでの釣果が細かく乗っていると自分が釣りに行った気分になれるのがいいですね。自分の釣りジャンルとは違う魚が見られたり、釣り方、タックルが紹介されていて、どのブログもとっても楽しく見せて頂きました。特に、釣った魚の写真が多かったり、魚をキープした記事があった後に、お魚料理が紹介してあるととっても好感度が高かったです。みなさんがこれからもどんどん釣りの楽しさをブログで伝えていって頂いて、「いい釣り人」がどんどん増えて行ってくれると嬉しいと思います。
オーシャンルーラーインストラクター:金丸竜児さん
ブログというツールは雑誌やテレビ等と違って、基本的には自分自身でプロデューサーとなり作り上げる媒体である為、良い意味でも悪い意味でも非常に個性が表れてしまいます。だからこそ、面白いブログや逆に面白みが欠けているもの、具体的には、誰から見られても分かってもらえるよう客観的な立場から面白おかしく作り上げているもの、あるいは、完全に自己満足だけで完結しているもの等、実に多用なブログが存在しています。
その中でも、今回ご応募頂けたブログは、比較的第三者に見てもらおうという目的のもとに作られているものが多く、実に楽しく閲覧させて頂きました。
もちろん、項目別に観察していくと、スキル面での差は其々見られますが、それはそれで今後少しずつさらに良いものにレベルアップしていけば良いかと思います。
インドアブームの到来で、釣り業界は以前ほどの勢いは無くなりましたが、それでも、何とかここまで盛り返せたのは、メーカーやメディアだけの力だけではなく、皆様方の協力や力があってこそだと考えております。
今後、釣り業界がさらに盛り上がるよう、これからもブログというツールを使って、ドシドシ新鮮な釣情報やマル秘メソッド等、発表して頂ければと願っております。
(株)釣研 代表取締役社長 :楠根丈司さん
今回の釣りブログコンテストは業界初の試みということもあり、どれだけの方がエントリーされるのか見当がつかない状態での開催となりました。しかし、いざスタートしてみると、そんな不安を吹き飛ばすかのように、おかげさまで数多くのエントリーをいただくことができました。皆様方には心より厚く御礼申し上げます。 審査に当たって開催主旨にもありますように、地域の優良釣り情報や釣りの楽しみ、釣り技術の向上に繋がる情報を発信しているか、また釣り場の美化運動を積極的に啓蒙しているか、それらにプラスして更新頻度も審査の基準とさせていただきました。また、応募資格の取消し事項に触れていないかも審査の対象とし、著作権を侵害した画像の掲載や公序良俗に反するサイトにリンクを貼ったブログが残念ながら数件ありました。それさえなければ最終審査にノミネートと思われる内容の物もありました。次回は是非改善して再度エントリーしていただきたいものです。
エントリーされた皆様のブログを拝見すると、本当に釣りを愛されている方ばかりで、生活の中心に釣りがあるのが感じ取れました。また、訪問された方に釣りの楽しみを伝えたいという思いが心から感じられものも数多くありました。一言で釣りの楽しみと言っても種々様々で、大物を釣る楽しみ、より多くの魚を釣る楽しみ、釣った魚を味わう楽しみ、釣り場で仲間と語らう楽しみ、家族で釣りをして面白さを分かち合う楽しみ、工夫して釣具を作る楽しみ等々。それらの楽しみを共有できる方々が訪問してコメントを残し、またその楽しみを感じたくて再訪し、そして仲間がどんどん増えていく。それもまた楽しみ。これからもブログという素晴らしいツールを活用して、より多くの方々にさらなる釣りの楽しさをプラスして情報発信していただけますようお願い申し上げます。
この総評を読ませて頂いて、更新頻度や写真etc
自分に言っているのでは??っと思わせれるような1文もあり・・・
4・5年ブログをしていて未だに甘い点があるきがします!!
釣りにおいても一緒です!!
まだまだ未熟です!!
グランプリを獲得された方のブログを拝見していると・・・
総評の模範となるようなのもでした!!
またコンテストが開かれると嬉しいです!!
反省を十分生かし今度こそ目指せ上位!!!!!!!!!!!!
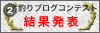
是非ご覧になってください

























※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます