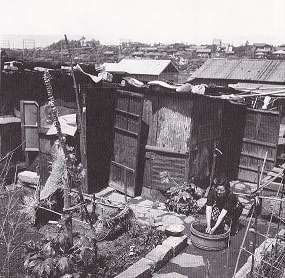はじめから見る 👉 自叙伝 『追 憶』 シリーズ
- 里帰り -
ひと月遅れのお盆を前に、待ちに待った田舎へ行くことになった。
上野駅では、人々が、夜行に乗るために、昼頃から行列を作って乗車を待つのであった。
帽子にMPと印された、国防色(カーキ色)の服を着けたアメリカ兵が、
駅の構内を右往左往しながら、乗客の整理をしていた。
車内に入るだけ人をつめ込み、割り込んで来た人を、引っこ抜くように…。
その状況を見て、子供心に、外国に居るような錯覚に陥って、寂しくなったものだった。
駅に来る途中、四年前の思い出を辿ってみようと、上野公園を一回りし、
心弾ませながら、石段に足をかけた瞬間 …。
ぞーっとした。
石段は、人でうずまっているのであった。
髪の毛や、髭がぼうぼうと伸び、
手のない人、足のない人達が、ボロボロの衣服をまとい、
石段を上下する人々に、物乞いをしているのであった。
この時は、哀れ、気の毒、かわいそうなどといった感情は湧かず、
恐ろしい、怖い、早くその場を逃れたいという思いで一杯であった。
叔母もその時、そう感じていたのだろうか、
私の手を引いて、引き返してしまったのであった。
「かわいそうに、戦争は嫌だね。」
「こわかった …。」
二人は、大きく息を吸って、溜め息をつくのであった。
それから延々と改札の順番を待っていた。
午後三時ころまでは、構外の列の中で、暑さをこらえていたが、
ようやくその頃から、構内に入って待つようになった。
叔母が、トイレに立って行った時に、
退屈だったので、おにぎりを一つ取り出して食べ始めようとしたところ、
どこからともなく浮浪児が二人やって来て、じっと立ちながら、
「おくれよう。おくれよう。」
「いいじゃんか。一つおくれよう。」
と二人に言い寄られた私は、
おろおろとして、おにぎりを持ちながら、
蛇に狙われた獲物の様に、身じろぎも出来ないでいるところへ、おばさんが帰って来てくれた。
「スヱ子、あげなさい。」
と私の持っているおにぎりと、もう一つカバンから取り出して、
「二人で仲良く食べなさい。」
と、手渡すのでした。
子供達は、もらうが早いか、一目散に駆けて行ってしまった。
しかし、九歳の私の手から、おにぎりがもぎ取られようとしていても周りの人は誰もそれを阻止しようとしなかった。
人のことまで、面倒みられない。自分のことで精一杯であったのかもしれない。
そうすれば、八王子の田舎町や、自分の里の人情あふれる環境が何とすばらしいものであるか...と、いろいろ思い出されるのであった。
ようやく乗車できたが、座席はなく、身動きすることすらできず、赤ちゃんの泣き声や、大人の怒鳴り声が、ムンムンする車中に響き、
なんかこのままどこか嫌な所へ運ばれて行かれるような錯覚を感ずるのであった。
そんな中で叔母は、持ってきた荷物を重ねて、私が腰をかけられるように、上手に作ってくれたのであった。
疲れたせいか、朝までぐっすりひと眠りしてしまった。
左には海が見えた。あれ!もう本荘に近いんだ。
水平線がくっきりと、朝の光を浴びて、水面がキラキラしている。
この海は、姉や弟が泳いでいる海とつながっているのだ。
汽車の中は静かで、今までの混み合いは、もう嘘のようであった。