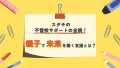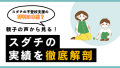▼本記事はこんな人におすすめ!
「不登校支援のスダチって具体的にどんなサポートをしているの?」
「不登校の子どもにどのようなサポートをすればいいの?」
今回は『不登校のお子さんの未来はどうなるのか』についてお答えしたいと思います。
不登校の親御さんにとって、進学や就職の将来がどうなるのか、とても気になるポイントだと思いますので、詳しく掘り下げていきます。
それでは、詳しく見ていきましょう。
▼記事を読むとわかること
・不登校のお子さんの進学状況について
・通信制高校の現実と課題について
・不登校のお子さんの就職や課題について
・親子のサポートの重要性について
スダチでは、学校で問題を抱えて行き渋りや不登校、ひきこもりとなったお子さん方を平均3週間で再登校に導いています。
2024年1月時点で1,000名以上のお子さんが再登校に成功しています。
お子さん方はみなさん主体的に再登校を果たし、その後は学校生活を自ら楽しんでいます。
お子さんが深く悩んでいる様子のときには、行き渋りが始まる前に一度スダチへ相談いただけたら幸いです。
現状の様子をヒアリングさせていただき、今お子さんが抱えている問題を根本解決していくために必要なアプローチをお話しさせていただきます。
無料オンライン相談は、1対1で顔出しも不要のため、この機会にご活用ください。
1.不登校でも高校進学可能?スダチのサポートが進路を広げる鍵
ここでは、不登校のお子さんの進学状況についてご説明します。
ますい「文科省のデータによると、不登校のお子さんの85.1%が高校に進学しています。ただし、その中で全日制高校へ進学している割合は不明確ですが、定時制や通信制が大部分を占めていると推測されます。高校進学率が高いのは親御さんが進路を真剣に考え、なんとか高校に入学させたいと願っているからだと思います。ただ、その進学先が適切かどうかが問題です。」
小川「そうですね。全日制高校に進学できるのは、勉強が非常にできる子や、特定の私立高校に進学するケースが多いです。ただ、多くの場合は定時制や通信制高校が選択肢となります。特に通信制高校に進学した場合、その後の進路が問題になることが多いです。文科省のデータでは、通信制高校に進学した生徒の32%が進路未決定、6%が退学しているという現実があります。」
ますい「通信制高校があるから大丈夫、という認識は危険ということですね。」
小川「進学率22.8%と、大学や短大に進む割合が低いことも大きな課題です。この数字を見ると、不登校の影響は高校以降の進路選択にまで大きく影響を与えていることがわかります。また、通信制高校に通ったとしても継続的に学習する習慣がないと、卒業後の進路がますます厳しくなる傾向があります。」
不登校のお子さんの約8割が高校に進学しているものの、定時制や通信制高校が大部分を占めていることがよくわかりますね。
また、大学進学率もそのうち約2割と低く、不登校がその後の進路にも影響を与えることが明らかですね。
そのため、スダチでは進学後の継続的な学習習慣のサポートや、親子での進路計画の立案等も見据えたサポートに取り組んでおります。
2.自由と責任のバランス!通信制高校の課題を親子で克服する方法
ここでは、通信制高校の現実と課題にする理由についてご説明します。
ますい「通信制高校に進んでも、自己管理が求められる環境で挫折するケースが多いです。親御さんのサポートがなければ、継続的な学習が難しくなる現実があります。通信制の環境は自由度が高い分、自己責任が重くのしかかります。」
小川「実際に通信制高校を選んだお子さんがモチベーションを保つのは非常に難しいです。たとえば、1年に1回だけの登校でも、毎日しっかり勉強するのは大人でも難しいですよね。こういった現状を親御さんも理解されているからこそ、スダチに相談に来られるケースが増えています。」
ますい「通信制高校に進んだ場合でも、親子の関係がしっかりしていて、お子さんが自分で学びたい意欲を持っていれば、立ち直ることは可能です。ただ、そのためには生活習慣の改善や親子の信頼関係を構築することが重要です。それがないと、通信制高校を選択しただけで安心するのは危険です。」
通信制高校は自由度が高い一方で、自己管理能力が求められるため、多くの生徒がモチベーションを維持できず挫折するケースもあるのですね。
今後は、親子の信頼関係を築きながらサポートする仕組みの整備や、生活習慣改善プログラムの導入が課題解決の鍵となるでしょう。
3.求人が増えても厳しい現実?不登校生の就職課題を解説
ここでは、就職の可能性と課題についてご説明します。
小川「次に就職についてですが、少子高齢化の影響で、求人は増えています。しかし、条件を選ばなければの話です。良い条件の職場を選ぼうとすると、一定の学歴やスキルが求められるのが現実です。不登校の影響が長引くと、これらの条件をクリアすることがさらに難しくなります。」
ますい「そうですね。ハローワークの求人情報を見ても、給与が非常に低い場合も多く、生活できる水準を確保するのが難しいこともあります。また、不登校の経験が就職活動でネックになるケースも少なくありません。採用する側としても、学校や職場で継続的に頑張れた実績があるかを重視するため、不登校期間中の状況が採用に影響を与えることがあります。」
小川「就職ができたとしても、すぐに辞めてしまうケースも多いです。それは、これまでの生活習慣が影響していることが多いですね。会社勤めでは時間やルールが厳格に求められるため、規則正しい生活が送れないと長続きしません。親御さんが今のうちからサポートをして、基盤を整えることが大切です。」
【関連記事】
不登校の小学生の家での過ごし方については下記で詳しく説明しています。
親子で作る不登校の小学生の家での過ごし方とは?経験者が解説します!
4.生活習慣を見直すだけで変わる!不登校解決の第一歩
ここでは、親子のサポートの重要性についてご説明します。
小川「不登校のお子さんの進学や就職を成功させるには、親子でのサポートが非常に重要です。特に生活習慣やデジタル機器との付き合い方、運動や食生活を整えることが欠かせません。これらを改善することで、自己管理能力や社会に適応する力を養うことができます。」
ますい「そうですね。スダチのサポートでは、生活リズムの改善やデジタルデトックスの実施、そしてお子さんのやる気を引き出すための褒め方や声かけの方法もお伝えしています。これらを取り入れることで、お子さんが社会に出て自立するための土台を築くことができます。」
小川「また、親御さん自身が正しい知識を持つことも重要です。不登校への正しい理解があれば、焦らずに対応することができます。親御さんが安心してサポートできる環境を作るためにも、私たちのような専門機関を頼っていただきたいです。」
生活習慣やデジタル機器の適切な管理、運動や食生活の改善が自己管理能力を高め、社会適応力を養う基盤となります。
そこで、スダチのサポートでは、生活リズムの整え方やデジタルデトックスの方法、子どものやる気を引き出す声かけの手法を提供しています。
今後も、親御さん自身の不登校理解を深める教育や、親子のサポート体制を強化するサポートを提供してまいります。
5.親子で進む不登校解決の道!スダチが提案する具体策
小川「現実は厳しい部分もありますが、不登校のお子さんでも進学や就職の可能性を広げることは十分可能です。そのためには、親子での正しいサポートが必要不可欠です。」
ますい「スダチでは、不登校のお子さんと親御さんが共に成長できるよう、さまざまなサポートを提供しています。もし、現状を改善したいと思われた方は、ぜひ私たちの無料相談にお越しください。一緒に解決策を考えていきましょう!」
いかがでしたか?
スダチでは、不登校のお子さんが進学や就職の可能性を広げるために、親子でのサポートを大切に考えています。
生活習慣の改善や正しい知識の提供を通じて、親御さんとお子さんが共に成長できる環境を整えてまいります。
私たちは、ただ結果を求めるのではなく、お子さんと親御さんが納得し、自立への道を歩むことが重要です。
そのため、現状を改善し未来への一歩を踏み出したい方に、最適なサポートを提供し続けていきます。
この記事でご興味を持たれた方は、ぜひスダチの無料相談をご利用ください。
今回の記事についてYoutubeでも確認できます。ぜひご覧ください。