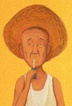前回2つのコラムでは、主に5教科で350点~400点くらいの生徒と、200点未満くらいの生徒のみにスポットをあてて話を進めた。
一方、最もたくさんの人数が集まる300点前後くらいの生徒にはふれてこなかった。
前回2つのコラムへの反響から、この、平均点前後の生徒達についても触れておくことにした。
そして今回も、学力というテーマにしぼって論じることにする。
また、全3回の長いコラムになったので、最後に「あとがき」をつけた。
・平均点前後の生徒は、だいたい予想通り
前回2つのコラムでは、読まれた方それぞれ、いろいろな感想を持たれた事だろう。
しかし、今回のテーマの平均点前後の生徒は、ほぼ皆さんが想像する通りではないだろうか。
私が長年たくさんの生徒を見てきた中で、平均点前後の成績の生徒は、だいたい以下のような人たちだ。
彼らの多くは、普段の自主勉はちょっとだけ、もしくはほぼやらない。
もし塾に通っていれば、普段の勉強は塾の勉強のみ。
しかし、テスト前1週間くらいは真面目に勉強をする。そして、テストまでには、各科目の単語や用語、公式等は一通り使いこなせるようにはしておく。
また、単語テストなどの小テストも最低限の準備はしてのぞむ。
学校の授業も一応真面目にうけている。
しかし、一応の勉強はするものの、意欲的に勉強をするわけでもない。
そんな彼らは、ストイックとまでは言わないが、最低限の自己管理はできている。
そして、バランスよく勉強、部活、友人、恋愛と青春を謳歌している、ある意味とても健全な中高生だ。
・平均前後の生徒の向学心
さて、このような平均点前後の生徒達であるが、真面目である一方、特別に向学心があるわけでもない印象を受ける。
最低限の勉強はするが、一生懸命勉強するというわけではない。
もしかしたら、彼らなりには一生懸命なのだろうが、成績上位者との熱量の差は明らかだ。
かつて、一斉指導の塾で短期間だけ講師をしたこともあるが、彼らは、比較的理解しやすい基本問題をやっているうちは真剣に授業を受けるが、彼らの技量の1ランク上の問題を扱うと、急に集中力が落ち始める。
ここに、成績上位者の向学心との差が見えてくる。
そんな彼らも、1対1で授業をやっているときは付いてきてくれるが、一斉指導だと緊張感がないのか、さじを投げてしまう。
やがて紆余曲折あり、私は独立して家庭教師を始めたのだが、1対1の個別で指導をしていても向学心の差のようなものは感じてしまう。
実際、平均点くらいから伸びない生徒は、私が出した宿題はちゃんとやってくるが、それ以上の事はほぼやらない。
学校のワークは、普段からコツコツやるわけではなく、テスト前にあわてて、一応ひと通りは解く。しかし、難問に限ってはよく分からないので答えを丸写しする。
もちろん、ワークの提出期限には、提出して恥ずかしくないだけの体裁を整えてから提出する。
良くも悪くも、実に中高生らしい中高生だ。
・平均前後の生徒の成績を上げるには
もちろん、成績を上げるのが私の仕事でもあるので、そんな彼らを見て「中高生らしいなぁ」と目を細めている場合ではない。
そして、その清々しいまでの中高生らしさが最大の壁なのである。
そう、彼らは積極的に勉強をするわけではないが、決して勉強ていないわけでもないのだ。
真剣に勉強をするのはテスト前など追い詰められた時だけだ。
それでもひと通り必要なことは身につけるまでやるので、平均点くらいにはなる。
これが、前に述べた200点未満の生徒達とは大きく違うところだ。
これくらいの勉強量なら、中級くらいの問題ならできるであろう事は皆さんにも想像できよう。
この「勉強をやっていないわけではない」が、ある程度の達成感を彼らに与えてしまうので、なかなかそれ以上にならない。
テスト前の追い詰められたとき以外ももう少し頑張ってほしいものだ。
そしてもう一つ、壁を越えるのに不可欠なのが、問題のレベルが「中の上」や「上の下」くらいの問題に取り組むということであるが、これもまた難しい。
中級よりレベルの高い問題を出したとしても、1対1の授業であれば手取り足取り指導できるが、一斉指導だと彼らの集中力は急に続かなくなる。
また、前回のコラムで述べたように、中級レベル以上の問題は学校でもあまり取り組まないという実態もよろしくない事態を招いている。
そこで重要なのが、根気よく生徒の技量のもう1ランク上の問題にチャレンジし続けていくことなのだ。
もちろん、根気よく続ければ、今までよりも1ランク上の問題もできるようになるのであるが、困ったのはこの先で、成績が上がるという体験を通しても、依然として受け身なままの生徒が多い。
「成績が上がった」の次は「この先生に任せておけば大丈夫」で終わってしまうのだ。
頼りにしてくれるのはうれしいが「それを自分でやってみよう」にはなかなかならない。
そして、相変わらず学校のワークはテスト前にあわててやるということを繰り返す。
一時的に成績が上がったとしても、本当の勝負は、より踏み込んだところまで自主的に勉強をするようになるかにかかっているのだ。
勉強を教えるというのは大変なことだが、彼らの性格に向き合うことがとても重要なのである。
・平均点くらいではいけないのか
部活で例えるなら、地区大会レベルのことしかしなければ地区大会レベルのまま伸びることはない。
県大会レベルの練習を県大会レベルになるまで続けることが、県大会レベルになるための条件だし、その上のレベルもまた同じだ。
平均点前後の彼らを見ていると、その上を目指す貪欲さがあまりない。
1つテストが終わると、次のテスト1週間前くらいまでは、のんびり休息タイムになってしまう。
成績を上げたいなら、とにかく学ぶ姿勢を変えていかねばならない。
少なくとも必要なのは、もう1ランク上の問題に取り組む姿勢である。
しかし一方で、私の家庭教師という立場を抜きに言わせてもらえば、平均点くらいというのは、立派とは言わないが悪くないとも思う。
こどもたちの全てに、あふれ出る向学心を求めるのは無理な話だし、全員が80点以上とれなければならないというものでもない。
平均点前後の生徒にありがちな勉強方や勉強量は先に述べた通りだが、それくらいのことをすれば最低でも50〜60点前後くらいになるのも事実だ。
言い換えれば、特別な事情でもない限り、誰でもそれくらいは取れるはずなのだ。
むしろ、勉強が好きでなかったとしても平均点くらい取れているなら、それなりの努力をしていると認めてあげたくなる。
なんでも全員が全国大会を目指さなければいけないということはなく、目標は県大会で十分という人もいるはずだ。
是非、子を持つ親であるなら、少しでも勉強ができるようになってほしいという思いと同時に、我が子の好奇心や向学心といった性格ともう一度向き合ってほしい。
普段はなかなか勉強しなくても、テスト前くらいは真剣に勉強するなら、それはそれで責任感のある健全な子供なのだと思う。
・彼らの岐路はその先にある
さて、そのような平均点前後の生徒達であるが、ひとつ残念に思うことがある。
彼らは最低限のことをちゃんとやる責任感のある中高生といえようが、しかし、それでも大学を目指すには、いささか心もとない学力なのだ。
それでも大学に行けてしまう大学全入時代の現代では、冷静に考えなければならない事が沢山ある。
現在、大学生の多くが大学生として求められる力を有しないまま大学生になってしまっている。これはある意味不幸なことだ.。
そして、人生の岐路として真剣に考えなければならない問題である。
一方、現代の子ども達を立派だと思う点もある。
それは、大学を目指すにあたり、目的意識を持っている人が多いということだ。
私が高校生だった20数年前は、自分の周りの友人を見回しても、明確な目的意識を持って大学へ行っている人はあまりいなかった。
今思い返しても、そんな友人は片手で足りるくらいしかいない。
しかし、今の現役高校生は明確な目的を持って大学を選んでいる人が多いというし、私もそう感じている。
これは素晴らしいことであると同時に社会問題として考えるべきことでもある。
せっかくの目的意識と学力のミスマッチがおきてしまっているのだ。
私の友人に、大学で教鞭をとっているのがいるが、やはり、学生の学力低下は如何ともしがたいと言っていた。
彼がやっているのは社会学なのだが、集めたデータの統計や分析をさせようとしたら、平均の出し方すらわからない学生がいたそうだ。
私立文系の大学とはいえ、中学生レベルの数学すらおぼつかないのは当たり前らしく、これでは学生に統計をとらせるなんて夢のまた夢である。
論文を書かせても、中学生の作文レベルが限界。
英語の授業は中学生の英語のやり直しで精一杯。
このような大学がごまんとあるのだ。
それでも卒業さえできれば、どんな大学を出ていても「大卒」という看板を掲げることができる。
しかし、そこに4年間という貴重な時間と、はたいた大枚に見合った価値があるのか冷静に考えるべきだと思う。
(あとがき)
誰でも学ぼうとすることは良いことだ。
また、大学に行きたいと思う学生の気持ちそのものを否定する気もない。
しかし人によっては、大学に行くよりも、専門学校や就職を選んだ方が有意義な場合もあるだろう。
大学に行けるから大学に行く、という選択はいささか早計ではないだろうか。
・世間は実に冷酷だ
現代は、偏差値50くらいの高校に通っていれば、もはや胸を張って大学生になれる時代だ。
偏差値40の高校でも、学年でトップの成績ならそこそこ名のある大学に推薦で行けてしまうこともある。
しかし、いざ大学に入学すると、一般入試の学生との学力差は非常に大きい。
中学生で例えるなら、5教科で250点の生徒と400点の生徒くらいの開きがあることも珍しくない。
偏差値40の高校でトップッだった生徒は、高校で生まれ変わった気分になってしまっているので、それほど差があることに気づかず大学に入学するのである。
もちろん、一般受験で入ったのならいいが、推薦などを利用して背伸びをしてしまうとそのあとがきつい。
そして、現実とのギャップにショックを受けて大学を中退してしまうのだ。
それでも高校は、生徒を大学に押し込んでしまえば目的達成なので「入学おめでとう、あとはがんばってね!」という具合に毎年生徒を大学に送り込み続けるのである。
一方、俗に言うFランや、Fランのちょっと上くらいの下位の大学ならそのような差を味わうことはあまりないだろう。
(Fランは以前はなかった言葉なので、わからない人は調べてください)
しかし最近では、文部科学省の指導もあって、授業の出席や試験などを厳しくする大学が増えているともいう。
そして「大学に行ったらバラ色だ!」という夢がもろくも崩れるのである。
さらに私が疑問に思うのが大学の授業料である。
もし、私立文系であれば、安く見積もっても4年間で500万円くらいはかかる。
学部によってはもっとかかることもある。
しかも、中には借金をしてまで大学に来る学生もいるわけだ。
大学側からすれば、借金を背負ってまで学費を納めてくれるのだから、ありがたいお客さんである。
大学は商売ではないはずだが、広く言えばサービス業とも言える。
こんな多大な借金を背負ってまで、お客さんがサービスを買いにくる業種が他にあるだろうか。
そして大学を卒業したら、借金返済におわれるのである。もちろん大学は、そうまでして通ってくれた学生の借金返済の責任なんか追わない。
なんて冷酷な世界だろう。
だからこそ、私は自分が受け持った生徒だけでも、ちゃんとした学力と思考力を持って大学生になってほしいと切に願っている。
言葉は悪いが、大学のいいカモにされないためにも、しっかり勉強して、むしろ大学を人生の踏み台として利用するくらいになってほしい。
学費を親が払うにしろ、借金をするにしろ、日本では大枚をはたかないと大学に行けないからだ。
もちろん、下位大学に通う学生の全てが、時間と金を無駄に浪費していると言うつもりはない。
しかし、未来ある若者が、大卒という看板を目の前にぶら下げられて、進路を冷静に考えられなくなっているような気もする。
そして大学では、年間100万円の学費を払ってまた中学の英語をやり直す。
年間100万円の学費を払って論文以前の作文の指導を受ける。
英語の文献はおろか、日本語の論文を読むのも一苦労だ。
多くの人にたくさんの学ぶ機会があるという点では素晴らしいが、その学費は、親が一生懸命稼いだお金だったり、学生本人がのちに返さなければならない借金だ。
まさに、誰でも大学に行けてしまう現代の悲劇といえよう。
勉強を教えて送り出す身としては、なんだか悔しいのである。
しかし、それでも大学生であるという高揚感が、全てを霧の中に隠してしまうようだ。
一方、最もたくさんの人数が集まる300点前後くらいの生徒にはふれてこなかった。
前回2つのコラムへの反響から、この、平均点前後の生徒達についても触れておくことにした。
そして今回も、学力というテーマにしぼって論じることにする。
また、全3回の長いコラムになったので、最後に「あとがき」をつけた。
・平均点前後の生徒は、だいたい予想通り
前回2つのコラムでは、読まれた方それぞれ、いろいろな感想を持たれた事だろう。
しかし、今回のテーマの平均点前後の生徒は、ほぼ皆さんが想像する通りではないだろうか。
私が長年たくさんの生徒を見てきた中で、平均点前後の成績の生徒は、だいたい以下のような人たちだ。
彼らの多くは、普段の自主勉はちょっとだけ、もしくはほぼやらない。
もし塾に通っていれば、普段の勉強は塾の勉強のみ。
しかし、テスト前1週間くらいは真面目に勉強をする。そして、テストまでには、各科目の単語や用語、公式等は一通り使いこなせるようにはしておく。
また、単語テストなどの小テストも最低限の準備はしてのぞむ。
学校の授業も一応真面目にうけている。
しかし、一応の勉強はするものの、意欲的に勉強をするわけでもない。
そんな彼らは、ストイックとまでは言わないが、最低限の自己管理はできている。
そして、バランスよく勉強、部活、友人、恋愛と青春を謳歌している、ある意味とても健全な中高生だ。
・平均前後の生徒の向学心
さて、このような平均点前後の生徒達であるが、真面目である一方、特別に向学心があるわけでもない印象を受ける。
最低限の勉強はするが、一生懸命勉強するというわけではない。
もしかしたら、彼らなりには一生懸命なのだろうが、成績上位者との熱量の差は明らかだ。
かつて、一斉指導の塾で短期間だけ講師をしたこともあるが、彼らは、比較的理解しやすい基本問題をやっているうちは真剣に授業を受けるが、彼らの技量の1ランク上の問題を扱うと、急に集中力が落ち始める。
ここに、成績上位者の向学心との差が見えてくる。
そんな彼らも、1対1で授業をやっているときは付いてきてくれるが、一斉指導だと緊張感がないのか、さじを投げてしまう。
やがて紆余曲折あり、私は独立して家庭教師を始めたのだが、1対1の個別で指導をしていても向学心の差のようなものは感じてしまう。
実際、平均点くらいから伸びない生徒は、私が出した宿題はちゃんとやってくるが、それ以上の事はほぼやらない。
学校のワークは、普段からコツコツやるわけではなく、テスト前にあわてて、一応ひと通りは解く。しかし、難問に限ってはよく分からないので答えを丸写しする。
もちろん、ワークの提出期限には、提出して恥ずかしくないだけの体裁を整えてから提出する。
良くも悪くも、実に中高生らしい中高生だ。
・平均前後の生徒の成績を上げるには
もちろん、成績を上げるのが私の仕事でもあるので、そんな彼らを見て「中高生らしいなぁ」と目を細めている場合ではない。
そして、その清々しいまでの中高生らしさが最大の壁なのである。
そう、彼らは積極的に勉強をするわけではないが、決して勉強ていないわけでもないのだ。
真剣に勉強をするのはテスト前など追い詰められた時だけだ。
それでもひと通り必要なことは身につけるまでやるので、平均点くらいにはなる。
これが、前に述べた200点未満の生徒達とは大きく違うところだ。
これくらいの勉強量なら、中級くらいの問題ならできるであろう事は皆さんにも想像できよう。
この「勉強をやっていないわけではない」が、ある程度の達成感を彼らに与えてしまうので、なかなかそれ以上にならない。
テスト前の追い詰められたとき以外ももう少し頑張ってほしいものだ。
そしてもう一つ、壁を越えるのに不可欠なのが、問題のレベルが「中の上」や「上の下」くらいの問題に取り組むということであるが、これもまた難しい。
中級よりレベルの高い問題を出したとしても、1対1の授業であれば手取り足取り指導できるが、一斉指導だと彼らの集中力は急に続かなくなる。
また、前回のコラムで述べたように、中級レベル以上の問題は学校でもあまり取り組まないという実態もよろしくない事態を招いている。
そこで重要なのが、根気よく生徒の技量のもう1ランク上の問題にチャレンジし続けていくことなのだ。
もちろん、根気よく続ければ、今までよりも1ランク上の問題もできるようになるのであるが、困ったのはこの先で、成績が上がるという体験を通しても、依然として受け身なままの生徒が多い。
「成績が上がった」の次は「この先生に任せておけば大丈夫」で終わってしまうのだ。
頼りにしてくれるのはうれしいが「それを自分でやってみよう」にはなかなかならない。
そして、相変わらず学校のワークはテスト前にあわててやるということを繰り返す。
一時的に成績が上がったとしても、本当の勝負は、より踏み込んだところまで自主的に勉強をするようになるかにかかっているのだ。
勉強を教えるというのは大変なことだが、彼らの性格に向き合うことがとても重要なのである。
・平均点くらいではいけないのか
部活で例えるなら、地区大会レベルのことしかしなければ地区大会レベルのまま伸びることはない。
県大会レベルの練習を県大会レベルになるまで続けることが、県大会レベルになるための条件だし、その上のレベルもまた同じだ。
平均点前後の彼らを見ていると、その上を目指す貪欲さがあまりない。
1つテストが終わると、次のテスト1週間前くらいまでは、のんびり休息タイムになってしまう。
成績を上げたいなら、とにかく学ぶ姿勢を変えていかねばならない。
少なくとも必要なのは、もう1ランク上の問題に取り組む姿勢である。
しかし一方で、私の家庭教師という立場を抜きに言わせてもらえば、平均点くらいというのは、立派とは言わないが悪くないとも思う。
こどもたちの全てに、あふれ出る向学心を求めるのは無理な話だし、全員が80点以上とれなければならないというものでもない。
平均点前後の生徒にありがちな勉強方や勉強量は先に述べた通りだが、それくらいのことをすれば最低でも50〜60点前後くらいになるのも事実だ。
言い換えれば、特別な事情でもない限り、誰でもそれくらいは取れるはずなのだ。
むしろ、勉強が好きでなかったとしても平均点くらい取れているなら、それなりの努力をしていると認めてあげたくなる。
なんでも全員が全国大会を目指さなければいけないということはなく、目標は県大会で十分という人もいるはずだ。
是非、子を持つ親であるなら、少しでも勉強ができるようになってほしいという思いと同時に、我が子の好奇心や向学心といった性格ともう一度向き合ってほしい。
普段はなかなか勉強しなくても、テスト前くらいは真剣に勉強するなら、それはそれで責任感のある健全な子供なのだと思う。
・彼らの岐路はその先にある
さて、そのような平均点前後の生徒達であるが、ひとつ残念に思うことがある。
彼らは最低限のことをちゃんとやる責任感のある中高生といえようが、しかし、それでも大学を目指すには、いささか心もとない学力なのだ。
それでも大学に行けてしまう大学全入時代の現代では、冷静に考えなければならない事が沢山ある。
現在、大学生の多くが大学生として求められる力を有しないまま大学生になってしまっている。これはある意味不幸なことだ.。
そして、人生の岐路として真剣に考えなければならない問題である。
一方、現代の子ども達を立派だと思う点もある。
それは、大学を目指すにあたり、目的意識を持っている人が多いということだ。
私が高校生だった20数年前は、自分の周りの友人を見回しても、明確な目的意識を持って大学へ行っている人はあまりいなかった。
今思い返しても、そんな友人は片手で足りるくらいしかいない。
しかし、今の現役高校生は明確な目的を持って大学を選んでいる人が多いというし、私もそう感じている。
これは素晴らしいことであると同時に社会問題として考えるべきことでもある。
せっかくの目的意識と学力のミスマッチがおきてしまっているのだ。
私の友人に、大学で教鞭をとっているのがいるが、やはり、学生の学力低下は如何ともしがたいと言っていた。
彼がやっているのは社会学なのだが、集めたデータの統計や分析をさせようとしたら、平均の出し方すらわからない学生がいたそうだ。
私立文系の大学とはいえ、中学生レベルの数学すらおぼつかないのは当たり前らしく、これでは学生に統計をとらせるなんて夢のまた夢である。
論文を書かせても、中学生の作文レベルが限界。
英語の授業は中学生の英語のやり直しで精一杯。
このような大学がごまんとあるのだ。
それでも卒業さえできれば、どんな大学を出ていても「大卒」という看板を掲げることができる。
しかし、そこに4年間という貴重な時間と、はたいた大枚に見合った価値があるのか冷静に考えるべきだと思う。
(あとがき)
誰でも学ぼうとすることは良いことだ。
また、大学に行きたいと思う学生の気持ちそのものを否定する気もない。
しかし人によっては、大学に行くよりも、専門学校や就職を選んだ方が有意義な場合もあるだろう。
大学に行けるから大学に行く、という選択はいささか早計ではないだろうか。
・世間は実に冷酷だ
現代は、偏差値50くらいの高校に通っていれば、もはや胸を張って大学生になれる時代だ。
偏差値40の高校でも、学年でトップの成績ならそこそこ名のある大学に推薦で行けてしまうこともある。
しかし、いざ大学に入学すると、一般入試の学生との学力差は非常に大きい。
中学生で例えるなら、5教科で250点の生徒と400点の生徒くらいの開きがあることも珍しくない。
偏差値40の高校でトップッだった生徒は、高校で生まれ変わった気分になってしまっているので、それほど差があることに気づかず大学に入学するのである。
もちろん、一般受験で入ったのならいいが、推薦などを利用して背伸びをしてしまうとそのあとがきつい。
そして、現実とのギャップにショックを受けて大学を中退してしまうのだ。
それでも高校は、生徒を大学に押し込んでしまえば目的達成なので「入学おめでとう、あとはがんばってね!」という具合に毎年生徒を大学に送り込み続けるのである。
一方、俗に言うFランや、Fランのちょっと上くらいの下位の大学ならそのような差を味わうことはあまりないだろう。
(Fランは以前はなかった言葉なので、わからない人は調べてください)
しかし最近では、文部科学省の指導もあって、授業の出席や試験などを厳しくする大学が増えているともいう。
そして「大学に行ったらバラ色だ!」という夢がもろくも崩れるのである。
さらに私が疑問に思うのが大学の授業料である。
もし、私立文系であれば、安く見積もっても4年間で500万円くらいはかかる。
学部によってはもっとかかることもある。
しかも、中には借金をしてまで大学に来る学生もいるわけだ。
大学側からすれば、借金を背負ってまで学費を納めてくれるのだから、ありがたいお客さんである。
大学は商売ではないはずだが、広く言えばサービス業とも言える。
こんな多大な借金を背負ってまで、お客さんがサービスを買いにくる業種が他にあるだろうか。
そして大学を卒業したら、借金返済におわれるのである。もちろん大学は、そうまでして通ってくれた学生の借金返済の責任なんか追わない。
なんて冷酷な世界だろう。
だからこそ、私は自分が受け持った生徒だけでも、ちゃんとした学力と思考力を持って大学生になってほしいと切に願っている。
言葉は悪いが、大学のいいカモにされないためにも、しっかり勉強して、むしろ大学を人生の踏み台として利用するくらいになってほしい。
学費を親が払うにしろ、借金をするにしろ、日本では大枚をはたかないと大学に行けないからだ。
もちろん、下位大学に通う学生の全てが、時間と金を無駄に浪費していると言うつもりはない。
しかし、未来ある若者が、大卒という看板を目の前にぶら下げられて、進路を冷静に考えられなくなっているような気もする。
そして大学では、年間100万円の学費を払ってまた中学の英語をやり直す。
年間100万円の学費を払って論文以前の作文の指導を受ける。
英語の文献はおろか、日本語の論文を読むのも一苦労だ。
多くの人にたくさんの学ぶ機会があるという点では素晴らしいが、その学費は、親が一生懸命稼いだお金だったり、学生本人がのちに返さなければならない借金だ。
まさに、誰でも大学に行けてしまう現代の悲劇といえよう。
勉強を教えて送り出す身としては、なんだか悔しいのである。
しかし、それでも大学生であるという高揚感が、全てを霧の中に隠してしまうようだ。