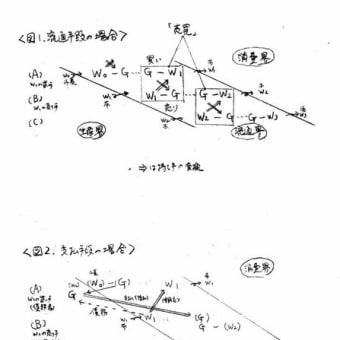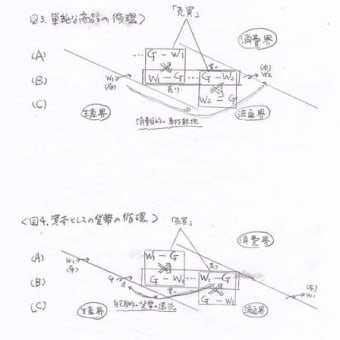「読む会」だより(20年11月用)文責IZ
(前回の議論など)
10月18日に行なわれた「読む会」では、労働力の価値をめぐって「マルクスの労働価値説は、スミスやリカードの労働価値説を発展させたものととらえてよいのか」、という質問が出ました。当日のチューターの説明は行き届いてなかったと思います。付録として岩波全書『経済学史』(久留間・玉野井共著)で、当該の問題について触れた部分を引用しておきます。参考願います。
第2篇第4章以降のいわば資本についての本論に入るにあたり、この間チューター自身、説明にピンとこないことがいくつかあったため、久留間鮫造の『貨幣論』などを読み返してみました。(『批判要綱』の「1859年のプラン草稿」に見られるように、資本論の第1篇「商品と貨幣」の部分は、「資本」の章以降のためのいわば理論的準備にあたると考えられます。)
そのうちの一つが、貨幣の第一の機能としてあげられている「価値尺度」の機能とはどのようなものか、という点です。今回はこの点について触れることにします。(次回はいわゆる「実現」の問題について触れたいと思います。また、矛盾の解決の仕方という抽象的な問題については、可能なら最後に触れます。)
(a.貨幣の「価値尺度」機能とはどのようなものか)
以前「たより」でも紹介しましたが、久留間は宇野の価値尺度論を批判する中で、「諸商品が金を貨幣にする過程と、貨幣=金で諸商品が自己の価値を表わす過程とを、区別しなければならない」と強調して、次のような比喩をしています。「これはある意味で大統領の場合に似ている。大統領を選ぶのは国民だけれども、ひとたび大統領として選ばれた者の名において国民の意思が発表されるということになると、大統領が今度は大統領としての機能をしている、と言えると思う。」(『貨幣論』大月版、P173~5)
比喩自身は分かりやすいのですが、チューターはその二つの過程の違いのなかに、「価格」(したがってまた「価値の価格への転化」)のもつ意味や意義についての重要な内容が含まれていることを、十分につかんでいなかったように思います。
大統領の例で言われているように、前の過程の結果が、次の過程では今度は前提として現れるということ自体には、難しいことはありません。人々の意志の代表化である選挙の結果として大統領が生まれると、次の過程では、大統領であることを前提にして、彼は特定の個人でありながら今度は人々の意思を代表して発言することになります。しかしこの場合、前の過程の結果としての大統領の行為は、やはり“同じ”人間の行為であり、また同じ人々の代表としての行為です。
ところが金の貨幣化(一般的等価物としての代表化・特定化・独占化)においては、諸商品の行為の結果が、次の過程では一見それとはまったく無縁な、金という一つの“物”の性格として現れ、しかも金をそのようなものとして現した(媒介した)関係は、結果では消えてしまうからこそ、理解が困難となるのです。
二つの過程について、久留間はこう説明しています。
「商品はまずこのようにして、金に貨幣という<経済的なあるいは社会的な……レポータ>形態規定を与えたうえで、今度は、この貨幣としての金で、それぞれに自分の価値を表示するわけです。単なる金ではなくてすでに貨幣になっている金で。諸商品が共同の行為によって金を貨幣にする過程と、すでに貨幣になっている金で、いちいちの商品が自分の価値を<価格という一律の形式で……レポータ>表わす過程とは違うわけです。」(同、P174)
前者の、諸商品が金を貨幣にする過程(つまり諸商品がその価値を排他的な一商品である一商品・金で表現する過程)は、形式から言えば、すべての商品が左辺にたって、右辺に一商品・金がおかれる、一般的な相対的価値形態の形式です。他方、後者の貨幣形態では、右辺に立つ商品が金に社会的に“固定化”されるということしか、形式的な違いはないように見えます。
ところが、このようにひとたび金が、唯一右辺に立ちうる独占的な一般的等価物として、すなわち貨幣として認められると、任意の一商品は、その価値を他の種々の諸商品の価値表現との関係の中で示さずとも、ただ一つの貨幣・金の量として示しさえすれば、価値表現されたことになります。第3章第1節ではこう触れられていました。
・「一商品の金での価値表現──x量の商品A=y量の貨幣商品──は、その商品の貨幣形態またはその商品の価格である。今では、鉄価値を社会的に通用するようにあらわすためには、 1トンの鉄=2オンスの金 というような一つの単独な等式で十分である。この等式は、もはや、他の諸商品の価値等式といっしょに整列する必要はない。というのは、等価物商品である金は、すでに<独占的な一般的等価物という……レポータ>貨幣の性質をもっているからからである。それゆえ、諸商品の一般的な相対的価値形態は、いまでは再びその最初の単純な、または個別的な相対的価値形態の姿をもっているのである。」(全集版、P126)
今では、1トンの鉄は、小麦やコーヒーなどの他の商品の一般的等価物との関係として示されずとも、 =2オンスの金 という単独な価値等式(すなわち価格形態)だけで、その価値を表現していることになります。
問題はまず、金が貨幣という(経済的なあるいは社会的な)形態規定を与えられると、諸商品の価値表現は、すべて“一律な”形式(=y量の金)になると同時に、それは他の諸商品の種々の価値表現といっしょに整列する(全集版の訳では、「一緒に列をつくって行進する」)必要がなくなる、ということの重要性です。
なぜそのようなことが可能になるかと言えば、第一に、すべての商品がその価値を貨幣・金の大きさで表わすのですから、一商品は、貨幣・金の大きさ(すなわち「価格」)でその価値を表現するならば、単に貨幣・金と関係をもつのではなくて、同時に他のすべての商品と価値関係をもっていることになります。つまり例えばある商品 1トンの鉄が「金2ポンド」という「価格」をもつならば、それは1トンの鉄が別の商品、たとえば2クォーターの小麦(=2ポンドの金)とか、80ポンドのコーヒー(=2ポンドの金)といった別の商品とも等価であるという、価値関係をもつことになり、つまり社会的支出労働量としての関係で他商品と相互に結ばれていることになるのです。
そしてこの場合、第二に、一般的等価物として右辺に立つという地位を独占している金は、左辺に立っている諸商品がすべてそれらの価値を金すなわち自分自身で表わしているのですから、他の諸商品との“直接的(絶対的)交換可能性”という金としての使用価値からは独立した独特な経済的形態規定をもつことになります。(すでに1章3節で触れたように、左辺に立つ諸商品の方は、この直接的交換可能性をもつことができません。)
これらの結果、金は、諸商品の交換関係の中にあっては、その物質的な自然形態の大きさによって価値の大いさを表わすもの(価値の自立的な存在物)となり、諸商品にたいして“価値そのもの”として振舞うことができるのです。
そこで、たとえば1トンの鉄の価値が2オンスの金(その貨幣名称がポンドであれば2ポンド)と等価である、という支出労働量としての相互の“関係”は、1トンの鉄の価値は金2ポンドである、という一つの“物”の大きさで表現されることになります。つまり、1トンの鉄の価値は、それ自身の支出労働量や他の諸商品の等置関係(価値関係)とは独立に、金という一使用価値の物質的大きさとして、つまり支出労働量という価値そのものとはまったく異質なものとして、表現されることになります。
金が貨幣となり、商品の価値が金量で(すなわち価格で)表わされるようになると、金が“価値そのもの”としてふるまうことを可能にしている条件であった──金を貨幣として生み出した諸商品の価値表現や、他の諸商品と直接的に交換可能であるという金の“社会的な”性質といった諸関係──は、すべて貨幣の陰に消えて見えなくなるのです。
ここに「これらのもの、金銀は、地の底から出てきたままで、同時にいっさいの人間労働の直接的化身である。ここに貨幣の魔術がある」(第2章、末尾)と言われる、貨幣の「魔術」の“仕掛け”があるのです。
前置きが長くなりましたが、貨幣の「価値尺度機能」について、マルクスは第3章の冒頭でこう触れています。
・「金の第一の機能は、商品世界にその価値表現の材料を提供すること、または、諸商品価値を同名の大きさ、すなわち質的に同じで量的に比較の可能な大きさとして表わすことにある。こうして、金は諸価値の一般的尺度として機能し、ただこの機能によってのみ、金という独自な等価物商品はまず貨幣になるのである。
・「金の第一の機能は、商品世界にその価値表現の材料を提供すること、または、諸商品価値を同名の大きさ、すなわち質的に同じで量的に比較の可能な大きさとして表わすことにある。こうして、金は諸価値の一般的尺度として機能し、ただこの機能によってのみ、金という独自な等価物商品はまず貨幣になるのである。
諸商品は、貨幣によって通約可能<同質なもの……レポータ>になるのではない。逆である。すべての商品が価値としては対象化された人間労働であり、したがって、それら自体として通約可能だからこそ、すべての商品は、自分たちの価値を同じ独自な一商品で共同に計ることができるのであり、また、そうすることによって、この独自な一商品を自分たちの共通な価値尺度すなわち貨幣に転化することができるのである。<外的な……レポータ>価値尺度としての貨幣は、諸商品の内在的な価値尺度の、すなわち労働時間の、必然的な現象形態である。
一商品の金での価値表現──……──は、その商品の貨幣形態またはその商品の価格である。(以下、上記の引用に続く)」(全集版、P125)
貨幣の「価値尺度」機能とは、諸商品の価値を価格(金重量)として一律に表示するための、貨幣・金の役割・機能であり、この貨幣・金の独特な機能は、すでに触れたように諸商品にたいして金が、その物質的な大きさが価値の大いさを表わすもの(価値の自立的な存在物)、“価値そのもの”として相対するということで成り立ちます。このことによって「商品世界にその価値表現の材料を提供すること」が可能となり、それによってはじめて、諸商品の価値は価格に転化することができるのです。
言い換えれば、商品に内在的な価値(すなわち諸商品の等置関係の内容・実体としての社会的支出労働時間)を、外在的な、物(貨幣・金)の属性とその大きさ──すなわち「価格」──として一律かつ対立的に表現し、“現象”させること、それが貨幣の「価値尺度」機能です。それは同時に商品と貨幣との対立的な関係において、価値を表現することが貨幣に具わった“専有”の機能となることでもあります──この点については次回のいわゆる“実現”の問題で、とり上げます。
そして貨幣・金のこの機能によって、価値は価格へと転化し、そこに貨幣“幻想”が──金物質そのものが価値であるからこそ金の大きさ(価格)で価値が計られる、あるいはだから価格は“観念的なもの”ではなくて金という実在的なものがもつ属性である、というような転倒した観念が──生ずるのです。
この諸個人が支出した種々の社会的労働時間を、貨幣・金という一つの物の大きさで表現する必要は、けっして宇野が言うような商品所有者の主観的な意図によってもたらされるのではありません。それは自然発生的な私的分業の下で社会的な生産が可能となるための必然的な条件なのです。諸個人が支出した私的な労働は、他の商品との直接的交換可能性をもつ貨幣・金という物の大きさとして“媒介的”に表現されることによって、はじめて社会的労働としての一律な“表現”を受けることができるのです。それは商品の二重化、すなわち商品相互による価値の対立的な表現の直接の結果なのであって、だからこそ価値表現における“主体”は人間ではなくて、人間の手の生産物である“商品”なのです。
諸商品が、その使用価値と区別される一律な価格表現をもつことによって、相互に等しいものとして関連しあうからこそ、はじめて使用価値どうしの交換(物々交換)は、個人的な欲望の制限を突き破り、“商品”として全面的な交換関係を発展させることができるようになるのです。
(他方、今後の研究課題になりますが、現代の管理通貨制度の下でのように、貨幣・金が直接流通に現れることがなくなってしまえば、諸商品はその価値を価格として世界中で一律に表現することができなくなり、貿易等に大きな混乱をもたらすことだけは明らかでしょう。)
(説明)第5章「労働過程と価値増殖過程」 第1節「労働過程」
「労働過程」については、先にも触れた「1859年のプラン草稿」でもほんの少ししか触れられていませんが、検討してみると生産的消費と個人的消費との区別の問題など、後に再び問題となってくる大きな事柄も含まれているので、簡単に済ますというわけにはいかないことが分かりました。
価値尺度の件で時間をとってしまったこともあり、今回は最初の説明項目のみを掲げて、説明等は次回以降に回させていただきます。
1)生産物の使用価値は、それを生み出した人間の社会関係・社会形態とは無関係であるが、同様に、使用価値の生産のための合目的的活動であるという労働の普遍的な性格は、それが資本家的な生産であるということによって変わるものではない。資本家的な生産においては、使用価値と同時に価値をもつ“商品”の生産のために労働力が用いられる。このために、労働対象と労働用具という客観的な条件のなかで行われる労働過程が、同時に価値増殖過程として遂行される。ここに資本家的生産の特徴がある。
(付録・参考)岩波全書『経済学史』(久留間・玉野井共著)、第3章「古典学派」より
・要するにスミスは、資本の蓄積と同時に、労働者は彼の労働の所産の全部をもはや取得しなくなるということ、したがってまた、「生産に必要な労働の量」と「支配しうる労働の量」とがもはや一致しなくなるということ、──こういうことからして、資本が蓄積された以後には、商品の生産に必要な労働力の割合はもはやそれらの商品を相互に交換するための規準にはならなくなると結論するのである。だがこの結論は明らかに誤っている。彼はむしろ反対に、リカードと共にこう結論すべきはずであった、すなわち、生産に必要な労働の量と支配しうる労働の量とは、こうした事情の下ではもはや一致しないがゆえに、後者<支配しうる労働の量>はもはや「正確に他の物の価値を測定」することはできない。この<資本の蓄積という>事情の変化によって影響されるのは後者であって、前者<生産に必要な労働の量>ではない。けだし価値の大きさの決定はその大きさの分割とは全く独立した問題であるから、と。
かくて、商品の価値はその生産に必要な労働時間によって決定されるという根本命題を、資本家的生産関係の到来による事態の変化に惑わされないであくまで貫いたということは、リカードの偉大な功績であったのである。
だがこの場合にもまた、スミスが陥った混乱と矛盾とは、リカードが想像したよりもより深い根底に根差していることに注意しなければならぬ。なるほど、普通の商品と商品との交換の場合には、リカードのように考えて少しも問題はない。だがスミスを迷わしたのはそれではなく、資本家社会に特有な資本と労働との交換であったのである。資本家は労賃(貨幣)を与えて労働者を雇い入れる。労働者は労賃を受け取る代わりに資本家のために労働する。ところでこの場合、労働者がが彼の労働によって資本家のためにつくり出す価値は、スミスが主張しリカードもまた承認するところによれば、「二つの部分に分解する、すなわち、一部分は彼らの労賃を支払い、他の部分は雇主が前貸しした原料と労賃との全資本に対する利潤を支払う」のである。換言すれば、労働者は、彼が受け取るところの貨幣のうちに含まれている労働時間を超える時間を、利潤分として、資本家のために労働するのである。すなわち、そこでは、結局において、より多くの生きた労働がより少ない対象化された労働と交換されるのである。この事実は本来の価値法則と矛盾しないか? この疑惑が、スミスを混乱せしめた根本的な動機であったのである。ところがリカードは、この問題には少しも注意しない。彼ははじめから、ここに一個の重大な問題が存在することにさえ気付かない。彼はひたすら普通の商品と商品との交換にのみ着眼し、労働者と資本家との間における商品価値の分配は、その商品の価値の大きさそのものの規定とは無関係であることを知って満足するのである。
かくして、さきにはスミスを惑わし、後にはリカードによって看過されたこの問題<資本と労働との交換にあっては、価値法則と矛盾する不等価交換が行われる>は、ついに古典派経済学にとっての一大暗礁となった。それは、あとに説明する平均利潤率ないし生産価格の問題とともに、この学派を理論的に崩壊せしめる重要な要因になったのである。
古典派経済学によって解決されなかったこの問題がその後の俗流経済学によって解決されなかったことは言うまでもない。否むしろ、古典学派によるこの問題の解決の不可能は、その後の資本家的経済学をして本来の価値理論を放棄せしめ、その代わりに完全な俗学的体系──現象の皮相的解釈──をもってするに至らしめた重要な転機をなしたのである。
かくしてこの問題は、マルクスに至るまで何ぴとによっても解決されなかった。ではマルクスはどのようにしてそれを解決したか。
彼によれば、資本家が労働者から買うところのものは労働力であって労働ではない。一種の商品としての労働力は、他のすべての商品と同様に、使用価値と共に価値をもっている。
『労働力の価値は、他の諸商品の価値と同様に、この独自な財貨の生産、したがってまた再生産に必要な労働時間によって規定されている。それが価値である限りでは、労働力そのものは、それに対象化されている社会的平均労働の一定分量のみを代表する。労働力は生きた個人の素質としてのみ存在する。個人の存在が与えられておれば、労働力の生産とは個人自身の再生産あるいは維持のことである。自分を維持するために、生きた個人は一定量の生活手段を必要とする。だから労働力の生産に必要な労働時間は、これらの生活手段の生産に必要な労働時間に帰着する、すなわち労働力の価値は、労働力の所有者の維持に必要な生活手段の価値である。』(資本論第1巻第4章、全集版P223)
では他面において、労働力の使用価値とはいったいなんであるか? 労働力はその名の示す如く労働する能力であり、その使用価値はこの能力の実現、すなわち労働である。ところが労働は、それが商品を生産する限りにおいては、使用価値と共に価値を創造する作用をもつ。すなわち労働力なる商品は、一面においてそれ自身の価値をもつとともに、他面にはまた、このそれ自身の価値とは全く無関係に、新たな価値を創造しうるという、一種特別の使用価値をもっている。そしてここに、資本家的生産の根本的秘密が横たわっているのである。資本家が利潤を得るのは決して価値法則に違反して得るのではない。彼はそれを価値法則に従って得るのである。彼は労働力をその価値どおりに購買する。そしてその購買と同時に、普通の商品購買者と同じように、この労働力の使用価値を受け取るのである。
『……労働力の使用価値である労働そのものは、販売された油の使用価値が油商人に属しないのと同様に、労働力の販売者には属しない。貨幣所有者はすでに労働力の日価値を支払っている。だから、1日間の労働力の使用は、1日中の労働は、彼に属する。労働力はまる1日作用し、労働し得るのだが、労働力の日々の維持は半労働日しか要しないという事情、したがって、労働力の1日間の使用が創造する価値はそれ自身の日価値の2倍の大きさだという事情は、購買者にとっては特殊な幸いであるが、しかし、販売者に対する不正などでは決してない。』(同、第5章P264)
このように、古典学派は「労働力」の認識に到達しえないで、「労働力に価値」を「労働の価値」として観念したために、その体系のうちに媒介されない矛盾を包含することになり、ついに学派として破綻するのやむなきに至ったのであるが、しかしこのことは、彼らがある意味で剰余価値の源泉を知覚していたことを否定するものではない。否むしろ、彼らがある意味で剰余価値の源泉を知覚していたればこそ──換言すれば、彼らが少なくとも事実上においてより多くの労働とより少ない労働との交換を認め、利潤や地代を不払の労働に帰したればこそ──彼らはさきに述べた矛盾に陥ることにもなったのである。思うに、結果からみれば、そこには事実の矛盾が──価値法則の事実上の逆転が──あるのであって、彼らの学説の矛盾はこの矛盾した事実を事実として認識したことに基づくのである。資本家的な偏見にとらわれ、資本家的生産の歴史的特質を把握しえなかった彼らは、この価値法則の事実上の逆転が労働力の商品化の結果であり、価値法則の発展の結果であることを看取することができなかった。したがって彼らは、剰余価値の発生を価値法則にもとづいて、価値法則から展開することはできなかった。だがそれにもかかわらず、彼らはこの発展の結果をば認識した。すなわち事実上において、より多くの労働とより少ない労働との交換を認め、利潤や地代を不払の労働に帰したのである。そしてここに、彼らの学説としての矛盾が生じることになったのである。だから彼らの学説におけるこの矛盾<価値法則の事実上の逆転を、価値法則から展開することなくただ結果として承認する>は、剰余価値の認識における彼らの欠陥を──資本家的視角に伴う必然的な欠陥を──表わすと同時に、俗流経済学に比しての彼らの偉大さを物語るものと言わねばならぬ。……(『経済学史』、岩波全書、第3章「古典学派」、P107~)