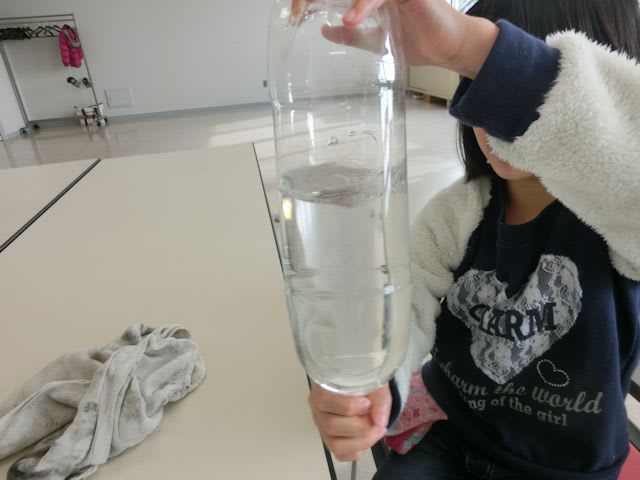実験タイトル一覧
「沼田町化石館おもしろ科学教室」は毎年11月から翌年3月まで月1回のペースで実施しています.
「竜巻発生装置」 2016/1/24
「雪の結晶」 2016/1/24
「大気圧のふしぎ」 2015/12/20
「金属はピカピカ」 アルミ缶をみがく 2014/11/22

「DNAの実験」 2014/2/22
「煮干しの解剖」 2014/1/25
「ホタルの光」 2013/12/14
「イカの解剖」 2013/11/9
「簡単浄水器」 2013/1/26
「火おこし」 2012/12/15
「ソーラークッカー」 2012/7/30
「ダンボールリサイクル工作」 2012/3/26
「不思議な噴水」 2012/2/18
「牛乳パックでカメラ」 2012/1/28
「ペットボトルで顕微鏡」 2011/12/17
「あまくておいしい火山の実験」 2011/2/19
「すっぱくておいしい実験」 2011/1/22
「ホカホカふんわりおいしい実験」 2010/12/11
「あまくておいしい実験」 2010/11/6
「紙でおもしろ科学工作」 2010/3/26
「フィルムケースでおもしろ科学工作」 2010/2/20
「プラコップでおもしろ科学工作」 2010/1/23
「ペットボトルでおもしろ科学工作」 2009/12/19
「CDでおもしろ科学工作」 2009/11/21
「いろんな電池でおもしろ実験」 2008/3/28
「音の出るおもしろ実験」 2008/2/16
「水蒸気でおもしろ実験」 2008/1/19
右:ポンポン蒸気船
「キャンドル作りでおもしろ実験」 2007/12/15
 左上:炎色反応キャンドル
左上:炎色反応キャンドル
右上:廃油リサイクルキャンドル
左下:レインボーキャンドル
「タンパク質でおもしろ実験」 2007/11/17
 左上:レモンチーズ
左上:レモンチーズ
右上:レモン豆腐
左下:小麦粉のガム
「空気の力でおもしろ実験」 2007/8/10
 左上:風船ホバークラフト
左上:風船ホバークラフト
右上:ミニ空気砲
左下:バブ・ロケット
「爆発」 2007/3/27


「空気の不思議」 2007/3/10


「雪の不思議」実験 2007/2/10


ホカホカ実験 2007/1/10


「光の不思議」実験



左上:コップと虫眼鏡で望遠鏡(2006/12/9)
右上:セロテープのステンドグラス(2006/12/9)
左下:CDで虹の見える箱(2006/12/9)
「熱の不思議」実験


 左上:輪ゴムに熱湯をかけると?(2006/11/18)
左上:輪ゴムに熱湯をかけると?(2006/11/18)
右上:縮むペットボトルラベル(2006/11/18)
左下:プラ板を焼くと?(2006/11/18)