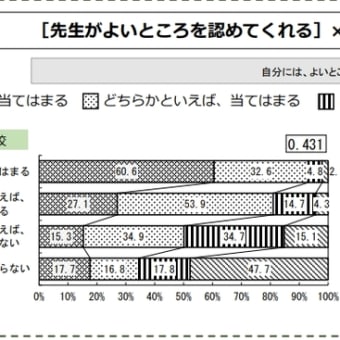公立高校専門学科
中学3年生の高校受験、進路指導、において「専門学科」つまり、工業高校・農業高校・商業高校などですね、僕は結構勧めています。
ただ、どういう先入観なのか、この時の親御さんの反応が非常に悪い。怒り出す親御さんもいるんです、結構ビックリ。
北海道から数校挙げてみますと
厚岸翔洋高校 海洋資源科 0.37 0.35 0.32
更別農業高校 農業科 0.33 0.35 0.15
当別高校 園芸デザイン科 0.23 0.23 0.21
福島商業高校 0.28 0.25 0.4
室蘭工業高校 環境土木科 0.28 0.4 0.25
大船渡東高校 農芸科学科 0.23 0.48 0.33
鹿島台商業高校 商業科 0.18 0.20 0.28
亘理高校 商業科 0.40 0.33 0.30
能代科学技術高校 生物資源科・生活福祉科 0.64 0.33 0.14
新庄神室産業高校 食料生産科 0.33 0.30 0.43
山辺高校 福祉科 0.27 0.31 0.38
喜多方桐桜高校 建設科 0.25 0.50 0.38
日立工業高校 電気科 0.80 0.10 0.30
羽生実業高校 商業科 0.33 0.26 0.21
総合工科高校 建築・都市工学科 0.45 0.48 0.24
この小数点は倍率です。令和3・4・5年度入学試験です。
この倍率の様に廃校になっても、そんな感じだから、というのもあるかな。
この場合ですと、当日、しっかりと名前を書けば合格です。
私立高校ではないので確定、絶対に合格です。
僕がこうした専門学科を勧めるのには理由があって「優秀な人材が集うから」これだけです。
その中で早く原石からダイヤモンドになった方がいい、そう考えているからです。
各々の専門分野を16歳から、突き進む。
だって、大学に進学しても「この学部学科でよかったのか…」とか悩んでしまう大学生も居る時代ですよ、もうこの時点で差がついています。
ただ、現状、専門学科というのは普通科の進学先が無いので受験する、そんな子どもたちが多い、もったいない。ガラも悪い、これまたもったいない。
2024年4月、今年度ですね、早稲田大学理工学部では高専卒業生が3年生に編入できる制度が始まりました。
僕から言わせれば遅い!!
無論、高専卒業生からしてみれば「大学なんて行ってもな~」それなりの資格なども合格してしまっているので意味がない、ニーズが無かった、というのもあったのでしょう。
早稲田大学側から「求む!優秀な人材!!」こういう動きです。
数年先には商学部に商業高校優先枠、工学部に工業高校優先枠、農学部に農業高校優先枠、ができる、僕はそう考えています。
これから大学入試の約60~70%は推薦入試に切り替わるので、ほぼ断定してもいい、そう考えています。
ただ、それには1つだけ問題があって、今、専門学科に在籍している高校生諸君!!
いかに自分たちが高度な事を学んでいるかという自覚がなさすぎ!!
これかな。
高校の3年間の学習量を考えると、1年生から電気科であれば電気、農業科であればバイオや獣医、というように学べる環境そのものが、どれだけ恵まれている環境にいるか、早く気が付いたもの勝ち、そういう時代です。
高校では「Super・Science・Highschool」に認定されるかどうか、文科省からそのサインを送ってもらいだしているのにどうもまだ響いていないようです。
どんどん、極めて、世界に誇れる人材になれれば、その可能性があるのに気が付いていない、これはあまりにももったいない。
僕は、バカだけど、行動力だけはあるので、休職して1年間インドで数学を若い時に学んでいました。
当時のインドは「IT最先端・数学教育最先端」こう言われていたので。

数学科に1年間通ったわけなんですが、もう、1ヶ月位でかな。
「アホくさ!!」
申し訳ないけど、そう感じました。
やっぱり自分で確認した方がいい、つくづくそう感じました。
単科大学で、そうね、高校受験ぐらい、そんなレベルだった。
数学に関して学んだことは1つもないです(笑)
日本に入ってきている情報というのは、例えてみれば、今、大谷翔平選手がアメリカではものすごい活躍してくれていますよね。
それを見たアメリカ人が「日本で野球をしている子ども達はとんでもなくレベルが高い」そう思い込んでしまっている、そんな感じ。
そりゃトップ選手はそうでしょうけど、小学生で野球初めたら物凄い選手に全員なるんだぞ~、そう思われたらあまりにも迷惑ですよね、全く同じ。
話を戻して、商業高校生だったら「簿記」かな、2級は合格するでしょう。
相当なミスをしない限り共通テストでも満点です。
そんなものは通過点で、その先、税理士でも、公認会計士でも目指せる環境に居る、この点に早く気が付いた方がいいです。
工業高校であれば、建築科なら測量の単位もあるでしょ?
図面1つ書いて数十万円の世界、意外と知られてない。
もう入学した時点、教科書を渡された時点で目の前にそうした道は開かれいてるのに、気が付いていない。
それで「俺、とりえねえし」もったいなさすぎる。
今の君たちの存在そのものが自分が自分で言い聞かせられるとりえ、自分を信じないとダメダメ!!

写真はインドの地下鉄です。
でもね、この先、工事はストップ状態で見通しは立っていませんでした。
工事を請け負っていたのは日本の有名ゼネコンです。
そう、日本の技術は世界一、だからこそインド政府にも「金出せるまで工事しないよ!」と強気に言える。
まあインドという国は賄賂王国なんでね、もともと政治不信が渦巻いている。
友人は「日本にお金払わない政治家がいけない、待ってくれている日本は優しい」こう言ってました。
友人って、言うまでもなくインド人ですよ、日本という国はそれだけの評価を受けているんですよね。日本人が日本人の強みに気が付いていないだけ。
僕自身も専門学科に高校は進学しました。普通科ではないです。
強みが出たのは「理科」かな。
大学受験の模試ってありますよね、いつも偏差値80を超えてた ( ^)o(^ )
はっきり言って楽勝でした。
大学受験の為に物理だの化学だの、そんなものは勉強した事は当然ないです、部活動が忙しかったのでそんな暇なかった、先輩の方が怖いんだもん。
高校時代の友人は今は大学教授となって悠々自適な生活をしているのもいて、コンニャロ~、ですよね。
でも、大学に入学した時点で1年生の中に4年生が紛れ込んでいる、こう考えてみると、それは、成績優秀だったのは明らか、彼は母子家庭であったけども奨学金も給付されていたのも明らか、目の前の道の先がどれだけ、輝いているのか、16歳にして気が付いた彼の勝ちです。
こういう友人を「勝者」と僕は呼んでいいと考えています。
僕もだけど、高校生の時はね「かわいそ~」「将来どうするの?」とか言われ続け3年間耐えて、部活の試合でも「バカは勉強しないでいいからいいよな~」勝っても聴こえるように言いやがる(怒)
でも、耐えるしかないじゃん。
模試を返してもらえに予備校に行けば
「こいつ工業高校とかなってんだけど(笑)」
「嘘書いてるんだけど(笑)」
ば~か!文句あるか! 気が付いたもの勝ちなんだよ!って感じてたかな。
この先、日本経済を見渡すと、現状では明るい課題が無いように感じてしまいます。評論家の中には政治家のせいにしてお先真っ暗、訳わからない。
最悪な場合アメリカに向かって
「国債もう買わない、全部売っていい?」
そう言えばいい。アメリカのATMからもう卒業すればいい。
下水道技術、これで世界に勝負かければいい、勝てる国などない。
我々の周囲に当たり前のようにあるものが、世界では「どうしても欲しい!」これでいくらでも円で勝負できるのに。
僕なんかは教育業界に居る訳なんですけどけど。
別に、数学の偏差値70とか、そんなものは難しくもなんともない。
いつも考えているのは今学んでいることをどう活かしてくれるかな?
その点が1番強い、だから専門学科を胸張って勧めています。
連日、YouTubeばっかりで申し訳ないんですけど
衆議院議員、松原仁さん。
上川大臣も頭の切れる有能な大臣、そう感じていましたが、この松原衆議院議員、有能さを「情」も含めて上回っている、これが日本人なんじゃないのかな。
僕はそう思いますけどね。
<