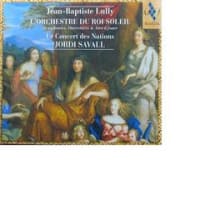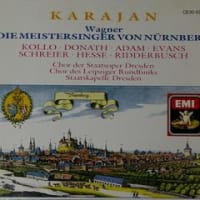パトリシア・プティボンの絶品アリア集に魅せられてフランス・バロックの森に足を踏み入れた僕が意識した作曲家は、リュリ、シャルパンティエ、ラモーの3人でした。ラモーについては以前にオペラを紹介しましたが、この中でもっとも僕の琴線に触れる作曲家が、ジャン=バティスト・リュリ(1632-87)です。
イタリアの出身ながらルイ14世の庇護(寵愛)を受けてフランスで活躍したリュリは、モリエールとのコンビによるバレエを盛り込んだ喜劇であるコメディ=バレや、独自の叙情悲劇(トラジディ・リリック)などを生み出しました。国王の後ろ盾によりフランス宮廷音楽界で絶大な権力を握ったリュリは、シャルパンティエなどのライバルに対しては容赦なく攻撃するなど野心家として知られ、一方で小姓と関係を結んで国王の不興を買うなど、波乱に満ちた生涯を送ったようです。このあたりは、ジェラール・コルビオの映画「王は踊る」でその一端を知ることができます。最期は指揮杖で足を打ち抜いたのがもとで死んだというのも結構有名ですよね。
かつては、リュリなんぞは過去の遺物で、とても現代人の耳には時代遅れでとても共感できるような音楽ではないものと多分みんなが思っていました。ひと昔前の演奏では確かにそうだったでしょう。しかしクリスティを代表とする新しいバロック演奏の出現により、ラモーやヘンデルなどと同様にリュリの作品も我々現代人にとって単なる骨董品の鑑賞ではなく、新鮮な息吹を吹き込まれて親近感をもって接することのできる音楽に蘇ったように思えます。
僕にとっては、トラジディ・リリックの幕切れで演奏されるシャコンヌなどの切なく感傷に満ちた旋律やコメディ=バレの明るい躍動感は、ラモーの構築感のある音楽よりもいっそう感覚的な親しみを感じるものとなっています。その個性が色濃く反映されている音楽は他のフランス・バロックの作曲家からは得られないものだと思われ、リュリの音楽に出会えていなかったらと思うと、プティボンに感謝することしきり、なのです。
こうしたリュリの音楽の入門編にうってつけなのは、クリスティが手兵レアール・フロリサンと録音した「魔法の島の歓楽:ヴェルサイユのディヴェルティスマン」と題した作品集です。「コメディ=バレから音楽悲劇への道程 太陽王の作曲家の作品を通して」という副題の付いたこの1枚物のアルバムは幅広い視点から彼の作品を紹介したもので、最後は「アルミード」のパッサカーユで締めくくられています。気品に満ちた演奏も非の打ちどころのないものです。ミンコフスキがこれも手兵のレ・ミュジシャン・ド・ルーブルと入れた「コメディ・バレエ作品集」は喜劇的な世界を面白おかしく歌い演じたものですが、僕にはちょっと羽目をはずしすぎな感じがします(吉本が好きな人にはいいかもしれません)。それよりもレオンハルト/ラ・プティ・バンドの「町人貴族」全曲は1973年の録音ながら演奏の古めかしさを感じさせず、大変優れたものだと思います。
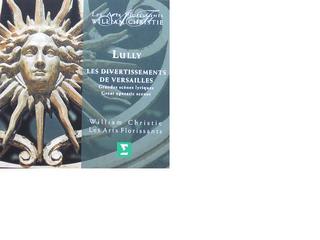
器楽のみの演奏では、ジョルディ・サヴァール/ル・コンセール・ナシォンによる「リュリ:太陽王のオーケストラ」がお勧めです。「町人貴族」や「王のヴェルサイユのための大ディヴェルティスマン」などの組曲を優雅な中にも生き生きとした演奏で聴くことができます。
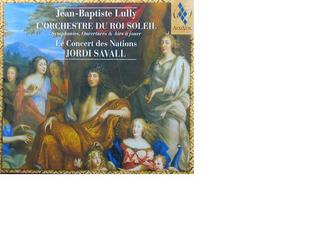
トラジディ・リリックの演奏としてはクリスティの「アティス」がエポックメーキングな演奏で評価も高いのですが、まだ僕はいまひとつ捉えきれていません。それよりヘレヴェッヘ/ラ・シャペル・ロアイアルの「アルミード」が絶品といえます。先ほど記した幕切れのパッサカーユに向かって物語が一気に収斂していく緊張感が、哀愁をたたえた音楽とともに聴きての胸に強く迫ってきます。
他にはミンコフスキの「ファエトン」もいいですし、牧歌劇「アシスとガラテア」も肩肘張らずに聴くことができます。

DVDはニケ/ターフェルムジーク・バロック・オーケストラによるトロントでの舞台上演「ペルセ」が廉価版で入手できます。あまり期待していなかったのですが、どうして実に楽しめる舞台となっていました。演出も適度に現代的で様式感もあり、好ましいものでした。日本語字幕はありませんが、比較的単純な筋書きなので気にするほどではありません。
他にはグラン・モテなどの宗教音楽もあり、ハルモニアムンディ・フランスやACCORDから一連のCDがリリースされています。これらのほとんどは母国フランスで生まれ発信されたものですが、往時のフランス宮廷の光と影を今に伝えるリュリの音楽は、時間と距離を超えて21世紀の我々にも語りかけてくれるのです。
イタリアの出身ながらルイ14世の庇護(寵愛)を受けてフランスで活躍したリュリは、モリエールとのコンビによるバレエを盛り込んだ喜劇であるコメディ=バレや、独自の叙情悲劇(トラジディ・リリック)などを生み出しました。国王の後ろ盾によりフランス宮廷音楽界で絶大な権力を握ったリュリは、シャルパンティエなどのライバルに対しては容赦なく攻撃するなど野心家として知られ、一方で小姓と関係を結んで国王の不興を買うなど、波乱に満ちた生涯を送ったようです。このあたりは、ジェラール・コルビオの映画「王は踊る」でその一端を知ることができます。最期は指揮杖で足を打ち抜いたのがもとで死んだというのも結構有名ですよね。
かつては、リュリなんぞは過去の遺物で、とても現代人の耳には時代遅れでとても共感できるような音楽ではないものと多分みんなが思っていました。ひと昔前の演奏では確かにそうだったでしょう。しかしクリスティを代表とする新しいバロック演奏の出現により、ラモーやヘンデルなどと同様にリュリの作品も我々現代人にとって単なる骨董品の鑑賞ではなく、新鮮な息吹を吹き込まれて親近感をもって接することのできる音楽に蘇ったように思えます。
僕にとっては、トラジディ・リリックの幕切れで演奏されるシャコンヌなどの切なく感傷に満ちた旋律やコメディ=バレの明るい躍動感は、ラモーの構築感のある音楽よりもいっそう感覚的な親しみを感じるものとなっています。その個性が色濃く反映されている音楽は他のフランス・バロックの作曲家からは得られないものだと思われ、リュリの音楽に出会えていなかったらと思うと、プティボンに感謝することしきり、なのです。
こうしたリュリの音楽の入門編にうってつけなのは、クリスティが手兵レアール・フロリサンと録音した「魔法の島の歓楽:ヴェルサイユのディヴェルティスマン」と題した作品集です。「コメディ=バレから音楽悲劇への道程 太陽王の作曲家の作品を通して」という副題の付いたこの1枚物のアルバムは幅広い視点から彼の作品を紹介したもので、最後は「アルミード」のパッサカーユで締めくくられています。気品に満ちた演奏も非の打ちどころのないものです。ミンコフスキがこれも手兵のレ・ミュジシャン・ド・ルーブルと入れた「コメディ・バレエ作品集」は喜劇的な世界を面白おかしく歌い演じたものですが、僕にはちょっと羽目をはずしすぎな感じがします(吉本が好きな人にはいいかもしれません)。それよりもレオンハルト/ラ・プティ・バンドの「町人貴族」全曲は1973年の録音ながら演奏の古めかしさを感じさせず、大変優れたものだと思います。
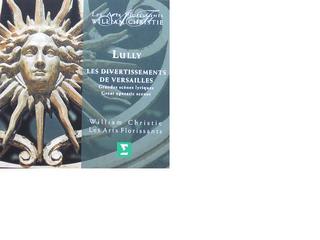
器楽のみの演奏では、ジョルディ・サヴァール/ル・コンセール・ナシォンによる「リュリ:太陽王のオーケストラ」がお勧めです。「町人貴族」や「王のヴェルサイユのための大ディヴェルティスマン」などの組曲を優雅な中にも生き生きとした演奏で聴くことができます。
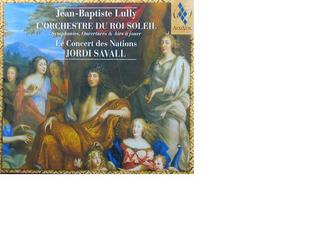
トラジディ・リリックの演奏としてはクリスティの「アティス」がエポックメーキングな演奏で評価も高いのですが、まだ僕はいまひとつ捉えきれていません。それよりヘレヴェッヘ/ラ・シャペル・ロアイアルの「アルミード」が絶品といえます。先ほど記した幕切れのパッサカーユに向かって物語が一気に収斂していく緊張感が、哀愁をたたえた音楽とともに聴きての胸に強く迫ってきます。
他にはミンコフスキの「ファエトン」もいいですし、牧歌劇「アシスとガラテア」も肩肘張らずに聴くことができます。

DVDはニケ/ターフェルムジーク・バロック・オーケストラによるトロントでの舞台上演「ペルセ」が廉価版で入手できます。あまり期待していなかったのですが、どうして実に楽しめる舞台となっていました。演出も適度に現代的で様式感もあり、好ましいものでした。日本語字幕はありませんが、比較的単純な筋書きなので気にするほどではありません。
他にはグラン・モテなどの宗教音楽もあり、ハルモニアムンディ・フランスやACCORDから一連のCDがリリースされています。これらのほとんどは母国フランスで生まれ発信されたものですが、往時のフランス宮廷の光と影を今に伝えるリュリの音楽は、時間と距離を超えて21世紀の我々にも語りかけてくれるのです。