カゴ釣りの一番の利点は、遠いポイントへの遠投が可能なこととコマセが仕掛けや付け餌と同調することにあり、アジ釣りでは投げサビキと並んで幅広い層が楽しめる釣法です。
遠投カゴ釣りをやってみたいけど難しそうだと踏み出せない釣り人が多いと思いますが、投げサビキより楽に遠投できてますし、夕マズメが終わって暗くなってからは投げサビキに釣れなくても遠投カゴ釣りには食ってきますので夜釣りをされる方にはいち推しです。是非チャレンジしてください。
少し沖めを回遊する中アジ・大アジを狙って遠投しましょう。
また、夏から秋に掛けての潮通しが良い磯や漁港の岸壁に、ソウダガツオ・ワカシ・ショウゴ・サバなど30~40cmの青物が回遊することがありハリスと鈎を2号アップさせるだけで狙うことができます。
磯の生え根や堤防のテトラポットの先から抜き上げることや遠心力と弾力でより遠投するために、投げサビキ兼用の竿は遠投磯竿インナー(中通し)の3~5号・5.2m又は外ガイドの3~5号・5.2mを使用します。
夜釣りがメインですので、ラインの穂先絡みやガイド絡みによる高切れや穂先折れなどのトラブル防止にはインナーがお奨めです。
私が実釣に使っているのは、
インナーガイドロッド
シマノブルズアイ4-520遠投 P SI
ダイワプレッサドライ5-52・F遠投(磯の青物兼用)
ダイワEMBLEM ISO5-52遠投
アウトガイドロッド
シマノブルズアイ4-520遠投 PTS(磯の青物兼用)
ダイワSHIDEN METAL SNIPER 4-53 遠投(磯の青物専用)
ダイワ大島磯遠投4-53遠投・F(磯の青物兼用)
ダイワプロ磯T4-53EB
宇崎日新エアステージISO5-450遠投(ヒラメの泳がせ兼用)
宇崎日新SUPERSQUARE RX ISO HD4-450遠投(アオリイカの泳がせ兼用)
です。

リールは、ナイロン5~6号を150~200m前後巻ける中型スピニング、シマノの6000番かダイワの4000番、PE使用なら2~3号を150~200m巻ける中型スピニング、シマノの5000番かダイワの3500番に、ラインキャパシティの8~9割程度巻くとトラブルが少なく使い勝手が良いので参考にしてください。
私が実釣に使っているのは、
ダイワブラディア3500(PE3-200)
ダイワカルディア4000(PE3-250)
ダイワトーナメントISO5000遠投(PE4-350)[ヒラマサなど磯の青物専用]
シマノバイオマスターC5000(PE3-190)
シマノナスキーC5000(PE3-190)
シマノバイオマスター6000(PE3-300)[ヒラマサなど磯の青物・ショワジギ兼用]
で、メーカースペックラインキャパシティ()内の80~90%を巻いています。
高比重に加工されたサスペンドタイプやシンキングタイプのPEなら、風や波による糸フケを抑えますので、スピニングリールでの遠投カゴ釣りに最適な道糸としてお奨めします。
ウキは、遠投する場合は10~15号負荷のカン付き又は中通し発泡ウキ、40mまでなら8~10号負荷のカン付き又は中通し発泡ウキを使用します。
私が最近使ってるのは、ウメズの遠投カゴボンバーやナイトアバター・釣研レッドシャトル・アマノバージョンパトリオット天使の矢・渚の遠投師遠投LED電気ウキなどの10~15号です。
遠投が効きますし飛行姿勢が安定しているため1.5号のハリスを使っても仕掛けがらみが少なくお奨めです。

オモリはカゴの材質や大きさにより異なりますが、10号負荷のウキにはオモリ負荷ギリギリ10号で試してみて視認できる範囲で調整します。
ウキの負荷表示はメーカーにより異なりますので現地で調整しますが、天秤プラカゴでしたらウキの負荷と同号のオモリを、ステンレスのアミカゴでしたらオモリ負荷より1号か2号軽いオモリを使います。
カゴはテンビンやオモリと一体となったプラカゴ、ステンレス網カゴ(極細目)、カゴ釣り専用ナイロンカゴなどを使用します。
私が考案したカゴ天秤「良竿スペシャル」は投入時の空気抵抗や巻き取り時の水の抵抗が少ないため、飛距離を伸ばせますし釣れた場合の回収も楽です。
アジは棚を釣れ!
ウキ下は、1.5~3ヒロ(カゴまで約2.2~4.5m)を基本にその日その時間の棚を早くつかみ調整すると釣果が上がります。
アジの棚(泳層)は、季節・時間帯・天候・海水温・群れの大きさなどによって異なります。
アジは深い所を回遊しているから底近くを釣れという話を見聞きしますが、それは間違った固定観念です。
水深10mの場所で上から矢引き(75cm)に棚取りしたら入れ食いなんてことがよくありますのでウキ止めの位置を調整しながら効率よく釣りましょう。
棚ボケしないウキ止め
遠投カゴ釣りや投げサビキ釣りではしっかり棚取りするためにウキ止めをガッチリと結ぶことが不可欠です。
ウキ止めはゴム製のものと糸タイプのものがありますが、重い仕掛けの遠投を繰り返すカゴ釣りではウキ止めゴムでは数回投げただけでガイドに当たったゴムがずれて棚ボケしてしまいますのでウキ止め糸を使います。
溝の付いた軸にラインを通して糸の両端を引き絞りながら絞め込むタイプのウキ止め糸は初心者でも簡単に結べます。
また、スプール巻きタイプのものはウキ止め糸の結び方を覚えれば簡単に結べます。
スプール巻きウキ止め糸の結び方
(株)釣研の図解「ウキ止め糸の結び方」
(株)ラインシステムの動画「ウキ止めの作り方」
ウキフカセ釣りの場合はウキが軽いため3~5回巻きで止まりますが、遠投カゴ釣りや投げサビキ釣りでは7回巻きと5回巻きの2連や3回巻きを加えた3連を1ヶ所にまとめてしっかり止めます。
1回の釣行で10~15回ウキ止め糸を動かす私は3連で止めています。
なお、ピンク・イエロー・オレンジ・グリーンなど蛍光色となっていますので、ウキ止め位置を視認するためにラインと対照的な目立つ色を選びましょう。
また、使用するラインの種類や太さ、アウトガイドかインナーガイドかなどによってそれに適合するウキ止め糸が各メーカーから発売されています。
遠投カゴ釣りや投げサビキ釣りでは、ポイントの水深・時間帯・狙う魚によってウキ止め糸を動かすことがよくあります。
絞め込むときは水で濡らしながら両端を少しずつ引いて巻いたコブの中心が膨らむように締め込みます。
棚を替えるためにウキ止め糸を動かすときはバケツに汲んだ海水の中で行ってください。
摩擦熱でラインを傷めるだけでなくPEラインの場合は指先をやけど(火傷)しますのでご注意ください。
近くで食わせろ!
遠投カゴ釣りでの数釣りの重要なポイントのひとつは近くで食わせることです。
100m先でも80m先でも食うなら80mで、80m先でも50m先でも食うなら50mで、50m先でも30m先でも食うなら30mへ投入するようにします。
100m先で食わせるよりも30m先で食わせたほうが巻き取る時間と体力の消耗を減らせ手返しが良くなり効率よく数を伸ばせますし、ハリが上下の固い顎に刺さっていれば問題ないものの、左右の軟らかい口縁に刺さった場合は巻きあげる途中でハリ穴が広がりすっぽ抜けたり口切れによるバラシが増えるからです。
また、近くのポイントにコマセを集中させることで周辺にいるアジを集めることができますので可能な限り近くにポイントを作って効率よく釣りましょう。
アジの棚とポイントのイメージ
漁港防波堤(波止)や沖堤(一文字堤防等)あるいは磯からの陸っぱりで狙うアジは、回遊するポイントの棚(泳層)に仕掛けを投入しなければ釣れません。
ポイントと棚(泳層)は、アジの群れの大小・活性・海水温・潮の濁り・季節・時間・潮汐・天候・海底の起伏・潮通おしなどによって刻々と変化しますので、その日その時間のポイントと棚を見極めることが釣果に直結するといえます。
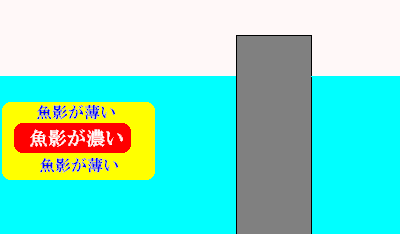
アジのカゴ釣り(カゴアジ)仕掛けは3つのパターン
アジのカゴ釣り仕掛けは3つのパターンがあります。
[パターン1]
市販のサビキには6~8本のサビキバリが付いていますがこれを2本目か3本目のハリスの下で幹糸を切りフロロカーボンハリスを足して全長が80~100cmにします。
サビキは、ハゲ皮・サバ皮・ピンクスキン・白スキン・蛍光グリーンスキンなどでその日その時のアタリサビキをいち早く見つけると釣果がアップします。
刺し餌(付け餌)を付けないこの仕掛けは「天秤サビキ」とか「カゴ釣りサビキ」などと呼ばれています。
夕マズメや朝マズメ前にアジが就餌スイッチが入る直前で、投げサビキにリレーする前に有効な仕掛けです。
[パターン2]
市販のハゲ皮サビキを2本目か3本目のハリスの下で幹糸を切りフロロカーボンハリスを足して全長が80~100cmにします。
刺し餌(付け餌)は、アミエビ・オキアミ・イカタン・パワーイソメを使います。
夕マズメの投げサビキに食わなくなる暗くなってから有効な仕掛けで、投げサビキはコマセと同調させることができませんが、この仕掛けはコマセと同調し漂うような動きと付け餌がアジの食い気を誘います。
投げサビキに食わなくなってからこの仕掛けにリレーすると再び釣れだします。
[パターン3]
30cmオーバーの尺アジやイサキが釣れる磯などで有効な仕掛けです。
ハリはチヌ1~2号・金袖9~10号・アジ9~10号、ハリスはフロロカーボンの2~3号、幹糸はフロロカーボンの3~4号で2本バリで仕掛けの全長は120~150cmにします。
刺し餌(付け餌)は、オキアミ・イカタン・アオイソメ・アカイソメを使い、アオイソメ・アカイソメはチモトが隠れるまで扱き上げタラシは1~3cmです。
25cmまでのサイズならパターン1か2を、30cmオーバーやイサキが釣れる場所ではパターン3を使い分けることをお奨めします。

くわせ餌別仕掛け
オキアミ・赤イソメ・イカタンをくわせ餌にして大アジやイサキなどを狙う時は、フロロカーボンの幹糸ハリス3号70~80cm、フロロカーボンハリス2号に金袖8~10号や金チヌの1~2.5号、アジ鈎8~10号などを結び全長120~150cmの2本バリ仕掛けにします。
また、アミエビ・オキアミ・アオイソメ・パワーイソメ・イカタンをくわせ餌にして中小アジを狙う時は、フロロカーボンの幹糸ハリス2号50~60cm、フロロカーボンハリス0.8~1.5号に金袖6~8号や金チヌの1号、アジ鈎7~8号などを結び全長80~100cmの2本バリ仕掛けにします。
パワーイソメやイカタンをくわせ餌にしたりくわせ餌を付けずに中小アジを狙う場合は、市販のサビキを2~3本に切り、全長が80~100cmになるようフロロカーボン2.5~3号のハリスを足して調節し吹流し状で使用します。
くわせ餌
くわせ餌は、朝夕のマヅメ時や日中は大粒赤アミやM又はLサイズのオキアミが効果的ですが、夜間は青イソメ(タラシは10~20mm)やイカタンに分があります。
なお、バイオワームは廃番となり釣具量販店の店頭から姿を消していますので、パワーイソメなど他の人工餌を使うことになります。
マルキューのプロモーションビデオ「パワーイソメ」~入れ食いも狙える、アジのカゴ釣り~ では開発に携わったフィッシングライターでありマルキューのフィールドテスターでもある林賢治さんが外房のカゴ釣りをレポートしています。
私はまだ何袋かバイオワームを冷凍してますが、このバイオワーム以外では自作のイカタンを使っています。
メーカーさんにはバイオワーム(競技キス3mm)をアジ用として再度販売してほしいし、同サイズの発光する白いバイオワームを開発してほしいと願っています。
イカタンの作り方
冷凍スルメイカのエンペラと足を外して割き皮を剥きます。
作るのは2種類です。
① 長さ1.5cm、幅3~4mmの小さな短冊状に切り食紅(食用色素赤)をまぶして完成です。
② 縦横高さすべて4~5mmの立方体に切り食紅(食用色素赤)をまぶして完成です。
これを小さなタッパー3つに小分けして冷凍保存し、釣りにはその1つを持って行きます。
1杯の冷凍スルメイカで10~15回の釣行(1回の実釣5~6時間)が可能ですのでコスパに優れています。

なお、南房の尺アジには、細めのアカイソメを2.5~3cm又は中太のアオイソメをそのままハリに通してハリスまでこき上げるかイカタンのチョン掛けがお奨めです。
時間帯別のくわせ餌は固定観念を持たずに何種類か持っていって試されることをお勧めします。

釣る人と釣れない人
「糸の縺れを解く人はよく釣れる」という格言がありますが、遠投カゴ釣りの場合釣果の差はどこに原因があるのでしょうか?
[よく釣る人]
① 釣り場に着いてから第1投までの時間が短い。
② コマセを惜しまない。
釣れだすまではポイント作りのために同じ場所に全開で投げコマセを振ってアジを集めている。
③ 釣れだすまでは小まめに棚を探っている。
④ 釣れだすまでは仕掛けや付け餌を替えて当日のアタリ仕掛けやアタリ餌を見付けようとしている。
⑤ 仕掛けの縺れ、ハリスの撚れ、ハリの折れや伸び、刺し餌(付け餌)、ウキ止めの点検を投入前に必ずやっている。
⑥ 夕マズメから朝マズメまでの間に、投げサビキ⇒遠投カゴ釣り⇒投げサビキと活性に応じてリレーしながら効率よく釣っている。
⑦ 投入ポイントがほぼ同じ場所である。
⑧ 投入し棚に届いたとき、少し流したときに必ず竿を煽ってコマセを放出してアジを寄せている。
⑨ 仕掛けを点検し喰わせ餌を付ける⇒カゴに餌を詰める⇒投入する⇒巻き上げる⇒アジを外す⇒クーラーボックスに入れる⇒仕掛けを点検し
喰わせ餌を付けるという一連の動作がリズミカルで無駄がない。
[釣れない人]
① 釣り場に着いてから仕掛け作りなどに手間取り第1投までの時間が長い。
② コマセカゴの目を絞って回収した時にコマセがカゴに残っている。
③ 釣れても釣れなくても棚を変えようとしない。
④ 仕掛けや付け餌を替えようとしない。
⑤ 仕掛けの縺れ、ハリスの撚れ、ハリの折れや伸び、刺し餌(付け餌)、ウキ止めの点検をしない。
⑥ 夕マズメに釣れた投げサビキにこだわり遠投カゴ釣りにリレーしない。
年間30回前後釣行していますが、夕マズメ終了後も投げサビキに釣れ続いた経験は年間1~2回程度です。
⑦ 投入ポイントが毎回違う場所である。
⑧ 投入し棚に届いても、竿を煽ってコマセを放出しないのでアジが寄らない。
⑨ 仕掛けを点検し喰わせ餌を付ける⇒カゴに餌を詰める⇒投入する⇒巻き上げる⇒アジを外す⇒クーラーボックスに入れる⇒仕掛けを点検し
喰わせ餌を付けるという一連の動作にリズムがなく無駄が多い。
よく釣る人は臨機応変
カゴアジ釣りにぴったりな四字熟語は臨機応変、その時その場に応じて「仕掛け」「付け餌」「棚」など適切な手段をとる人、たくさんのバリエーションを持っている人は釣り上手です。
スピニング仕様か、両軸仕様か
大物のマダイやヒラマサなどを狙う釣り人に、ABUの6500番の両軸リール愛用者が増えています。
使用ラインはターゲットにより5~8号のナイロン系を200m程度巻き、竿は両軸専用の5.2~6.2m、3~5号を使います。
両軸仕様のタックルは、習熟することにより遠投できることと、平行巻のためパワーが発揮できることにありますが、バックラッシュなどのライントラブルを起こしやすいため、よほど練習しないと上手く投入できませんので、上級者向と考えてください。
大型スピニングリール(ダイワ5000~5500遠投タイプ)に5~8号のナイロン系を200m、あるいは中・大型スピニング(ダイワ4500~5000遠投タイプ)にPEの4号を250m(ダイワのUVF 磯センサー+Siは250m巻)巻いた仕様でも、大物のマダイやヒラマサなどにも十分対応できますし、ベテランの中にも両軸は使用しないという釣師が多いのも事実です。
私も使い勝手がよい中大型スピニングリールに4-520のインナーガイドやアウトガイドのロッドを多用しています。
両軸仕様の竿にスピニングリールの組合せ、逆にスピニング仕様の竿に両軸リールの組合せでは、リールシートの位置や握る位置が異なるため互換性がありませんので、各自のスタイルやメインターゲットを考えて購入してください。
その他の留意点
仕掛けがカゴやウキに絡まるトラブルの相談を度々受けますが、ハリスをフロロカーボンにして着水寸前にサミングすると絡まる頻度が大幅に減ります。
また、中通しウキからウメズ遠投カゴボンバー・天使の矢AMANOバージョンパトリオット・ピアレ超遠投ウキ・サンナー遠投カゴウキなどのカン付きプロペラウキに替えると絡みトラブルが激減します。
釣り始めは、コマセカゴの目を全開にし、ウキが立ったら竿を大きく煽ってコマセを振り出して1~2分流し、もう一度煽って1~2分流して、あたりが無ければ回収します。
アジの活性が高くポイントに集まって投入たびに入れ掛かるようになったら、コマセカゴの目は半開から3分の1まで絞っても良いでしょう。
サビキを選ぶ時の注意点ですが、
例えば、がまかつのハゲ皮サビキ金袖7号でも、幹糸4号-ハリス2号は活性が高い時の投げサビキに、幹糸3号-ハリス1.5号は通常時の投げサビキに、幹糸2号-ハリス1号はカゴ釣りにと使い分けます。
幹糸2号-ハリス1号を投げサビキに使うと幹糸が切れてしまいますし、その逆に幹糸3号-ハリス1.5号をカゴ釣りに使うと食いが落ちます。
同じメーカー、同じ種類、同じ号数のサビキでも幹糸とハリスの号数(太さ)が異なりますので、釣法に適ったものを選んでください。


遠投カゴ釣りをやってみたいけど難しそうだと踏み出せない釣り人が多いと思いますが、投げサビキより楽に遠投できてますし、夕マズメが終わって暗くなってからは投げサビキに釣れなくても遠投カゴ釣りには食ってきますので夜釣りをされる方にはいち推しです。是非チャレンジしてください。
少し沖めを回遊する中アジ・大アジを狙って遠投しましょう。
また、夏から秋に掛けての潮通しが良い磯や漁港の岸壁に、ソウダガツオ・ワカシ・ショウゴ・サバなど30~40cmの青物が回遊することがありハリスと鈎を2号アップさせるだけで狙うことができます。
磯の生え根や堤防のテトラポットの先から抜き上げることや遠心力と弾力でより遠投するために、投げサビキ兼用の竿は遠投磯竿インナー(中通し)の3~5号・5.2m又は外ガイドの3~5号・5.2mを使用します。
夜釣りがメインですので、ラインの穂先絡みやガイド絡みによる高切れや穂先折れなどのトラブル防止にはインナーがお奨めです。
私が実釣に使っているのは、
インナーガイドロッド
シマノブルズアイ4-520遠投 P SI
ダイワプレッサドライ5-52・F遠投(磯の青物兼用)
ダイワEMBLEM ISO5-52遠投
アウトガイドロッド
シマノブルズアイ4-520遠投 PTS(磯の青物兼用)
ダイワSHIDEN METAL SNIPER 4-53 遠投(磯の青物専用)
ダイワ大島磯遠投4-53遠投・F(磯の青物兼用)
ダイワプロ磯T4-53EB
宇崎日新エアステージISO5-450遠投(ヒラメの泳がせ兼用)
宇崎日新SUPERSQUARE RX ISO HD4-450遠投(アオリイカの泳がせ兼用)
です。

リールは、ナイロン5~6号を150~200m前後巻ける中型スピニング、シマノの6000番かダイワの4000番、PE使用なら2~3号を150~200m巻ける中型スピニング、シマノの5000番かダイワの3500番に、ラインキャパシティの8~9割程度巻くとトラブルが少なく使い勝手が良いので参考にしてください。
私が実釣に使っているのは、
ダイワブラディア3500(PE3-200)
ダイワカルディア4000(PE3-250)
ダイワトーナメントISO5000遠投(PE4-350)[ヒラマサなど磯の青物専用]
シマノバイオマスターC5000(PE3-190)
シマノナスキーC5000(PE3-190)
シマノバイオマスター6000(PE3-300)[ヒラマサなど磯の青物・ショワジギ兼用]
で、メーカースペックラインキャパシティ()内の80~90%を巻いています。
高比重に加工されたサスペンドタイプやシンキングタイプのPEなら、風や波による糸フケを抑えますので、スピニングリールでの遠投カゴ釣りに最適な道糸としてお奨めします。
ウキは、遠投する場合は10~15号負荷のカン付き又は中通し発泡ウキ、40mまでなら8~10号負荷のカン付き又は中通し発泡ウキを使用します。
私が最近使ってるのは、ウメズの遠投カゴボンバーやナイトアバター・釣研レッドシャトル・アマノバージョンパトリオット天使の矢・渚の遠投師遠投LED電気ウキなどの10~15号です。
遠投が効きますし飛行姿勢が安定しているため1.5号のハリスを使っても仕掛けがらみが少なくお奨めです。

オモリはカゴの材質や大きさにより異なりますが、10号負荷のウキにはオモリ負荷ギリギリ10号で試してみて視認できる範囲で調整します。
ウキの負荷表示はメーカーにより異なりますので現地で調整しますが、天秤プラカゴでしたらウキの負荷と同号のオモリを、ステンレスのアミカゴでしたらオモリ負荷より1号か2号軽いオモリを使います。
カゴはテンビンやオモリと一体となったプラカゴ、ステンレス網カゴ(極細目)、カゴ釣り専用ナイロンカゴなどを使用します。
私が考案したカゴ天秤「良竿スペシャル」は投入時の空気抵抗や巻き取り時の水の抵抗が少ないため、飛距離を伸ばせますし釣れた場合の回収も楽です。
アジは棚を釣れ!
ウキ下は、1.5~3ヒロ(カゴまで約2.2~4.5m)を基本にその日その時間の棚を早くつかみ調整すると釣果が上がります。
アジの棚(泳層)は、季節・時間帯・天候・海水温・群れの大きさなどによって異なります。
アジは深い所を回遊しているから底近くを釣れという話を見聞きしますが、それは間違った固定観念です。
水深10mの場所で上から矢引き(75cm)に棚取りしたら入れ食いなんてことがよくありますのでウキ止めの位置を調整しながら効率よく釣りましょう。
棚ボケしないウキ止め
遠投カゴ釣りや投げサビキ釣りではしっかり棚取りするためにウキ止めをガッチリと結ぶことが不可欠です。
ウキ止めはゴム製のものと糸タイプのものがありますが、重い仕掛けの遠投を繰り返すカゴ釣りではウキ止めゴムでは数回投げただけでガイドに当たったゴムがずれて棚ボケしてしまいますのでウキ止め糸を使います。
溝の付いた軸にラインを通して糸の両端を引き絞りながら絞め込むタイプのウキ止め糸は初心者でも簡単に結べます。
また、スプール巻きタイプのものはウキ止め糸の結び方を覚えれば簡単に結べます。
スプール巻きウキ止め糸の結び方
(株)釣研の図解「ウキ止め糸の結び方」
(株)ラインシステムの動画「ウキ止めの作り方」
ウキフカセ釣りの場合はウキが軽いため3~5回巻きで止まりますが、遠投カゴ釣りや投げサビキ釣りでは7回巻きと5回巻きの2連や3回巻きを加えた3連を1ヶ所にまとめてしっかり止めます。
1回の釣行で10~15回ウキ止め糸を動かす私は3連で止めています。
なお、ピンク・イエロー・オレンジ・グリーンなど蛍光色となっていますので、ウキ止め位置を視認するためにラインと対照的な目立つ色を選びましょう。
また、使用するラインの種類や太さ、アウトガイドかインナーガイドかなどによってそれに適合するウキ止め糸が各メーカーから発売されています。
遠投カゴ釣りや投げサビキ釣りでは、ポイントの水深・時間帯・狙う魚によってウキ止め糸を動かすことがよくあります。
絞め込むときは水で濡らしながら両端を少しずつ引いて巻いたコブの中心が膨らむように締め込みます。
棚を替えるためにウキ止め糸を動かすときはバケツに汲んだ海水の中で行ってください。
摩擦熱でラインを傷めるだけでなくPEラインの場合は指先をやけど(火傷)しますのでご注意ください。
近くで食わせろ!
遠投カゴ釣りでの数釣りの重要なポイントのひとつは近くで食わせることです。
100m先でも80m先でも食うなら80mで、80m先でも50m先でも食うなら50mで、50m先でも30m先でも食うなら30mへ投入するようにします。
100m先で食わせるよりも30m先で食わせたほうが巻き取る時間と体力の消耗を減らせ手返しが良くなり効率よく数を伸ばせますし、ハリが上下の固い顎に刺さっていれば問題ないものの、左右の軟らかい口縁に刺さった場合は巻きあげる途中でハリ穴が広がりすっぽ抜けたり口切れによるバラシが増えるからです。
また、近くのポイントにコマセを集中させることで周辺にいるアジを集めることができますので可能な限り近くにポイントを作って効率よく釣りましょう。
アジの棚とポイントのイメージ
漁港防波堤(波止)や沖堤(一文字堤防等)あるいは磯からの陸っぱりで狙うアジは、回遊するポイントの棚(泳層)に仕掛けを投入しなければ釣れません。
ポイントと棚(泳層)は、アジの群れの大小・活性・海水温・潮の濁り・季節・時間・潮汐・天候・海底の起伏・潮通おしなどによって刻々と変化しますので、その日その時間のポイントと棚を見極めることが釣果に直結するといえます。
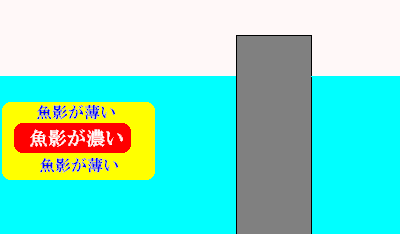
アジのカゴ釣り(カゴアジ)仕掛けは3つのパターン
アジのカゴ釣り仕掛けは3つのパターンがあります。
[パターン1]
市販のサビキには6~8本のサビキバリが付いていますがこれを2本目か3本目のハリスの下で幹糸を切りフロロカーボンハリスを足して全長が80~100cmにします。
サビキは、ハゲ皮・サバ皮・ピンクスキン・白スキン・蛍光グリーンスキンなどでその日その時のアタリサビキをいち早く見つけると釣果がアップします。
刺し餌(付け餌)を付けないこの仕掛けは「天秤サビキ」とか「カゴ釣りサビキ」などと呼ばれています。
夕マズメや朝マズメ前にアジが就餌スイッチが入る直前で、投げサビキにリレーする前に有効な仕掛けです。
[パターン2]
市販のハゲ皮サビキを2本目か3本目のハリスの下で幹糸を切りフロロカーボンハリスを足して全長が80~100cmにします。
刺し餌(付け餌)は、アミエビ・オキアミ・イカタン・パワーイソメを使います。
夕マズメの投げサビキに食わなくなる暗くなってから有効な仕掛けで、投げサビキはコマセと同調させることができませんが、この仕掛けはコマセと同調し漂うような動きと付け餌がアジの食い気を誘います。
投げサビキに食わなくなってからこの仕掛けにリレーすると再び釣れだします。
[パターン3]
30cmオーバーの尺アジやイサキが釣れる磯などで有効な仕掛けです。
ハリはチヌ1~2号・金袖9~10号・アジ9~10号、ハリスはフロロカーボンの2~3号、幹糸はフロロカーボンの3~4号で2本バリで仕掛けの全長は120~150cmにします。
刺し餌(付け餌)は、オキアミ・イカタン・アオイソメ・アカイソメを使い、アオイソメ・アカイソメはチモトが隠れるまで扱き上げタラシは1~3cmです。
25cmまでのサイズならパターン1か2を、30cmオーバーやイサキが釣れる場所ではパターン3を使い分けることをお奨めします。

くわせ餌別仕掛け
オキアミ・赤イソメ・イカタンをくわせ餌にして大アジやイサキなどを狙う時は、フロロカーボンの幹糸ハリス3号70~80cm、フロロカーボンハリス2号に金袖8~10号や金チヌの1~2.5号、アジ鈎8~10号などを結び全長120~150cmの2本バリ仕掛けにします。
また、アミエビ・オキアミ・アオイソメ・パワーイソメ・イカタンをくわせ餌にして中小アジを狙う時は、フロロカーボンの幹糸ハリス2号50~60cm、フロロカーボンハリス0.8~1.5号に金袖6~8号や金チヌの1号、アジ鈎7~8号などを結び全長80~100cmの2本バリ仕掛けにします。
パワーイソメやイカタンをくわせ餌にしたりくわせ餌を付けずに中小アジを狙う場合は、市販のサビキを2~3本に切り、全長が80~100cmになるようフロロカーボン2.5~3号のハリスを足して調節し吹流し状で使用します。
くわせ餌
くわせ餌は、朝夕のマヅメ時や日中は大粒赤アミやM又はLサイズのオキアミが効果的ですが、夜間は青イソメ(タラシは10~20mm)やイカタンに分があります。
なお、バイオワームは廃番となり釣具量販店の店頭から姿を消していますので、パワーイソメなど他の人工餌を使うことになります。
マルキューのプロモーションビデオ「パワーイソメ」~入れ食いも狙える、アジのカゴ釣り~ では開発に携わったフィッシングライターでありマルキューのフィールドテスターでもある林賢治さんが外房のカゴ釣りをレポートしています。
私はまだ何袋かバイオワームを冷凍してますが、このバイオワーム以外では自作のイカタンを使っています。
メーカーさんにはバイオワーム(競技キス3mm)をアジ用として再度販売してほしいし、同サイズの発光する白いバイオワームを開発してほしいと願っています。
イカタンの作り方
冷凍スルメイカのエンペラと足を外して割き皮を剥きます。
作るのは2種類です。
① 長さ1.5cm、幅3~4mmの小さな短冊状に切り食紅(食用色素赤)をまぶして完成です。
② 縦横高さすべて4~5mmの立方体に切り食紅(食用色素赤)をまぶして完成です。
これを小さなタッパー3つに小分けして冷凍保存し、釣りにはその1つを持って行きます。
1杯の冷凍スルメイカで10~15回の釣行(1回の実釣5~6時間)が可能ですのでコスパに優れています。

なお、南房の尺アジには、細めのアカイソメを2.5~3cm又は中太のアオイソメをそのままハリに通してハリスまでこき上げるかイカタンのチョン掛けがお奨めです。
時間帯別のくわせ餌は固定観念を持たずに何種類か持っていって試されることをお勧めします。

釣る人と釣れない人
「糸の縺れを解く人はよく釣れる」という格言がありますが、遠投カゴ釣りの場合釣果の差はどこに原因があるのでしょうか?
[よく釣る人]
① 釣り場に着いてから第1投までの時間が短い。
② コマセを惜しまない。
釣れだすまではポイント作りのために同じ場所に全開で投げコマセを振ってアジを集めている。
③ 釣れだすまでは小まめに棚を探っている。
④ 釣れだすまでは仕掛けや付け餌を替えて当日のアタリ仕掛けやアタリ餌を見付けようとしている。
⑤ 仕掛けの縺れ、ハリスの撚れ、ハリの折れや伸び、刺し餌(付け餌)、ウキ止めの点検を投入前に必ずやっている。
⑥ 夕マズメから朝マズメまでの間に、投げサビキ⇒遠投カゴ釣り⇒投げサビキと活性に応じてリレーしながら効率よく釣っている。
⑦ 投入ポイントがほぼ同じ場所である。
⑧ 投入し棚に届いたとき、少し流したときに必ず竿を煽ってコマセを放出してアジを寄せている。
⑨ 仕掛けを点検し喰わせ餌を付ける⇒カゴに餌を詰める⇒投入する⇒巻き上げる⇒アジを外す⇒クーラーボックスに入れる⇒仕掛けを点検し
喰わせ餌を付けるという一連の動作がリズミカルで無駄がない。
[釣れない人]
① 釣り場に着いてから仕掛け作りなどに手間取り第1投までの時間が長い。
② コマセカゴの目を絞って回収した時にコマセがカゴに残っている。
③ 釣れても釣れなくても棚を変えようとしない。
④ 仕掛けや付け餌を替えようとしない。
⑤ 仕掛けの縺れ、ハリスの撚れ、ハリの折れや伸び、刺し餌(付け餌)、ウキ止めの点検をしない。
⑥ 夕マズメに釣れた投げサビキにこだわり遠投カゴ釣りにリレーしない。
年間30回前後釣行していますが、夕マズメ終了後も投げサビキに釣れ続いた経験は年間1~2回程度です。
⑦ 投入ポイントが毎回違う場所である。
⑧ 投入し棚に届いても、竿を煽ってコマセを放出しないのでアジが寄らない。
⑨ 仕掛けを点検し喰わせ餌を付ける⇒カゴに餌を詰める⇒投入する⇒巻き上げる⇒アジを外す⇒クーラーボックスに入れる⇒仕掛けを点検し
喰わせ餌を付けるという一連の動作にリズムがなく無駄が多い。
よく釣る人は臨機応変
カゴアジ釣りにぴったりな四字熟語は臨機応変、その時その場に応じて「仕掛け」「付け餌」「棚」など適切な手段をとる人、たくさんのバリエーションを持っている人は釣り上手です。
スピニング仕様か、両軸仕様か
大物のマダイやヒラマサなどを狙う釣り人に、ABUの6500番の両軸リール愛用者が増えています。
使用ラインはターゲットにより5~8号のナイロン系を200m程度巻き、竿は両軸専用の5.2~6.2m、3~5号を使います。
両軸仕様のタックルは、習熟することにより遠投できることと、平行巻のためパワーが発揮できることにありますが、バックラッシュなどのライントラブルを起こしやすいため、よほど練習しないと上手く投入できませんので、上級者向と考えてください。
大型スピニングリール(ダイワ5000~5500遠投タイプ)に5~8号のナイロン系を200m、あるいは中・大型スピニング(ダイワ4500~5000遠投タイプ)にPEの4号を250m(ダイワのUVF 磯センサー+Siは250m巻)巻いた仕様でも、大物のマダイやヒラマサなどにも十分対応できますし、ベテランの中にも両軸は使用しないという釣師が多いのも事実です。
私も使い勝手がよい中大型スピニングリールに4-520のインナーガイドやアウトガイドのロッドを多用しています。
両軸仕様の竿にスピニングリールの組合せ、逆にスピニング仕様の竿に両軸リールの組合せでは、リールシートの位置や握る位置が異なるため互換性がありませんので、各自のスタイルやメインターゲットを考えて購入してください。
その他の留意点
仕掛けがカゴやウキに絡まるトラブルの相談を度々受けますが、ハリスをフロロカーボンにして着水寸前にサミングすると絡まる頻度が大幅に減ります。
また、中通しウキからウメズ遠投カゴボンバー・天使の矢AMANOバージョンパトリオット・ピアレ超遠投ウキ・サンナー遠投カゴウキなどのカン付きプロペラウキに替えると絡みトラブルが激減します。
釣り始めは、コマセカゴの目を全開にし、ウキが立ったら竿を大きく煽ってコマセを振り出して1~2分流し、もう一度煽って1~2分流して、あたりが無ければ回収します。
アジの活性が高くポイントに集まって投入たびに入れ掛かるようになったら、コマセカゴの目は半開から3分の1まで絞っても良いでしょう。
サビキを選ぶ時の注意点ですが、
例えば、がまかつのハゲ皮サビキ金袖7号でも、幹糸4号-ハリス2号は活性が高い時の投げサビキに、幹糸3号-ハリス1.5号は通常時の投げサビキに、幹糸2号-ハリス1号はカゴ釣りにと使い分けます。
幹糸2号-ハリス1号を投げサビキに使うと幹糸が切れてしまいますし、その逆に幹糸3号-ハリス1.5号をカゴ釣りに使うと食いが落ちます。
同じメーカー、同じ種類、同じ号数のサビキでも幹糸とハリスの号数(太さ)が異なりますので、釣法に適ったものを選んでください。






















私は普段、PE2.5号に3号の6.3mの竿でカゴ釣りをしております。
質問なのですが、PE直結で使用されているようですが、アジでもクッションゴムは不使用で大丈夫なのでしょうか?
また、プラカゴ・ステンレスカゴ・網カゴなど、いろんなカゴの種類がありますが、カゴの使い分けなどはされますか?
よろしければ教えて頂けますと嬉しいです。
よろしくお願いします。
長期間留守にしていたので返信が遅くなりました。
ごめんなさい。
僕はほとんどプラかごです。
ただし、極端な食い渋りの時は網カゴで、パイプ天秤でフカセ気味にしてハリスを1.5メートルと長めにしています。
アミエビも倍は消費しますのでお勧めできないです。(笑)