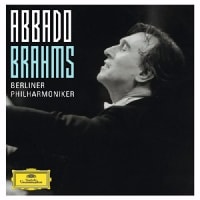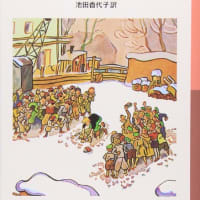はー、わかりきってはいたことですけど、オリンピックまで四年あるっていうことは、プログラムを×4(ショートとフリーあるから×8??)用意して、シーズンごとにグランプリシリーズ×2戦、ファイナル、全日本、四大陸、世界選手権と、ある程度書いていかなくちゃいけないわけですけど……自分的に一番盛り上がらなくちゃいけないオリンピックで、実は盛り下がるんじゃないかなーっていうのがあったりして(^^;)
いえ、一度どっかにその演技に関して何か書いてしまうと、今度は少し別の切り口によって書かなきゃいけないっていうのがあって――そういう意味でキャシーのブラックスワンは特に失敗しちゃった気がします

あーいや、実は最初書いたの読むと、キャシーのプログラムは「レ・シルフィード」っていうことになってて、でもレ・シルフィードってショピ二アーナというか、ようするに全曲ショパンの曲じゃないですか。だったらそれ、ようするにショパン・メドレーってことでしょ☆っていうことになるし、それでキャシーが蘭や愛榮に勝つって難しいかなと思ったりして……あ、ショパン・メドレーはようするに、曲の選び方次第でかなりいいプログラムになると思うんですよ(^^;)
でも「レ・シルフィード」って、そんなに力強いような曲じゃない気がするから……とか思って、蘭がフリーで白鳥滑ってるので、ブラックスワンはどうだろう――って思ったというか。まあ、そんなこと言ったら、いかにも白鳥滑りそうな愛榮がブラックスワンっていうのもアリだったと思うんですけど、でもそれだとなんか「いかにも」な展開で面白くないですしねえww
まあ、なんにしても今回の一番の言い訳事項は、トリプルアクセル&三回転-三回転組と、三回転-三回転&ダブルアクセル組でこの点差っておかしいんじゃねえの??という。。。
点数の出方については、男子含め、かなりおかしいとわたし自身思ってて(汗)、今読み返してて思うのは、トリプルアクセル&三回転-三回転組については、80点を越えてて実は全然おかしくないってことです(^^;)
あー、これ書いてる時、メドたんがブレイク(?)するちょい前くらいだったんですよ。なので、女子の点数は出ても76~78点くらいまでじゃないと変かな……という、変な先入観がわたしにありまして。小説だからといってあんまり馬鹿みたいな高得点をつけちゃいけないなって多少思ってたのもあって、蘭の得点はなるべく抑え目にと思ってました。
でもコッペリアの時は、最後のほう80点越えてもいいなと思って、そう書き直そうとしたんですけど、その時なんか疲れてて、「書き直すのめんどくさいから、もうこのまま
 しちゃえ!」とか思って直さなかったのです(^^;)
しちゃえ!」とか思って直さなかったのです(^^;)でもその後、メドたんの登場(というか、ジュニア時代から注目されてたとは思うんですけど
 )で、トリプルアクセル入れてなくてもあれだけの高得点が出る、&後半で3フリップ-3トウループを跳ぶことで、あれだけの得点が出る……というのを見て、三回転-三回転&ダブルアクセル組でも、十分そのくらいのラインを狙うことが可能であることがわかり。。。
)で、トリプルアクセル入れてなくてもあれだけの高得点が出る、&後半で3フリップ-3トウループを跳ぶことで、あれだけの得点が出る……というのを見て、三回転-三回転&ダブルアクセル組でも、十分そのくらいのラインを狙うことが可能であることがわかり。。。まあ、話の展開としては正直アレなんですけど(ドレ?
 )、結局そうしたこと含めて直すところがたくさんあるので、試合内容と点数に関して直したい場合は、そこだけ訂正すればいいので――この件についても棚上げしておいて、いつか直す機会があったら蘭と愛榮あたりは80点越しても全然いいんじゃないかなって思いました(^^;)
)、結局そうしたこと含めて直すところがたくさんあるので、試合内容と点数に関して直したい場合は、そこだけ訂正すればいいので――この件についても棚上げしておいて、いつか直す機会があったら蘭と愛榮あたりは80点越しても全然いいんじゃないかなって思いました(^^;)あと、これも面倒くさいので、これで基礎点の合計が△□点で、GOEでこのくらい点数がついて……とか、あんまし考えてなかったんですけど、書き進めるに従って、結局のところひとりひとりそのあたりを明確にしておいたほうが統一感を持って点数をつけるためには絶対に必須だということがわかった次第です(今ごろww
 )
)ふう~
 まあ、なんにしてもそんなこんな(?)で、とにかく一通り連載しておいて、直すのはあとあと――なんて言って、毎回わたしどの小説も同じこと言って直した試しが一度もありません(^^;)
まあ、なんにしてもそんなこんな(?)で、とにかく一通り連載しておいて、直すのはあとあと――なんて言って、毎回わたしどの小説も同じこと言って直した試しが一度もありません(^^;)なんでかっていうと、直そうとか言う前に、次に書きたいことが出てくるので、そっち書いてるうちに、その小説書いてる時にも「あとで直せば……」とか言いつつ連載していって、あとから色々間違いとかわかっても直した試しなんていっぺんもないんですよね

ええと、わたしこの小説(六花のⅠ含む)書く前に、ちょっと長い小説(六花ほどじゃないけど・笑)書いてて、これ終ったら次はそれをやろうと思ってます。あと、そんなに書きたいわけじゃないんですけど(笑)、「ゾンビ帝国興亡史」っていう話を時間ある時に書くかもなーとか思ってて

まあ、そんなことを今に至るまで繰り返してきてるもので、直すとしても間隔が相当あくかと思います。。。
なんにしても、あとは女子のフリーですね!そこさえ終われば、あとのことはある程度早いので(たぶん)、もうちょっとと思ってがんばろうかにゃ


それではまた~!!

黒鳥ですぐ思い浮かぶのがやっぱりリレハンメルのこの演技。この時、バイウル若干16歳!!

ソトニコワちゃんの、黒鳥の魂を感じるブラックスワン♪(^^)
翼の表現のところが、もうほんとに最高ですよね

ちょっと番外編(?)かもしれませんけども、高橋選手の伝説のプログラムのひとつ。懐かしいですね♪(^^)
わたし、ナタリー・ポートマンのブラックスワン大好きなんですけど、でもこの黒鳥の聖飢魔Ⅱ的メイクは……ジークフリート王子もビビること請け合いって思うの、わたしだけじゃないですよね?(^^;)
ダイヤモンド・エッジ<第二部>-【54】-
最終グループ、第五滑走者はリュドミラ・ペトロワである。
彼女は今、ある悩みを抱えていた。もちろん、今回のオリンピックの勝敗を左右するほど深刻な悩みではないにしても――パヴロワコーチの自分に対する贔屓からそれははじまったことなので、コーチ次第でどうにかなったと思うと、リュドミラとしてはやりきれない気持ちで一杯だった。
もちろん、そのことを一度リュドミラはラリサに相談したことがある。マリアとサーシャとリュドミラとは、昔は仲良し三人組だったものの、サーシャがリュドミラよりもマリアよりも頭一個分才能が抜きん出ていた。そこで、マリアとリュドミラは彼女とは少し距離を置く形で仲良くなり――彼女が恋人とのつきあいに溺れてスケートから疎遠になってからもその状態は続いた。
母親がヤクの売人という噂のあるボーイフレンドとの交際を禁じたのは、リュドミラの目にはあまりにも当然のことに思えた。リュドミラの母が聞いた話によれば、実際に少し薬にも手を出していたようだとのことだった。だから、サーシャがスケートクラブに戻ってきたら仲良くしてあげるのよ、と。
リュドミラにしても最初はそのつもりだったし、マリアともそう話していた。昔みたいに三人で仲良くなれるといいね、とそんなふうに……けれど実際は、今度はリュドミラがひとり孤立して、マリアとサーシャが昔の結びつきを復活させるということになったのだ。
『オリンピックまでは我慢することね。オリンピックが終われば、また何かが変わってくるでしょうし……言っておくけどリューダ、トップというのは常に孤独なものなのよ。マリアやサーシャがもしあなたにとって本当の友達なら、あなたがオリンピックでメダルを取ってもやっかんだりせず、祝福してくれるでしょうね。でもわたしの時はそうじゃなかったわ。最初の金メダルを取るまでの間に、色んなことがあったもの。でもあなたにはコーチであるわたしがいるし、エリーナもいるわ。それで十分ではなくて?』
(そうだろうか)と、リュドミラは疑問に感じる。もし本当にリュドミラが何に代えてもオリンピックのメダルが欲しいというのなら、それもいいのかもしれない。けれど、もしその時にずっと親友だと思ってきたマリアの祝福がないなら、仮に金メダルを取ったとしても、それはそれほどまでに価値があると言えるのだろうか?……
もちろん、スケートクラブのみんなは基本的に仲がいいため、練習の時に親しく話せる友達はリュドミラにとって他にもいる。けれど、マリアが自分に当てつけるようにサーシャとふたりで仲良くしているのを見るたび、リュドミラの胸の奥はチクリと痛んだ。
選手村では、マリアとサーシャがふたりで部屋を取り、リュドミラは中国の王花琳と同室ということになった。「ここ、空いてる?」と聞かれて、まさか「もう他に人がいる」と嘘をつくわけにもいかない。もっとも王花琳のことをリュドミラは嫌いではない。彼女はかなり性格のはっきりした女性のようで、よくわからないことはなんでもずけずけリュドミラに聞いてきた。中国はオリンピックの出場枠が一枠ということで、「自分にすべて懸かっているかと思うと緊張するわ」と弱音を吐いたりと、意外に可愛らしい一面もあった。
とはいえ、やはり事はオリンピックだ。リュドミラとしては気心の知れたマリアと同室であることが理想だったし、緊張感から神経がナーバスになっていたせいもあり、何故今こんなことになっているのだろうと、夜に涙で枕を濡らしたものである。
試合会場入りするバスの中でも、リュドミラとマリアの間にはどこかぎくしゃくした空気が流れるのみだった。昔、小さな頃に(いつかふたりでオリンピックに行こうね!)と約束したのを、リュドミラはもちろん覚えている。その夢がせっかく叶ったのに、こんなひどいことってあるだろうか?
会場入りしたあとも、リュドミラとマリアとは、控え室で隣りあって柔軟体操しながらも、心は離れていた。もちろん、いくら友達とはいえライバルでもあるわけだから、そうおかしなこともなかったかもしれない。けれど、リュドミラとしてはやはり、この心が通じ合っていない状態というのはストレスだし、苦痛でもあった。一応顔を合わせれば挨拶くらいはするし、「調子のほうはどう?」とお互い聞いたりもする。けれど、ただそれだけだった。
それでもリュドミラは一度会場入りを果たし、六分間練習の済んだあとは、完全に自分と自分の演技のことだけに集中した。マリアは二番滑走だったので、すぐに彼女の姿もなくなり、リュドミラは他に控え室に残っている選手である灰島蘭のことを見た。赤いイヤホンを耳に嵌め、iPodで曲を選択する仕種をしたあとは、ピラティスマットの上で開脚し、柔軟体操の続きに取り掛かっている。
『ねえ、リューダ。あなた、灰島蘭のことをどう思う?』
『素晴らしい選手だと思います。選手としてだけじゃなく、人間的にも話しやすくて魅力があるっていうか……』
『そう。でもあの子、ちょっと可哀想じゃない?生い立ちとか色々、そういうことだけど。四回転は確かに凄いと思うけど、わたしが思うにはただそれだけね。あくまでこれはわたしが個人的に思うことだけど、あの子はたぶん四回転に固執するあまり、メダルは取れずに終わると思うのよ。それに、五輪シーズンには向かないショートを諦めずに滑るつもりのようだから、そっちは得点が伸び悩むだろうし……なんといっても事はオリンピックですもの。これでフリーで崩れれば灰島蘭は金メダルどころか銅メダルさえあやしいかもしれないわ。わたし、オリンピックでは金愛榮とあなたとキャシーが表彰台に乗るのではないかと思ってるの。もちろん、マリアが頑張るか他の選手が崩れるかしてくれてあの子も銅メダルくらい手に出来るといいのだけれど……』
(パヴロワコーチの言うことには言い逆らわないほうがいい)――というのは、今ではスケートクラブ内に暗黙の了解として浸透していることである。だからこの時もリュドミラは黙ったままでいた。けれど、本当の彼女の本音はこうだった。
(もし金メダルを取るとしたら、絶対この子だ。わたしにはわかる……この子か金愛榮。あるいはキャシー・アーヴィングが取る可能性がとても高い。そしてわたしは自分が金メダルに輝けないなら、蘭に金メダルを取って欲しいと思ってる)
そう思った瞬間、リュドミラは自分の心の奥で何か変化が起きたのを感じた。最初、すぐにはそれが何かわからなかった。けれど、フォームローラーを使って体をほぐしている時にハッとあることに気づく。
(そっか。わかったわ……こういう形の友情もあるのよ。お互いをライバルとして認め合い、高めあうのと同時に、それ以外では仲良くしたりということが、わたしは蘭となら出来ると思う。何か今、わかった気がする。どうしてわたしは蘭の存在を知った時から「この子にだけは負けたくない」と直感的に感じたのか、そのことが……)
それがどのスポーツ競技でも、トップを目指すアスリートというのは孤独な戦いに明け暮れているものだ。けれどきっと自分は蘭とならずっと戦友のような関係でいられるだろう――そう思うと何か、リュドミラは嬉しかった。もちろん、蘭のほうでは同じスケート選手として一番意識しているのは金愛榮らしいので、リュドミラに対してそこまで強い対抗意識はないかもしれない。
(でもわたし、蘭のそんなところも好きなのよね)
リュドミラが思わずくすりと微笑んでいると、誰かが彼女の肩に手を置いた。エリーナが時間がやって来たことを知らせにきたのだ。
(さあ、勝負の時がやって来たわ!!)
エリーナと並んで廊下を歩いていくと、リンクサイドに出る入口のところでパヴロワコーチと合流する。その隣にはマリアの姿があり、彼女は泣いていた。けれどそれは、演技を失敗した悔し涙ではなく、嬉し涙に近い何かだということがわかり、リュドミラはほっとした。
「マリアのことは気にすることないわ。とてもいい演技だったの。オリンピックのプレッシャーに押し潰されず、あの子は本当によくやったわ」
それから、今度はマリアにエリーナがついていき、リュドミラはラリサとともにリンクサイドへ近づいていった。金愛榮の演技が終わった途端、きっと耳をつんざくような歓声が聴こえることだろう。前滑走者の演技の良し悪しについて知りたくないリュドミラは、iPodのボリュームを上げると、心拍数が下がらぬよう小刻みに体を動かし続ける。
今季のシーズン後半になってから、リュドミラのショートプログラムにはトリプルアクセルが入っていない。もちろん、ショートではトリプルアクセルではなくダブルアクセルで行きたいとラリサに言うのは、リュドミラにしてもとても勇気のいることだった。何分、今ショートプログラムにトリプルアクセルを組み込んでくる選手は三人もいるからだ。灰島蘭と金愛榮とエリカ・バーミンガム……けれど、オリンピックでトリプルアクセルが成功するかどうかと考えすぎて萎縮するより、ダブルアクセルで手堅く攻めてフリープログラムで挽回する――リュドミラはどうしてもそうした形にしたかった。
きっとすぐ、「じゃああんたは金メダルを取る気がないっていうことのね!?」とでも怒鳴られ、軽く一時間ばかりも説教を食らうことになるだろうと思ったのに、ラリサは案外あっさり「それでもいいわよ」と言っていた。そのかわり、「別のところで確実に得点を得られるように難易度を上げるけど、いいわね」と。
結局のところ、この方法でリュドミラはロシア選手権でも欧州選手権でも金メダルを手にしていた。そしてはっきり気づいたのだ。ずっとショートプログラムのトリプルアクセルがネックになっていて、そこに大きなストレスを感じるあまり、萎縮した演技しか出来なかったのだと……。
もちろん、欧州選手権にも世界の強豪が集まるとはいえ、そこには灰島蘭の姿も金愛榮の姿もキャシー・アーヴィングの姿もない。けれど、精神をこうしてある種の縛りから解き放つことで――より伸び伸びとプログラム全体をまとめられるという自信を持てることのほうが、今のリュドミラには重要だったのである。
リュドミラがショートの曲である『ミッションインポッシブル』を大音量で聞きながら、振付の確認とジャンプの成功イメージを高めていた時、ぽん、と肩に手を置かれ、リュドミラは金愛榮の演技が終わったことを知った。
イヤホンを取ると、思っていたとおり物凄い大歓声が耳に入ってくる。(きっと、金愛榮は会心の演技をしたんだろうな)と思うものの、そのことに関して心にあまり動揺はない。同じ東洋人だというのに、不思議とリュドミラが強い関心を抱きライバルとも思うのは灰島蘭であって、金愛榮に対して思うことはあまりないのだった。
金愛榮の得点が電光掲示板に表示された時も見なかったし、リュドミラは淡々とジャンプを跳び、もう一度氷にエッジをよく馴染ませるように、氷の感触をしっかり捉えるようにして滑った。それでも観客席の歓声の大きさから、(今一位なのはおそらく、蘭か金愛榮のどちらかだろう)と、そう察しをつける。
(でも、わたしが勝負を懸けるのはフリースケーティングだ。ショートプログラムでは、出来る限り点差を詰める形で蘭や金愛榮の真下に着けておきたい)
「あなたなら、絶対にやれるわ。自分に自信を持って思いきっていきなさい。いいわね!?」
「……はい!!」
リュドミラには自信があった。トリプルアクセルではなくダブルアクセルなら確実に決められるし、冒頭の三回転ルッツ-三回転トゥループならば、リュドミラの場合トリプルアクセルよりもずっと成功率が高い。
リュドミラは十秒前くらいにスターティングポジションに着くと、一度大きく息を吸ってから、すうとゆっくり吐きだす。
最初のポーズは、両手を横にして自分の顔や姿を隠すようにするというものだった。ここでリュドミラが演じるのはCBP(ロシア対外情報庁)の諜報員であり、自分の正体が敵にバレるということはすなわち死を意味する……といった意味がある。
衣装は一部革の素材が使われた、エメラルドグリーンを基調としたもので、胸のあたりが編み上げブーツのように革紐で結ばれている。ラリサによれば緑というのは<不信や裏切り>を表わしているということだったが、リュドミラはそうしたことをあまり深く考えなかった。衣装のほうもそれほど気に入っているというわけではなかったものの、とりあえず動きやすいし、たまにはこうした変わった衣装も悪くはないと思っていた。
曲がはじまり、誰もが聞いたことのある例の主題が流れると、ノリのいいジャズダンスを踊るような振付で、リュドミラは3ルッツ-3トゥループへ向かう。最初にトリプルアクセルを跳び、次にこの3ルッツ-3トゥループを跳ぶということに挑戦していると、最初にこのコンビネーションジャンプが来て、最後に後半でダブルアクセルを跳べは良いという演技構成は、リュドミラにとって格段にプレッシャーの減ることだった。それはもしかしたら蘭が、四回転の練習をはじめるようになってから、トリプルアクセルをより確実に決められるようになったこととも通じる何かがあるかもしれない。
そして勢いとスピード感のあるスケーティングによってトップスピードに乗ると、リュドミラは最初のルッツだけでなく、質の高いセカンドジャンプによって三回転-三回転を完璧に決めてみせる。着氷後はイーグルの姿勢から男を誘惑するような演技をしてみせ、バタフライからのフライングキャメルスピン。次にウィンドミルからのレイバックスピンを美しいビールマン姿勢によって回りきる。
バヴロワコーチの創作したオリジナルのシナリオによると、リュドミラが演じているのはロシアからアメリカのCIAへ送りこまれた女スパイといったところらしい。だが、いかにもよくある話という気はするが、リュドミラは職場で知り合った男性と恋愛関係になってしまう。恋人と祖国への思いの間でリュドミラは苦しむが、アメリカの国家を揺るがすある情報を得ると、ロシアへ帰国することを心に決める。婚約者はリュドミラの正体を知り憤激するが、リュドミラはそんな彼のことを愛によって殺す……というのが、リュドミラの演じているプログラムの外郭となるストーリーらしい。だが、このこともリュドミラは実はあまり深く考えていない。
続くステップシークエンスでも、スピードに乗ったままツイズル・カウンター・ブラケット、ツイズル・ロッカー・ブラケット……といったように、いわゆる三連続のディフィカルトターンをレベル4が取れるよう滑りながら、右方向・左方向の両方でリュドミラは演じてみせる。蘭や金愛榮、キャシー・アーヴィングなどもそうだが、彼女たちは見た目以上に遥かに難しいステップやターンを氷上に刻む間も、スピードが落ちない。また、ジャンプへ向かう時に加速する以外ではほとんどステップが入っているというのも、リュドミラを含めた女子トップ選手の共通項であり、これはエッジの使い方と重心移動によってスピードを出しているのである。
スピードとパワー。特にリュドミラの『ミッションインポッシブル』は、その一言に尽きた。三分間ほとんど休むところのないこのショートプログラムと、フリーでのエイトトリプルをこなすために――リュドミラは心肺機能を高めるためのキツいトレーニングを長く続けている。
ステップシークエンスで、恋人を含めた敵の組織を割合あっさり始末すると、最後に銃に見立てた両手にフッと息を吹きかけ、リュドミラのミッションは終了となる。続く後半ジャンプのトリプルフリップとダブルアクセルを、ともに難しいステップから両手を上げて着氷してみせ、最後は足替えコンビネーションスピンにより一気に演技を締め括る。
耳なじみのある有名な映画の主題曲ということで、リュドミラの演技に観客は熱狂した。けれど、その盛り上がりをリュドミラ自身は至極冷静に受けとめつつ、はじまりと同じポーズをとくと、まずはジャッジに向け丁寧にお辞儀した。それから観客席の大歓声に応えるように両手を広げ、胸元に手を当てて頭を下げる。
トリプルアクセルを入れてのノーミスの演技というのであれば、今ごろリュドミラもガッツポーズが出るくらい狂喜していたかもしれない。けれど、ショートでトップに立つであろう選手と点差を五点以内にするという、最初からそのように計算されたプログラムであるため、リュドミラとしてもやはり少し複雑だった。
「よくやったわね。これで間違いなく七十点は越えてくるはずだから……金愛榮や灰島蘭とは大きくても五点も差はつかないはずよ」
「だといいんですけど……」
リュドミラはブレードにエッジカバーを嵌めると、コーチの手に一度預けておいた大きなペンギンのぬいぐるみを受け取る。首のところにロシア語で「Людмила」とリュドミラの名前の刻まれた銀色のネックレスがかかっている。
リュドミラはペンギンのぬいぐるみを抱っこしながら、片手でチュッとキスをカメラの向こうに送る。「Я тебя люблю!ヤ チェビャー リュブリュー!」(愛してる)との言葉とともに。それから少し唇を尖らせると、ペンギンの可愛いほっぺにもキスした。
――と、ここで得点が出る。
技術点=41.14、演技構成点=35.42、合計点=76.56ポイント。
ラリサから七十点台には間違いなく乗るだろうと言われていたものの、それでも実際に得点が出てみるまではリュドミラも不安だった。そして次に画面が切り替わり、<Rank3>と表示されたのを見て少しほっとする。というのも、この時点で一位である金愛榮の得点が79.11ポイント、第二位の灰島蘭が78.99と、フリーで逆転が難しいというほど離されてはいなかったからだ。
「ああ、よかったあ……」
「そうね。でもリューダ、あんたがもしトリプルアクセルを成功さぜていたら――きっと一位だったに違いなかったと思うわよ」
もちろん、リュドミラにはラリサが何を言いたいかはわかっている。<本当の女王らしい勝ち方>ということについて、ラリサには彼女独自の美学というものがあるらしいからだ。けれど、ダブルアクセルにしたからこそ、リュドミラは変に神経質に緊張することなく伸び伸び滑ることが出来たのだと、自分でわかっている。
「コーチ、ありがとうございます。本当に……」
「あら、そんなことを言うのはまだ早いわよ、リューダ。なんといってもまだフリースケーティングが残ってるんですからね。感謝するならフリーで最高の演技をしてみせてわたしに恩返ししてちょうだい」
この時、ラリサが満面笑顔になって微笑んだため、リュドミラは一瞬ドキリとした。彼女はもうと言うべきかまだというべきか、とにかく今四十二歳くらいの年齢なはずである。けれど、どう見ても三十台前半くらいにしか見えないし、現役時代に誇っていた美貌を今も維持しているようなところがある。そのせいで大抵の人は彼女に幻惑されるあまりというべきか、ラリサの気まぐれな性格を許容範囲内のものとして受け止めてしまうのだ。
リュドミラはマリア同様、過去にはコーチを変えようかと思ったこともある。けれど今は、美しいパヴロワコーチのギリシャ彫刻のような横顔を見つめて、(この人にずっとついてきて良かった……)と、胸に感動にも近い思いが去来するばかりだった。







ザグレブオリンピック、女子シングル・ショートプログラム最終滑走者はキャシー・アーヴィングだった。
ドバイオリンピックで銀メダルになってから四年……色々なことがあったとキャシーは思う。
言うまでもなく、フィギュアスケートの女子シングルのトップ争いは競争が激しい。ドバイオリンピック後、一年休養すると言っていた如月葵がすぐに復帰し、キャシーとしても大きな大会で金メダルを取ることは難しかった。けれど、灰島蘭がシーズンを通して不調であり、やがて葵が妊娠と同時に引退してからは、道が開けてきたかのようだった。
グランプリシリーズで戦った時の感触から、世界選手権でも金メダルは難しいだろうと思ったものの、初めて世界女王に輝くことが出来た時には嬉しかった。ドバイオリンピックで銀メダルを取った時と同じ喜びと達成感があった。
そしてこの時、キャシーは心に決めた。あとタイトルとして欲しいのはグランプリファイナルのタイトルとオリンピックの金メダルだ、と。正直なところを言って、もし圭が結婚して欲しいとでも言ってくれるのなら、キャシーはすぐにもスケート競技から身を引いていたことだろう。けれど、そんなことはありえないとわかっているがゆえに、彼と同じく三年後にあるザグレブオリンピックを見据えて、ただひたすらトレーニングに励むという日々を過ごした。
それでも、圭が練習の合間に時々会ってくれるということが、キャシーにとって何よりの心の支えだった。プログラムや衣装、振付、トレーニングの計画……そうしたことについては、キャシーは大体のことをコーチであるヒラリー・ローレンに任せている。常に彼女が主導権を握っていくつかの選択肢をキャシーに与え、キャシーのほうではその中のひとつを選びながらも自分のアイディアも時折混ぜていく――といった二人三脚によって、キャシーとローレンの関係は成り立っていた。
実際、ローレンはキャシーのことを小さい時から知っているだけでなく、彼女の良き理解者でもあった。スケートの才能ということに関していえば、すば抜けた天性のセンスを持っていたとはいえ、キャシーは基本的に練習嫌いだった。いつもパート練習ばかりして楽なほうへ楽なほうへと流れていきたがるようなところがあるのだが、それでも「今日は通してちょうだい!!」と言ってみると、完璧に滑りこなしてしまうのだから、舌を巻かざるをえない。ローレンにしても「いかに短い時間で質のいい練習をキャシーにさせるか」については、随分骨を折ったものである。
また、精神面においては圭との関係が何よりも重要だとわかっていた。そこでキャシーには秘密で、圭とも時々連絡を取り合い、「最低でもオリンピックが終わるまでは別れないっていうことよね?それ、守ってもらわなくちゃ絶対困るわ!」などと、時に激しく言い合ったこともあった。
そしてキャシー自身が「圭がオリンピックで金メダルを取って、わたしも金メダルを取れたとしたら、わたしたちの関係も何か変わるかもしれないと思うの」と言っていたように――ローレンもその可能性はあるだろうと考えていた。交際している恋人同士がともに同じスケート競技のオリンピックで金メダルを取る……それはとてもありえそうもないことだが、可能性が低ければこそ、そこに何か運命のようなものを感じて、圭がキャシーにプロポーズしてくれるか、あるいは将来の約束を明確にしてくれる――という、何かそうしたことがキャシーの身に起きて欲しいとは、ローレンにしても思っていたのである。
けれど、今のところは圭に結婚の意志はないのだ。なんでも、キャシーの話によれば、再び恋人同士のようにつきあうということの前提として、「将来のことや結婚といったことはないと思ってくれ」ということが暗黙の了解事項としてあったという。その上、これも言葉としてはっきり聞いたわけではないものの――「彼、葵のことがまだ好きなのよ」ということだった。
「ええっ!?でも彼女はもう、お兄さんのリョウの奥さんでしょ?」
スケーターラウンジで一緒に休憩していた時に、ローレンはびっくりしてサンドイッチを食べる手が止まった。
「まあ、確かにそうだけど……でも誰かのことを本質的に好きってなったら、そういうものじゃない?DNAがまったく同じ双子がいて、ひとりの女を取りあうだなんて、なんだかドラマみたいよね。だけど、葵ってわたしの目から見てあんまり恋敵って感じじゃないのよ。むしろ圭と同じ顔とはいえ、あんな超のつく変人と結婚してもいいだなんて、尊敬に値する聖女って感じよ。わたし、彼女とも圭の話はよくするけど、まあ脈はないわね。それが日本人の古風な考え方によるものなのかどうかはわからないけど、葵にとって自分の夫はリョウひとりだけって感じみたい。流産した時にリョウは葵が傷つくようなことを言って、暫く冷却期間があったみたいなんだけど、その間圭は普通の女なら間違いなくよろめくっていうくらい彼女のことを優しく慰めたらしいのよ。でも葵の気はやっぱり変わらなかったみたい。で、むしろそれであればこそ――圭にとっても彼女は聖女か何かみたいなものなんじゃない?」
「そんなことがあったなんてねえ。でもキャシー、やっぱりわたしにはあなたのことも不思議よ。わたしがキャシーだったら、そんな状態の昔の男なんかにはさっさと見切りをつけて諦めるわね。それで、次の恋のステップに進むの。キャシー、あなたならおつきあいしたがる男の子なんか、わんさといるでしょうに、どうして圭のことにそんなに拘るの?」
「それはたぶん、わたしが古風な女だからじゃない?」
如月葵から作り方を教えてもらったというオニギリを食べながら、キャシーは誰もいないリンクを見渡し、自嘲するように笑った。
「十代の頃って、わたしのまわりでもみんな、あっちとつきあったりこっちと別れたりって、何かそんな感じだった。だからね、わたしとしても一応わかるのよ。ひとりの人が自分の世界のすべてだなんて、もっと他に広い世界があるかもしれないとか、何かそんなことはね。だけどわたし……これから他の誰とつきあっても、いつも心の中で圭と比べることになると思うの。圭はもっとああだったとかこうだったとか。こういうのも、結構不幸よね。人生の一番最初にこれ以上もないくらいいい男とつきあうことになるだなんて、まずないわよ。だから、圭の気持ちもわかる。わたしがもし男だったら、そりゃひとりの女だけじゃ満足なんてとても出来ないもの。そう考えたらね、まあ最終的に圭がわたしの元に戻ってくれたらいいわけ。それで、圭が遊びで他の女とつきあう間……わたしのほうに誰もいないっていうか、そんなのも魅力のないつまんない女みたいで嫌だから、そういう意味でわたしも誰か他の男とつきあうかもしれないわ。でもただそれだけよ」
「圭って、遊びで女性とつきあったりするタイプではないんじゃない?それに彼、トップスケーターとして名前も顔も知られてるわけだから、変な女性にひっかかったりして訴訟沙汰になったりしたら大変じゃない。わたしが思うに……誰か、如月葵を忘れさせてくれるような、あるいはどことなく彼女に似たタイプのお嬢さんとつきあって結婚したりしたらどうするつもり?」
「わたしだって、伊達に長く圭とつきあってきたわけじゃないのよ」
そう言って、キャシーは屋敷の使用人に作らせているお弁当の果物を摘んだ。
「断言してもいいわ。圭って、普通の女で満足できるタイプじゃないの。そりゃ誰にでも優しいし、相手に一時的であれそうした慰めが必要だと思ったら寝るかもしれないわ。今わたしともそうしてるみたいにね。だけど、それだけよ。葵のことを好きだって思ってた時くらいの何がしかでもない限りは、結婚にまでは踏みきらないんじゃないかしらね」
「だけどキャシー、あなたは本当にそれでいいの?」
「いいのよ。圭みたいないい男を一度知っちゃうと、他の男がみんなゴミみたいに思える。ようするにね、これは長期戦なの。圭が一度結婚して子供が出来たって関係ないわ。その相手とだって、もしかしたら別れるかもしれないでしょ」
「…………………」
ローレンとしてはもはや言葉もなかった。確かに、ローレンの目から見てもケイ=コバヤカワは滅多にいない好青年ではある。けれど、彼が結婚して子供が出来たとしても諦めないというのは――流石に執着の度合いが異常ではないだろうか?
「わかってるわよ、ヒラリー。圭が誰か他の女性と結婚してしまったら、その時には諦めるべきだっていうのはね。だけど、人って時の流れとともに変わっていくものじゃない。わたしも、可能性は低いけど、圭と同じくらい好きになれる誰かにいつか出会えるかもしれないし……でもそれでもね、圭がわたしにとって世界一の男だってことには変わりないと思うの」
(むしろ、そこまで好きになれる相手に出会えたというだけでも……その運命に感謝すべきなのかしら)
なんにしても、リンクを離れた友人としてではなく、スケートのコーチとしては圭が「オリンピックが終わるまでは別れを切り出さない」ということだけでも満足しなくてはならない。そして、圭が金メダルを逃してしまっただけでなく、結局のところどの色のメダルをもアメリカにもたらさなかった今――彼らの関係はどうなるのだろうとローレンは心配している。
「圭に会いにいったんだけど……思ったほど見た目は落ち込んでるような感じじゃなかったわ。足のほうもね、試合後暫くは痛んだらしいんだけど、日数が経つにつれて大分マシになってきたって。もちろんね、圭の言ってることや雰囲気は額面通りじゃないと思うの。でも足に炎症がありながらも精一杯のことをやって第五位だったんだから、満足してるって言うのよ」
もちろん、キャシーは知っている。圭が四年前とうとう自分の双子の兄に叛旗を翻す態度をフリーの前日に取ったということは。そして圭自身が思っていた以上に兄のリョウはダメージを受け、フリーでまさかの五回連続してのジャンプ失敗……確かに、そのこと自体に対してはキャシーもリョウに対して気の毒に感じるのだが、それより何よりキャシーは常に圭の味方なのである。結局のところ、それでリョウが怒り狂って兄弟関係を断絶させたというわけでもなく、結果としてはあれで良かったのではないだろうかと、キャシーは思っていたりもする。というのも、それが<何故>というのはわからないし、うまく説明も出来ないにしても、リョウはあれ以来確かに変わったのだ。たとえば、テニス。以前までは適当に「ボールをまわす」ということもせず、勝負に勝つことしか頭になかったリョウだったが、今ではミックスダブルスを組んでも適度にラリーを楽しめるといったように変わっていたのである。
(じゃなかったらあいつが女子選手のことなんて本気で見るわけがないものね)
それまでは灰島蘭やリュドミラ・ペトロワといった選手をライバル視し、勝つための対策を練ってきたキャシーとローレンであったが、ここに新たな強敵として金愛榮が加わった。
「あんた、一体なんてことしてくれたのよ……!!」
これは金愛榮が一年休んで臨んだグランプリシリーズのあとに、キャシーがリョウに直接言った言葉である。
「文句があるなら葵に言え。俺はあんな可愛い野良猫、絶対拾わないほうがいいって最初に言ったんだ。ところがな、両親を飛行機事故で亡くして可哀想だの、スケートが心の支えになればだの言って教えだしたのはあいつなんだ。で、俺は葵が妊娠してからは、あいつにリンクに立って欲しくなかった。それで代わりに俺が愛榮を教えるっていうことになったのさ」
確かに、両親を飛行機のテロ事件で亡くしたというのは、同情してあまりある。葵にしても、金愛榮にここまでの潜在能力が隠されているとは、当初は思ってもみなかったのだろう。けれど、マスコミが騒ぐのも無理はない、金愛榮のリョウを見るあの目つき……自分が葵の立場ならば、とても我慢は出来ないと、キャシーはそう思ったものだった。
そしてこの時キャシーは、「あんたみたいな鈍い男、見たこともないわ!」と、リョウに対して彼が不可解に感じる捨て科白を残していたのだった。けれど、葵が第二子(正確には第三子だろうか)を妊娠していると聞いて、リョウと葵の関係はうまくいっているのだろうとキャシーも思う。むしろ今では、金愛榮のほうが気の毒なようにさえ感じられてきた。自分にしても、コーチのローレンが女でなくて男……あるいは振付師のアランでもいい。彼のことをキャシーは、ゲイでさえなかったら圭の次にいい男だと感じているが、アランがもし自分のコーチであったりしたら、間違いなく恋焦がれていたことだろう。そしてもしその彼にすでに奥さんや子供がいたりしたら――想像してみただけでも、キャシーは苦しくてたまらなくなってくる。
オリンピックのショートプログラムへと向かう時、キャシーはいつも通りよく集中していた。会場の廊下の奥まった隅のほうで、ウォーミングアップのためのルーティンを繰り返す。六分間練習が終わったあとは、三十分以上時間があくこともあり、トレーナーと一緒に時間をかけて体のバランスをチェックしたり、瞬発力や反射能力を高めるための一連の運動を行った。
キャシーは最終滑走や出番が遅めの時にはこうすることで余計なことを考えないようにしている。日系人トレーナーのミスター・マカベは、色々な道具を使ってゲーム感覚で体が本番に向けよく動くようにしてくれる……そしてキャシーは、本番前に自分を呼びにきたローレンに対し、「今一位についてるのは誰?」と、勝負を意識した質問をした。
「金愛榮よ。そして第二位が灰島蘭。三位がリュドミラ・ペトロワね。ある意味、予想どおりといったところ」
「そう」
自分の演技本番に向けて集中しているキャシーの態度はそっけない。けれど、そのまるで機械かサイボーグのような冷静な横顔に、ローレンとしては頼もしいものを感じるばかりである。「いつも通り」、「練習通り」のイメージを頭の中でなぞる……それが一番だった。
「金愛榮の得点は?」
キャシーはまたいかにもな事務的口調でそう聞いた。彼女がオリンピックに向けてシーズン後半からショートのプログラムを変えてきたことは知っていた。アルバン・ベルクのオペラ『ルル』――四大陸の時の試合を見ていて、キャシーもまた蘭同様「やられたわ!」と思ったものだった。けれど、金愛榮がどのような高得点をマークしていたにしても、キャシーは動じなかった。普通であれば、ライバルがノーミスだったかどうか、得点がどのくらい伸びたかなど、試合が終わるまでは知りたくないものである。だがキャシーは違った。むしろ先に知っておいたほうが、自分がパフォーマンスとしてどのくらいのものを出さなければならないかがわかるので、聞いておいたほうがいいのだ。
「79.11ポイントよ。そして第二位の灰島蘭の得点が78.99、三位のリュドミラ・ペトロワが76.56ポイント。でもキャシー、あなたがショートで最高の演技をしさえすれば、きっと金愛榮を越えることが出来るわ」
確かに去年の世界選手権で、キャシーは今のプログラムでショート一位に立った。けれど、フリーでリュドミラ、灰島蘭、金愛榮に抜かれて総合では第四位だった。あの時と同じことが起きないためには、必ずしも必要なのは一位という順位ではない。翌日のフリーで底力を出すためにも、理想としては一位の金愛榮と二位の灰島蘭の間くらいの得点が理想だという気がした。もちろん、たったの0.01ポイント差で相手に敗れることもあると思えば、得点は高いに越したことはない。だが、キャシーは戦略として、一位ではなく二位くらいでもいいのだと思えたことで――ほんの少しだけ気持ちに余裕が出来て楽になった。むしろ、金愛榮にはこのまま一位でいてもらって、オリンピックのプレッシャーからフリーで崩れた彼女を追い抜く形で自分がトップに立てたらと、そんなふうにキャシーは想像する。
ローレンとともにリンクサイドに進んでからも、キャシーは見た目、冷静そのものというより――どこかふてぶてしい猫を思わせるような態度でさえあった。日本の放送席のほうでも、キャシーがちらと映った時、「流石はアメリカ女王の貫禄というか、そんな威厳を感じさせますね」と明智司郎は語っていたようである。
リュドミラと入れ違いになるように、キャシーはリンクへ出ていき――花束やぬいぐるみなどがあまり放りこまれていない一画を見つけて、スケーティングの感触を確かめたのちは、まずそこで三回転フリップを跳んだ。やがて、フラワーガールたちがリンク上に放り込まれたものを片付けていくと、完璧無比と言われる三回転ルッツ-三回転ループを決めた。そして最後にダブルアクセル……何も問題はないと、キャシーはそう冷静に自分を見つめて、コーチであるローレンの元まで戻ってくる。
「何も問題はないみたいね?」
「そうね。強いていえば、最終滑走だからリンクが荒れてるのがなんだわね。前に滑った選手の溝に運悪く嵌まるとか……いかにもありえそうじゃない。いつもはミスをしない選手がミスすると、「おおーっと、アメリカの女王アーヴィングもオリンピックの魔物に捕われたか!?」なんて言われちゃうのよ、きっと」
ローレンはここでくすりと笑った。
「それだけ冷静に自分を分析できるということは、大丈夫みたいね?」
「大丈夫ではないけれど……わたしはやると決まってることややらなきゃいけないことに関しては妥協するのが嫌なだけよ。これまであんなにトレーニングしてきたのが無駄になるのも嫌。ようするに、功利主義的に考えて、元を取りたいのね。そんな自分を可愛げのない嫌な人間だとも思うけど、こういうスケート競技の場では性格的に向いてるのかもしれないわ」
「キャシー……そんなことないわ。わたし、あなたが大好きよ。あなたは美人で可愛くて、世界一スケートの上手い女の子よ。さあ、手を出して」
銀糸や金糸によって精緻な刺繍のされた手袋をはめ、キャシーが手を伸ばすと、その手をローレンがぎゅっと握る。
「この四年、頑張ってきたわよね、わたしたち。喧嘩して、ドーナツ店でドーナツ食べて仲直りしたこともあったわ。圭のことは残念だったけど、彼の分まであなたが頑張って金メダルを取って、圭のことを振り返らせてみせなさいよ。いいわね?」
「ええ。正直……圭がメダルを取れなかっただなんて、今も信じられないくらいだけど、それとこれとは別のことだから。わたしはわたしで、彼とは別の道を行くわ」
緊張していないように見えても、ローレンにはキャシーの顔が緊張で強張っているとわかっていた。最後、彼女を笑顔にさせてから送り出したいと思いながらも――ここから先はローレンにもどうかするということは出来ない。一度リンクに立ち、演技がはじまってしまえば、ローレンにはただ祈りながら彼女を見守るということしか出来ない。
「キャサリン・アーヴィング!」と名前をコールされると、キャシーは一度頷いてみせてから、フェンスの上で重ねたローレンの手を離した。極度の緊張状態から、試合前に自分と話したことは覚えていないかもしれないとローレンは思いもする。けれど、極限状態で無意識の内にも出た言葉だからこそ、今のキャシーの言葉は重要ではないかとローレンは思った。
(そうよ、キャシー!あなたはあなたの道を行くべきなのよ。それがもし圭とは別の道であったとしても……あなたなら、どんな道も最高のものに変えていけるはずだから。それだけの強い力をあなたは持っているのよ!)
キャシーは会場の声援に応えて笑顔で手を上げたりすることもなく、六分間練習のあと、随分時間が経ってしまったことから、この時も自分の足と足の一部のように機能するスケート靴、その下のブレードとエッジ……それが吸いつくようにひとつになるようにと、最後までその感触に神経を走らせつつ、時間ギリギリにようやくスタートポジションについた。
キャシーのショートプログラムの曲は『ブラックスワン』。
はじまりは、オデットとジークフリート王子のアダージョだが、このあたりの表現をその後、キャシーは少し変えた。最初はそんなオデットとジークフリート王子の姿を木陰から見て嫉妬する――といった解釈だったのだが、その後少し進んで、オディールはオデットの姿に自分を重ね合わせ、彼女と成り代わることを決意するのだ。そして、ここから3ルッツ-3ループ。いつもながらの、スピード感のある完璧な着氷に、大きな拍手と口笛だけでなく、多くのアメリカ国旗が高く掲げられる。
フライングキャメルスピンを鳥の翼を思わせる優雅な動きによって舞い、そしてステップシークエンス。ここも、キャシーは解釈を変えて、以前とは違うように演じるようになっていた。以前は、悪魔的でコケティッシュなバレエにおける「いかにも」なオディールだった。けれど、今は切なく苦悩するオディールへと変わったのだ。ジークフリート王子の心を我が物としたい……けれど、女の魅力によって誘惑し、それで王子のことを自分のものに出来たとしても――それを本物の愛と呼ぶことは出来ない。ましてや永遠の愛などからは程遠いものだ。けれど、それでもいいから王子の愛が欲しい!と渇望せずにはいられない狂気にも近い感情をキャシーは見事に演じ、見る者をゾクリとするような鳥肌の立つ世界へ誘った。
そしてここから後半ジャンプのトリプルフリップをスパイラル・ロッカー・カウンター・スリーターンとステップを入れてから跳び、シャーロットスパイラルからのダブルアクセルを成功させる。あとはブラックスワンにとっての最高の見せ場――32回転のグラン・フェッテ・アン・トゥールナンを回るところで、キャシーはコンビネーションスピン、レイバックスピンと、息もつかせぬ速さで連続して回る。そして最後は――自分の真実の姿を見ても愛して欲しいという願いをこめ、キャシーは顔から仮面をはぎとるポーズによって終えた。
キャシーはオリンピックという大舞台でノーミスの演技をしたにも関わらず……いつもの冷静な横顔を崩すことなく、バレエのレヴェランス(お辞儀)を思わせる優雅な仕種でジャッジと観客に礼をした。あとはただ、ぬいぐるみや花束をどこか儀礼的に拾い上げ、真っ直ぐリンクゲートのほうへ戻ってくる。
「今日も完璧だったわ。キャシー、きっとあなたが第一位よ!」
感動のあまり、美しい青い瞳に涙を滲ませて、ローレンはそう言った。
「点数が出るまではまだわからないけど……まあ、二位だったにしても、金愛榮と僅差ならいいわ」
ローレンからエッジカバーを受け取り、ブレードに嵌めると、彼女に預けておいたぬいぐるみを抱いて、キャシーはコーチと一緒にキス&クライへ向かう。そこで、ローレンからタオルを受け取ると、顔や首筋に流れる汗を軽く押さえるようにして拭いた。
この時のキャシーの姿というのは、本人がそうと意識してないだけに、尚一層のこと美しいと、オーロラビジョンを通して見た観客も、あるいはテレビやインターネットで見ている視聴者たちも思っていたに違いない。
やがて、下のほうにあるモニターにキャシーのショートプログラムの得点が表示される。
技術点=42.55、演技構成点=36.66、合計点=79.21ポイント。
次に画面が切り替わり、<Rank1>と表示されて、キャシーは思わず溜息を着いた。
何分、去年の世界選手権の経験があるため、そう素直に手放しでは喜べないのだ。
けれど、ローレンは隣の愛弟子の腕に手をかけると、彼女の心中を察して言った。
「キャシー、フリープログラムはあの時とは違うものを滑るのよ」
「ええ、そうね……」
ストラヴィンスキーの<火の鳥>は、キャシーがこれまで滑ったフリープログラムの中で、もっとも高得点をマークした作品だった。本当はショートが<ブラックスワン>ということになると、フリーも同じ「鳥もの」ということで迷ったのだが、今はふたつとも彼女にとってこれ以上もなく素晴らしい芸術作品になったと、キャシーもローレンも感じている。
(でも、得点的には灰島蘭の<白鳥の湖>のほうが上だし、金愛榮のブラームスの交響曲第三番も、リュドミラのエイト・トリプルの入った<ブエノスアイレスのマリア>も凄くいいプログラムだ。ローレンは灰島蘭もリュドミラも高難度のプログラムなだけにプレッシャーがかかって四回転を失敗したり、エイト・トリプルのうちふたつはジャンプミスするんじゃないかなんて言ってたけど……みんながみんなベストの演技をしたらどうなるかはわからない……!)
奇妙な話、キャシーは自分のライバルが失敗してくれて、自分が金メダルを手にするのを願うのと同時に――全員が全員最高の演技をした上で順位が決まって欲しいとも思うのだった。そしてこの時、ショートで一位に立ったにも関わらず、キャシーの横顔は厳しいままだったのだが、キス&クライから立ち上がるという段になってようやく笑顔となり、観客席に向けキャシーは大きく手を振ってみせたのだった。
一応念のため、もう一度女子シングル・ショートプログラムの順位を確認しておこう。
第一位=キャサリン・アーヴィング(79.21)
第二位=金愛榮(79.11)
第三位=灰島蘭(78.99)
第四位=リュドミラ・ペトロワ(76.56)
第五位=マリア・ラヴロワ(73.43)
第六位=エリカ・バーミンガム(72.67)
第七位=石原のぞみ(71.14)
第八位=高見沢由紀(70.82)
第九位=サーシャ・アルツェバルスカヤ(69.57)
第十位=李葵姫(68.23)
>>続く。