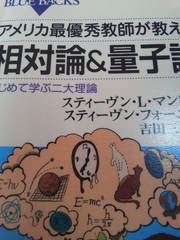
ブルーバックスの本。サブタイトルとして「初めて学ぶ2大理論」とある。
一応、学校で電気を勉強してたので、量子論については、計算はあやしいけど目次レベルのアウトラインは知っていたつもりだった。一方、現代物理のもう一本の柱である相対論は、ほとんど知らない。電磁気でちょろっと出てきたローレンツ変換くらいか。
実際、量子論は半導体他で応用範囲は広いが、相対論は応用範囲はない(勉強してもしょうがない)と言われていた。
この本の面白いところは、第一章だ。科学ってどう進歩するのか?何が正しいのかというと、できるだけシンプルなものが正しいだろう、とみんな信じることから始まる。地動説は天動説よりもシンプルだっと。
不変なものは、なんだろうというところからスタートする。
相対論ではc(光速)が不変と考える訳だ。
「時間が存在する唯一の理由は、すべてのことが同時に起こらないようにするためである。― アルベルト・アインシュタイン」(P27)
つまりアインシュタインは時間とは結構軽いものとして捉えていたわけだ。
発明した本人がどう考えていたか?どういった発想でこの理論をつくったのか。これが物事を理解するうえで早道なんじゃないだろうか?
相対論の結論として、例のE=mc^2の式が出てくる。相対論が最も応用されたのはこの部分だろうか。しかし原子爆弾や原発など、評価は芳しくない。あまりにも巨大すぎて負の側面が目立つ。(選挙の争点にもなってしまった)
今アインシュタインが生きていたら、何をかんがえていたろうか?いろいろかんがえさえる本だ。
物理っておもしろい。もう一度、物理をじっくり勉強してみたいな・・。



















