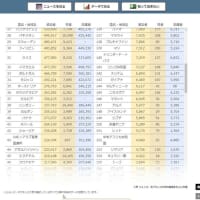宗教は過去のすべて、つまり現在に残った、過去の記憶、文化。それは、決して教義や教本、聖典に書かれたものだけではない。繰り返される儀式、典礼、どこででも交わされる挨拶、会釈のたぐい。
オリバー・クロムウェルによって率いられたイングランド議会軍によるアイルランド再占領ー11年戦争、1649年~1653年、、
ノーラ・ウェブスター/コムル・トビーン著、栩木伸明とちぎ訳/新潮クレスト2017.11 山東/滋賀ほか
滋賀県立:紹介
BOOK Bang 新潮社波:レビュー2017年12月号 掲載
小さな町の力
[レビュアー] 横山貞子(英文学者)
*
小さな田舎町で、カトリックの信仰が浸透している。アイルランドにキリスト教が伝わったのは、イギリスよりも早かった。以来、教会と学校によってカトリックの教えを伝えてきた。それに、十七世紀半ば、清教徒クロムウェルのアイルランド侵略を、アイルランド人は決して忘れない。(横山貞子)
オリバー・クロムウェルによって率いられたイングランド議会軍によるアイルランド再占領ー11年戦争、1649年~1653年、、
ノーラ・ウェブスター/コムル・トビーン著、栩木伸明とちぎ訳/新潮クレスト2017.11 山東/滋賀ほか
滋賀県立:紹介
夫を突然亡くしたアイルランドの専業主婦、ノーラ。子供たちを抱え、20年ぶりに元の職場に再就職したノーラが、ゆっくりと自己を立て直し、生きる歓びを発見していくさまを描く。アイルランドを代表する作家が自身の母を投影した自伝的小説。
【コルム・トビーン】1955年、アイルランド南東部ウェックスフォード州生まれ。ユニバーシティ・カレッジ・ダブリンで歴史と英文学を学び、ジャーナリストを経て小説を発表。主な作品に『ブルックリン』など。現在はアメリカのコロンビア大学で教鞭を執っている。(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
【栩木伸明】1958年、東京生まれ。早稲田大学教授。専門はアイルランド文学・文化。著書に『アイルランドモノ語り』など。(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
【コルム・トビーン】1955年、アイルランド南東部ウェックスフォード州生まれ。ユニバーシティ・カレッジ・ダブリンで歴史と英文学を学び、ジャーナリストを経て小説を発表。主な作品に『ブルックリン』など。現在はアメリカのコロンビア大学で教鞭を執っている。(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
【栩木伸明】1958年、東京生まれ。早稲田大学教授。専門はアイルランド文学・文化。著書に『アイルランドモノ語り』など。(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
BOOK Bang 新潮社波:レビュー2017年12月号 掲載
小さな町の力
[レビュアー] 横山貞子(英文学者)
夫を急病で失ったのは四十代半ば。四人の子供がいる。貯金はない。こういう条件の母子家庭は、世界中のどこにもあるのだが、その渦中にある人間像が描かれることは少ない。当事者は、一日々々を生きるのに精いっぱいで、記録しているゆとりはない。
ここに、よく観察し、そして記憶する息子がいた。自分の昔の体験を、息子に話すのを好んだ母親がいた。息子は、成人後はスペイン、南米、北米東部に住み、ときどき、アイルランドにいる母を見舞う程度だったようだ。それだけに、帰省中に聴かされる母親の話は熱を帯びたことだろう。この母は八十歳まで生きた。
母の没後、息子は十四年かけて、小説としてこの作品を仕上げた。この家族が暮らすのはアイルランド南東部。町中がお互いを知っているような、小さな田舎町で、カトリックの信仰が浸透している。アイルランドにキリスト教が伝わったのは、イギリスよりも早かった。以来、教会と学校によってカトリックの教えを伝えてきた。それに、十七世紀半ば、清教徒クロムウェルのアイルランド侵略を、アイルランド人は決して忘れない。独立を達成した今も、イギリスとプロテスタントに対する反感は残っている。
作者の母と重なる主人公ノーラは、夫の死後、毎日、予告なしにやってくる弔問客に疲れて、ダブリンに移ろうかと考える。ところが、子供のときから知っている女子修道院長は、「心配ないわ……町があなたを守ってくれます」と言う。
結婚する前に十一年間働いていた、町内の会社から、再就職の声がかかる。現社長も、その夫人も、先代社長も、ノーラが若いころからの知り合いの仲だ。小さい町が守ってくれている。それは、おそらく、後になってから気づくことなのだろう。
出勤してみると、直接の上司は、十代のころノーラがいじわるをした、まさにその女性だった。当然、お返しがはじまる。まじめで有能なノーラの像が、ここで急に活き活きとしてくる。実際に母からきいた話なのか。作者の創作か。
ノーラは、自分の悲しみを人に訴えない生きかたを選び、人に憐れみを乞わない姿勢を通してきた。ノーラの父が亡くなったときに母のとった、町中の人に自分のほうから憐れみを求める態度が、反面教師の働きをした。末息子のコナーが、学業はよくできるのに、成績が下の級に移されたとき、ノーラはそれを不当と思う。だが、教師に泣きつくのは、彼女のやりかたではない。住所がわかる限りの教師たちに、同文の手紙を手書きで書く。息子がもとの級に戻るまで、毎朝、学校前でピケを張って、教師の登校を阻止する、という内容だ。その独りデモ、独りピケを、だれの助けも借りずに、連日、実行し、ついに目的を果たす。
ノーラは、超人のように見える。子供から見た母は、そう見えるのだろう。ノーラが与えるこの印象は、もっと長い年月のあいだに起こったことを、夫の死後三年間に凝縮して配置してあるために、生じているかもしれない。
亡夫は、この中高一貫男子校の教師だった。長男ドナルは父親を尊敬し、父のようになりたいと思っていた。その父を失って以来はじまった、彼の吃音は、別の寄宿制高校に転校すると、自然に治まる。父の影から解放されたのだ。この小説の作者となるのは、彼、ドナルのほうである。
夫の生前、ノーラは自分の家庭に満ち足りていた。ところが、意外なものとの出会いが、夫の死後、待っていた。それは、音楽だ。レコード・コンサートに誘われ、黒い盤から流れ出る音楽をきいて、衝撃を受ける。夫は音楽に関心がなく、自分の仕事には静かさが必要だと思っていた人だった。ノーラは音楽に強く惹かれ、乏しい家計の中から古いプレーヤーとレコードを買う。こんなに美しいものがあった! レコードをひとりで聴く楽しみを、ノーラは持つようになる。それは、夫には決してついてこられない場所だった。
作者が母から、こういう体験を聞いたのか、それとも創作なのか、それはわからない。だが、ここは、読んでいて心に響く、すばらしいところだ。
作者の母は、一九二一年生まれ。この物語の背景は、一九六〇年代の終わりから七〇年代のはじめにかけて、ということになる。田舎の町が、そこに住む人を再生させる力を保っていた時代と言えるだろうか。別の文化圏に置いても通る、根の深い普遍性を持つ庶民伝になっている。
ここに、よく観察し、そして記憶する息子がいた。自分の昔の体験を、息子に話すのを好んだ母親がいた。息子は、成人後はスペイン、南米、北米東部に住み、ときどき、アイルランドにいる母を見舞う程度だったようだ。それだけに、帰省中に聴かされる母親の話は熱を帯びたことだろう。この母は八十歳まで生きた。
母の没後、息子は十四年かけて、小説としてこの作品を仕上げた。この家族が暮らすのはアイルランド南東部。町中がお互いを知っているような、小さな田舎町で、カトリックの信仰が浸透している。アイルランドにキリスト教が伝わったのは、イギリスよりも早かった。以来、教会と学校によってカトリックの教えを伝えてきた。それに、十七世紀半ば、清教徒クロムウェルのアイルランド侵略を、アイルランド人は決して忘れない。独立を達成した今も、イギリスとプロテスタントに対する反感は残っている。
作者の母と重なる主人公ノーラは、夫の死後、毎日、予告なしにやってくる弔問客に疲れて、ダブリンに移ろうかと考える。ところが、子供のときから知っている女子修道院長は、「心配ないわ……町があなたを守ってくれます」と言う。
結婚する前に十一年間働いていた、町内の会社から、再就職の声がかかる。現社長も、その夫人も、先代社長も、ノーラが若いころからの知り合いの仲だ。小さい町が守ってくれている。それは、おそらく、後になってから気づくことなのだろう。
出勤してみると、直接の上司は、十代のころノーラがいじわるをした、まさにその女性だった。当然、お返しがはじまる。まじめで有能なノーラの像が、ここで急に活き活きとしてくる。実際に母からきいた話なのか。作者の創作か。
ノーラは、自分の悲しみを人に訴えない生きかたを選び、人に憐れみを乞わない姿勢を通してきた。ノーラの父が亡くなったときに母のとった、町中の人に自分のほうから憐れみを求める態度が、反面教師の働きをした。末息子のコナーが、学業はよくできるのに、成績が下の級に移されたとき、ノーラはそれを不当と思う。だが、教師に泣きつくのは、彼女のやりかたではない。住所がわかる限りの教師たちに、同文の手紙を手書きで書く。息子がもとの級に戻るまで、毎朝、学校前でピケを張って、教師の登校を阻止する、という内容だ。その独りデモ、独りピケを、だれの助けも借りずに、連日、実行し、ついに目的を果たす。
ノーラは、超人のように見える。子供から見た母は、そう見えるのだろう。ノーラが与えるこの印象は、もっと長い年月のあいだに起こったことを、夫の死後三年間に凝縮して配置してあるために、生じているかもしれない。
亡夫は、この中高一貫男子校の教師だった。長男ドナルは父親を尊敬し、父のようになりたいと思っていた。その父を失って以来はじまった、彼の吃音は、別の寄宿制高校に転校すると、自然に治まる。父の影から解放されたのだ。この小説の作者となるのは、彼、ドナルのほうである。
夫の生前、ノーラは自分の家庭に満ち足りていた。ところが、意外なものとの出会いが、夫の死後、待っていた。それは、音楽だ。レコード・コンサートに誘われ、黒い盤から流れ出る音楽をきいて、衝撃を受ける。夫は音楽に関心がなく、自分の仕事には静かさが必要だと思っていた人だった。ノーラは音楽に強く惹かれ、乏しい家計の中から古いプレーヤーとレコードを買う。こんなに美しいものがあった! レコードをひとりで聴く楽しみを、ノーラは持つようになる。それは、夫には決してついてこられない場所だった。
作者が母から、こういう体験を聞いたのか、それとも創作なのか、それはわからない。だが、ここは、読んでいて心に響く、すばらしいところだ。
作者の母は、一九二一年生まれ。この物語の背景は、一九六〇年代の終わりから七〇年代のはじめにかけて、ということになる。田舎の町が、そこに住む人を再生させる力を保っていた時代と言えるだろうか。別の文化圏に置いても通る、根の深い普遍性を持つ庶民伝になっている。
*