11月26日(水) 「シュガータイム」(小川 洋子著)
三週間ほど前から、わたしは奇妙な日記をつけ始めた―。春の訪れとともにはじまり、秋の淡い陽射しのなかで終わった、わたしたちのシュガータイム。青春最後の日々を流れる透明な時間を描く、芥川賞作家の初めての長篇小説。
主人公が過食症になり、おかしな日記をつけることから話は始まる。恋人とのふれあいや、背が伸びない奇病の弟、そして友達など、まっとうな青春小説だった。新聞のある作家のお薦め作品にあったので読んでみた。
11月30(日) 「悪人」(吉田 修一著)
福岡市内に暮らす保険外交員の石橋佳乃が、携帯サイトで知り合った金髪の土木作業員に殺害された。二人が本当に会いたかった相手は誰だったのか? 佐賀市内に双子の妹と暮らす馬込光代もまた、何もない平凡な生活から逃れるため、出会い系サイトへアクセスする。そこで運命の相手と確信できる男に出会えた光代だったが、彼は殺人を犯していた。
<彼女は自首しようとする男を止め、一緒にいたいと強く願う。光代を駆り立てるものは何か? その一方で、被害者と加害者に向けられた悪意と戦う家族たちがいた。> ← この辺が凄い
誰がいったい悪人なのか? 事件の果てに明かされる殺意の奥にあるものは? 毎日出版文化賞と大佛次郎賞受賞した著者の最高傑作、待望の文庫化。
12月4日(木) 「1945年のクリスマス」(ベアテ・シロタ・ゴードン著)
ロシアのピアニストの娘として生まれ、5歳の時父に伴い来日。のちに単身渡米、戦後GHQ民放局のスタッフとして再来日。日本で苦しい生活をしていた両親と劇的な再会を果たす。戦争と芸術と愛に彩られた女性の生涯。
凄い人生を歩んだものだ。後半のいろいろな人達との交流も興味深かった。
ベアテという名前は、母親が敬愛していたシュテファン・ツヴァイクの作品に登場する「ベアテ夫人」からとったという。そして、父親も「ベアテ・シロタ」の音の響きの美しさから、すぐに賛成したとも。
12月5日(金) 「聖地Cs」(木村 裕也著)
原発事故による居住制限区域内で被曝した牛たちを今も生かそうとする牧場で、ボランティアに来た女性が見たものは―「聖地Cs」。非正規雇用で働く男性が「猫が苦しむ社会は、ヒトも苦しむ社会」だと切実に思うまでの日々を描いた「猫の香箱を死守する党」。現代社会の問題を真正面から捉えた二篇を収録。
作者にとって1本の映画がきっかけだった。それは、福島第一原発周辺で被災した動物と人間のドキュメンタリー「犬と猫と人間と2」。取り残された牛舎に1頭が生き残っていた。仲間の死骸のそばで汚物に埋まりながら。絶望も苦しみも通りこしたそのうつろな目を見たとき、”命をどのように扱っているか。ここに問題の塊がある。動物を投して人間社会の形が見えてくる感触があった”と。(11/1朝日新聞)
リアルな震災後文学に脱帽です。時にこんな本も必要でいて、考えることも多い。
12月14日(日) 「さよならを待つふたりのために」(ジョン・グリーン著)
ヘイゼルは十六歳。甲状腺がんが肺に転移して以来、三年も酸素ボンベが手放せない生活。骨肉腫で片脚を失った少年オーガスタスと出会い、互いにひかれあうが…。死をみつめながら日々を生きる若者の姿を力強く描く、傑作青春小説。
「きっと、星のせいじゃない」(映画化のタイトル)(因みに原題は「The Fault In Our Stars」)のちらしを見たのが始まりでした。不治の病にかかった若い男女の話というと涙を誘って……。しかしこの作品はある目的を持ってオランダへ出掛けたりします?! 眩しいほどの明るさと希望を与えてくれるのです。原作が先になりましたが、映画も楽しみです。
12月18日(木) 「アラスカを追いかけて」(ジョン・グリーン著)
伝記が好きで、著名人の「最期の言葉」を知ることが好きなパッジは、ラブレーがのこした言葉「偉大なるもしかして」を探しに、アラバマの寄宿高校に転校する。そこで、個性豊かなチップや日本人のタクミと友だちになる。そのなかでも本好きの美少女アラスカは、頭の回転が速く、飾らない性格だが、ミステリアスな雰囲気もあり、パッジは心惹かれてゆく。パッジたちが「人生最悪の日」について告白しあっているとき、アラスカの心の傷が明かされる。ある夜、アラスカが泣きながら、ひどくあわてた様子で、「行かなきゃ、どうしても行かなきゃならないの」という言葉をのこし、車で寮を出て行く。そこには、「悲劇」が待ちかまえていた......。
ジョン・グリーン繋がりで読んでみた。この作品も映画化されてるらしい。
12月25(木) 「処刑までの十章」(連城 三紀彦著)
ひとりの平凡な男が突然消えた。弟直行は、土佐清水で起きた放火殺人事件、四国の寺で次々と見つかるバラバラ死体が、兄の失踪と関わりがあるのではと高知へと向かう。真相を探る度に嘘をつく義姉を疑いながらも翻弄される直行。夫を殺したかもしれない女に熱い思いを抱きながら、真実を求めて事件の迷路を彷徨う。禁断の愛、交錯する嘘と真実。これぞ、連城マジック *の極み。
*「ごく短い掌編であれ、大作であれ、連城三紀彦の小説はどれも、とにかく大技という感じがする。強烈な芳香を放つ謎と、めくるめくどんでん返しの連続は、この作家のトレードマークだったが、そのような時として殆ど異常とさえ映る「物語り」の構え自体が、比類無く大きく、強い。…… たおやかさと繊細さの内に宿っている。稀有な小説家であったと思う。」(11/30朝日新聞)
一周忌を記念してこの作品と「女王」が刊行された。誰?や何故?の真実を求めて一気に読み進んだ。”アサギマダラ”や”午前五時七十一分”……
12月27(土) 「グレース・オブ・モナコ」(ジェフリー・ロビンソン著)
グレース・ケリー本人とレーニエ3世、そして彼らの3人の子供たちと深い交流のあったジャーナリストだからこそ知る、モナコ公妃としての人生を全力で生きたグレースの素顔。家族を愛しモナコ発展のために身を捧げた彼女の大きな人間性を、近しい人々の多くの証言も交えて明らかにしていく。衝撃の死の真相も家族によって語られた。美しいハリウッド・スターの恋物語というイメージを覆す、硬派で華麗なノンフィクション。
妃を最も愛した四人の方々、夫君のレーニエ三世、現大公アルベール二世、カロリーヌ公女、そしてステファニー公女の深い理解とお力添えを得て書き上げられた。多くの人達のインタビューに基づいている。著者が生前のグレースと親交があったとエピローグに書かれている。
「わたしにとってグレース・ケリーはかけがいのないひとでした。彼女えもががプリンセスだったからでもあーと、女優だったからでも、友人だったからでもなく、これまでに出会った中でいちばんすばらしい女性だったからです。グレースに会うといつも、誰もがやさしい、あたたかな気持ちになったものです。いっしょにいるだけで幸せを感じられるひとでした。(J・スチュワート)
12月30(火) 「恋文」(連城 三紀彦著)
マニキュアで窓ガラスに描いた花吹雪を残し、夜明けに下駄音を響かせアイツは部屋を出ていった。結婚10年目にして夫に家出された歳上でしっかり者の妻の戸惑い。しかしそれを機会に、彼女には初めて心を許せる女友達が出来たが…。表題作をはじめ、都会に暮す男女の人生の機微を様々な風景のなかに描く『紅き唇』『十三年目の子守歌』『ピエロ』『私の叔父さん』の5編。直木賞受賞。
いずれの作品も良かった。不思議な世界へ連れていってくれた。他の作品も読みたくなりました。





























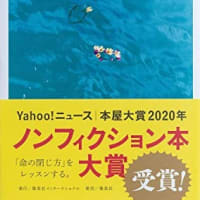

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます