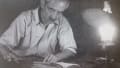季節をもどす 雨…

【自註】
長かった冬が漸く終わると、山国信州には潮のようにどっと春が押し寄せて来る。どこのにも桃や桜や梅や杏子が一時に咲いて、ついこの間まで裸だった木々はもう柔らかな緑の若葉にくるまれている。いろいろな小鳥の歌が賑やかに、頭上の雲も帆のようだ。別荘の持ち主が経営している小さい牧場の丘のてっぺんに立つと、北西の空を遠く、まだ雪を光らせている北アルプスの槍や穂高や常念の頭が見える。
みんななじみの山々だ。
私はうっとりと過去を思い、しみじみと現在の自分を考える。
そしてともすれば甘い感傷に陥ろうとする気持ちを引き立てるように、
堅くて冷めたい安山岩にしっかりと臀(しり)を据える。
***********
安山岩(あんざんがん)
***********
日本ではもっとも多く分布する火山岩。

英名の andesite は、南米アンデス山中のMarmato産の粗面岩様の火山岩に対し、アンデスの名をとり -ite をつけたもの。日本語訳は、はじめ富士岩(明治17年)と訳されたが、地質調査所ではアンデス山の石の意で、安山岩と訳して用いた。以後、富士岩・安山岩が明治20年代までは併用された。(ウキペディアより引用)

(大阪府豊中市=箕面方面= 撮影:3月9日)
春の牧場 自註 富士見高原詩集(尾崎喜八)より
あかるく青いなごやかな空を
春の白い雲の帆がゆく。
谷の落葉松、丘の白樺、
古い村落を点々といろどる
あんず 桜が 旗のようだ。
ほのぼのと赤い二十里の
大気にうかぶ槍や穂高が
私に流離の歌をうたう。
牧柵や 蝶や 花や 小川が
存在もまた旅だと私に告げる。
だが 緑の牧の草のなかで
風に吹かれている一つの岩、
春愁をしのぐ安山岩の
この堅い席こそきょうの私には好ましい。
あかるく青いなごやかな空を
春の白い雲の帆がゆく。
谷の落葉松、丘の白樺、
古い村落を点々といろどる
あんず 桜が 旗のようだ。
ほのぼのと赤い二十里の
大気にうかぶ槍や穂高が
私に流離の歌をうたう。
牧柵や 蝶や 花や 小川が
存在もまた旅だと私に告げる。
だが 緑の牧の草のなかで
風に吹かれている一つの岩、
春愁をしのぐ安山岩の
この堅い席こそきょうの私には好ましい。
【自註】
長かった冬が漸く終わると、山国信州には潮のようにどっと春が押し寄せて来る。どこのにも桃や桜や梅や杏子が一時に咲いて、ついこの間まで裸だった木々はもう柔らかな緑の若葉にくるまれている。いろいろな小鳥の歌が賑やかに、頭上の雲も帆のようだ。別荘の持ち主が経営している小さい牧場の丘のてっぺんに立つと、北西の空を遠く、まだ雪を光らせている北アルプスの槍や穂高や常念の頭が見える。
みんななじみの山々だ。
私はうっとりと過去を思い、しみじみと現在の自分を考える。
そしてともすれば甘い感傷に陥ろうとする気持ちを引き立てるように、
堅くて冷めたい安山岩にしっかりと臀(しり)を据える。
***********
安山岩(あんざんがん)
***********
日本ではもっとも多く分布する火山岩。

英名の andesite は、南米アンデス山中のMarmato産の粗面岩様の火山岩に対し、アンデスの名をとり -ite をつけたもの。日本語訳は、はじめ富士岩(明治17年)と訳されたが、地質調査所ではアンデス山の石の意で、安山岩と訳して用いた。以後、富士岩・安山岩が明治20年代までは併用された。(ウキペディアより引用)
著者 尾崎喜八
薄あおい大空(大阪府豊中市:北の空)撮影:2016年3月6日
「早春の道」 自註 富士見高原詩集(尾崎喜八)より
「のべやま」と書いた停車場で汽車をおりて、
私の道がここからはじまる。
高原の三月、
早春のさすらいの
哀愁もまた歌となる
さびしくて自由な私の道が。
開拓村の村はずれ、
年若い母親と子供二人に山羊一匹、
薄あおい大空 雪の光のきびしい山、
まだ冬めいた風景の奥に遠く消えこむ枯草の道。
これが私に最初の画だ、歌のはじめだ。
私はこの画の中にしばしとどまる、
この牧歌にしばし私の調べをまじえる。
清らかな貧しさと愛のやわらぎ、
これが私たちのけさの歌だ。
第一歩の祝福がここにあり、
私のさすらいがここからはじまる。
私の道がここからはじまる。
高原の三月、
早春のさすらいの
哀愁もまた歌となる
さびしくて自由な私の道が。
開拓村の村はずれ、
年若い母親と子供二人に山羊一匹、
薄あおい大空 雪の光のきびしい山、
まだ冬めいた風景の奥に遠く消えこむ枯草の道。
これが私に最初の画だ、歌のはじめだ。
私はこの画の中にしばしとどまる、
この牧歌にしばし私の調べをまじえる。
清らかな貧しさと愛のやわらぎ、
これが私たちのけさの歌だ。
第一歩の祝福がここにあり、
私のさすらいがここからはじまる。
【自註】
待ち兼ねていた春が漸(ようや)くその気配を見せたので、
或る朝早く富士見から汽車に乗って八ヶ岳の東の裾野を、
昔書いた「念場ガ原と野辺山ノ原」への遠足に出かけた。
近くは権現や赤岳、遠くは奥秩父の金峯山や南アルプスの雪の峯々を眺めながら、野辺山の広大な白樺林を歩き廻ったり美ノ森へ登ったりして、晩くなったら清里の何処かへ泊ってもいいという至極のんびりとした遠足だった。
早春は私にとって何か知らぬが心に哀愁を覚える季節である。
それも場所が山や高原のような自然の中だと特にいちじるしい。
元来哀愁には常に或る種の美の要素が含まれている。
その美は私の場合、詩につながり音楽につながる。
或る音楽のえにもいえず美しいラルゲットやアダージョを聴いている時、それはいつでも私を喜ばせる歌であると同時に哀愁の歌でもある。
そしてそれが此処では野辺山の原の三月の自然の景観であり、開拓村の若い農夫とその子供たちと彼らの一匹の山羊だった。
私が自分をもまたその画中の一点景に加えたのは果たして僭越の沙汰だったろうか。
しかしたとえそうであっても、
伸びやかにすんなりと出来たこの詩は、
このまま永く一人でそのさすらいを続けるだろう。

*写真、地図は、ウキペディアより引用させていただきました。
*現地に赴き、「早春のさすらい」をスケッチをしたいものです。
「雪の夕暮」 自註 富士見高原詩集(尾崎喜八)より
窓を開けてお前はいう。
「また雪が降り出して来ました。
この雪はきょう一日 今夜一晩降りつづいて、
いよいよ私たちを世の中から
遠く柔らかく隔てるでしょう」と。
遠く、そして柔らかく・・・・・・
ほんとうにお前のいうとおりだ。
もしも此の世を愛するなら、
その美をめで、その貴いものを尊ぶなら、
私たちはそれを手荒く扱ったり 弄(もてあそ)んだり
なれなれしくそれと戯れてはいけないのだ。
つねに柔らかく接して、別れを重ねて、
私たちの愛や讃美や信頼の心を
ながく新鮮に保たなければならない、
もしも自然や人生や芸術から
生きる毎日の深淵な意味を汲もうと願うなら。
お前はいう、
「もう向うの村も見えなくなりました。
こんなに積もってゆく大雪では
あの娘たちも今夜は遊びに来ないでしょう」と。
そして私はいう、
「今夜は久しぶりでシュティフターを読もう。
それともカロッサにしようか」と。
【自註】
「お前」というのは勿論私の妻の事で、彼女は時どきこんな思い入ったような殊勝な言葉も洩らすのである。
又別の時だが、「おばあちゃんのお墓の上で、春が三度目のリボンをひるがえしています」などとも言った。
おばあちゃんとはそれより四年前に死んだ私の母の事である。
私たち普通の人間は大抵この世の毎日の生活や目にする物に馴れっ子になって、心情の上でも木目荒く粗雑に生きている。
本当は常にいくらかの隔たりを保って人間や世界に接しながら、あたかも長い病いから癒えた者のような感謝の念と新鮮な気持ちとで生きてゆくべきではないだろうか。
馴れればういういしかった初心も失われ、真実や美にも鈍感になり、尊重すべき人生に対して、悪く言えば、「すれっしからし」になってしまう。
私たち夫婦はこういう心で、オーストラリアの作家シュティフターやドイツのハンス・カロッサの書いた物を戦前から尊び愛していた。
それ故か「遠く柔らかく」の一語が契機となって、時も折、誰も遊びに来ない雪降りの夜を、久しぶりに彼らの『さまざまな石』か『指導と信徒』でも一緒に読もうという気になったのである。
******************
すれっからし【擦れっ枯らし】
さまざまな経験をして、悪賢くなったり、
人柄が悪くなったりしていること。
******************
すれっからし【擦れっ枯らし】
さまざまな経験をして、悪賢くなったり、
人柄が悪くなったりしていること。
******************

~自註 富士見高原詩集について~
<出版時期>
(1)1969年(昭和44年)出版社:青娥書房 喜八77歳 (限定千部)
(2)1984年(昭和59年)出版社:鳥影社 喜八没後10年
*尾崎喜八(1892.1.31-1974.2.4)没82歳。富士見在住は、七年間<1946年(昭和21年)から1952年(昭和27年)>です。
『花咲ける孤独』(代表的詩集)
詩人 尾崎喜八には、長野県富士見在住時代にものを集めた『花咲ける孤独』という詩集があります。(昭和30年2月出版)しかし、今ではもう絶版になっており、その後『尾崎喜八詩文集』第三巻として出版され今日に至っています。(昭和34年10月出版)
『自註 富士見高原詩集』
『自註 富士見高原詩集』は、「花避ける孤独」以降の作品も加え、富士見高原で得た詩からだけ総数七十篇を選んで出版されています。
 『自註 富士見高原詩集』を出す気になった理由は、それは【自註】である、と喜八は以下のことを語っています。
『自註 富士見高原詩集』を出す気になった理由は、それは【自註】である、と喜八は以下のことを語っています。「作者自身が自分の詩に註釈を施し、或はそれの出来たいわれを述べ、又はそれに付随する心境めいたものを告白して、読者の鑑賞や理解への一助とするという試み」である。
詩は言葉と文字の芸術であると同時に作者の心の歌であるから、本来ならばその上更に、解説その他を加える必要ないはずだが、色々と出る選詩集の中に、選者その人の鑑賞や、註釈や、或いは批判めいた物さえ添えられている場合が多くなり、それは又それで必ずしも悪くはないが、しかしそのために作者本人がいくらか困惑を感じる場合も絶無とは言えない。
鑑賞や批判が原作者の本来の意図や気持ちと食い違ったり、註釈に誤りがあったりしたのでは、迷惑するのは作者ばかりか、心ある読者、鑑賞力の一層すぐれた読者の中には、その事に不満や不快を感じる人さえいるのである。
現に私はそういう例を幾つか知っているので、今度は敢えて自註という新しい試みに手を染めた。ともかく、私はこういうことをやってみた。あとは読者の自由な判断に任せるほかはない。まず、詩を読み、更に註を読めば、或いは私という人間の心と生活と芸術とを一層よく理解してもらえるかと思うのである。
(1969年<昭和44年>11月7日 立冬の日)
 『自註 富士見高原詩集の再販にあたって』(巻末)に、妻:尾崎実子(みつこ)は、こう語っています。
『自註 富士見高原詩集の再販にあたって』(巻末)に、妻:尾崎実子(みつこ)は、こう語っています。戦後の厳しい生活を、信州富士見の大自然の中で過すことの出来たその七年間は、尾崎にとって最も詩のこころの澄み、充実した時期でした。新鮮な喜びに輝いた眼を忘れることが出来ません。
七十数年の私の生涯の中で出逢った自然や、音楽や文学や人々から受けたその時々の感動の数々を、再び尾崎が私を誘って詩的な心を移し植えながら歩んでくれるような気がいたします。
新たにこの自註詩集をお読み下さるお若い方々、場所は信州富士見でなくても、それぞれの場所で同じような体験や感動をお受けになることがおありでしょう。
そしてこの自註を読まれて、ご自分達もその時にやはり詩のこころを持たれたという事に気付いてくださるのではないでしょうか。
(1984年<昭和59年>2月5日 立春の日)
「第17回富士見高原 詩のフォーラム」
詩人:尾崎喜八ゆかりの地、富士見町
富士見高原のミュージアムにて
2014年8月23日(土)

富士見分水荘書斎にて(写真:勝山甲一氏)