細胞といわれるもののお話をしましょう。
まず、細胞はすでにそれ自体、染色体を伴なう核と他の多くの下部単位とからなる、一つの複合的構成体だということです。細胞というのは、その中で多くの出来事が生まれている一つの社会のようなものなのですね。
もろもろの単純な細胞が、互いに集まり、互いに「協調」しあうことによって、生命体を構成している複雑な細胞を現実に生み出しているのですね。その「協調」の結果、細胞の中には他の細胞の内部に住みつくものまで現れました。このように、生命体を構成している細胞は、共生的統一体と呼べるようなものに一致しているのですね。私はこうしたことを考えていると、いつもこう思うのです。宇宙という無限のような空間も、何かの生命体の一つの細胞であり、私たちはその細胞の下部単位の中に住みつく、小さな生命体なのではないのかと・・・・・(;^^A)
私たちの細胞の内部に見られる諸々の下部単位は、どれをとっても、もともとは細胞の先祖だったものばかりだそうです。その先祖たちは、共存して助け合うことによって、お互いの連続性を支え、維持していく術を身につけていったのですね。またそう言った共存の起源は、ある一つの場所で起こったただ一つの出来事であったのではなく、多くの様々な場所と多くの様々な原因という出会いとに始めから分散して起こった出来事だったのであって、そうした原因という出会いの名残は今日でも見いだすことができるそうです。
地上における生命の歴史の大半が、生命が地上に存在してきた歴史の四分の三が、単細胞のただのバクテリア的生命でしかなかったそうです。残りの四分の一の時代に入って、複雑な細胞がはじめて出現したそうです。私たちは普段、マクロな世界で自然淘汰を語ります。生きるため生き残るため、もしくは、豊かな生活のために変化の材料として伝言ゲームで学んだ自然淘汰説を利用します。しかし、生きるため生き残るため、豊かな生活のためのルーツはもともと、ミクロの世界が築き上げたルールであることを意味しているのですね。つまり、単独での変化はありえないということです。原因との出会いがあり、「協調」のもとに豊かさへの可能性を広げているのですね。ミクロの世界では三十六億年前からずっと続いているのですね。
次は、伝言ゲームによる自然淘汰説の生物学的混乱のお話をしましょう。これはきっとダーウィンがマクロの世界で最も興味を持った、「協調」という世界なのではないかと私は思っています・・・・・つづく。

















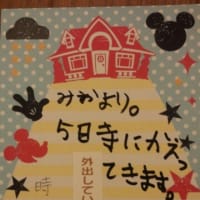


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます