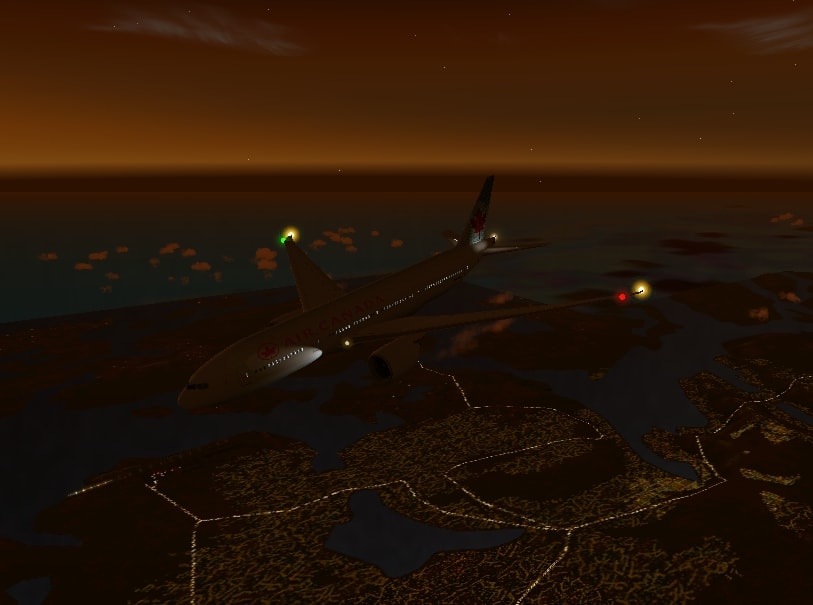島国と言えば、この国とよく比較されるが....
まぁ資質が違うし、イギリスなんていうと..豪邸と言えば貴族階級..だし
まぁ 格差なんていうけど、この国は昔から階級と言う格差があった...
最近勲章を着けているおじさんがいるけど...日本の場合戦前に逆戻り..かな..
ということで、この国の都市部の庶民は、
日本で言うと隣と壁が共有の住宅が多いとか色々とテクスチャーを見ていても特徴がある...
. . . 本文を読む
先週、本物スポッターになったのは報告したけど、
その時に色々、気が付いたことがある。
そのなかの1つが、これ...
言われてみれば、STAL性の高い航空機が、大型機と一緒の離陸点に
並ぶ必要性は更々ないわけで、サさっと手前から停止線に到着...
本物は先に離陸体制に入った機体から優先...
ところが、FSのAI機と混ぜて飛んでいる場合、
この停止線に早く到着した方が、先に離陸できる。
これ. . . . 本文を読む
空と海を時々見に行く...
空なんか地球のどこにいても見れるのでは...
おらは時々眺めるのだけど、Fsの空や海をみて...
さて、Fsで、空や海はどうしてあんな感じになるの...というと、
ずばり配色のテクスチャーがある。
その配色テクスチャーファイルはずばり色見本...みたいなのだ。
別に難しくない...感覚的な要素がすべてである。
だからたぶん、100人いたら100人答えが変わるような気 . . . 本文を読む
FSの最大の楽しみはこれ...
ネットを通じて、導入可能。
FSXは、今もノーマルの人が多いかも...
実は、おら..買って2回しか触らない..FSXなのだ。
ということで、最近もこのFSⅨのテクスチャー交換をしている。
この手が詳しい人は..たぶん上のシーンで気が付いているかも..
そう、駐機場のコンクリート面を交換した。
こっちの方が、なんとなく自然に感じたのだ。
まぁ、これもAUTOG . . . 本文を読む
実は去年、おらも引越しに苦労した、あのバンコクの新空港。
なんと空港が穴だらけで、離着陸にも支障が出ているらしい。
で、国内線だけだが、ドムファン空港に戻るのだそうだ。
これって、またAI便大変更作戦...
要はVTBSからVTBD...探しかな..
(国内線を切り分けておけばよかった...)
と言った具合になるらしい。
ということで、おらは早速昨日から作業開始しているけど、難航なのだ...
. . . 本文を読む
今日は、おらも疲れているので小ネタでいく。
で、最近ネットで見るのは実機の操縦席ビデオの公開HP...
A340netあたりが有名だけど..おらもよく見ている。
そこで思ったのは、去年ある小さな空港にB747SPを永久展示するために、
小型機しか発着できない飛行場に強行回送していたシーン...
ニタッ.. できるのか...
まぁ3回ほど着陸復航しましたが、30分ほどで降りれました。
ところで . . . 本文を読む
今更だけど、FSのAI機の欠点がこれ..
まぁ直す方法もあるけど、結構大変な動作になってくる。
基本はある程度、航空交通量を減らすことが基本かなと思う。
それにしてもだ。
アメリカのハブ アンド スポークス運行は、ほぼ同じ時間に
同じ会社の機体がハブ空港に集まるんだなぁ..
と実感してしまった。 . . . 本文を読む
3Dとは言うけど、4Dなんていう人は、まだ見たこと無い...かな...と、言っても現実世界の皆さんは、Fsでも、このことで日々...楽しんだり..苦しんだりしている...それとは..だけど、まず、一般的な話から行くと..2Dから始まる..2次元の世界..要はテレビもパソコンの画面も...画用紙に描いてある絵に..写真も全て平面社会...2Dなのだ..算数語でいくと、いつも使う X軸とY軸の話になる . . . 本文を読む
FSⅨでフライデーベイ辺りを うろうろ...するのが趣味の今日この頃..とにかく、この話にFSXをいじくる場合たどり着くのか...世界中で、色々なプロジェクト様が起動中の小道具のFSX対応化..実は本屋で見ていたら...参考書が無いんです...ね。仕方なく、検索していると、洋書にbegining DIRECT X10..らしき本...発見。 でも、売り切れでした。さてさて、まぁハードがギリギリ . . . 本文を読む
今日は完全にFS2004...いやFSⅨに戻る。
以前からトラフィツクツールを使うけど、現実にどう使うの..
と言われてしまった。
これ..おらはこう使っている。..
AI機..まぁ付属のMSAI機でもよいけど...その路線を旅するのだ。
大体だが、各AIプロジェクトは全世界の便...数は数えてないけど
5万便くらいはあるのか...
と具体的の航空会社と現実の時間帯に現実の便名...で飛んでい . . . 本文を読む