■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
『軍儀のルール』
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
一、【用語についての簡単な定義】
【軍儀盤】……九×九の八十一マスの盤。この上で戦う。先手から見て一番右の行が1筋、一番上の列が一段である。
【矢倉】……駒が積み重なった状態のものを矢倉と呼ぶ。自軍敵軍問わず、二層もしくは三層まで駒を重ねることが出来る。
【二層矢倉】……二層に重なった矢倉。
【三層矢倉】……三層に重なった矢倉。
【筋】……タテの行のこと。全九筋。
【段】……ヨコの列のこと。全九段。
【層】……矢倉の高さのこと。全三層。
【新】……手駒から新たに盤上へ打ち込むこと。「あらた」と読む。「新する」などと述する。
【手駒】……敵軍駒を取ると入手できる駒。新することができる。
【場駒】……盤上に既にいる駒のこと。
【敵軍駒】……対戦相手が扱う駒。
【自軍駒】……自分が扱う駒。
【黒軍】……先手の駒。駒の黒い方。
【白軍】……後手の駒。駒の白い方。
【表駒】……表側の駒。初期陣形配置は表駒のみで始める。敵軍裏駒を取ると手駒に加わる。
【裏駒】……裏側の駒。敵軍表駒を取ると手駒に加わる。
【初期陣形配置】……開戦をする前にそれぞれの自軍領地内で、自由に陣立てすること。
【打ち始め】……初期陣形配置し始めること。
【済み】……初期陣形配置が終わること。
【開戦】……「済み」の後、いよいよぶつかり合う勝負が始まるということ。
【終局】……勝負がつくこと。
【再陣形配置】……千日手が成立した際に行われる陣立てのこと。基本的に、初期陣形配置と変わらないが、いくつか変更がある。
【不動駒】……「砦」「砲」などの可動範囲追加効果を持ち、自らは動くことの出来ない駒のこと。
【可動範囲追加効果】……「砦」「砲」のすぐ上(二層目)に乗った駒の可動範囲を追加する効果。
【猪駒】……「忍」「香」「兵」などの強制回収効果を持つ駒のこと。
【強制回収効果】……次の移動が不可能になった駒(忍、兵、香)に関する効果。
【地駒】……「砦」「砲」「忍」「上」などの地連特性を持つ駒のこと。
【地連特性】……その駒のすぐ上に新することが出来る特性。
【強制再配置効果】……「香」の持つ効果。敵軍駒の「香」を取ったら、直ちに、それの表駒を自軍領地内に再設置しなければならない。
【裏切り効果】……「へ」の持つ効果。矢倉最上層にいる敵軍駒を取ると成立する。「へ」の下層の駒は、敵軍が自軍に、自軍が敵軍になる。
【一層三層交換効果】……「謀」の持つ効果。「謀」が一層か三層にいる時、「謀」と一層か三層にいる自軍駒を交換することが出来る。
【身代わり効果】……「侍」の持つ効果。条件を満たすと「帥」と場所を交換できる。
【千日手】……同一局面を四回繰り返すこと。指し直しとなる。
【反則】……ルールを破ること。反則をすると、反則をしたものは負けとなる。反則をすると終局である。
【ニへ】……同じ筋に二つ「へ」が存在すること。
【手ニへ】……新でニへになること。
【場ニへ】……場駒の移動でニへになること。
【二兵】……同じ筋に二つ「兵」が存在すること。
【手ニ兵】……新でニ兵になること。
【場ニ兵】……場駒の移動でニ兵になること。
【詰み】……「帥」が逃げられない状態になること。詰むと終局である。
【へ詰め】……「へ」で詰むこと。
【手兵詰め】……新した「兵」で詰むこと。
【入玉】……「帥」が敵軍領地に入ることを入玉と言う。将棋ほどのメリットはない。
【王手】……「帥」が次の一手で負けそうになることである。
【投了】……負けを認めること。投了すると終局である。
【不動攻撃】……不動のまま敵軍駒を取ること。
【移動攻撃】……移動して敵軍駒を取ること。
ニ、【軍儀盤】
・九×九の八十一マス上で戦う。
・将棋盤と同様のものを使う。
三、【駒の大きさ】
・ヨコ26.0mm×タテ19.0mm×厚さ16.0mmの直方体である。(駒を麻雀牌で代用しているので、そのための暫定である。)
四、【筋、段、層】
・タテを筋、ヨコを段、ジョウゲを層と呼ぶ。
・先手から見て一番右の行が1筋、一番上の列が一段である。
五.【黒軍と白軍】
・黒軍と白軍が有り、黒軍なら黒軍の駒、白軍なら白軍の駒しか使えない。
・黒軍が先手である。
六、【黒軍領地と白軍領地】
・黒軍領地は先手から見て、七、八、九段の領域である。
・白軍領地は先手から見て、一、二、三段の領域である。
七、【駒の種類】
・駒はニ十種類二十三枚が二組である。
・黒軍と白軍がある。
・駒は十種類二十三枚が表駒、十種類二十二枚が裏駒、である。
八、【駒の名称】
【表駒】
・「謀」―はかる。謀将。参謀。―
・「侍」―さむらい。侍。剣豪。―
・「兵」―ひょう。歩兵。―
・「忍」―しのび。忍者。下忍。―
・「砲」―おおづつ。大砲。砲台。カタパルト。―
・「砦」―とりで。守備基地。タワー。―
・「臥」―が。がりょう。臥龍。―
・「雛」―ひな。鳳雛。―
・「帥」―すい。総帥。元帥。―
・「弓」―ゆみ。弓矢。弓将―
【裏駒】
・「筒」―つつ。てつはう。短筒。短銃。―
・「槍」―やり。長槍。槍将。―
・「さ」―さ。ひらがなさむらい。―
・「と」―と。と金。―
・「へ」―へ。へぬへぬ。―
・「上」―じょう。上忍。―
・「龍」―りゅう。龍王。―
・「鳳」―ほう。鳳凰。―
・「香」―かおる。香車。―
・「や」―や。矢。矢尻。―
九、【駒の数】
【表駒】
・「謀」×ニ枚。
・「侍」×二枚。
・「兵」×九枚。
・「忍」×三枚。
・「砲」×一枚。
・「砦」×一枚。
・「臥」×一枚。
・「雛」×一枚。
・「帥」×一枚。
・「弓」×二枚。
【裏駒】
・「筒」×二枚。
・「槍」×二枚。
・「さ」×一枚。
・「と」×一枚。
・「へ」×七枚。
・「上」×三枚。
・「龍」×一枚。
・「鳳」×一枚。
・「香」×二枚。
・「や」×二枚。
十、【表駒と裏駒の対応関係】
☆「表駒」⇔「裏駒」
・「謀」⇔「筒」
・「侍」⇔「槍」
・「兵」⇔「さ、と、へ」
・「忍」⇔「上」
・「砲」⇔「香」
・「砦」⇔「香」
・「臥」⇔「龍」
・「雛」⇔「鳳」
・「帥」⇔「無し」
・「弓」⇔「や」
十一、【駒の動き】
・別に可動範囲を図示したものがある。
・敵軍自軍問わず、全ての駒は、基本(一層目)、二層目、三層目、敵駒上での可動範囲が決まっている。
・基本的には(例外はある)、手駒から盤上へ駒を新する時には、二層目、三層目に置くことが出来ない。
・「砲」「砦」は、初期陣形配置の場所から動かすことが出来ない。
・「砲」「砦」は、常に一層目に配置される。二層目、三層目には配置されない。
【表駒】
・「謀」の動き。
・一層目(基本)
斜め一画ずつと、前方に一画動ける。
・二層目
一層目の動きに、後方一画を足した分動ける。
・三層目
斜め一画ずつと、左右に一間とばして一画ずつ、後方の斜めに一間飛ばして一画ずつ動ける。
・敵上……「と」と同じ動き。
・「侍」の動き。
・一層目(基本)
前後左右に一画ずつと、前方斜めに一画ずつ動ける。
・二層目
左右に一画ずつ、前方斜めに一画ずつ、前後に一間飛ばして一画ずつ動ける。
・三層目
二層目と同じ。
・敵上……「と」と同じ動き。
・「兵」の動き。
・一層目(基本)
前方に一画動ける。
・二層目
前方に一画と、左右に一間飛ばして一画ずつ動ける。
・三層目
前方斜めに一画ずつと、左右に一間飛ばして一画ずつ動ける。
・敵上……「と」と同じ動き。
・「忍」の動き。
・一層目(基本)
二画前の左右に動ける。
・二層目
二画前の左右と、前方斜めに一画ずつ動ける。
・三層目
二層目と同じ。
・敵上……「と」と同じ動き。
・「砲」の動き。
・一層目(基本)
動けない。
・二層目
なし。
・三層目
なし。
・敵上……なし。
・「砦」の動き。
・一層目(基本)
動けない。
・二層目
なし。
・三層目
なし。
・敵上……なし。
・「臥」の動き。
・一層目(基本)
タテ・ヨコ直線に自由に動ける。
・二層目
斜め一画ずつ動ける。
・三層目
二層目と同じ。
・敵上……「と」と同じ動き。
・「雛」の動き。
・一層目(基本)
斜め四方に自由に動ける。
・二層目
前後左右に一画ずつ動ける。
・三層目
二層目と同じ。
・敵上……「と」と同じ動き。
・「帥」の動き。
・一層目(基本)
前後左右斜めに一画ずつ動ける。
・二層目
一層目と同じ。
・三層目
一層目と同じ。
・敵上……なし。
・「弓」の動き。
・一層目(基本)
前と左右に一間飛ばして一画ずつ動ける。
・二層目
前方斜めに一間飛ばして一画ずつと、前後に一画ずつ動ける。
・三層目
前方斜めに一間飛ばして一画ずつと、後ろと左右に一間飛ばして一画ずつ動ける。
・敵上……「と」と同じ動き。
【裏駒】
・「筒」の動き。
・基本(一層目)
斜めに一画づつ動ける。
・二層目、三層目
前後左右に一画づつ動ける。
・敵上……「と」と同じ動き。
・「槍」の動き。
・基本(一層目)
前方に二画、左右と後方に一画づつ動ける。
・二層目
斜めに一画づつ動ける。
・三層目
二層目と同じ。
・敵上……「と」と同じ動き。
・「さ」の動き。
・一層目(基本)
前後左右に一画づつ動ける。
・二層目
斜めに一画づつ動ける。
・三層目
二層目と同じ。
・敵上……「と」と同じ動き。
・「と」の動き。
・一層目(基本)
前後左右に一画ずつと、前方斜めに一画ずつ動ける。
・二層目
一層目と同じ。
・三層目
一層目と同じ。
・敵上……「と」と同じ動き。
・「へ」の動き。
・一層目(基本)
左右に一画ずつ動ける。
・二層目
一層目と同じ。
・三層目
一層目と同じ。
・敵上……「と」と同じ動き。
・「上」の動き。
・一層目(基本)
「忍(一層目)」の動きに、後方一画を足した分動ける。
・二層目
「忍(ニ層目)」の動きに、後方一画を足した分動ける。
・三層目
「忍(ニ層目)」の動きに、二画後ろの左右と、後方斜めに一間飛ばして一画ずつ動ける。
・敵上……「と」と同じ動き。
・「龍」の動き。
・一層目(基本)
「臥(一層目)」の動きに、斜めに一画ずつ足した分動ける。
・二層目
斜め一画ずつ動ける。
・三層目
二層目と同じ。
・敵上……「と」と同じ動き。
・「鳳」の動き。
・一層目(基本)
「雛」の動きに、前後左右に一画ずつ足した分動ける。
・二層目
前後左右に一画ずつ動ける。
・三層目
二層目と同じ。
・敵上……「と」と同じ動き。
・「香」の動き。
・一層目(基本)
前方にのみ真っ直ぐ動ける。
・二層目
斜め一画ずつ動ける。
・三層目
二層目と同じ。
・敵上……「と」と同じ動き。
・「や」の動き。
・一層目(基本)
前後に一画ずつと、後方斜めに一画ずつ動ける。
・二層目
前後に一画ずつと、後方斜めに一間飛ばして一画ずつ動ける。
・三層目
前後に一画ずつと、後方斜めに一画ずつ、後方斜めに一間飛ばして一画ずつ動ける。
・敵上……「と」と同じ動き。
十二、【初期陣形配置】
・初期陣形配置では、自軍敵軍問わず、全ての筋にそれぞれ「兵」が配置されてなければならない。
・初期陣形配置は、それぞれの自軍領地で行う。
・初期陣形配置は好きなように並べて良い。但し、一層目を置いていない場所に、二層目を置くことは出来ないし、二層目を置いていない場所に、三層目をおくことも出来ない。
・初期陣形配置は、一手ずつ交互に行う。
・先手、後手は好きに決めてよい。
・初期陣形配置は、全ての駒を使うこと。
・初期陣形配置は、表駒のみで行う。
・裏駒は初期陣形配置の段階では、存在しない。
十三、【手駒】
・敵軍駒を取れば、自分の手駒にすることが出来る。
・手駒があれば、新することが出来る。
・「帥」「砦」「砲」これら三つが、手駒に存在することはない。
十四、【矢倉の扱い】
・同じ矢倉の中に、同じ種類の自軍駒を存在させてはならない。
ex)
「兵」「兵」「兵」は禁止である。
「兵」「兵」「槍」は禁止である。
「兵」「へ」「と」は可能である。
自軍「槍」、自軍「へ」、敵軍「槍」、は可能である。
※他にもいろいろありますので、考えてみてください。
・敵軍駒が一層上もしくは一層下にいる場合、その駒を攻撃できる。
・敵軍駒が二層上もしくは二層下にいる場合、その駒を攻撃できない。
・自軍敵軍問わず、一枚であれ二枚であれその駒の上に駒が乗っていれば、その駒は移動できない。
・矢倉の中で移動できるのは最上層の駒だけである。
・二層矢倉の一層目へと割り込んで移動、移動攻撃することは出来ない。
・三層矢倉の一層目及び二層目へと割り込んで移動、移動攻撃することは出来ない。
・自軍の駒が移動する先の矢倉の三層目に乗っているとき、その矢倉のある場所が自軍駒の可動範囲内であっても、その場所に移動することは出来ない。
・敵軍の駒が移動する先の矢倉の最上層に乗っているとき、その矢倉のある場所が自軍駒の可動範囲内ならば、その駒を攻撃することが出来る。
十五、【王手に関して】
・「帥」は王手をかけられた際には、自軍駒がいるマスに逃げることが出来ない。
・「帥」は王手を指されている場所には、逃げることが出来ない。
十六、【対局の終了】
・どちらかの「帥」が詰む。
・どちらかの打ち手が投了する。
・どちらかの打ち手が反則をする。
この三つのどれかに当てはまれば対局は終了である。
十七、【反則】
・反則は、即座に負けとなる。
・一度手から離れた駒を、指しなおすのは、反則である。
【ニへ】
・ニへの反則(手ニへ、場ニへの反則)はそのニへに気付いた時、投了してしまった後でなければ、指摘して相手の反則を取ることが出来る。
・場ニへも手ニへ反則である
・ニへは如何なる時も禁止である。
・ニへは、同じ筋に自軍「ヘ」が二つ以上存在してはならないと言う事である。
【手ニへ】
・「へ」を新した際に、ニへになると反則である。
【場ニへ】
・同じ筋に既に「へ」がいるのに、その筋へと「へ」を動かすと反則である。
【二兵】
・手ニ兵は反則である。場ニ兵は反則でない。
・ニ兵の反則は、新した時のみの反則なので、相手がその一手を指した時に、自身が次の手を打つ前に、指摘した場合のみ、相手の反則を取ることが出来る。
・初期陣形配置の時のみ、場二兵も反則となる。(開戦後、場ニ兵は反則にならない)
【手ニ兵】
・「兵」を新した際に、ニ兵になると反則である。(場ニ兵は反則でない)
・手ニ兵の反則を見逃してしまい、後から気付いても、後の祭りであるので、あきらめなさい。
・手ニ兵は、同じ筋に「兵」が何個あろうが構わないが、自軍駒「兵」がある筋に手駒から兵を打ち込んではならないと言うことである。
【へ詰め】
・「帥」を「へ」で詰めると反則である。
【手兵詰め】
・「帥」を新した「兵」で詰めると反則である。(場兵詰めは反則でない)
十八、【棋譜の表記について】
・先手は「▲」で示す。
・後手は「▽」で示す。
・基本的に「▲筋―段―層―駒名」のように示す。
ex)「▲1―2―1―龍」「▽5―5―1―忍」など。
・手駒から新たに盤上へ打ち込むことを「新」といい、棋譜では「▲3―3―1―へ新」などと表記する。
・「▽4―3―1―忍」「▽6―3―1―忍」とあった場合に「▽5―5―1―忍」と打つと、どちらの駒が動いたか分からない。
なので、この場合は、「▽5―5―1―忍[6―3―1]」の様に、忍の後ろの[]に元あった場所を表記する。
・初期陣形配置に於ける「兵」の裏駒「さ」「と」などの配置については、(▲「7―7―1―さ、3―7―1―と」、▽「3―3―2―さ、5―1―1―と」)の様に、[済み]の前に書いておく。
・敵駒の「兵」を手駒にした際、それの裏駒が「へ」以外の「さ」「と」であった場合には、「▽7―7―1―忍[と入手]」の様に[]の中に入手した裏駒を表記する。
・不動攻撃する際の表記は、「筋―段―不●(不動攻撃の対象のいる層の数字)―駒名」と表記する。
ex1)「1―2―不1―忍」(←※「忍」は二層目にいて、一層目を不動攻撃している。攻撃後一層目にいる)など。
ex2)「1―2―不3―忍」(←※「忍」は二層目にいて、三層目を不動攻撃している攻撃後も二層目にいる)など。
ex3)「1―2―不2―忍」(←※「忍」は一層目か三層目にいて、二層目を不動攻撃している。攻撃後、一層目か二層目にいる。)など。
・対戦相手が直前に打ったマスと同じ場所を表記する時には、「同―駒名」と表記する。
ex1)「▽5―5―1―忍、▲同―上」など。
ex2)「▲3―3―3―謀、▽同―不3―侍」など。
・一層三層交換効果は、「▲筋―段―1or3―謀⇔●(交換する対象の駒)」と表記する。
ex1)「▲5―7―1―謀⇔兵」(←※「5―7―1」に「謀」がいて、三層目の「兵」と位置を交換した)など。
ex2)「▲4―8―3―謀⇔忍」(←※「4―8―3」に「謀」がいて、一層目の「忍」と位置を交換した)など。
・身代わり効果は、「▲筋―段―1―侍⇔帥」などと表記する。
「▲5―9―1―侍⇔帥」(←※「5―9―1」に「侍」がいて、隣接する「帥」と位置を交換した)
・裏切り効果は、「▲筋―段―層―へ[▲2―●(二層目にいる裏切った後の駒)、▲1―◎(一層目にいる裏切った後の駒)]」などと表記する。
ex1)「▲2―3―3―へ[▲2―筒、▲1―上]」(←二層目に「▽謀」、一層目に「▽忍」がいたが、それぞれ裏切って「▲筒」、「▲上」になった)など。
・強制再配置効果は、「▲筋―段―層―駒名[筋―段―1―砦or砲]」と表記する。
ex1)「▲3―3―1―忍[1―8―1―砲]」など。
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
【棋譜の具体例】
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
[打ち始め]
▲1―7―1―兵、▽9―3―1―兵、▲2―7―1―兵、▽8―3―1―兵、
▲3―7―1―兵、▽7―3―1―兵、▲4―7―1―兵、▽6―3―1―兵、
▲5―9―1―兵、▽5―1―1―兵、▲6―7―1―兵、▽4―3―1―兵、
▲7―8―1―兵、▽3―2―1―兵、▲8―7―1―兵、▽2―3―1―兵、
▲9―7―1―兵、▽1―3―1―兵、▲9―9―1―砦、▽9―1―1―砲、
▲1―9―1―砲、▽1―1―1―砦、▲1―9―2―弓、▽9―1―2―弓、
▲9―9―2―弓、▽1―1―2―弓、▲7―9―1―雛、▽2―1―1―忍、
▲5―8―1―侍、▽3―1―1―雛、▲8―9―1―忍、▽5―2―1―侍、
▲5―7―1―臥、▽5―3―1―臥、▲5―7―2―忍、▽5―3―2―忍、
▲2―9―1―忍、▽8―1―1―忍、▲3―8―1―謀、▽7―2―1―謀、
▲7―7―1―侍、▽3―3―1―侍、▲8―8―1―帥、▽2―2―1―帥、
▲7―8―2―謀、▽3―2―2―謀、
(▲「3―7―1―さ、8―7―1―と」、▽「6―3―1―さ、5―1―1―と」)、
[済み]
「開戦」
▲1―6―1―兵、▽7―3―2―忍、▲1―5―1―兵、▽6―5―1―忍[5―3―2]、
▲同―忍、▽同―忍、▲1―4―1―兵、▽同―兵、
▲同―弓、▽7―7―1―忍、▲同―謀、▽5―7―1―臥、
▲同―雛、▽6―5―1―上新、▲6―6―1―雛、▽5―7―1―へ新、
▲6―8―1―謀、▽6―7―1―へ、▲同―謀、▽2―8―1―へ新、
▲2―9―2―謀、▽1―3―1―槍新、▲1―2―1―兵新、▽同―弓、
▲同―弓、▽同―槍、▲3―4―1―や新、▽4―4―1―や新、
▲2―5―1―上新、▽4―2―1―雛、▲3―3―1―や、▽同―忍、
▲同―上、▽同―や、▲3―4―1―上新、▽3―1―1―帥、
▲4―2―1―上、▽同―帥、▲7―5―1―雛、▽5―3―1―へ新、
▲5―4―1―上新、▽4―1―1―帥、▲6―2―1―へ新、▽同―侍、
▲同―上、▽6―1―1―忍新、▲5―4―1―槍新、▽5―2―1―兵、
▲8―6―1―鳳新、▽5―1―1―弓新、▲5―5―1―槍新、▽4―2―1―龍新、
▲5―6―1―龍新、▽6―4―1―忍新、▲同―雛、▽同―兵、
▲5―3―1―槍、▽同―兵、▲6―2―2―兵新、▽5―2―1―龍、
▲6―4―1―鳳[さ入手]、▽6―3―1―侍新、▲8―6―1―鳳、▽6―4―1―上、
▲1―6―1―龍、▽1―3―1―兵新、▲2―5―1―上新、▽2―2―1―鳳新、
▲3―3―1―上、▽同―謀、▲6―5―1―さ新、▽6―3―2―上、
▲3―5―1―弓新、▽4―2―1―謀、▲7―7―1―忍、▽5―5―1―上、
▲同―弓、▽5―4―1―侍、▲3―4―1―忍新、▽3―3―1―鳳、
▲4―2―1―忍、▽同―帥、▲3―5―1―弓、▽2―2―1―鳳、
▲2―8―1―謀、▽7―4―1―忍新、▲7―6―1―鳳、▽8―4―1―上新、
▲7―6―2―謀、▽同―上、▲同―不2―鳳、▽6―5―1―侍、
▲同―鳳、▽6―6―1―筒、新▲同―鳳、▽同―鳳、
▲3―4―1―忍新、▽4―1―1―帥、▲4―2―1―槍新、▽同―龍、
▲同―兵、▽5―2―1―帥、▲6―4―1―臥新[なぜ、6―2―2―臥新と打たなかった?]、▽6―3―1―兵新、
▲6―6―1―臥、▽同―忍、▲同―龍、▽6―2―1―帥、
▲5―5―1―上新、▽4―4―1―雛新、▲5―5―2―謀、▽5―3―2―雛、
▲6―4―1―兵新、▽5―2―1―侍新、▲4―1―1―筒新、▽5―3―3―侍、
▲3―6―1―雛新、▽5―5―2―侍、▲同―不2―上、▽5―4―1―筒新、
▲5―2―1―槍新、▽5―2―1―雛、▲同―筒、▽同―帥、
▲4―1―1―兵、▽6―2―1―侍新、▲4―2―1―鳳新、▽6―2―1―侍⇔帥、
▲6―3―1―兵[さ入手]、▽同―謀、▲同―上、▽同―筒、
▲5―2―1―鳳、▽同―帥、▲6―3―1―雛、▽6―2―1―帥、
▲7―2―1―槍新[詰み]。
[終局]
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
十九、【特性】
【「帥」の特性】
・「帥」は王手された時、自軍駒がいるマスに逃げることが出来ない。
・「帥」は王手を指されている場所には、逃げることが出来ない。
・「帥」の上に、他の如何なる駒も重ねることは出来ない。
・可動範囲追加効果を享受できない。
・手駒にならない。
【「砦」の特性】
・不動駒である。
・移動攻撃が出来ない。
・不動攻撃が出来ない。
・可動範囲追加効果がある。
・地連特性を持つ。
・手駒にならない。
【「砲」の特性】
・不動駒である。
・移動攻撃が出来ない。
・可動範囲追加効果がある。
・地連特性を持つ。
・手駒にならない。
【「忍」の特性】
・自軍敵軍問わず、駒を飛び越えて移動することが出来る。
・猪駒である。
・地連特性を持つ。
【「上」の特性】
・自軍敵軍問わず、駒を飛び越えて移動することが出来る。
・地連特性を持つ。
【「弓」の特性】
・自軍敵軍問わず、駒を飛び越えて移動することが出来る。
【「へ」の特性】
・手ニへ、場ニへの反則がある。
・ヘ詰めの反則がある。
・裏切り効果がある。
【「兵」の特性】
・手ニ兵の反則がある。
・手兵詰めの反則がある。
・裏駒が三種類ある。
・猪駒である。
・初期陣形配置の際、全ての筋に自軍「兵」を配置しなければならない。
【「謀」の特性】
・一層三層交換効果がある。
【「香」の特性】
・強制再配置効果がある。
・猪駒である。
【「侍」の特性】
・身代わり効果がある。
【「臥」「龍」「雛」「鳳」の特性】
・可動範囲追加効果を享受できない。
【「筒」「槍」「さ」「と」「や」】
・特性がない。
※【地連特性】
・基本的に既に盤上にある駒の上へと新することは出来ないが、地連特性を持つ駒は、例外である。
・地連特性とは、その駒の上に別の駒が乗っていなければ、そこに新することが出来る特性である。
・地駒(「砦」「砲」「忍」「上」)のみ、地連特性を持つ。
【「砦」】
・「砦」の駒の上に他の駒が乗っていなければ、「砦」の上に新することが出来る。
・「砦」の上に手駒から直接、新する場合、その駒は何でも良い(「帥」「砲」以外)。
【「砲」】
・「砲」の駒の上に他の駒が乗っていなければ、「砲」の上に新することが出来る。
・「砲」の上に手駒から直接、新する場合、その駒は何でも良い(「帥」「砦」以外)。
【「忍」】
・「忍」の駒の上に他の駒が乗っていなければ、「忍」の上に新することが出来る。
・「忍」の上に手駒から直接、新する場合、その駒は裏駒でなければならない。
【「上」】
・「上」の駒の上に他の駒が乗っていなければ、「上」の上に新することが出来る。
・「上」の上に手駒から直接、新する場合、その駒は表駒(「帥」「砲」「砦」以外)でなければならない。
二十、【効果】
【可動範囲追加効果】
・可動範囲追加効果を持つ「砲」「砦」のことを特に不動駒と呼ぶ。
・不動駒は、不動駒のすぐ上(二層目)の自軍駒の可動範囲を、追加することが出来る。
・不動駒は、不動駒を一層目とした矢倉の三層目の駒には、可動範囲追加効果を享受させることが出来ない。
・不動駒の可動範囲追加効果によって、敵軍自軍問わず駒を飛び越すことは出来ない。
・「臥」「龍」「鳳」「雛」「帥」「香」これらの駒は不動駒の可動範囲追加効果を享受できない。
・「砲」は自軍領地内を超えて、可動範囲を追加することが出来る。
☆「砲」の可動範囲追加効果の範囲。
可動範囲追加効果の範囲は、「砲」から前方に真っ直ぐである。
・「砦」が他の駒へと追加できる可動範囲は自軍領地内のみである。自軍領地内を越えて、可動範囲を追加することは出来ない。
☆砦」の可動範囲追加効果の範囲。
可動範囲追加効果の範囲は、「砦」が「▲5―7―1」にいるとすると、
▲「7―7―全層、6―7―全層、4―7―全層、3―7―全層、6―8―全層、5―8―全層、4―8―全層、5―9―全層」である。
可動範囲追加効果の範囲は、「砦」が「▲5―9―1」にいるとすると、
▲「5―7―全層、6―8―全層、5―8―全層、4―8―全層、7―9―全層、6―9―全層、4―9―全層、3―9―全層」である。
【一層三層交換効果】
・一層目の自軍駒「謀」と、三層目の自軍駒(「帥」以外)の場所を変えても良い。一手として扱う。
・三層目の自軍駒「謀」と、一層目の自軍駒(「砲」「砦」以外)の場所を変えても良い。一手として扱う。
・連続して同じ矢倉の「謀」が一層三層交換効果を使うことは出来ない。
【身代わり効果】
・「侍」の持つ効果。「侍」の前後左右一画に、王手されている「帥」が居た場合、「帥」と場所を交換できる。矢倉にいる「侍」はこの効果を持たない。一手として扱う。
【裏切り効果】
・「へ」の持つ効果。「へ」が矢倉最上層にいる敵軍駒を取ると成立する。「へ」の下層の駒は、敵軍が自軍に、自軍が敵軍になる。
・自軍駒の上に乗るだけでは、この「へ」の裏切り効果は発動しない。
・「へ」が三層目の敵軍駒を取った場合、二層目と一層目の駒は裏切る。例えば、二層目と一層目の駒がそれぞれ敵軍表駒だった場合には、どちらも自軍裏駒になる。
・「へ」が二層目の敵軍駒を取った場合、一層目の駒は裏切る。例えば、一層目の駒が敵軍表駒だった場合には、自軍裏駒になる。
・ひっくり返す作業は一手として数えない。ひっくり返す作業が終わった後、相手の手番となる。
【強制回収効果】
・強制回収効果を持つ「兵」「忍」「香」のことを、特に猪駒と呼ぶ。
・猪駒は、次の移動が出来なくなる一手を指した時、その手を指した後、相手が次の手を指す前の間に、強制回収効果が発動する。
・強制回収効果が発動その駒は自分か相手かどちらかの手駒になる。この作業は一手として数えない。この作業が終了した後、相手の手番に移る。
・猪駒のいずれかが強制回収効果を発動した時、敵軍駒を取っていたなら、猪駒は敵軍の手駒になる。
・猪駒のいずれかが強制回収効果を発動した時、敵軍駒を取っていなかったら、猪駒は自軍の手駒になる。
・猪駒は、次の移動が出来なくなるマスへ新することが出来ない。(これを認めると、事実上パスを認めることになるので認めない)
【強制再配置効果】
・裏駒の「香」を入手した場合、その表駒が「砲」であれ「砦」であれ、新たに自軍領地内に再設置しなければならない。香を入手した後、相手が次の手を指す前の間に行う。配置する場所は任意とし、初期陣形配置の場所と違っていて良い。この作業は一手として数えない。この作業が終了した後、相手の手番に移る。
二十一、【千日手】
・同一局面を四回繰り返すこと。これを千日手と言う。千日手が成立すると、指し直しとなる。
・千日手が発生した時には、陣形配置からやり直す。
・千日手が発生し、陣形配置をやり直すことになった際、その時の黒軍領地は新しく設定され、先手から見て、六、七、八段となり、以後、九段を使えない。
・千日手が発生し、陣形配置をやり直すことになった際、その時の白軍領地は新しく設定され、先手から見て、二、三、四段となり、以後、一段を使えない。
・千日手が発生し、陣形配置をやり直すことになった際、全ての駒は初期状態に戻さず、その時にそれぞれ自軍であった場駒、手駒で陣形配置する。
・千日手が発生し、陣形配置をやり直すことになった際、先手と後手を入れ替える。
・千日手が発生し、陣形配置をやり直すことになった際、初期陣形配置と同じように配置していく。
・千日手が発生し、陣形配置をやり直すことになった際、それぞれの軍は、初期陣形配置と違い、全ての筋に「兵」を配置する必要はなく、場ニ兵にならないようにすれば良い。
(勿論、開戦後の場ニ兵は反則ではない。)
・千日手での「初期陣形配置」「打ち始め」「済み」「開戦」との対応語ははそれぞれ、「再陣形配置」「再び始め」「再び済み」「再開戦」となる。
二十二、【駒の飛び越し】
・「忍」「弓」「上」のみが、自軍敵軍問わず駒を飛び越して移動することが出来る。
・「忍」「弓」「上」以外の駒は、自軍敵軍問わず駒を飛び越して移動することが出来ない。
二十三、【矢倉に向かっての移動について】
・可動範囲内に自軍駒がいる場合、それが既に三層の矢倉か、帥の駒でなければ、上に乗ることが出来る。
・敵軍の矢倉へ攻撃する場合、攻撃対象となるのは最上層の駒だけである。
二十四、【駒の攻撃】
・駒の攻撃には移動を伴う攻撃と、移動を伴わない攻撃がある。移動を伴う攻撃を移動攻撃、移動を伴わない攻撃を不動攻撃と言う。
・移動攻撃では、可動範囲内の敵軍駒向かって移動し、その対象の駒が居た場所を占有することで、その駒を手駒とすることが出来る。
・不動攻撃では、上か下の層に敵軍駒がいたときに、一手でその駒を手駒とすることが出来る。
・上の層への不動攻撃では、その対象の駒を取るだけでよい。
・下の層への不動攻撃では、その対象の駒があった場所を占有することで、その駒を手駒とすることが出来る。
・手駒から直接、敵軍駒を取ることは出来ない。
・可動範囲内に敵軍駒がいて、それが矢倉の場合は、最上層のみ移動攻撃できる。
・可動範囲内に敵軍駒がいるなら、自軍駒のいる場所がどの層であっても、矢倉の最上層の敵軍駒を移動攻撃できる。
二十五、【場ニへ反則勝ちを誘導する】
「▲2―3―1―兵[裏駒へ]、▽2―3―2―忍、▲1―3―1―へ、▽2―1―1―へ」と、あったとする。
この状態から「▲2―3―2―へ」と最上層にいる敵軍駒「忍」を取ると、矢倉の一層目にいる自軍駒「兵」が裏切り、敵軍駒の裏駒「へ」になる。
そうすると、「▽2―1―1―へ、▽2―3―1―へ」となり、相手は場ニへで反則で、この場合、相手の負けとなる。
かなりエグい手ではあるが、意識していれば成立しにくい手である。
しかし、これを食らって負けたらちょっとかっこ悪いかも。
もちろん三層矢倉に対しても有効である。
例えば、「▲2―3―1―兵[裏駒へ]、▲2―3―2―弓、▽2―3―3―忍、▲1―3―1―へ、▽2―1―1―へ」とあったとする。
この状態から「▲2―3―3―へ」と最上層にいる敵軍駒「忍」を取ると、矢倉の一層目と二層目にいる自軍駒が裏切る、この場合「弓」「兵」が裏切り、それぞれ敵軍駒の裏駒「や」「へ」になる。
この場合、「や」はあってもなくても同じだが、また「へ」が二筋に出来たので、「▽2―1―1―へ、▽2―3―1―へ」となり、相手は場ニへで反則で、この場合も、相手の負けとなる。
二十六、【敵軍駒「砦」と自軍駒「帥」の関係】
・自軍駒「帥」が敵軍駒「砦」の敵上に乗っている状況が発生してしまった場合、一層目にある砦と、自軍手駒にある駒と交換してもよい。
なお、手駒がない場合、もしくは、交換したくない場合、「砦」(つまり「香」ね)を手駒に加えるだけでよい。
※この状況が発生するかもしれないと考えなければならない理由は、敵上での動きが決まっていない帥と攻撃能力がない「砦」が存在してしまっているからである。ついでに言うなら、「砦」以外の駒はその駒の上に乗っかっている駒に対して、攻撃が出来るので……、そもそも「帥」が敵軍駒のみで構成された二層矢倉もしくは三層矢倉を攻撃したら、その時点で自軍の負けであり、つまりは王手が指されている場所に移動攻撃すると言うことであり、それなら、「帥」は敵上での可動範囲設定はいらないかなと思ってそういう風にした矢先、そういえば「砦」の攻撃能力なくしちゃったんだった、と思い出して、どうしよう、と、困った状況になっちゃったわけさ、まぁ、そんなこんなで、いろいろ考えてみたのだが、そもそもこの条件を達成するためには「帥」が入玉していなければならないわけで、更に入玉した「帥」が上手いこと敵軍のみで構成された二層矢倉になっている「砦」に対して攻撃を成立させなければならないわけで、どんだけ希少な状況なのさと思ったわけだよ、うん、だから、僕はこんな状況がもし発生したのなら、少しくらいボーナスを上げてもいいかなって思ったんだ、だからね、こういった理由からこのルールは出来たのさ。
二十七、【その他】
・将棋と違い、敵軍領地内に入っても成ることはない。
・駒は無理に重ねなくとも良い。
・砲、砦以外の駒で、いくら層を重ねても、可動範囲が追加されることはない。あくまでも、その駒がどの層にいるかによってその駒の可動範囲は決定しているのである。
・手駒に表駒「兵」が二つ以上あり、それらのなかに裏駒が「と」か「さ」の「兵」が混ざっているのなら、相手にわからないようにシャッフルしても良い。
相手が不安な様であれば、第三者に頼んでも良い。
そもそも、無理にしなくても良い。
・「可動範囲追加効果」「一層三層交換効果」「身代わり効果」「裏切り効果」等は権利である。
・「強制回収効果」「強制再配置効果」は強制である。
『軍儀のルール』
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
一、【用語についての簡単な定義】
【軍儀盤】……九×九の八十一マスの盤。この上で戦う。先手から見て一番右の行が1筋、一番上の列が一段である。
【矢倉】……駒が積み重なった状態のものを矢倉と呼ぶ。自軍敵軍問わず、二層もしくは三層まで駒を重ねることが出来る。
【二層矢倉】……二層に重なった矢倉。
【三層矢倉】……三層に重なった矢倉。
【筋】……タテの行のこと。全九筋。
【段】……ヨコの列のこと。全九段。
【層】……矢倉の高さのこと。全三層。
【新】……手駒から新たに盤上へ打ち込むこと。「あらた」と読む。「新する」などと述する。
【手駒】……敵軍駒を取ると入手できる駒。新することができる。
【場駒】……盤上に既にいる駒のこと。
【敵軍駒】……対戦相手が扱う駒。
【自軍駒】……自分が扱う駒。
【黒軍】……先手の駒。駒の黒い方。
【白軍】……後手の駒。駒の白い方。
【表駒】……表側の駒。初期陣形配置は表駒のみで始める。敵軍裏駒を取ると手駒に加わる。
【裏駒】……裏側の駒。敵軍表駒を取ると手駒に加わる。
【初期陣形配置】……開戦をする前にそれぞれの自軍領地内で、自由に陣立てすること。
【打ち始め】……初期陣形配置し始めること。
【済み】……初期陣形配置が終わること。
【開戦】……「済み」の後、いよいよぶつかり合う勝負が始まるということ。
【終局】……勝負がつくこと。
【再陣形配置】……千日手が成立した際に行われる陣立てのこと。基本的に、初期陣形配置と変わらないが、いくつか変更がある。
【不動駒】……「砦」「砲」などの可動範囲追加効果を持ち、自らは動くことの出来ない駒のこと。
【可動範囲追加効果】……「砦」「砲」のすぐ上(二層目)に乗った駒の可動範囲を追加する効果。
【猪駒】……「忍」「香」「兵」などの強制回収効果を持つ駒のこと。
【強制回収効果】……次の移動が不可能になった駒(忍、兵、香)に関する効果。
【地駒】……「砦」「砲」「忍」「上」などの地連特性を持つ駒のこと。
【地連特性】……その駒のすぐ上に新することが出来る特性。
【強制再配置効果】……「香」の持つ効果。敵軍駒の「香」を取ったら、直ちに、それの表駒を自軍領地内に再設置しなければならない。
【裏切り効果】……「へ」の持つ効果。矢倉最上層にいる敵軍駒を取ると成立する。「へ」の下層の駒は、敵軍が自軍に、自軍が敵軍になる。
【一層三層交換効果】……「謀」の持つ効果。「謀」が一層か三層にいる時、「謀」と一層か三層にいる自軍駒を交換することが出来る。
【身代わり効果】……「侍」の持つ効果。条件を満たすと「帥」と場所を交換できる。
【千日手】……同一局面を四回繰り返すこと。指し直しとなる。
【反則】……ルールを破ること。反則をすると、反則をしたものは負けとなる。反則をすると終局である。
【ニへ】……同じ筋に二つ「へ」が存在すること。
【手ニへ】……新でニへになること。
【場ニへ】……場駒の移動でニへになること。
【二兵】……同じ筋に二つ「兵」が存在すること。
【手ニ兵】……新でニ兵になること。
【場ニ兵】……場駒の移動でニ兵になること。
【詰み】……「帥」が逃げられない状態になること。詰むと終局である。
【へ詰め】……「へ」で詰むこと。
【手兵詰め】……新した「兵」で詰むこと。
【入玉】……「帥」が敵軍領地に入ることを入玉と言う。将棋ほどのメリットはない。
【王手】……「帥」が次の一手で負けそうになることである。
【投了】……負けを認めること。投了すると終局である。
【不動攻撃】……不動のまま敵軍駒を取ること。
【移動攻撃】……移動して敵軍駒を取ること。
ニ、【軍儀盤】
・九×九の八十一マス上で戦う。
・将棋盤と同様のものを使う。
三、【駒の大きさ】
・ヨコ26.0mm×タテ19.0mm×厚さ16.0mmの直方体である。(駒を麻雀牌で代用しているので、そのための暫定である。)
四、【筋、段、層】
・タテを筋、ヨコを段、ジョウゲを層と呼ぶ。
・先手から見て一番右の行が1筋、一番上の列が一段である。
五.【黒軍と白軍】
・黒軍と白軍が有り、黒軍なら黒軍の駒、白軍なら白軍の駒しか使えない。
・黒軍が先手である。
六、【黒軍領地と白軍領地】
・黒軍領地は先手から見て、七、八、九段の領域である。
・白軍領地は先手から見て、一、二、三段の領域である。
七、【駒の種類】
・駒はニ十種類二十三枚が二組である。
・黒軍と白軍がある。
・駒は十種類二十三枚が表駒、十種類二十二枚が裏駒、である。
八、【駒の名称】
【表駒】
・「謀」―はかる。謀将。参謀。―
・「侍」―さむらい。侍。剣豪。―
・「兵」―ひょう。歩兵。―
・「忍」―しのび。忍者。下忍。―
・「砲」―おおづつ。大砲。砲台。カタパルト。―
・「砦」―とりで。守備基地。タワー。―
・「臥」―が。がりょう。臥龍。―
・「雛」―ひな。鳳雛。―
・「帥」―すい。総帥。元帥。―
・「弓」―ゆみ。弓矢。弓将―
【裏駒】
・「筒」―つつ。てつはう。短筒。短銃。―
・「槍」―やり。長槍。槍将。―
・「さ」―さ。ひらがなさむらい。―
・「と」―と。と金。―
・「へ」―へ。へぬへぬ。―
・「上」―じょう。上忍。―
・「龍」―りゅう。龍王。―
・「鳳」―ほう。鳳凰。―
・「香」―かおる。香車。―
・「や」―や。矢。矢尻。―
九、【駒の数】
【表駒】
・「謀」×ニ枚。
・「侍」×二枚。
・「兵」×九枚。
・「忍」×三枚。
・「砲」×一枚。
・「砦」×一枚。
・「臥」×一枚。
・「雛」×一枚。
・「帥」×一枚。
・「弓」×二枚。
【裏駒】
・「筒」×二枚。
・「槍」×二枚。
・「さ」×一枚。
・「と」×一枚。
・「へ」×七枚。
・「上」×三枚。
・「龍」×一枚。
・「鳳」×一枚。
・「香」×二枚。
・「や」×二枚。
十、【表駒と裏駒の対応関係】
☆「表駒」⇔「裏駒」
・「謀」⇔「筒」
・「侍」⇔「槍」
・「兵」⇔「さ、と、へ」
・「忍」⇔「上」
・「砲」⇔「香」
・「砦」⇔「香」
・「臥」⇔「龍」
・「雛」⇔「鳳」
・「帥」⇔「無し」
・「弓」⇔「や」
十一、【駒の動き】
・別に可動範囲を図示したものがある。
・敵軍自軍問わず、全ての駒は、基本(一層目)、二層目、三層目、敵駒上での可動範囲が決まっている。
・基本的には(例外はある)、手駒から盤上へ駒を新する時には、二層目、三層目に置くことが出来ない。
・「砲」「砦」は、初期陣形配置の場所から動かすことが出来ない。
・「砲」「砦」は、常に一層目に配置される。二層目、三層目には配置されない。
【表駒】
・「謀」の動き。
・一層目(基本)
斜め一画ずつと、前方に一画動ける。
・二層目
一層目の動きに、後方一画を足した分動ける。
・三層目
斜め一画ずつと、左右に一間とばして一画ずつ、後方の斜めに一間飛ばして一画ずつ動ける。
・敵上……「と」と同じ動き。
・「侍」の動き。
・一層目(基本)
前後左右に一画ずつと、前方斜めに一画ずつ動ける。
・二層目
左右に一画ずつ、前方斜めに一画ずつ、前後に一間飛ばして一画ずつ動ける。
・三層目
二層目と同じ。
・敵上……「と」と同じ動き。
・「兵」の動き。
・一層目(基本)
前方に一画動ける。
・二層目
前方に一画と、左右に一間飛ばして一画ずつ動ける。
・三層目
前方斜めに一画ずつと、左右に一間飛ばして一画ずつ動ける。
・敵上……「と」と同じ動き。
・「忍」の動き。
・一層目(基本)
二画前の左右に動ける。
・二層目
二画前の左右と、前方斜めに一画ずつ動ける。
・三層目
二層目と同じ。
・敵上……「と」と同じ動き。
・「砲」の動き。
・一層目(基本)
動けない。
・二層目
なし。
・三層目
なし。
・敵上……なし。
・「砦」の動き。
・一層目(基本)
動けない。
・二層目
なし。
・三層目
なし。
・敵上……なし。
・「臥」の動き。
・一層目(基本)
タテ・ヨコ直線に自由に動ける。
・二層目
斜め一画ずつ動ける。
・三層目
二層目と同じ。
・敵上……「と」と同じ動き。
・「雛」の動き。
・一層目(基本)
斜め四方に自由に動ける。
・二層目
前後左右に一画ずつ動ける。
・三層目
二層目と同じ。
・敵上……「と」と同じ動き。
・「帥」の動き。
・一層目(基本)
前後左右斜めに一画ずつ動ける。
・二層目
一層目と同じ。
・三層目
一層目と同じ。
・敵上……なし。
・「弓」の動き。
・一層目(基本)
前と左右に一間飛ばして一画ずつ動ける。
・二層目
前方斜めに一間飛ばして一画ずつと、前後に一画ずつ動ける。
・三層目
前方斜めに一間飛ばして一画ずつと、後ろと左右に一間飛ばして一画ずつ動ける。
・敵上……「と」と同じ動き。
【裏駒】
・「筒」の動き。
・基本(一層目)
斜めに一画づつ動ける。
・二層目、三層目
前後左右に一画づつ動ける。
・敵上……「と」と同じ動き。
・「槍」の動き。
・基本(一層目)
前方に二画、左右と後方に一画づつ動ける。
・二層目
斜めに一画づつ動ける。
・三層目
二層目と同じ。
・敵上……「と」と同じ動き。
・「さ」の動き。
・一層目(基本)
前後左右に一画づつ動ける。
・二層目
斜めに一画づつ動ける。
・三層目
二層目と同じ。
・敵上……「と」と同じ動き。
・「と」の動き。
・一層目(基本)
前後左右に一画ずつと、前方斜めに一画ずつ動ける。
・二層目
一層目と同じ。
・三層目
一層目と同じ。
・敵上……「と」と同じ動き。
・「へ」の動き。
・一層目(基本)
左右に一画ずつ動ける。
・二層目
一層目と同じ。
・三層目
一層目と同じ。
・敵上……「と」と同じ動き。
・「上」の動き。
・一層目(基本)
「忍(一層目)」の動きに、後方一画を足した分動ける。
・二層目
「忍(ニ層目)」の動きに、後方一画を足した分動ける。
・三層目
「忍(ニ層目)」の動きに、二画後ろの左右と、後方斜めに一間飛ばして一画ずつ動ける。
・敵上……「と」と同じ動き。
・「龍」の動き。
・一層目(基本)
「臥(一層目)」の動きに、斜めに一画ずつ足した分動ける。
・二層目
斜め一画ずつ動ける。
・三層目
二層目と同じ。
・敵上……「と」と同じ動き。
・「鳳」の動き。
・一層目(基本)
「雛」の動きに、前後左右に一画ずつ足した分動ける。
・二層目
前後左右に一画ずつ動ける。
・三層目
二層目と同じ。
・敵上……「と」と同じ動き。
・「香」の動き。
・一層目(基本)
前方にのみ真っ直ぐ動ける。
・二層目
斜め一画ずつ動ける。
・三層目
二層目と同じ。
・敵上……「と」と同じ動き。
・「や」の動き。
・一層目(基本)
前後に一画ずつと、後方斜めに一画ずつ動ける。
・二層目
前後に一画ずつと、後方斜めに一間飛ばして一画ずつ動ける。
・三層目
前後に一画ずつと、後方斜めに一画ずつ、後方斜めに一間飛ばして一画ずつ動ける。
・敵上……「と」と同じ動き。
十二、【初期陣形配置】
・初期陣形配置では、自軍敵軍問わず、全ての筋にそれぞれ「兵」が配置されてなければならない。
・初期陣形配置は、それぞれの自軍領地で行う。
・初期陣形配置は好きなように並べて良い。但し、一層目を置いていない場所に、二層目を置くことは出来ないし、二層目を置いていない場所に、三層目をおくことも出来ない。
・初期陣形配置は、一手ずつ交互に行う。
・先手、後手は好きに決めてよい。
・初期陣形配置は、全ての駒を使うこと。
・初期陣形配置は、表駒のみで行う。
・裏駒は初期陣形配置の段階では、存在しない。
十三、【手駒】
・敵軍駒を取れば、自分の手駒にすることが出来る。
・手駒があれば、新することが出来る。
・「帥」「砦」「砲」これら三つが、手駒に存在することはない。
十四、【矢倉の扱い】
・同じ矢倉の中に、同じ種類の自軍駒を存在させてはならない。
ex)
「兵」「兵」「兵」は禁止である。
「兵」「兵」「槍」は禁止である。
「兵」「へ」「と」は可能である。
自軍「槍」、自軍「へ」、敵軍「槍」、は可能である。
※他にもいろいろありますので、考えてみてください。
・敵軍駒が一層上もしくは一層下にいる場合、その駒を攻撃できる。
・敵軍駒が二層上もしくは二層下にいる場合、その駒を攻撃できない。
・自軍敵軍問わず、一枚であれ二枚であれその駒の上に駒が乗っていれば、その駒は移動できない。
・矢倉の中で移動できるのは最上層の駒だけである。
・二層矢倉の一層目へと割り込んで移動、移動攻撃することは出来ない。
・三層矢倉の一層目及び二層目へと割り込んで移動、移動攻撃することは出来ない。
・自軍の駒が移動する先の矢倉の三層目に乗っているとき、その矢倉のある場所が自軍駒の可動範囲内であっても、その場所に移動することは出来ない。
・敵軍の駒が移動する先の矢倉の最上層に乗っているとき、その矢倉のある場所が自軍駒の可動範囲内ならば、その駒を攻撃することが出来る。
十五、【王手に関して】
・「帥」は王手をかけられた際には、自軍駒がいるマスに逃げることが出来ない。
・「帥」は王手を指されている場所には、逃げることが出来ない。
十六、【対局の終了】
・どちらかの「帥」が詰む。
・どちらかの打ち手が投了する。
・どちらかの打ち手が反則をする。
この三つのどれかに当てはまれば対局は終了である。
十七、【反則】
・反則は、即座に負けとなる。
・一度手から離れた駒を、指しなおすのは、反則である。
【ニへ】
・ニへの反則(手ニへ、場ニへの反則)はそのニへに気付いた時、投了してしまった後でなければ、指摘して相手の反則を取ることが出来る。
・場ニへも手ニへ反則である
・ニへは如何なる時も禁止である。
・ニへは、同じ筋に自軍「ヘ」が二つ以上存在してはならないと言う事である。
【手ニへ】
・「へ」を新した際に、ニへになると反則である。
【場ニへ】
・同じ筋に既に「へ」がいるのに、その筋へと「へ」を動かすと反則である。
【二兵】
・手ニ兵は反則である。場ニ兵は反則でない。
・ニ兵の反則は、新した時のみの反則なので、相手がその一手を指した時に、自身が次の手を打つ前に、指摘した場合のみ、相手の反則を取ることが出来る。
・初期陣形配置の時のみ、場二兵も反則となる。(開戦後、場ニ兵は反則にならない)
【手ニ兵】
・「兵」を新した際に、ニ兵になると反則である。(場ニ兵は反則でない)
・手ニ兵の反則を見逃してしまい、後から気付いても、後の祭りであるので、あきらめなさい。
・手ニ兵は、同じ筋に「兵」が何個あろうが構わないが、自軍駒「兵」がある筋に手駒から兵を打ち込んではならないと言うことである。
【へ詰め】
・「帥」を「へ」で詰めると反則である。
【手兵詰め】
・「帥」を新した「兵」で詰めると反則である。(場兵詰めは反則でない)
十八、【棋譜の表記について】
・先手は「▲」で示す。
・後手は「▽」で示す。
・基本的に「▲筋―段―層―駒名」のように示す。
ex)「▲1―2―1―龍」「▽5―5―1―忍」など。
・手駒から新たに盤上へ打ち込むことを「新」といい、棋譜では「▲3―3―1―へ新」などと表記する。
・「▽4―3―1―忍」「▽6―3―1―忍」とあった場合に「▽5―5―1―忍」と打つと、どちらの駒が動いたか分からない。
なので、この場合は、「▽5―5―1―忍[6―3―1]」の様に、忍の後ろの[]に元あった場所を表記する。
・初期陣形配置に於ける「兵」の裏駒「さ」「と」などの配置については、(▲「7―7―1―さ、3―7―1―と」、▽「3―3―2―さ、5―1―1―と」)の様に、[済み]の前に書いておく。
・敵駒の「兵」を手駒にした際、それの裏駒が「へ」以外の「さ」「と」であった場合には、「▽7―7―1―忍[と入手]」の様に[]の中に入手した裏駒を表記する。
・不動攻撃する際の表記は、「筋―段―不●(不動攻撃の対象のいる層の数字)―駒名」と表記する。
ex1)「1―2―不1―忍」(←※「忍」は二層目にいて、一層目を不動攻撃している。攻撃後一層目にいる)など。
ex2)「1―2―不3―忍」(←※「忍」は二層目にいて、三層目を不動攻撃している攻撃後も二層目にいる)など。
ex3)「1―2―不2―忍」(←※「忍」は一層目か三層目にいて、二層目を不動攻撃している。攻撃後、一層目か二層目にいる。)など。
・対戦相手が直前に打ったマスと同じ場所を表記する時には、「同―駒名」と表記する。
ex1)「▽5―5―1―忍、▲同―上」など。
ex2)「▲3―3―3―謀、▽同―不3―侍」など。
・一層三層交換効果は、「▲筋―段―1or3―謀⇔●(交換する対象の駒)」と表記する。
ex1)「▲5―7―1―謀⇔兵」(←※「5―7―1」に「謀」がいて、三層目の「兵」と位置を交換した)など。
ex2)「▲4―8―3―謀⇔忍」(←※「4―8―3」に「謀」がいて、一層目の「忍」と位置を交換した)など。
・身代わり効果は、「▲筋―段―1―侍⇔帥」などと表記する。
「▲5―9―1―侍⇔帥」(←※「5―9―1」に「侍」がいて、隣接する「帥」と位置を交換した)
・裏切り効果は、「▲筋―段―層―へ[▲2―●(二層目にいる裏切った後の駒)、▲1―◎(一層目にいる裏切った後の駒)]」などと表記する。
ex1)「▲2―3―3―へ[▲2―筒、▲1―上]」(←二層目に「▽謀」、一層目に「▽忍」がいたが、それぞれ裏切って「▲筒」、「▲上」になった)など。
・強制再配置効果は、「▲筋―段―層―駒名[筋―段―1―砦or砲]」と表記する。
ex1)「▲3―3―1―忍[1―8―1―砲]」など。
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
【棋譜の具体例】
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
[打ち始め]
▲1―7―1―兵、▽9―3―1―兵、▲2―7―1―兵、▽8―3―1―兵、
▲3―7―1―兵、▽7―3―1―兵、▲4―7―1―兵、▽6―3―1―兵、
▲5―9―1―兵、▽5―1―1―兵、▲6―7―1―兵、▽4―3―1―兵、
▲7―8―1―兵、▽3―2―1―兵、▲8―7―1―兵、▽2―3―1―兵、
▲9―7―1―兵、▽1―3―1―兵、▲9―9―1―砦、▽9―1―1―砲、
▲1―9―1―砲、▽1―1―1―砦、▲1―9―2―弓、▽9―1―2―弓、
▲9―9―2―弓、▽1―1―2―弓、▲7―9―1―雛、▽2―1―1―忍、
▲5―8―1―侍、▽3―1―1―雛、▲8―9―1―忍、▽5―2―1―侍、
▲5―7―1―臥、▽5―3―1―臥、▲5―7―2―忍、▽5―3―2―忍、
▲2―9―1―忍、▽8―1―1―忍、▲3―8―1―謀、▽7―2―1―謀、
▲7―7―1―侍、▽3―3―1―侍、▲8―8―1―帥、▽2―2―1―帥、
▲7―8―2―謀、▽3―2―2―謀、
(▲「3―7―1―さ、8―7―1―と」、▽「6―3―1―さ、5―1―1―と」)、
[済み]
「開戦」
▲1―6―1―兵、▽7―3―2―忍、▲1―5―1―兵、▽6―5―1―忍[5―3―2]、
▲同―忍、▽同―忍、▲1―4―1―兵、▽同―兵、
▲同―弓、▽7―7―1―忍、▲同―謀、▽5―7―1―臥、
▲同―雛、▽6―5―1―上新、▲6―6―1―雛、▽5―7―1―へ新、
▲6―8―1―謀、▽6―7―1―へ、▲同―謀、▽2―8―1―へ新、
▲2―9―2―謀、▽1―3―1―槍新、▲1―2―1―兵新、▽同―弓、
▲同―弓、▽同―槍、▲3―4―1―や新、▽4―4―1―や新、
▲2―5―1―上新、▽4―2―1―雛、▲3―3―1―や、▽同―忍、
▲同―上、▽同―や、▲3―4―1―上新、▽3―1―1―帥、
▲4―2―1―上、▽同―帥、▲7―5―1―雛、▽5―3―1―へ新、
▲5―4―1―上新、▽4―1―1―帥、▲6―2―1―へ新、▽同―侍、
▲同―上、▽6―1―1―忍新、▲5―4―1―槍新、▽5―2―1―兵、
▲8―6―1―鳳新、▽5―1―1―弓新、▲5―5―1―槍新、▽4―2―1―龍新、
▲5―6―1―龍新、▽6―4―1―忍新、▲同―雛、▽同―兵、
▲5―3―1―槍、▽同―兵、▲6―2―2―兵新、▽5―2―1―龍、
▲6―4―1―鳳[さ入手]、▽6―3―1―侍新、▲8―6―1―鳳、▽6―4―1―上、
▲1―6―1―龍、▽1―3―1―兵新、▲2―5―1―上新、▽2―2―1―鳳新、
▲3―3―1―上、▽同―謀、▲6―5―1―さ新、▽6―3―2―上、
▲3―5―1―弓新、▽4―2―1―謀、▲7―7―1―忍、▽5―5―1―上、
▲同―弓、▽5―4―1―侍、▲3―4―1―忍新、▽3―3―1―鳳、
▲4―2―1―忍、▽同―帥、▲3―5―1―弓、▽2―2―1―鳳、
▲2―8―1―謀、▽7―4―1―忍新、▲7―6―1―鳳、▽8―4―1―上新、
▲7―6―2―謀、▽同―上、▲同―不2―鳳、▽6―5―1―侍、
▲同―鳳、▽6―6―1―筒、新▲同―鳳、▽同―鳳、
▲3―4―1―忍新、▽4―1―1―帥、▲4―2―1―槍新、▽同―龍、
▲同―兵、▽5―2―1―帥、▲6―4―1―臥新[なぜ、6―2―2―臥新と打たなかった?]、▽6―3―1―兵新、
▲6―6―1―臥、▽同―忍、▲同―龍、▽6―2―1―帥、
▲5―5―1―上新、▽4―4―1―雛新、▲5―5―2―謀、▽5―3―2―雛、
▲6―4―1―兵新、▽5―2―1―侍新、▲4―1―1―筒新、▽5―3―3―侍、
▲3―6―1―雛新、▽5―5―2―侍、▲同―不2―上、▽5―4―1―筒新、
▲5―2―1―槍新、▽5―2―1―雛、▲同―筒、▽同―帥、
▲4―1―1―兵、▽6―2―1―侍新、▲4―2―1―鳳新、▽6―2―1―侍⇔帥、
▲6―3―1―兵[さ入手]、▽同―謀、▲同―上、▽同―筒、
▲5―2―1―鳳、▽同―帥、▲6―3―1―雛、▽6―2―1―帥、
▲7―2―1―槍新[詰み]。
[終局]
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
十九、【特性】
【「帥」の特性】
・「帥」は王手された時、自軍駒がいるマスに逃げることが出来ない。
・「帥」は王手を指されている場所には、逃げることが出来ない。
・「帥」の上に、他の如何なる駒も重ねることは出来ない。
・可動範囲追加効果を享受できない。
・手駒にならない。
【「砦」の特性】
・不動駒である。
・移動攻撃が出来ない。
・不動攻撃が出来ない。
・可動範囲追加効果がある。
・地連特性を持つ。
・手駒にならない。
【「砲」の特性】
・不動駒である。
・移動攻撃が出来ない。
・可動範囲追加効果がある。
・地連特性を持つ。
・手駒にならない。
【「忍」の特性】
・自軍敵軍問わず、駒を飛び越えて移動することが出来る。
・猪駒である。
・地連特性を持つ。
【「上」の特性】
・自軍敵軍問わず、駒を飛び越えて移動することが出来る。
・地連特性を持つ。
【「弓」の特性】
・自軍敵軍問わず、駒を飛び越えて移動することが出来る。
【「へ」の特性】
・手ニへ、場ニへの反則がある。
・ヘ詰めの反則がある。
・裏切り効果がある。
【「兵」の特性】
・手ニ兵の反則がある。
・手兵詰めの反則がある。
・裏駒が三種類ある。
・猪駒である。
・初期陣形配置の際、全ての筋に自軍「兵」を配置しなければならない。
【「謀」の特性】
・一層三層交換効果がある。
【「香」の特性】
・強制再配置効果がある。
・猪駒である。
【「侍」の特性】
・身代わり効果がある。
【「臥」「龍」「雛」「鳳」の特性】
・可動範囲追加効果を享受できない。
【「筒」「槍」「さ」「と」「や」】
・特性がない。
※【地連特性】
・基本的に既に盤上にある駒の上へと新することは出来ないが、地連特性を持つ駒は、例外である。
・地連特性とは、その駒の上に別の駒が乗っていなければ、そこに新することが出来る特性である。
・地駒(「砦」「砲」「忍」「上」)のみ、地連特性を持つ。
【「砦」】
・「砦」の駒の上に他の駒が乗っていなければ、「砦」の上に新することが出来る。
・「砦」の上に手駒から直接、新する場合、その駒は何でも良い(「帥」「砲」以外)。
【「砲」】
・「砲」の駒の上に他の駒が乗っていなければ、「砲」の上に新することが出来る。
・「砲」の上に手駒から直接、新する場合、その駒は何でも良い(「帥」「砦」以外)。
【「忍」】
・「忍」の駒の上に他の駒が乗っていなければ、「忍」の上に新することが出来る。
・「忍」の上に手駒から直接、新する場合、その駒は裏駒でなければならない。
【「上」】
・「上」の駒の上に他の駒が乗っていなければ、「上」の上に新することが出来る。
・「上」の上に手駒から直接、新する場合、その駒は表駒(「帥」「砲」「砦」以外)でなければならない。
二十、【効果】
【可動範囲追加効果】
・可動範囲追加効果を持つ「砲」「砦」のことを特に不動駒と呼ぶ。
・不動駒は、不動駒のすぐ上(二層目)の自軍駒の可動範囲を、追加することが出来る。
・不動駒は、不動駒を一層目とした矢倉の三層目の駒には、可動範囲追加効果を享受させることが出来ない。
・不動駒の可動範囲追加効果によって、敵軍自軍問わず駒を飛び越すことは出来ない。
・「臥」「龍」「鳳」「雛」「帥」「香」これらの駒は不動駒の可動範囲追加効果を享受できない。
・「砲」は自軍領地内を超えて、可動範囲を追加することが出来る。
☆「砲」の可動範囲追加効果の範囲。
可動範囲追加効果の範囲は、「砲」から前方に真っ直ぐである。
・「砦」が他の駒へと追加できる可動範囲は自軍領地内のみである。自軍領地内を越えて、可動範囲を追加することは出来ない。
☆砦」の可動範囲追加効果の範囲。
可動範囲追加効果の範囲は、「砦」が「▲5―7―1」にいるとすると、
▲「7―7―全層、6―7―全層、4―7―全層、3―7―全層、6―8―全層、5―8―全層、4―8―全層、5―9―全層」である。
可動範囲追加効果の範囲は、「砦」が「▲5―9―1」にいるとすると、
▲「5―7―全層、6―8―全層、5―8―全層、4―8―全層、7―9―全層、6―9―全層、4―9―全層、3―9―全層」である。
【一層三層交換効果】
・一層目の自軍駒「謀」と、三層目の自軍駒(「帥」以外)の場所を変えても良い。一手として扱う。
・三層目の自軍駒「謀」と、一層目の自軍駒(「砲」「砦」以外)の場所を変えても良い。一手として扱う。
・連続して同じ矢倉の「謀」が一層三層交換効果を使うことは出来ない。
【身代わり効果】
・「侍」の持つ効果。「侍」の前後左右一画に、王手されている「帥」が居た場合、「帥」と場所を交換できる。矢倉にいる「侍」はこの効果を持たない。一手として扱う。
【裏切り効果】
・「へ」の持つ効果。「へ」が矢倉最上層にいる敵軍駒を取ると成立する。「へ」の下層の駒は、敵軍が自軍に、自軍が敵軍になる。
・自軍駒の上に乗るだけでは、この「へ」の裏切り効果は発動しない。
・「へ」が三層目の敵軍駒を取った場合、二層目と一層目の駒は裏切る。例えば、二層目と一層目の駒がそれぞれ敵軍表駒だった場合には、どちらも自軍裏駒になる。
・「へ」が二層目の敵軍駒を取った場合、一層目の駒は裏切る。例えば、一層目の駒が敵軍表駒だった場合には、自軍裏駒になる。
・ひっくり返す作業は一手として数えない。ひっくり返す作業が終わった後、相手の手番となる。
【強制回収効果】
・強制回収効果を持つ「兵」「忍」「香」のことを、特に猪駒と呼ぶ。
・猪駒は、次の移動が出来なくなる一手を指した時、その手を指した後、相手が次の手を指す前の間に、強制回収効果が発動する。
・強制回収効果が発動その駒は自分か相手かどちらかの手駒になる。この作業は一手として数えない。この作業が終了した後、相手の手番に移る。
・猪駒のいずれかが強制回収効果を発動した時、敵軍駒を取っていたなら、猪駒は敵軍の手駒になる。
・猪駒のいずれかが強制回収効果を発動した時、敵軍駒を取っていなかったら、猪駒は自軍の手駒になる。
・猪駒は、次の移動が出来なくなるマスへ新することが出来ない。(これを認めると、事実上パスを認めることになるので認めない)
【強制再配置効果】
・裏駒の「香」を入手した場合、その表駒が「砲」であれ「砦」であれ、新たに自軍領地内に再設置しなければならない。香を入手した後、相手が次の手を指す前の間に行う。配置する場所は任意とし、初期陣形配置の場所と違っていて良い。この作業は一手として数えない。この作業が終了した後、相手の手番に移る。
二十一、【千日手】
・同一局面を四回繰り返すこと。これを千日手と言う。千日手が成立すると、指し直しとなる。
・千日手が発生した時には、陣形配置からやり直す。
・千日手が発生し、陣形配置をやり直すことになった際、その時の黒軍領地は新しく設定され、先手から見て、六、七、八段となり、以後、九段を使えない。
・千日手が発生し、陣形配置をやり直すことになった際、その時の白軍領地は新しく設定され、先手から見て、二、三、四段となり、以後、一段を使えない。
・千日手が発生し、陣形配置をやり直すことになった際、全ての駒は初期状態に戻さず、その時にそれぞれ自軍であった場駒、手駒で陣形配置する。
・千日手が発生し、陣形配置をやり直すことになった際、先手と後手を入れ替える。
・千日手が発生し、陣形配置をやり直すことになった際、初期陣形配置と同じように配置していく。
・千日手が発生し、陣形配置をやり直すことになった際、それぞれの軍は、初期陣形配置と違い、全ての筋に「兵」を配置する必要はなく、場ニ兵にならないようにすれば良い。
(勿論、開戦後の場ニ兵は反則ではない。)
・千日手での「初期陣形配置」「打ち始め」「済み」「開戦」との対応語ははそれぞれ、「再陣形配置」「再び始め」「再び済み」「再開戦」となる。
二十二、【駒の飛び越し】
・「忍」「弓」「上」のみが、自軍敵軍問わず駒を飛び越して移動することが出来る。
・「忍」「弓」「上」以外の駒は、自軍敵軍問わず駒を飛び越して移動することが出来ない。
二十三、【矢倉に向かっての移動について】
・可動範囲内に自軍駒がいる場合、それが既に三層の矢倉か、帥の駒でなければ、上に乗ることが出来る。
・敵軍の矢倉へ攻撃する場合、攻撃対象となるのは最上層の駒だけである。
二十四、【駒の攻撃】
・駒の攻撃には移動を伴う攻撃と、移動を伴わない攻撃がある。移動を伴う攻撃を移動攻撃、移動を伴わない攻撃を不動攻撃と言う。
・移動攻撃では、可動範囲内の敵軍駒向かって移動し、その対象の駒が居た場所を占有することで、その駒を手駒とすることが出来る。
・不動攻撃では、上か下の層に敵軍駒がいたときに、一手でその駒を手駒とすることが出来る。
・上の層への不動攻撃では、その対象の駒を取るだけでよい。
・下の層への不動攻撃では、その対象の駒があった場所を占有することで、その駒を手駒とすることが出来る。
・手駒から直接、敵軍駒を取ることは出来ない。
・可動範囲内に敵軍駒がいて、それが矢倉の場合は、最上層のみ移動攻撃できる。
・可動範囲内に敵軍駒がいるなら、自軍駒のいる場所がどの層であっても、矢倉の最上層の敵軍駒を移動攻撃できる。
二十五、【場ニへ反則勝ちを誘導する】
「▲2―3―1―兵[裏駒へ]、▽2―3―2―忍、▲1―3―1―へ、▽2―1―1―へ」と、あったとする。
この状態から「▲2―3―2―へ」と最上層にいる敵軍駒「忍」を取ると、矢倉の一層目にいる自軍駒「兵」が裏切り、敵軍駒の裏駒「へ」になる。
そうすると、「▽2―1―1―へ、▽2―3―1―へ」となり、相手は場ニへで反則で、この場合、相手の負けとなる。
かなりエグい手ではあるが、意識していれば成立しにくい手である。
しかし、これを食らって負けたらちょっとかっこ悪いかも。
もちろん三層矢倉に対しても有効である。
例えば、「▲2―3―1―兵[裏駒へ]、▲2―3―2―弓、▽2―3―3―忍、▲1―3―1―へ、▽2―1―1―へ」とあったとする。
この状態から「▲2―3―3―へ」と最上層にいる敵軍駒「忍」を取ると、矢倉の一層目と二層目にいる自軍駒が裏切る、この場合「弓」「兵」が裏切り、それぞれ敵軍駒の裏駒「や」「へ」になる。
この場合、「や」はあってもなくても同じだが、また「へ」が二筋に出来たので、「▽2―1―1―へ、▽2―3―1―へ」となり、相手は場ニへで反則で、この場合も、相手の負けとなる。
二十六、【敵軍駒「砦」と自軍駒「帥」の関係】
・自軍駒「帥」が敵軍駒「砦」の敵上に乗っている状況が発生してしまった場合、一層目にある砦と、自軍手駒にある駒と交換してもよい。
なお、手駒がない場合、もしくは、交換したくない場合、「砦」(つまり「香」ね)を手駒に加えるだけでよい。
※この状況が発生するかもしれないと考えなければならない理由は、敵上での動きが決まっていない帥と攻撃能力がない「砦」が存在してしまっているからである。ついでに言うなら、「砦」以外の駒はその駒の上に乗っかっている駒に対して、攻撃が出来るので……、そもそも「帥」が敵軍駒のみで構成された二層矢倉もしくは三層矢倉を攻撃したら、その時点で自軍の負けであり、つまりは王手が指されている場所に移動攻撃すると言うことであり、それなら、「帥」は敵上での可動範囲設定はいらないかなと思ってそういう風にした矢先、そういえば「砦」の攻撃能力なくしちゃったんだった、と思い出して、どうしよう、と、困った状況になっちゃったわけさ、まぁ、そんなこんなで、いろいろ考えてみたのだが、そもそもこの条件を達成するためには「帥」が入玉していなければならないわけで、更に入玉した「帥」が上手いこと敵軍のみで構成された二層矢倉になっている「砦」に対して攻撃を成立させなければならないわけで、どんだけ希少な状況なのさと思ったわけだよ、うん、だから、僕はこんな状況がもし発生したのなら、少しくらいボーナスを上げてもいいかなって思ったんだ、だからね、こういった理由からこのルールは出来たのさ。
二十七、【その他】
・将棋と違い、敵軍領地内に入っても成ることはない。
・駒は無理に重ねなくとも良い。
・砲、砦以外の駒で、いくら層を重ねても、可動範囲が追加されることはない。あくまでも、その駒がどの層にいるかによってその駒の可動範囲は決定しているのである。
・手駒に表駒「兵」が二つ以上あり、それらのなかに裏駒が「と」か「さ」の「兵」が混ざっているのなら、相手にわからないようにシャッフルしても良い。
相手が不安な様であれば、第三者に頼んでも良い。
そもそも、無理にしなくても良い。
・「可動範囲追加効果」「一層三層交換効果」「身代わり効果」「裏切り効果」等は権利である。
・「強制回収効果」「強制再配置効果」は強制である。













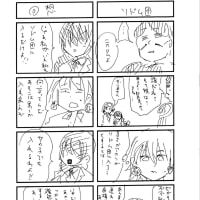






見落としてたらすいません<(_ _)>
但是還是來留言了www
只是想給你一點鼓勵
你好害喔! :)
日本語で理解できない場合: ニースのルール....私はちょうど聞かせて、モバイルレンジの拡張効果のスタックですか? (ピースがカタパルトと要塞の両方の範囲内にある場合、効果を受け取った場合、それはティア3に移動しますか?)
さ~、日本語で書いてみようか。。。このルールはどこから集まっていたの?聞いたの理由は、redditやネトである「ぐんぎ」って言うゲームも見つけられるのです。その軍議とこれはちょっと違いがある。例えばっその軍議では裏駒のことぜんぜんない。それに他の駒もある。だから困っている~ 「ぐんぎ」って言うゲームはぢっちですか?