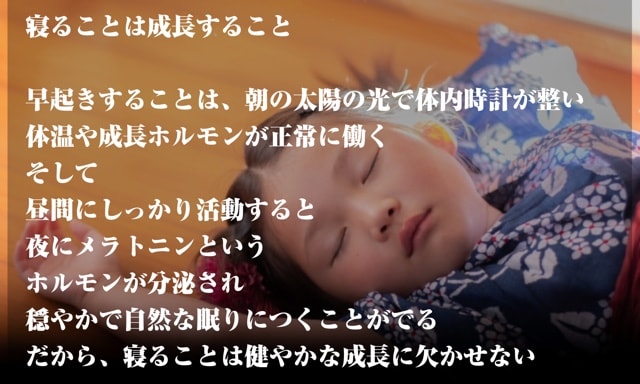
こんにちは、四谷大塚NETフォーラム塾上本町教室塾長・学びスタジオ®︎代表の奧川えつひろです。
ご訪問いただき、ありがとうございます。
今回は、睡眠について書きます。
❤︎夜9時以降に寝る0〜2歳児が、5割以上
2021年の調査で、
夜9時以降に寝る0〜2歳児が、5割以上いるそうです。
遅寝が、
子どもの頭と心と体の成長に
大きな悪影響を与えます。
例えば、
キレやすい、
肥満になる、
三角形が描けない……
❤︎生後3〜4ヶ月ごろから昼と夜の区別がつく
赤ちゃんが生後3~4ヶ月ごろになると、
昼と夜の区別がつき始めるます。
だから、
生まれてすぐから
早寝早起きをさせることが大切です。
赤ちゃんのときに、
朝起こさず、
夜も寝かせないという状態だと、
睡眠のリズムが崩れたまま
成長することになります。
❤︎睡眠のリズムは成長に大きく関わる
睡眠のリズムは、
子どもの成長に大きく関わります。
事実、
早寝早起きの子どもの方が成績も良く、
東大生に早寝早起きの人が多いことも事実です。
勉強に限らず、
音楽でも、
スポーツでも、
その子がもともと持っている力を100%に引き出すことができるのが早寝早起きのリズムです。
❤︎幼児は10~13時間、小学生は9~11時間の睡眠を
“早起き”の目安は、
太陽と共に起きるのが理想的です。
実際は朝6~7時ぐらいに起こせるといいですね。
WHO(世界保健機関)が推奨する睡眠時間は、
0〜3カ月は14〜17時間、
4〜11カ月は12〜16時間、
1〜2歳は11〜14時間、
3〜5歳の幼児は10〜13時間です。
幼児は、
夜8時までに寝かせて朝6時か7時に起こすのが良いリズムです。
また、
小学生は9~11時間です。
夜9時までに寝かせて朝6時か7時に起こすのが良いリズムです。
早起きさせたら、
昼間はなるべく頭を使ったり、
身体を動かすことをさせましょう。
疲れないと子どもは寝ませんから。
❤︎テレビ、ゲームは危険
.
スマホやゲーム、テレビなどは、
子どもには危険です。
しっかりコントロールしないといけません。
親がゲームの時間をコントロールして、
早く寝かせるようにしましょう
❤︎睡眠のリズムが悪いと、心身ともにトラブルが起こる原因に
朝、太陽の光が、
目の中にある視交叉上核(しこうさじょうかく)へ入ると、
体内時計が駆動されます。
体内時計が整うと、
体温や成長ホルモンも正常に働きます。
そして昼間にしっかり動いておくと、
夜にメラトニンというホルモンが分泌され、
穏やかで自然な眠りを誘います。
しかし、
このリズムが上手くいかないと、
体温調節ができず、
免疫が下がって風邪をひきやすくなったり、
排便のタイミングも悪くなったりします。
また脳の働きにも影響が出て、
イライラして攻撃性が強くなったり、
情緒が不安定になったりします。
❤︎睡眠は、量とリズムと質が重要
睡眠は、
ただ長い時間眠ればいいということではないです。
量だけでなく、
リズム、つまり早く寝るということ、
そして質も重要です。
質の良い睡眠とは、
朝までぐっすり眠れていれば大丈夫です。
睡眠は、
深い眠りのノンレム睡眠と、
浅い眠りのレム睡眠をきちんと繰り返しており、
夜中に何度も起きてしまうのはあまり質の良い睡眠とは言えません。
早く寝れば、
明け方にレム睡眠が十分にとれて起きる準備ができ、
お腹も動き始めます。
そうすると、
朝ごはんも美味しく食べらるようになります。
.
子どもの睡眠不足は、
薬を飲んで治すものではありません。
保護者の方が子どもを早く寝かせて、
早起きさせればいいだけのことなのです。
❤︎早く寝るコツ
親が早く寝かせようと思うことです。
今は、
親も子どももやることが多いので、
まずは親も子どもも寝る時間と一日のスケジュールを決めましょう。
そして早く寝る準備をして、
電気を消して布団に入れましょう。
以上のことを努力して早く寝れば、
朝も楽に早く起きることができます。
子どもが生き生きと発達するために睡眠は必須のものです。
“寝る子は育つ”
正しい睡眠のリズム
早寝早起きを習慣にしてください。
❤︎まとめ。寝ることは成長すること
早く寝て、早起きをすることは、
朝の太陽の光で
体内時計が整い
体温や成長ホルモンも正常に働きます
そして
昼間にしっかり動いておくと、
夜にメラトニンというホルモンが分泌され、
穏やかで自然な眠りにつくことができます。
健やかな成長に欠かせない条件です。
ご訪問いただき、ありがとうございます。
今回は、睡眠について書きます。
❤︎夜9時以降に寝る0〜2歳児が、5割以上
2021年の調査で、
夜9時以降に寝る0〜2歳児が、5割以上いるそうです。
遅寝が、
子どもの頭と心と体の成長に
大きな悪影響を与えます。
例えば、
キレやすい、
肥満になる、
三角形が描けない……
❤︎生後3〜4ヶ月ごろから昼と夜の区別がつく
赤ちゃんが生後3~4ヶ月ごろになると、
昼と夜の区別がつき始めるます。
だから、
生まれてすぐから
早寝早起きをさせることが大切です。
赤ちゃんのときに、
朝起こさず、
夜も寝かせないという状態だと、
睡眠のリズムが崩れたまま
成長することになります。
❤︎睡眠のリズムは成長に大きく関わる
睡眠のリズムは、
子どもの成長に大きく関わります。
事実、
早寝早起きの子どもの方が成績も良く、
東大生に早寝早起きの人が多いことも事実です。
勉強に限らず、
音楽でも、
スポーツでも、
その子がもともと持っている力を100%に引き出すことができるのが早寝早起きのリズムです。
❤︎幼児は10~13時間、小学生は9~11時間の睡眠を
“早起き”の目安は、
太陽と共に起きるのが理想的です。
実際は朝6~7時ぐらいに起こせるといいですね。
WHO(世界保健機関)が推奨する睡眠時間は、
0〜3カ月は14〜17時間、
4〜11カ月は12〜16時間、
1〜2歳は11〜14時間、
3〜5歳の幼児は10〜13時間です。
幼児は、
夜8時までに寝かせて朝6時か7時に起こすのが良いリズムです。
また、
小学生は9~11時間です。
夜9時までに寝かせて朝6時か7時に起こすのが良いリズムです。
早起きさせたら、
昼間はなるべく頭を使ったり、
身体を動かすことをさせましょう。
疲れないと子どもは寝ませんから。
❤︎テレビ、ゲームは危険
.
スマホやゲーム、テレビなどは、
子どもには危険です。
しっかりコントロールしないといけません。
親がゲームの時間をコントロールして、
早く寝かせるようにしましょう
❤︎睡眠のリズムが悪いと、心身ともにトラブルが起こる原因に
朝、太陽の光が、
目の中にある視交叉上核(しこうさじょうかく)へ入ると、
体内時計が駆動されます。
体内時計が整うと、
体温や成長ホルモンも正常に働きます。
そして昼間にしっかり動いておくと、
夜にメラトニンというホルモンが分泌され、
穏やかで自然な眠りを誘います。
しかし、
このリズムが上手くいかないと、
体温調節ができず、
免疫が下がって風邪をひきやすくなったり、
排便のタイミングも悪くなったりします。
また脳の働きにも影響が出て、
イライラして攻撃性が強くなったり、
情緒が不安定になったりします。
❤︎睡眠は、量とリズムと質が重要
睡眠は、
ただ長い時間眠ればいいということではないです。
量だけでなく、
リズム、つまり早く寝るということ、
そして質も重要です。
質の良い睡眠とは、
朝までぐっすり眠れていれば大丈夫です。
睡眠は、
深い眠りのノンレム睡眠と、
浅い眠りのレム睡眠をきちんと繰り返しており、
夜中に何度も起きてしまうのはあまり質の良い睡眠とは言えません。
早く寝れば、
明け方にレム睡眠が十分にとれて起きる準備ができ、
お腹も動き始めます。
そうすると、
朝ごはんも美味しく食べらるようになります。
.
子どもの睡眠不足は、
薬を飲んで治すものではありません。
保護者の方が子どもを早く寝かせて、
早起きさせればいいだけのことなのです。
❤︎早く寝るコツ
親が早く寝かせようと思うことです。
今は、
親も子どももやることが多いので、
まずは親も子どもも寝る時間と一日のスケジュールを決めましょう。
そして早く寝る準備をして、
電気を消して布団に入れましょう。
以上のことを努力して早く寝れば、
朝も楽に早く起きることができます。
子どもが生き生きと発達するために睡眠は必須のものです。
“寝る子は育つ”
正しい睡眠のリズム
早寝早起きを習慣にしてください。
❤︎まとめ。寝ることは成長すること
早く寝て、早起きをすることは、
朝の太陽の光で
体内時計が整い
体温や成長ホルモンも正常に働きます
そして
昼間にしっかり動いておくと、
夜にメラトニンというホルモンが分泌され、
穏やかで自然な眠りにつくことができます。
健やかな成長に欠かせない条件です。


















